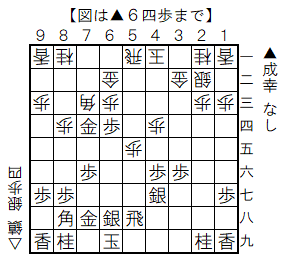今月見た夢を記しておこう。
まずは3日に見た夢。
海岸であるゲームが行われていた。基本は野球のようなのだが、守りのチームは沖にいて、バッターは浜辺から打つ。ピッチャーは大きな波に合わせて投げるので、波全体がボールみたいで、大変な迫力になる。
得点は1点ごとではなく、けっこうまとまって入る。108-100になり、最終回の2アウト、バッターに木村拓哉が入った。
ピッチャーがものすごい波(ボール)を投げるとキムタクが打ち返し、なぜか8点が入り同点になった。
……というところで目が覚めた。
続いてかなり飛んで、30日に見た夢。
最近実生活で左上の歯3本すべての調子が悪くて気が滅入っているのだが、これを踏まえて、左上の歯4本が歯茎ごと取れてしまった夢を見た。
ここで小便でいったん起き、寝直した。
仮面ライダーのサラセニアンの回で、サラセニアンが100人の少年少女を改造しようとした。
何人かは改造されてしまったが、そのうちの少女(全身が緑がかっている)は、そのせいで身体能力がアップし、器械体操みたいなものがうまくなった。
……というところで、目が覚めた。
きょうで9月も終わりなので、もうアップします。
まずは3日に見た夢。
海岸であるゲームが行われていた。基本は野球のようなのだが、守りのチームは沖にいて、バッターは浜辺から打つ。ピッチャーは大きな波に合わせて投げるので、波全体がボールみたいで、大変な迫力になる。
得点は1点ごとではなく、けっこうまとまって入る。108-100になり、最終回の2アウト、バッターに木村拓哉が入った。
ピッチャーがものすごい波(ボール)を投げるとキムタクが打ち返し、なぜか8点が入り同点になった。
……というところで目が覚めた。
続いてかなり飛んで、30日に見た夢。
最近実生活で左上の歯3本すべての調子が悪くて気が滅入っているのだが、これを踏まえて、左上の歯4本が歯茎ごと取れてしまった夢を見た。
ここで小便でいったん起き、寝直した。
仮面ライダーのサラセニアンの回で、サラセニアンが100人の少年少女を改造しようとした。
何人かは改造されてしまったが、そのうちの少女(全身が緑がかっている)は、そのせいで身体能力がアップし、器械体操みたいなものがうまくなった。
……というところで、目が覚めた。
きょうで9月も終わりなので、もうアップします。