都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「スイス・スピリッツ」 Bunkamura ザ・ミュージアム 3/25
Bunkamura ザ・ミュージアム(渋谷区道玄坂2-24-1)
「スイス・スピリッツ -山に魅せられた画家たち- 」
3/4-4/9
まさか現代アートまで展示されているとは思いもよりませんでした。スイスの山、アルプスをテーマに、近代絵画からコンテンポラリーまでを幅広くカバーします。なかなか意欲的な展覧会です。
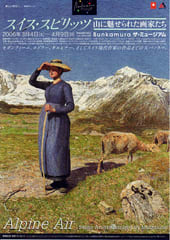
ともかく、絵画の並ぶ中盤までの流れとポップ・アート以降の展示では趣きが大分異なりますが、まずはオーソドックスに、画家がいつ頃アルプスを描き始めたのかという所から展覧会は始まります。それによるとアルプスが身近な対象として意識され出したのは18世紀頃。それまで遠景ばかりが描かれていた山々が、科学の隆盛と共に研究や探索の対象となっていく。科学者らに同行して山へ入った画家たちが、記録として間近で山を描き始めるようになるのです。意外な接点でした。

ここではその先駆者として活躍したヴォルフの作品がズラリと並びます。ベタッと塗られた油絵具にて、ゴツゴツとした岩山を表現した油彩も悪くはありませんが、水彩の方がより魅力的に映りました。中でも洞窟越しにアルプスを眺めた「シュタンス近くのドラゴン洞窟」(1775頃)が美しい作品です。陽の光に当たった洞窟の岩肌が、黄色をはじめとする明るい色調でまとめられています。洞窟から見える湖や村の遠景も構図として面白いのですが、左端にて写生をしている帽子を被った画家の姿がより印象的です。ひんやりとした洞窟の中の空気すら伝わってくるような作品でした。

1848年のスイス連邦の成立に伴って、アルプスは国家統合の象徴的地位を占めるようになります。それに重なるのが絵画では古典主義からロマン派の時期です。ここでもいくつか興味深い作品が展示されていましたが、カラムの「ルツェルン湖」(1854-57)はなかなか魅力的でした。赤茶けた岩山と波がうねるルツェルン湖。沖に一艘の小舟が出ていることが分かります。手前で砕ける波の表現はどこかクルーベのよう。砂を飲み込みながら濁っている湖の姿が印象に残りました。
初期モダニズム絵画を紹介したセクション(第3章「1900年前後初期モダニズムにおける山岳風景」)では、ホドラー、ジャコメッティ、セガンティーニらの描くアルプスの光景が光ります。この展覧会で最も華やかな一角です。

アルプスの光景が光に包まれて輝いている二点、セガンティーニの「アルプスの真昼」(1891)と、ジロンの「ラヴェイの農民と風景」(1885)は実に鮮やかな色彩美で目を楽しませてくれる作品です。(画像は「ラヴェイの農民と風景」。「アルプスの真昼」は一番上にアップしたパンフレットに掲載されている作品です。)光眩しい川辺にて二人の男女が手をつないでいる「ラヴェイ」。大きな鎌と重たそうな女性の荷物が農民の労働をイメージさせますが、その二人の様子はどこか恋仲のようにも見えます。また荒々しいタッチにて点描画のようにまとめ上げた「アルプスの真昼」は、同じく農民と思われる女性が描かれていますが、こちらは一人で日向にて眩しそうに帽子のつばへ手をかけています。そして頭上に広がる真っ青な空。透き通ったその空気は、天に近い山の高さを巧みに伝えてきます。油彩と言うよりもパステル画のような味わいもまた興味深いところです。

第4章(「色と色彩の解放」)には、クレー(2点)やイッテン(1点)の興味深い作品がいくつか並んでいました。まるで塗り絵のように色彩が分割されている「入り江の汽船」(1937)。クレー晩年の作品です。芝色の山と水色の入り江。そこに一隻の汽船が左から入って来ています。またもう一点の「贋の岩」(1927)は、線と面が交錯する幾何学的な構図にて、閉塞感の漂う洞穴が描かれた作品でした。重たく崩れそうな岩。深い闇の奥。画像が手元にないのが残念ですが、私はこちらの作品により惹かれました。
キルヒナーら表現主義作家の作品が並ぶコーナーを超えると、一気にポップアートやコンテンポラリーの世界へと進みます。もちろんここでの絵画は、あくまで表現の一形態に過ぎません。空の木枠を壁に引っかけて、その掛かる様子が山に見えるというレーツの「これだってニーセン山」(1978)など、下らなさ満点の作品もありますが、真っ当な写真(?)にて山へ迫った作品もいくつか展示されています。とは言えやはり何でもありの現代アートです。展示室中央にドーンと置かれた巨大な岩石(もちろん作品!)や、ただのボロ切れなどをキャンバスに閉じ込めて山に似せかけた作品(スーター「絵画」)などは、思わずここが品の良い(?)あのBunkamuraだということを忘れさせるようなインパクトがあります。ちなみに私がこのコーナーで最も惹かれたのは、一番最後の暗室に展示されていたシュタイナーとレンツリンガーによる「山崩れ」(2005)というオブジェです。真っ赤な宝石の如く輝いている、まるで氷河のような結晶の山。それが溶け出すかのように水の音を立てながら崩れています。そして素材はなんとライトの破片と固体化された膨張溶液。そう言えば至る所にプラスチックのライトが突き刺さっていました。チープな素材を使いながらもなかなか美感があります。最後を飾るのに相応しい作品かもしれません。
「アルプスが描かれたキレイな絵がたくさんあるのだろう。」などと思って出向くと良い意味で期待を裏切られます。ちょっぴり刺激的な展覧会です。次の日曜までの開催です。
「スイス・スピリッツ -山に魅せられた画家たち- 」
3/4-4/9
まさか現代アートまで展示されているとは思いもよりませんでした。スイスの山、アルプスをテーマに、近代絵画からコンテンポラリーまでを幅広くカバーします。なかなか意欲的な展覧会です。
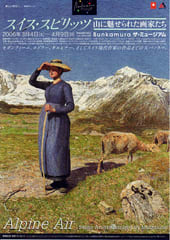
ともかく、絵画の並ぶ中盤までの流れとポップ・アート以降の展示では趣きが大分異なりますが、まずはオーソドックスに、画家がいつ頃アルプスを描き始めたのかという所から展覧会は始まります。それによるとアルプスが身近な対象として意識され出したのは18世紀頃。それまで遠景ばかりが描かれていた山々が、科学の隆盛と共に研究や探索の対象となっていく。科学者らに同行して山へ入った画家たちが、記録として間近で山を描き始めるようになるのです。意外な接点でした。

ここではその先駆者として活躍したヴォルフの作品がズラリと並びます。ベタッと塗られた油絵具にて、ゴツゴツとした岩山を表現した油彩も悪くはありませんが、水彩の方がより魅力的に映りました。中でも洞窟越しにアルプスを眺めた「シュタンス近くのドラゴン洞窟」(1775頃)が美しい作品です。陽の光に当たった洞窟の岩肌が、黄色をはじめとする明るい色調でまとめられています。洞窟から見える湖や村の遠景も構図として面白いのですが、左端にて写生をしている帽子を被った画家の姿がより印象的です。ひんやりとした洞窟の中の空気すら伝わってくるような作品でした。

1848年のスイス連邦の成立に伴って、アルプスは国家統合の象徴的地位を占めるようになります。それに重なるのが絵画では古典主義からロマン派の時期です。ここでもいくつか興味深い作品が展示されていましたが、カラムの「ルツェルン湖」(1854-57)はなかなか魅力的でした。赤茶けた岩山と波がうねるルツェルン湖。沖に一艘の小舟が出ていることが分かります。手前で砕ける波の表現はどこかクルーベのよう。砂を飲み込みながら濁っている湖の姿が印象に残りました。
初期モダニズム絵画を紹介したセクション(第3章「1900年前後初期モダニズムにおける山岳風景」)では、ホドラー、ジャコメッティ、セガンティーニらの描くアルプスの光景が光ります。この展覧会で最も華やかな一角です。

アルプスの光景が光に包まれて輝いている二点、セガンティーニの「アルプスの真昼」(1891)と、ジロンの「ラヴェイの農民と風景」(1885)は実に鮮やかな色彩美で目を楽しませてくれる作品です。(画像は「ラヴェイの農民と風景」。「アルプスの真昼」は一番上にアップしたパンフレットに掲載されている作品です。)光眩しい川辺にて二人の男女が手をつないでいる「ラヴェイ」。大きな鎌と重たそうな女性の荷物が農民の労働をイメージさせますが、その二人の様子はどこか恋仲のようにも見えます。また荒々しいタッチにて点描画のようにまとめ上げた「アルプスの真昼」は、同じく農民と思われる女性が描かれていますが、こちらは一人で日向にて眩しそうに帽子のつばへ手をかけています。そして頭上に広がる真っ青な空。透き通ったその空気は、天に近い山の高さを巧みに伝えてきます。油彩と言うよりもパステル画のような味わいもまた興味深いところです。

第4章(「色と色彩の解放」)には、クレー(2点)やイッテン(1点)の興味深い作品がいくつか並んでいました。まるで塗り絵のように色彩が分割されている「入り江の汽船」(1937)。クレー晩年の作品です。芝色の山と水色の入り江。そこに一隻の汽船が左から入って来ています。またもう一点の「贋の岩」(1927)は、線と面が交錯する幾何学的な構図にて、閉塞感の漂う洞穴が描かれた作品でした。重たく崩れそうな岩。深い闇の奥。画像が手元にないのが残念ですが、私はこちらの作品により惹かれました。
キルヒナーら表現主義作家の作品が並ぶコーナーを超えると、一気にポップアートやコンテンポラリーの世界へと進みます。もちろんここでの絵画は、あくまで表現の一形態に過ぎません。空の木枠を壁に引っかけて、その掛かる様子が山に見えるというレーツの「これだってニーセン山」(1978)など、下らなさ満点の作品もありますが、真っ当な写真(?)にて山へ迫った作品もいくつか展示されています。とは言えやはり何でもありの現代アートです。展示室中央にドーンと置かれた巨大な岩石(もちろん作品!)や、ただのボロ切れなどをキャンバスに閉じ込めて山に似せかけた作品(スーター「絵画」)などは、思わずここが品の良い(?)あのBunkamuraだということを忘れさせるようなインパクトがあります。ちなみに私がこのコーナーで最も惹かれたのは、一番最後の暗室に展示されていたシュタイナーとレンツリンガーによる「山崩れ」(2005)というオブジェです。真っ赤な宝石の如く輝いている、まるで氷河のような結晶の山。それが溶け出すかのように水の音を立てながら崩れています。そして素材はなんとライトの破片と固体化された膨張溶液。そう言えば至る所にプラスチックのライトが突き刺さっていました。チープな素材を使いながらもなかなか美感があります。最後を飾るのに相応しい作品かもしれません。
「アルプスが描かれたキレイな絵がたくさんあるのだろう。」などと思って出向くと良い意味で期待を裏切られます。ちょっぴり刺激的な展覧会です。次の日曜までの開催です。
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )









