都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「美術館は『通路』である」 東京都現代美術館・川俣正 通路トーク(Cafe Talk65)
東京都現代美術館・川俣正「通路」/通路トーク(Cafe Talk65)
「美術館は『通路』である」
2/23 15:30~
川俣正×住友文彦(東京都現代美術館学芸員)
MOTの「通路」展の関連イベント、作家川俣正のトークセッションに参加してきました。タイトルは「美術館は『通路』である」、ようは美術館学芸員住友文彦氏との対談です。カフェトークということで、川俣本人もビールを片手に、かなりラフな感覚で思いを語っていたように見えました。以下、私のメモです。録音したわけではないので不完全ですが、発言を順に挙げていきます。
ー ー ー
住友文彦(以下、S) 今回の展示を企画した理由について。まず、MOTのコレクションより日本人作家の展示をしようと考えたが、巨大なこのMOTという箱をいつもと異なったように使ってみたいと思った。また、美術館のあり方を再考する観点から、普段、美術館であまり仕事をしていない人物をピックアップして考えた。それが川俣である。
近年、美術館は、元々「美術」でないとされているジャンルを取り入れている。(例、ジブリ、フェラーリ)その反面、企画会社が強く美術館の仕事に関与してきた。その場で働いている人間としては一種のジレンマを感じている。
川俣正(以下、K) 民間、外部の美術館への関与は、学芸員へのある種の攻撃ではないか。
S これまでの美術館のあり方ではダメだという認識は持っている。変化が要請されているのも分かっている。しかしそれで、美術館が単なるサービス業になって良いのかという疑問もある。ただの場所貸しではデパートの催事場と変わらない。もちろん美味しいレストラン、そして子どもが気軽に来られるような工夫は重要だろう。
K 学芸員には、「美術は社会の中で特別である。そして、一部な人の特殊技術を紹介する場が美術館だ。」という認識があるのではないか。それは良くない点だ。専門性を要求されるのはやむを得ないにしろ、それと一般性とにどう折り合いを付けるかが問われている。
S 学芸員の仕事は極めて多岐に及んでいる。様々な点において外部の風を入れるのは重要。そしてその専門性は学芸員の視点ではなく、美術館の外にあるかもしれない。
K 美術館では6年ぶりの個展。日本でも3回やっている。先日、「これからは美術館に戻るのか。」と聞かれたが、そういうつもりは全くない。むしろ美術館だからどうだというような、その場所に対してのこだわりはない。
S 自分の仕事以外で美術館に行くことがあるか。
K 殆ど行かない。関心のある作家が10人いたとしたら、そのうちせいぜい1つの展示を見る程度だろう。それに、同時進行のプロジェクトをかかえる自分の仕事上、美術館で他の展示を見たりするなどの余裕がない。本音を言ってしまえば、美術館が好きでないということかもしれないが。MOTでは確か94年の展示に参加している。それ以降、ここへ来たのは、NHKの取材で付き合った榎倉の個展のみ。
S MOTの印象はどうか。
K スペースがともかく巨大。上下、遠近については比較的自由に使えるが、石造りの外観は堅牢で、いかにも権威主義的。横浜のトリエンナーレで使った倉庫とは正反対だ。人がどう動いていくのかというイメージがなかなか描けない。だからこそ今回の展示は、ヒューマンスケールでどういう動きが出来るのかを考えた。
S ヒューマンスケールは、今回の一つのキーワードかもしれない。入場者同士の出会いの場、そして例えばラボのように、相互の活動が交流し合うような場面を見ることが出来る。
K アクティビティを美術館へ持ちこむ。多くのボランティアと準備したり、活動をラボで行ったり、ワークショップで現在進行形のアイデアを膨らませたりと、常に変化があるような場にした。アクティビティをそれぞれの時間で区切って、その「今」を提示し、さらに次に連続して繋げる。この展覧会ではそういった日常性を大切にしたい。
S よく入場者に「このラボは展示の後どうなるのか。」ということを聞かれる。それはいわゆる美術館で見る「作品」の行き先、または「完成」に対する一般的な考え方だ。今回はそうではなく、言わば「通り過ぎる途中」をそのまま見せているのではないか。これまでの川俣の仕事をこの美術館を使ってやっていること。始まりも終わりもなく、ただずっと続くとしか言えない。「完成」を求める入場者に対し、分からないことをそのまま提示しておく。
K 決して無責任というわけではないが、これらのプロジェクトは完成することがない。活動は永続的なもの。例えばある入院患者が治療を終え、一度退院した後、再度症状が出てまた入院することがある。治癒を、結果、または完成の意味と捉えれば、それを求めるのは極めて難しいのではないだろうか。完成という何かを残すのは、おそらく人がある特定の時間(人生)だけしか生きることが許されないため、その後にも自らの何かを残したいという憧れだろう。それに対して、別になくなっても良いではないか、また全てが整理されて完成されなくても良いではないかという気持ちを持っている。もちろん見に来る人々は納得しないかもしれない。この展覧会でも「いつが見頃か。」と聞かれることがあるが、その答えはない。
S そのようなある種の「永続」を見るため、今回の展示ではパスポートチケットも用意している。
K いかにその時間、場所と付き合っていくかという観点が重要。例えば外科的な手術で治療を施すのではなく、その病気とどう付き合って生きていくのかという感覚に近いかもしれない。「脱力系のアート」と言われても良い。盛り上がらないものの良さを見出したい。
S 今回の通路は300人のボランティアの手によって作られた。その光景を見ていると、彼らが「見る」よりも「作る」方が楽しいことを知ったような気がする。この展示では、作品と鑑賞者が対立する関係には決してならない。その場へ関与することが重要だ。そのために参加型のワークショップがある。
K 美術館で土嚢を積んで、ベニヤ板をたてると言うような、本来の場所のあり方から逸脱した行為にも面白さがあるのではないか。口コミレベルにまで降りて、美術館にある権威をとった上で、何かを共同で行う。
S 美術館の権威と作家のそれがあまりにも近過ぎるという指摘もある。
K 若い作家はむしろ美術館の権威を必要とするのが普通だろう。
S 美術館で開催するということと、外で開催することに違いはあるか。
K その違いはあっても気にしない。どちらが良いというわけではない。美術館であろうと、その外であろうと、関わり方は千差万別。
S 活動において、作品の自主性や、また社会との関わり方を川俣本人ではなく、ラボのメンバーが自由にすることもある。
K それを美術館の中でやるのが面白い。但し、美術館の中でやるということは、その活動が一種の見世物にもなるということだ。そしてその見せることに対して、今回どう応じるかを考えたつもりだ。
S 大学などで活動するのとはやはり違うのか。
K 全く異なる。大学での活動をそのまま美術館へ移したわけではない。先に「脱力系のアート」と言ったが、見世物としてどう盛り上げるのかも考えた。無気力と脱力は違う。また美術館の中で提示すると「作品的」に見えるのも事実だろう。その要素を取っ払った上にて、こういう展覧会も出来るのだということを見せたかった。
S ラボで見られる各プロジェクトのテーマの重いものが多いが。
K そのテーマの中で「嘘」をつくこともしたかった。言葉は悪いが、そうすることで真っ正直に取り組んだ場合と違う面が開けてくる。嘘とは一種のスルーとも言えるかもしれない。その重さをスルーしてかわすことで、別の展開を模索する。
S 例えば炭坑プロジェクトではどうなのか。
K シンボルとなるタワーをあえて建てない。ただ、周囲にはもう建てない方が良いと言われたのも事実だ。
S 鉄塔を建てることで街を再生させるイメージはどうなるのか。
K シンボルを否定して、淡々と進む日常を受け入れてしまうこと。ただ歩く、ただ進む、それが「通路」だ。どうやっていけばその「通路」と向かい合えるのかをその場で考えていく。
S 今回の展示では実際に「通路」が出来るプロセスを見たが、作る際にはどのようなことを考えているのか。
K 実は最初はかなり不安。何年か前にこの展示の話があったが、何をどうするかということについて色々悩んだ。またアイデアを発酵させる時間が重要だ。そしてもちろんこの「通路」も発酵させたい。先にコンセプトありきで細部をつめるやり方ではなく、むしろ細部を連ねて最後にある程度の体系的なものが見通せる方が良い。「通路」はその細部同士を繋ぐものに過ぎない。マラソンのようにスタートとゴールが結びついていた一本の道ではない。
ー ー ー
 「川俣正/通路/美術出版社」
「川俣正/通路/美術出版社」
以上です。また最後に、質疑応答での氏の発言もいくつか記録しておきます。
Q 現代美術は自己満足なのか。
K 自己満足で当然。そして、その自己満足にお金を出す人々がいるこの社会がとても面白いと思う。
Q ベニヤを使った理由は。
K 誰でも扱える素材だから。美術に必要とされる特殊な技術は一切いらない。
Q 展示ファイルをめくったら監視員に注意された。
K 監視員が目をそらした隙にめくってください。
Q 通路に順路がある。
K 美術館側としては、中で迷ってしまう人がいるのが問題なのだろう。
このトークショーを含めた「通路」展の私の感想は、また別エントリに書きたいと思います。
「美術館は『通路』である」
2/23 15:30~
川俣正×住友文彦(東京都現代美術館学芸員)
MOTの「通路」展の関連イベント、作家川俣正のトークセッションに参加してきました。タイトルは「美術館は『通路』である」、ようは美術館学芸員住友文彦氏との対談です。カフェトークということで、川俣本人もビールを片手に、かなりラフな感覚で思いを語っていたように見えました。以下、私のメモです。録音したわけではないので不完全ですが、発言を順に挙げていきます。
ー ー ー
住友文彦(以下、S) 今回の展示を企画した理由について。まず、MOTのコレクションより日本人作家の展示をしようと考えたが、巨大なこのMOTという箱をいつもと異なったように使ってみたいと思った。また、美術館のあり方を再考する観点から、普段、美術館であまり仕事をしていない人物をピックアップして考えた。それが川俣である。
近年、美術館は、元々「美術」でないとされているジャンルを取り入れている。(例、ジブリ、フェラーリ)その反面、企画会社が強く美術館の仕事に関与してきた。その場で働いている人間としては一種のジレンマを感じている。
川俣正(以下、K) 民間、外部の美術館への関与は、学芸員へのある種の攻撃ではないか。
S これまでの美術館のあり方ではダメだという認識は持っている。変化が要請されているのも分かっている。しかしそれで、美術館が単なるサービス業になって良いのかという疑問もある。ただの場所貸しではデパートの催事場と変わらない。もちろん美味しいレストラン、そして子どもが気軽に来られるような工夫は重要だろう。
K 学芸員には、「美術は社会の中で特別である。そして、一部な人の特殊技術を紹介する場が美術館だ。」という認識があるのではないか。それは良くない点だ。専門性を要求されるのはやむを得ないにしろ、それと一般性とにどう折り合いを付けるかが問われている。
S 学芸員の仕事は極めて多岐に及んでいる。様々な点において外部の風を入れるのは重要。そしてその専門性は学芸員の視点ではなく、美術館の外にあるかもしれない。
K 美術館では6年ぶりの個展。日本でも3回やっている。先日、「これからは美術館に戻るのか。」と聞かれたが、そういうつもりは全くない。むしろ美術館だからどうだというような、その場所に対してのこだわりはない。
S 自分の仕事以外で美術館に行くことがあるか。
K 殆ど行かない。関心のある作家が10人いたとしたら、そのうちせいぜい1つの展示を見る程度だろう。それに、同時進行のプロジェクトをかかえる自分の仕事上、美術館で他の展示を見たりするなどの余裕がない。本音を言ってしまえば、美術館が好きでないということかもしれないが。MOTでは確か94年の展示に参加している。それ以降、ここへ来たのは、NHKの取材で付き合った榎倉の個展のみ。
S MOTの印象はどうか。
K スペースがともかく巨大。上下、遠近については比較的自由に使えるが、石造りの外観は堅牢で、いかにも権威主義的。横浜のトリエンナーレで使った倉庫とは正反対だ。人がどう動いていくのかというイメージがなかなか描けない。だからこそ今回の展示は、ヒューマンスケールでどういう動きが出来るのかを考えた。
S ヒューマンスケールは、今回の一つのキーワードかもしれない。入場者同士の出会いの場、そして例えばラボのように、相互の活動が交流し合うような場面を見ることが出来る。
K アクティビティを美術館へ持ちこむ。多くのボランティアと準備したり、活動をラボで行ったり、ワークショップで現在進行形のアイデアを膨らませたりと、常に変化があるような場にした。アクティビティをそれぞれの時間で区切って、その「今」を提示し、さらに次に連続して繋げる。この展覧会ではそういった日常性を大切にしたい。
S よく入場者に「このラボは展示の後どうなるのか。」ということを聞かれる。それはいわゆる美術館で見る「作品」の行き先、または「完成」に対する一般的な考え方だ。今回はそうではなく、言わば「通り過ぎる途中」をそのまま見せているのではないか。これまでの川俣の仕事をこの美術館を使ってやっていること。始まりも終わりもなく、ただずっと続くとしか言えない。「完成」を求める入場者に対し、分からないことをそのまま提示しておく。
K 決して無責任というわけではないが、これらのプロジェクトは完成することがない。活動は永続的なもの。例えばある入院患者が治療を終え、一度退院した後、再度症状が出てまた入院することがある。治癒を、結果、または完成の意味と捉えれば、それを求めるのは極めて難しいのではないだろうか。完成という何かを残すのは、おそらく人がある特定の時間(人生)だけしか生きることが許されないため、その後にも自らの何かを残したいという憧れだろう。それに対して、別になくなっても良いではないか、また全てが整理されて完成されなくても良いではないかという気持ちを持っている。もちろん見に来る人々は納得しないかもしれない。この展覧会でも「いつが見頃か。」と聞かれることがあるが、その答えはない。
S そのようなある種の「永続」を見るため、今回の展示ではパスポートチケットも用意している。
K いかにその時間、場所と付き合っていくかという観点が重要。例えば外科的な手術で治療を施すのではなく、その病気とどう付き合って生きていくのかという感覚に近いかもしれない。「脱力系のアート」と言われても良い。盛り上がらないものの良さを見出したい。
S 今回の通路は300人のボランティアの手によって作られた。その光景を見ていると、彼らが「見る」よりも「作る」方が楽しいことを知ったような気がする。この展示では、作品と鑑賞者が対立する関係には決してならない。その場へ関与することが重要だ。そのために参加型のワークショップがある。
K 美術館で土嚢を積んで、ベニヤ板をたてると言うような、本来の場所のあり方から逸脱した行為にも面白さがあるのではないか。口コミレベルにまで降りて、美術館にある権威をとった上で、何かを共同で行う。
S 美術館の権威と作家のそれがあまりにも近過ぎるという指摘もある。
K 若い作家はむしろ美術館の権威を必要とするのが普通だろう。
S 美術館で開催するということと、外で開催することに違いはあるか。
K その違いはあっても気にしない。どちらが良いというわけではない。美術館であろうと、その外であろうと、関わり方は千差万別。
S 活動において、作品の自主性や、また社会との関わり方を川俣本人ではなく、ラボのメンバーが自由にすることもある。
K それを美術館の中でやるのが面白い。但し、美術館の中でやるということは、その活動が一種の見世物にもなるということだ。そしてその見せることに対して、今回どう応じるかを考えたつもりだ。
S 大学などで活動するのとはやはり違うのか。
K 全く異なる。大学での活動をそのまま美術館へ移したわけではない。先に「脱力系のアート」と言ったが、見世物としてどう盛り上げるのかも考えた。無気力と脱力は違う。また美術館の中で提示すると「作品的」に見えるのも事実だろう。その要素を取っ払った上にて、こういう展覧会も出来るのだということを見せたかった。
S ラボで見られる各プロジェクトのテーマの重いものが多いが。
K そのテーマの中で「嘘」をつくこともしたかった。言葉は悪いが、そうすることで真っ正直に取り組んだ場合と違う面が開けてくる。嘘とは一種のスルーとも言えるかもしれない。その重さをスルーしてかわすことで、別の展開を模索する。
S 例えば炭坑プロジェクトではどうなのか。
K シンボルとなるタワーをあえて建てない。ただ、周囲にはもう建てない方が良いと言われたのも事実だ。
S 鉄塔を建てることで街を再生させるイメージはどうなるのか。
K シンボルを否定して、淡々と進む日常を受け入れてしまうこと。ただ歩く、ただ進む、それが「通路」だ。どうやっていけばその「通路」と向かい合えるのかをその場で考えていく。
S 今回の展示では実際に「通路」が出来るプロセスを見たが、作る際にはどのようなことを考えているのか。
K 実は最初はかなり不安。何年か前にこの展示の話があったが、何をどうするかということについて色々悩んだ。またアイデアを発酵させる時間が重要だ。そしてもちろんこの「通路」も発酵させたい。先にコンセプトありきで細部をつめるやり方ではなく、むしろ細部を連ねて最後にある程度の体系的なものが見通せる方が良い。「通路」はその細部同士を繋ぐものに過ぎない。マラソンのようにスタートとゴールが結びついていた一本の道ではない。
ー ー ー
 「川俣正/通路/美術出版社」
「川俣正/通路/美術出版社」以上です。また最後に、質疑応答での氏の発言もいくつか記録しておきます。
Q 現代美術は自己満足なのか。
K 自己満足で当然。そして、その自己満足にお金を出す人々がいるこの社会がとても面白いと思う。
Q ベニヤを使った理由は。
K 誰でも扱える素材だから。美術に必要とされる特殊な技術は一切いらない。
Q 展示ファイルをめくったら監視員に注意された。
K 監視員が目をそらした隙にめくってください。
Q 通路に順路がある。
K 美術館側としては、中で迷ってしまう人がいるのが問題なのだろう。
このトークショーを含めた「通路」展の私の感想は、また別エントリに書きたいと思います。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
「MOTアニュアル 2008」 東京都現代美術館
東京都現代美術館(江東区三好4-1-1)
「MOTアニュアル 2008 - 解きほぐすとき - 」
2/9-4/13

毎年恒例、今回で第9回を数える「MOTアニュアル」です。今年は以下の5名の作家が登場していました。
金氏徹平(1978-)
高橋万里子(1970-)
立花文穂(1968-)
手塚愛子(1976-)
彦坂敏昭(1983-)

全体を通して見ると、その「解きほぐすとき」というキーワードも分からないわけではありませんが、この手のグループ展はむしろ頭を真っ白にして、まさに感性の趣くままに見た方が気軽に楽しめます。高橋万里子のポートレートでは、前半部の人形をモチーフとした作品よりも、彼女の母を捉えたという連作7点のシリーズの方がより魅力的です。スポットライトを強く浴びた一人の女性が、ポーズこそ異なれども、何やら『考える人』のような面持ちにて写し出されています。独得の焦点のぼやけた肖像と、その背景に写る深い影が、あたかも女性の思考の揺らぎ、または逡巡する様子を差し示しているようにも思えました。しばらく眺めていると、彼女より由来するどことない不安感を覚える作品です。作家とモデルとの親密性が、見る側にも作品との一体感をもたらしているのかもしれません。

金氏徹平では混在する素材によって生み出された奇怪な構造物に、まるでホワイトチョコかホイップクリームのような白色塗料(石膏か樹脂でしょうか。)を塗りかけた作品が印象に残ります。オモチャの車やパイプ、それにどこでもあり得るようなプラスチックケースやカゴを組み上げて、さながら巨大ウエディングケーキとも建物ともいえるようなオブジェを生み出していました。そしてそれと同様の趣向による、6点の小品もまた可愛気です。何個かに連なるハサミが白に浸り、またビールの泡ような王冠型の白がグラスより飛び跳ねていました。各素材の本来の質感を喪失させ、白の持つ力で特異な美しさをもたらすその手法に感心させられます。それに白関連としては、日常に潜む意外な美感を軽妙に写真へ表した「white heat」も見応えがありました。シャッターの閉まる地下街の白い蛍光灯や、白い泡に包まれた洗車中の車があれほどの美しく思えたのは初めてです。
5名の中で最も惹かれたのは、横11メートルにも及ぶ巨大な織物がともかく圧倒的な手塚愛子でした。「層の機」(2008)と名付けられたそのタペストリーには、花や鳥などのモチーフがモザイク状になって雅やかに描かれています。黄色やオレンジなどの華やかな色調とは裏腹に、どこか宗教画の大作を見ているような気持ちにもさせられる不思議な作品です。またもう一点、赤と深い緑の油彩が対になった「空白と充満を同時にぶら下げる」(2004)も見応えがありました。桔梗の花のようなシルエットや、レースのような模様が、暗い色調より仄かに浮かび上がっています。あたかも実際にレース、もしくは糸をキャンバスへと織り込んでいるかのようです。
金氏はワンダーサイト渋谷(~3/2)、また手塚は第一生命南ギャラリー(~3/11)で、それに高橋は川崎市民ミュージアム(~3/30まで)でそれぞれ個展、もしくはグループ展を開催しています。機会があればその展示も見に行きたいと思いました。(彦坂は3/7より資生堂art eggで個展。)
4月13日までの開催です。
「MOTアニュアル 2008 - 解きほぐすとき - 」
2/9-4/13

毎年恒例、今回で第9回を数える「MOTアニュアル」です。今年は以下の5名の作家が登場していました。
金氏徹平(1978-)
高橋万里子(1970-)
立花文穂(1968-)
手塚愛子(1976-)
彦坂敏昭(1983-)

全体を通して見ると、その「解きほぐすとき」というキーワードも分からないわけではありませんが、この手のグループ展はむしろ頭を真っ白にして、まさに感性の趣くままに見た方が気軽に楽しめます。高橋万里子のポートレートでは、前半部の人形をモチーフとした作品よりも、彼女の母を捉えたという連作7点のシリーズの方がより魅力的です。スポットライトを強く浴びた一人の女性が、ポーズこそ異なれども、何やら『考える人』のような面持ちにて写し出されています。独得の焦点のぼやけた肖像と、その背景に写る深い影が、あたかも女性の思考の揺らぎ、または逡巡する様子を差し示しているようにも思えました。しばらく眺めていると、彼女より由来するどことない不安感を覚える作品です。作家とモデルとの親密性が、見る側にも作品との一体感をもたらしているのかもしれません。

金氏徹平では混在する素材によって生み出された奇怪な構造物に、まるでホワイトチョコかホイップクリームのような白色塗料(石膏か樹脂でしょうか。)を塗りかけた作品が印象に残ります。オモチャの車やパイプ、それにどこでもあり得るようなプラスチックケースやカゴを組み上げて、さながら巨大ウエディングケーキとも建物ともいえるようなオブジェを生み出していました。そしてそれと同様の趣向による、6点の小品もまた可愛気です。何個かに連なるハサミが白に浸り、またビールの泡ような王冠型の白がグラスより飛び跳ねていました。各素材の本来の質感を喪失させ、白の持つ力で特異な美しさをもたらすその手法に感心させられます。それに白関連としては、日常に潜む意外な美感を軽妙に写真へ表した「white heat」も見応えがありました。シャッターの閉まる地下街の白い蛍光灯や、白い泡に包まれた洗車中の車があれほどの美しく思えたのは初めてです。
5名の中で最も惹かれたのは、横11メートルにも及ぶ巨大な織物がともかく圧倒的な手塚愛子でした。「層の機」(2008)と名付けられたそのタペストリーには、花や鳥などのモチーフがモザイク状になって雅やかに描かれています。黄色やオレンジなどの華やかな色調とは裏腹に、どこか宗教画の大作を見ているような気持ちにもさせられる不思議な作品です。またもう一点、赤と深い緑の油彩が対になった「空白と充満を同時にぶら下げる」(2004)も見応えがありました。桔梗の花のようなシルエットや、レースのような模様が、暗い色調より仄かに浮かび上がっています。あたかも実際にレース、もしくは糸をキャンバスへと織り込んでいるかのようです。
金氏はワンダーサイト渋谷(~3/2)、また手塚は第一生命南ギャラリー(~3/11)で、それに高橋は川崎市民ミュージアム(~3/30まで)でそれぞれ個展、もしくはグループ展を開催しています。機会があればその展示も見に行きたいと思いました。(彦坂は3/7より資生堂art eggで個展。)
4月13日までの開催です。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
「MOTコレクション ポップ道」 東京都現代美術館(常設展示)
東京都現代美術館(江東区三好4-1-1)
「MOTコレクション ポップ道:1960s-2000s」
2007/10/20-2008/4/13

昨年秋より開催されている展示ですが、先日、川俣、アニュアル展を見た際、改めて楽しむことにしました。東京都現代美術館の常設展より、1階のスペースを用いて展開されているポップアートの特集です。

失礼ながらも以前はMOT常設展にあまり良いイメージがありませんでしたが、新収蔵品もお目見えした昨年度の第一期コレクション展より、打って変わっての見応えのある企画が続いているように思えます。今回のテーマは言うまでもなくポップアートです。同美術館オープンの際にその高額な購入費において物議を醸し出したというリキテンシュタインの名画、「ヘア・リボンの少女」(1965)から、新美オープニングの「美術探検」展のちらし表紙も飾った、トム・ウェッセルマンの「浴槽コラージュ#2」(1963)などの『古典』はもちろん、横尾、小沢剛、奈良、森村、それにこれをポップとして良いのかどうか悩んでもしまう会田の「戦争画」シリーズなど、近年の日本のアーティストらの作品もかなり揃っていました。藤本の「EARS WITH CHAIR」に腰をかけ、耳を傾けながら、スゥのレイヤーを通じた青い光を感じることは、宮島の圧倒的なカウンターと並び、この美術館の楽しみ方の定番の一つにもなったのではないでしょうか。その掴みは抜群です。
大回顧展ではその物量に圧倒されてしまい、逆にあまり印象に残らなかった大竹伸朗ですが、ここでは「ぬりどき日本列島」(1997)がなかなか面白い作品です。何と全64点にも及ぶという塗り絵がずらりと並んでいますが、そこにこめられたアイロニカルな視点と、それを体現するかのような安吾の絵に、思わずこちらもつられて笑ってしまいます。全く整理されていない、散らかった部屋で安吾が佇むデラックス塗り絵を仕上げるのは相当に大変そうです。


奈良美智の二点のポートレートと、アレックス・カッツの同じく二点のそれの組み合わせ(7室)が意外にもマッチしていていました。愛くるしさとどこか睨みつけるような相反する目で鑑賞者を見つめる奈良の「White Night」(2006)と、映画のワンシーンのような、言い換えればあたかもこの場に偶然居合わせて、またすぐに消え去ってしまうかのようなカッツの「リンダ」(1989)の存在が、お互いを意識せずとも確実に交差しています。またその裏手、8室でのリンゴに扮した森村の「批評とその愛人A」(1990)と、布の人形が本当に話しているように見えるアウスラーのオブジェ、「1.2.3」(1996)もこれまた奇妙に調和している作品です。布の人形の顔が話し出すイメージを、森村のリンゴに置き換えたらまた面白いのではないでしょうか。

これより続く常設展3階では、収蔵先の選定に難儀しているのか、岡本太郎の「明日の神話」が会期延長で公開中です。(6/29まで)こちらも必見です。
ポップ道(MOTコレクション第4期)は4月13日まで開催されています。
「MOTコレクション ポップ道:1960s-2000s」
2007/10/20-2008/4/13

昨年秋より開催されている展示ですが、先日、川俣、アニュアル展を見た際、改めて楽しむことにしました。東京都現代美術館の常設展より、1階のスペースを用いて展開されているポップアートの特集です。

失礼ながらも以前はMOT常設展にあまり良いイメージがありませんでしたが、新収蔵品もお目見えした昨年度の第一期コレクション展より、打って変わっての見応えのある企画が続いているように思えます。今回のテーマは言うまでもなくポップアートです。同美術館オープンの際にその高額な購入費において物議を醸し出したというリキテンシュタインの名画、「ヘア・リボンの少女」(1965)から、新美オープニングの「美術探検」展のちらし表紙も飾った、トム・ウェッセルマンの「浴槽コラージュ#2」(1963)などの『古典』はもちろん、横尾、小沢剛、奈良、森村、それにこれをポップとして良いのかどうか悩んでもしまう会田の「戦争画」シリーズなど、近年の日本のアーティストらの作品もかなり揃っていました。藤本の「EARS WITH CHAIR」に腰をかけ、耳を傾けながら、スゥのレイヤーを通じた青い光を感じることは、宮島の圧倒的なカウンターと並び、この美術館の楽しみ方の定番の一つにもなったのではないでしょうか。その掴みは抜群です。
大回顧展ではその物量に圧倒されてしまい、逆にあまり印象に残らなかった大竹伸朗ですが、ここでは「ぬりどき日本列島」(1997)がなかなか面白い作品です。何と全64点にも及ぶという塗り絵がずらりと並んでいますが、そこにこめられたアイロニカルな視点と、それを体現するかのような安吾の絵に、思わずこちらもつられて笑ってしまいます。全く整理されていない、散らかった部屋で安吾が佇むデラックス塗り絵を仕上げるのは相当に大変そうです。


奈良美智の二点のポートレートと、アレックス・カッツの同じく二点のそれの組み合わせ(7室)が意外にもマッチしていていました。愛くるしさとどこか睨みつけるような相反する目で鑑賞者を見つめる奈良の「White Night」(2006)と、映画のワンシーンのような、言い換えればあたかもこの場に偶然居合わせて、またすぐに消え去ってしまうかのようなカッツの「リンダ」(1989)の存在が、お互いを意識せずとも確実に交差しています。またその裏手、8室でのリンゴに扮した森村の「批評とその愛人A」(1990)と、布の人形が本当に話しているように見えるアウスラーのオブジェ、「1.2.3」(1996)もこれまた奇妙に調和している作品です。布の人形の顔が話し出すイメージを、森村のリンゴに置き換えたらまた面白いのではないでしょうか。

これより続く常設展3階では、収蔵先の選定に難儀しているのか、岡本太郎の「明日の神話」が会期延長で公開中です。(6/29まで)こちらも必見です。
ポップ道(MOTコレクション第4期)は4月13日まで開催されています。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
「ロートレック展」 サントリー美術館
サントリー美術館(港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン・ガーデンサイド)
「ロートレック展 パリ、美しき時代を生きて」
1/26-3/9

移転リニューアル後、同美術館では初めてとなる西洋絵画の展覧会です。版画、ポスター、油彩、挿絵、素描など全250点の作品(出品リスト)にて、世紀末のパリを足早に駆け抜けたロートレック(1864-1901)の画業を俯瞰します。
ロートレックをこれほどまとめて観賞するのは初めてですが、今回の展示で特に見入ったのは、作品の大半を占めていたポスターではなく、日本初出品であるというオルセーの所蔵品を中心とした油彩絵画群でした。ちらし表紙を飾る「黒いボアの女」(1892)は、ロートレックに特徴的な線描、つまりは簡素でありながらも、どこか執拗に塗られたような表現が、対象の一瞬の動きを封じ込めるかのようにして捉えた見事な作品です。木の葉を振りかけたような、地の色もそのままにした線が体や腕の肉付きを大胆に表し、またその反面での塗り込まれた白い顔が彼女の表情を丁寧に伝えています。手を腰にまわし、睨みをきかすような面持ちに、思わず後ずさりしてしまうような勢いも感じました。


冴えた構図を見る作品が目立ちますが、スカートをたくしあげたダンサーを後ろから捉えた「大開脚」(1893)はとりわけ魅力的です。キャプションにある浮世絵の影響はそれほど感じられませんでしたが、ダイナミックに蹴り上げるダンサーの前景とそれを覗き込む観客の後景との対比、またはステージをスカート部分を同じ地の色で表現してしまう器用な塗りわけには強く感心させられました。また後ろといえば、半裸で座りながら身繕いする女性を後方上部からの視点で描く「赤毛の女」(1889)も印象に残ります。背中が語り出してくるかのようなその構図もさることながら、透き通るかのような白と薄い青の色遣いが絶品です。繊細な感性を見出します。
ムーラン街の娼婦を描いた「サロンにて、ソファ」(1893)も、その色の魅力に長けた作品と言えるのではないでしょうか。どこか気怠い様にて、おそらくは仕事前に休憩をとる彼女らが表されていますが、画面を支配する朱色の深みはまるでゴーガンを思わせるものです。もちろんこの作品だけによるものではありませんが、世紀末パリの一種の混沌とした日常の一コマを、これほどの臨場感をたたえて描くとはまさに見事の一言に尽きます。実際のところ、これまでロートレックにはあまり惹かれたことがありませんでしたが、これらの油彩だけでも彼の稀な画力を十分に感じることが出来ました。噛めばかむほどその魅力が増していきます。
先日の日曜日の夕方に観賞しましたが、入場待ちの列が出来るほど混雑していました。会期末には会場の熱気もさらに高まりそうです。
3月9日まで開催されています。
「ロートレック展 パリ、美しき時代を生きて」
1/26-3/9

移転リニューアル後、同美術館では初めてとなる西洋絵画の展覧会です。版画、ポスター、油彩、挿絵、素描など全250点の作品(出品リスト)にて、世紀末のパリを足早に駆け抜けたロートレック(1864-1901)の画業を俯瞰します。
ロートレックをこれほどまとめて観賞するのは初めてですが、今回の展示で特に見入ったのは、作品の大半を占めていたポスターではなく、日本初出品であるというオルセーの所蔵品を中心とした油彩絵画群でした。ちらし表紙を飾る「黒いボアの女」(1892)は、ロートレックに特徴的な線描、つまりは簡素でありながらも、どこか執拗に塗られたような表現が、対象の一瞬の動きを封じ込めるかのようにして捉えた見事な作品です。木の葉を振りかけたような、地の色もそのままにした線が体や腕の肉付きを大胆に表し、またその反面での塗り込まれた白い顔が彼女の表情を丁寧に伝えています。手を腰にまわし、睨みをきかすような面持ちに、思わず後ずさりしてしまうような勢いも感じました。


冴えた構図を見る作品が目立ちますが、スカートをたくしあげたダンサーを後ろから捉えた「大開脚」(1893)はとりわけ魅力的です。キャプションにある浮世絵の影響はそれほど感じられませんでしたが、ダイナミックに蹴り上げるダンサーの前景とそれを覗き込む観客の後景との対比、またはステージをスカート部分を同じ地の色で表現してしまう器用な塗りわけには強く感心させられました。また後ろといえば、半裸で座りながら身繕いする女性を後方上部からの視点で描く「赤毛の女」(1889)も印象に残ります。背中が語り出してくるかのようなその構図もさることながら、透き通るかのような白と薄い青の色遣いが絶品です。繊細な感性を見出します。
ムーラン街の娼婦を描いた「サロンにて、ソファ」(1893)も、その色の魅力に長けた作品と言えるのではないでしょうか。どこか気怠い様にて、おそらくは仕事前に休憩をとる彼女らが表されていますが、画面を支配する朱色の深みはまるでゴーガンを思わせるものです。もちろんこの作品だけによるものではありませんが、世紀末パリの一種の混沌とした日常の一コマを、これほどの臨場感をたたえて描くとはまさに見事の一言に尽きます。実際のところ、これまでロートレックにはあまり惹かれたことがありませんでしたが、これらの油彩だけでも彼の稀な画力を十分に感じることが出来ました。噛めばかむほどその魅力が増していきます。
先日の日曜日の夕方に観賞しましたが、入場待ちの列が出来るほど混雑していました。会期末には会場の熱気もさらに高まりそうです。
3月9日まで開催されています。
コメント ( 14 ) | Trackback ( 0 )
「諏訪敦 絵画作品展」 佐藤美術館
佐藤美術館(新宿区大京町31-10)
「諏訪敦 絵画作品展 複眼リアリスト」
1/17-2/24

卓越したリアリスム表現によって表される人物は、制作者諏訪が心に想う、一種の幻影なのかもしれません。日本の写実系絵画のきっかけを作った(*)ともいう、諏訪敦の個展です。初期作品、及び前衛舞踏家大野一雄に取材した一連のシリーズ、またはかの有名な女性の裸体などの絵画が紹介されています。

肌の皺、眉の生え際、そして唇の襞から黒子、さらには吹き出物など、まずは諏訪の「超絶的描写能力」(*)に裏打ちされた細やかな表現に目を奪われるところですが、しばらくその前に立っていると落ち着かない、奇妙な感覚に襲われました。それは不在の感覚、また言い換ればリアルな表現を通して現れる、半ば対象を捉えられないもどかしさです。実際、諏訪は対象の人物と生活空間を共有するほどの関係を築いてから制作に取り組むそうですが、結果、生まれてきたのは、むしろその実体が支持体に乗り切らない、言わば重量感のない、古びた石膏像をそのまま写したような絵画でした。リアルな描写を突き詰め、その細部の細部までを半ば写し絵として描けば描くほど、これが逆にあくまでも対象を離れた絵画であるという感覚がずしりと重くのしかかってきます。一般的な意味においてこれほどリアルであるのに、どこか矛盾した虚しさを感じるのはそのためかもしれません。
諏訪が時にシュールに、特に近作において夢想的な構図な手がけているのは、そのような不在の感覚を自身でも確かに肌で感じ取っているからではないでしょうか。彼が上でも触れた対象への全人格的な取材、もしくはその時間の共有は、どのようなリアルな表現でも絵画で表せない、言わば足りない部分を補うための一種の免罪符として行っている行為として捉えられるようにも感じられます。単に写実的というだけでない、むしろその奥から立ち上がってくる幻影こそが、諏訪作品を大きく支配しているのです。
全体の印象からすれば、これらの作品を写実や技巧という言葉で括ってしまうのには相当な抵抗感があります。実体と表された像の隙間、言わば魂の浮遊した影を示していることに、諏訪の大きな魅力があるのではないでしょうか。
本日、日曜日まで開催されています。
*ちらしより引用。
「諏訪敦 絵画作品展 複眼リアリスト」
1/17-2/24

卓越したリアリスム表現によって表される人物は、制作者諏訪が心に想う、一種の幻影なのかもしれません。日本の写実系絵画のきっかけを作った(*)ともいう、諏訪敦の個展です。初期作品、及び前衛舞踏家大野一雄に取材した一連のシリーズ、またはかの有名な女性の裸体などの絵画が紹介されています。

肌の皺、眉の生え際、そして唇の襞から黒子、さらには吹き出物など、まずは諏訪の「超絶的描写能力」(*)に裏打ちされた細やかな表現に目を奪われるところですが、しばらくその前に立っていると落ち着かない、奇妙な感覚に襲われました。それは不在の感覚、また言い換ればリアルな表現を通して現れる、半ば対象を捉えられないもどかしさです。実際、諏訪は対象の人物と生活空間を共有するほどの関係を築いてから制作に取り組むそうですが、結果、生まれてきたのは、むしろその実体が支持体に乗り切らない、言わば重量感のない、古びた石膏像をそのまま写したような絵画でした。リアルな描写を突き詰め、その細部の細部までを半ば写し絵として描けば描くほど、これが逆にあくまでも対象を離れた絵画であるという感覚がずしりと重くのしかかってきます。一般的な意味においてこれほどリアルであるのに、どこか矛盾した虚しさを感じるのはそのためかもしれません。
諏訪が時にシュールに、特に近作において夢想的な構図な手がけているのは、そのような不在の感覚を自身でも確かに肌で感じ取っているからではないでしょうか。彼が上でも触れた対象への全人格的な取材、もしくはその時間の共有は、どのようなリアルな表現でも絵画で表せない、言わば足りない部分を補うための一種の免罪符として行っている行為として捉えられるようにも感じられます。単に写実的というだけでない、むしろその奥から立ち上がってくる幻影こそが、諏訪作品を大きく支配しているのです。
全体の印象からすれば、これらの作品を写実や技巧という言葉で括ってしまうのには相当な抵抗感があります。実体と表された像の隙間、言わば魂の浮遊した影を示していることに、諏訪の大きな魅力があるのではないでしょうか。
本日、日曜日まで開催されています。
*ちらしより引用。
コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )
「浮世絵の夜景」 太田記念美術館
太田記念美術館(渋谷区神宮前1-10-10)
「浮世絵の夜景」
2/1-2/26
どちらかというと夏向きの展示かもしれませんが、浮世絵における夜景の表現も趣き深いものがあります。江戸、及び明治の夜景を表した浮世絵、全70点にて構成された展覧会です。

チラシ表紙を飾るこの作品が展覧会の目玉かもしれません。お馴染みの畳敷きの肉筆コーナーで一際異彩を放っていたのは、葛飾応為の「吉原格子先の図」でした。江戸博の北斎展における、エキゾチックで西洋画風の浮世絵も記憶に新しいところですが、この応為作を見るとそれらの作品を思い起こします。明暗の大胆なコントラストに、格子をのぞき込むシルエット状の人々、そしてその置物のような形状、さらには鳥瞰的な遠近法などに、西洋画の影響を見ることが出来るのではないでしょうか。実際のところ、かの里帰り作とどう関係しているのかは不明ですが、一風変わった感覚が魅力的に感じられました。
例えば夜桜、花火、月見など、夜に情緒を見出す日本人の感性を楽しめるのも嬉しいところです。夜桜では、シルエットになった木と粉雪のように散る花びらが対比的な広重の「隅田堤闇夜の桜」、また月見では、三枚合わせの大判の画面に、茶屋の二階でどこか退廃の風を漂わせながら月を見やる清長の「大川端楼上の月見」などに惹かれました。また『昼夜比べ』と題して、同じ場所を昼と夜に描き分けた、小林清親の「茶の水雪」と「御茶水蛍」も見応えがあります。中央線開通前の鬱蒼とした木立の覆うお茶の水を、一点は昼景の冬景色にて、またもう一点は闇よりぽっと浮かび上がる蛍の明かりにて叙情的に表していました。ちなみに今回の展覧会では、この小林ら、主に明治期以降に活躍した絵師の浮世絵も数多く展示されています。江戸と東京の夜景を見比べて見るのもまた一興です。
最後にはお待ちかねの巴水が登場していました。『巴水ブルー』も目に染みるお馴染みの夕景も出ていましたが、その中ではやや異質な「潮来の夕暮」が印象的です。上から順に、月、高木、小舟、またその影、そして手前の潮来の水面と、巴水の得意とする縦のラインが見事に示されていました。
館内にはかなり余裕がありました。今月26日までの開催です。
「浮世絵の夜景」
2/1-2/26
どちらかというと夏向きの展示かもしれませんが、浮世絵における夜景の表現も趣き深いものがあります。江戸、及び明治の夜景を表した浮世絵、全70点にて構成された展覧会です。

チラシ表紙を飾るこの作品が展覧会の目玉かもしれません。お馴染みの畳敷きの肉筆コーナーで一際異彩を放っていたのは、葛飾応為の「吉原格子先の図」でした。江戸博の北斎展における、エキゾチックで西洋画風の浮世絵も記憶に新しいところですが、この応為作を見るとそれらの作品を思い起こします。明暗の大胆なコントラストに、格子をのぞき込むシルエット状の人々、そしてその置物のような形状、さらには鳥瞰的な遠近法などに、西洋画の影響を見ることが出来るのではないでしょうか。実際のところ、かの里帰り作とどう関係しているのかは不明ですが、一風変わった感覚が魅力的に感じられました。
例えば夜桜、花火、月見など、夜に情緒を見出す日本人の感性を楽しめるのも嬉しいところです。夜桜では、シルエットになった木と粉雪のように散る花びらが対比的な広重の「隅田堤闇夜の桜」、また月見では、三枚合わせの大判の画面に、茶屋の二階でどこか退廃の風を漂わせながら月を見やる清長の「大川端楼上の月見」などに惹かれました。また『昼夜比べ』と題して、同じ場所を昼と夜に描き分けた、小林清親の「茶の水雪」と「御茶水蛍」も見応えがあります。中央線開通前の鬱蒼とした木立の覆うお茶の水を、一点は昼景の冬景色にて、またもう一点は闇よりぽっと浮かび上がる蛍の明かりにて叙情的に表していました。ちなみに今回の展覧会では、この小林ら、主に明治期以降に活躍した絵師の浮世絵も数多く展示されています。江戸と東京の夜景を見比べて見るのもまた一興です。
最後にはお待ちかねの巴水が登場していました。『巴水ブルー』も目に染みるお馴染みの夕景も出ていましたが、その中ではやや異質な「潮来の夕暮」が印象的です。上から順に、月、高木、小舟、またその影、そして手前の潮来の水面と、巴水の得意とする縦のラインが見事に示されていました。
館内にはかなり余裕がありました。今月26日までの開催です。
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )
「日本の版画 1941-1950 『日本の版画とは何か』」 千葉市美術館
千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)
「日本の版画 1941-1950 『日本の版画とは何か』」
1/12-3/2

1997年以来、何と足かけ12年にもわたって開催されてきた(*1)という、同美術館の「日本の版画」シリーズ第5弾(最終回)です。今回は第二次大戦前後、まさに「戦争に翻弄された」時代(パンフレットより)の版画史を辿ります。
章立ては以下の通りです。
1.「戦中の創作版画」
戦時体制下の版画制作。翼賛組織「日本版画奉公会」の発足。(1943)
2.「奉公する版画」
戦争のための版画。前線への版画(献納版画)の提供。プロパガンダ。
3.「戦中の版画本」
出版統制下、良質な作品を細々と世に送り出した出版人、志茂太郎とその周辺を追う。
4.「標本たちの箱庭 - 加藤太郎と杉原正己 - 」
同時代の二人の版画家。シュルレアリスムに傾倒した加藤太郎など。
5.「焦土より - 進駐軍と日本の版画 - 」
日本版画協会の再開。進駐軍が日本の版画を大量に購入。
6.「戦後 - 抽象と具象の間に - 」
版画表現が具象から抽象へと流れる一方、プロレタリア版画(生活版画)の制作も活発に。
7.「世界という舞台へ」
エピローグ。駒井哲郎、浜口陽三、瑛九ら。ビエンナーレにおける棟方への賞賛。版画国日本の復興。
上でも触れましたが、当然ながら、この時代の版画史は戦争と切り離せません。各種版画協会が1943年に翼賛の奉公会に統合されたことからして、その苦難の歴史を鑑みることが出来ますが、実際に展示されている作品のモチーフを見ても、戦争の影の濃いものが目立ちます。子どもたちが紙芝居に見入る様を表した武藤完一の「中国の風景」(1940年。1章)に登場する紙芝居の絵は、爆弾の炸裂する戦争の光景そのものです。また多くの版画家が共同して絵を提供したカレンダー、「日本版画協会カレンダー」の「1943年1月」(畦地梅太郎。1章)も、椰子の木の向こうに広がる海に軍艦がぽっかりと浮いていました。それに、軍人を英雄視した奥山儀八郎の「軍神加藤建夫少将像」(1943年。2章)や、戦時中、日本が主催した大東亜会議の出席者(東条首相など。)7名をモチーフにした「大東亜会議列席代表像(1943年。2章)」などは、版画と戦争体制との関係をもっと端的に示した作品とも言えるでしょう。雑誌「エッチング」(1943年。2章)の巻頭文が、この時代の雰囲気を象徴的に伝えています。そこには、「日本は世界唯一の版画国であり、版画は輸送船の中にも航空機の中にも兵隊の首嚢の中にも組み込まれる。」(一部改変)とあるわけです。


とは言え、戦中の作家でも、例えば第4章で紹介される二人、加藤太郎と杉原正己は独自の表現を貫いています。草花を重々しいタッチで示した杉原正己の「作品」(1944年)や、銃をモチーフにとりながらも、そこに蝶や羽を隠す加藤太郎の「JEU D' OBJET2 - 欲望」(1945)などは、この時代の一般的な具象版画と一味異なっていました。これらが戦後の抽象表現へと繋がっていく部分もありそうですが、病気に倒れ、後に除隊して版画を制作し続けたという加藤らにこうした自由な表現の息遣いが見られるのがまた興味深く感じられます。

戦後の版画はまさに百花繚乱です。進駐軍が日本の版画を買いあさったというエピソードは、何やら明治期に西洋へ流失した浮世絵の過程を想起させますが、ともかくもそれまで抑えられていた多用な表現が少しずつ開花していきます。先にカレンダーに軍艦を登場させた畦地では、鋭角的な線が寒々とした山の雪景色を描く「雪渓」(1952年。6章)が魅力的です。また稲垣知雄の「黒壺の花」(1948年。6章)は、まるでキュビズムのような錯綜した画面が浮かび上がっています。そして定番の浜口、駒井、恩地らの作家も多く紹介されていますが、その中では特に浜口の「臥婦」(1950年。7章)が印象に残りました。浜口の女性像というだけでも目新しく感じてしまいます。

全5回のうち、残念ながら最後の今回だけしか見られませんでしたが、同美術館の高い企画力に裏打ちされた非常に充実した展覧会と言えるのではないでしょうか。全240点にも及ぶ作品をじっくり見ていくと、いくら時間があっても足りないほどです。
3月2日まで開催されています。
*1 千葉市美術館「日本の版画」シリーズ
日本の版画1 1900-1910 「版のかたち百相」(1997/9/9-10/12)
日本の版画2 1911-1920 「刻まれた『個』の饗宴」(1999/9/21-10/24)
日本の版画3 1921-1930 「都市と女と光と影と」(2001/9/18-10/21)
日本の版画4 1931-1940 「棟方志功登場」(2004/8/31-10/3)
日本の版画5 1941-1950 「日本の版画とは何か」(2008/1/12-3/2)
*関連リンク
足かけ12年 シリーズ展「日本の版画」完結 千葉市美術館(asahi.com)
「日本の版画 1941-1950 『日本の版画とは何か』」
1/12-3/2

1997年以来、何と足かけ12年にもわたって開催されてきた(*1)という、同美術館の「日本の版画」シリーズ第5弾(最終回)です。今回は第二次大戦前後、まさに「戦争に翻弄された」時代(パンフレットより)の版画史を辿ります。
章立ては以下の通りです。
1.「戦中の創作版画」
戦時体制下の版画制作。翼賛組織「日本版画奉公会」の発足。(1943)
2.「奉公する版画」
戦争のための版画。前線への版画(献納版画)の提供。プロパガンダ。
3.「戦中の版画本」
出版統制下、良質な作品を細々と世に送り出した出版人、志茂太郎とその周辺を追う。
4.「標本たちの箱庭 - 加藤太郎と杉原正己 - 」
同時代の二人の版画家。シュルレアリスムに傾倒した加藤太郎など。
5.「焦土より - 進駐軍と日本の版画 - 」
日本版画協会の再開。進駐軍が日本の版画を大量に購入。
6.「戦後 - 抽象と具象の間に - 」
版画表現が具象から抽象へと流れる一方、プロレタリア版画(生活版画)の制作も活発に。
7.「世界という舞台へ」
エピローグ。駒井哲郎、浜口陽三、瑛九ら。ビエンナーレにおける棟方への賞賛。版画国日本の復興。
上でも触れましたが、当然ながら、この時代の版画史は戦争と切り離せません。各種版画協会が1943年に翼賛の奉公会に統合されたことからして、その苦難の歴史を鑑みることが出来ますが、実際に展示されている作品のモチーフを見ても、戦争の影の濃いものが目立ちます。子どもたちが紙芝居に見入る様を表した武藤完一の「中国の風景」(1940年。1章)に登場する紙芝居の絵は、爆弾の炸裂する戦争の光景そのものです。また多くの版画家が共同して絵を提供したカレンダー、「日本版画協会カレンダー」の「1943年1月」(畦地梅太郎。1章)も、椰子の木の向こうに広がる海に軍艦がぽっかりと浮いていました。それに、軍人を英雄視した奥山儀八郎の「軍神加藤建夫少将像」(1943年。2章)や、戦時中、日本が主催した大東亜会議の出席者(東条首相など。)7名をモチーフにした「大東亜会議列席代表像(1943年。2章)」などは、版画と戦争体制との関係をもっと端的に示した作品とも言えるでしょう。雑誌「エッチング」(1943年。2章)の巻頭文が、この時代の雰囲気を象徴的に伝えています。そこには、「日本は世界唯一の版画国であり、版画は輸送船の中にも航空機の中にも兵隊の首嚢の中にも組み込まれる。」(一部改変)とあるわけです。


とは言え、戦中の作家でも、例えば第4章で紹介される二人、加藤太郎と杉原正己は独自の表現を貫いています。草花を重々しいタッチで示した杉原正己の「作品」(1944年)や、銃をモチーフにとりながらも、そこに蝶や羽を隠す加藤太郎の「JEU D' OBJET2 - 欲望」(1945)などは、この時代の一般的な具象版画と一味異なっていました。これらが戦後の抽象表現へと繋がっていく部分もありそうですが、病気に倒れ、後に除隊して版画を制作し続けたという加藤らにこうした自由な表現の息遣いが見られるのがまた興味深く感じられます。

戦後の版画はまさに百花繚乱です。進駐軍が日本の版画を買いあさったというエピソードは、何やら明治期に西洋へ流失した浮世絵の過程を想起させますが、ともかくもそれまで抑えられていた多用な表現が少しずつ開花していきます。先にカレンダーに軍艦を登場させた畦地では、鋭角的な線が寒々とした山の雪景色を描く「雪渓」(1952年。6章)が魅力的です。また稲垣知雄の「黒壺の花」(1948年。6章)は、まるでキュビズムのような錯綜した画面が浮かび上がっています。そして定番の浜口、駒井、恩地らの作家も多く紹介されていますが、その中では特に浜口の「臥婦」(1950年。7章)が印象に残りました。浜口の女性像というだけでも目新しく感じてしまいます。

全5回のうち、残念ながら最後の今回だけしか見られませんでしたが、同美術館の高い企画力に裏打ちされた非常に充実した展覧会と言えるのではないでしょうか。全240点にも及ぶ作品をじっくり見ていくと、いくら時間があっても足りないほどです。
3月2日まで開催されています。
*1 千葉市美術館「日本の版画」シリーズ
日本の版画1 1900-1910 「版のかたち百相」(1997/9/9-10/12)
日本の版画2 1911-1920 「刻まれた『個』の饗宴」(1999/9/21-10/24)
日本の版画3 1921-1930 「都市と女と光と影と」(2001/9/18-10/21)
日本の版画4 1931-1940 「棟方志功登場」(2004/8/31-10/3)
日本の版画5 1941-1950 「日本の版画とは何か」(2008/1/12-3/2)
*関連リンク
足かけ12年 シリーズ展「日本の版画」完結 千葉市美術館(asahi.com)
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
「槙原泰介 『flooring』」 資生堂ギャラリー
資生堂ギャラリー(中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階)
「第2回 shiseido art egg 槙原泰介 flooring」
2/8-3/2

既製品を素材として用い、鑑賞者の五感に揺さぶりをかけるインスタレーションを手がける(公式HPより引用。一部改変。)という、槙原泰介の個展です。今回はある楽器が、さながら群生する木々のように空間を埋め尽くしています。
楽器の名をここに記してしまうと、実際の展示を見る面白さが半減してしまうので触れませんが、それは目にする機会も多い、その形を例えて言えば蓮の葉、もしくは大きな花とも出来るような楽器です。それがギャラリーの2つのホワイトキューブを所狭しと埋め尽くして、『林立』しています。すくっと立ち、また上部のライトへ向かって伸びていくかのような様子はどこか植物を連想させ、また逆にその無機質でミニマルな構成が、これらの全体を一種の装置であるような気配を生み出しています。確かに五感を働かせて、そのインスタレーションから何らかのイメージを汲み取っていきたい作品です。
先にこのインスタレーションを『木々』や『蓮の葉』とも例えましたが、下から見上げると前者のイメージが、また上から見下ろすと蓮の葉の群れ、つまりは蓮池を見ているような印象を受けました。コンセプトからして極めてシンプルではありますが、意外にも居心地の良い空間が立ち上がっています。

『ある楽器』を是非、会場で確かめてみて下さい。3月2日までの開催です。
*関連エントリ
「窪田美樹 DESHADOWED - かげとり」
「第2回 shiseido art egg 槙原泰介 flooring」
2/8-3/2

既製品を素材として用い、鑑賞者の五感に揺さぶりをかけるインスタレーションを手がける(公式HPより引用。一部改変。)という、槙原泰介の個展です。今回はある楽器が、さながら群生する木々のように空間を埋め尽くしています。
楽器の名をここに記してしまうと、実際の展示を見る面白さが半減してしまうので触れませんが、それは目にする機会も多い、その形を例えて言えば蓮の葉、もしくは大きな花とも出来るような楽器です。それがギャラリーの2つのホワイトキューブを所狭しと埋め尽くして、『林立』しています。すくっと立ち、また上部のライトへ向かって伸びていくかのような様子はどこか植物を連想させ、また逆にその無機質でミニマルな構成が、これらの全体を一種の装置であるような気配を生み出しています。確かに五感を働かせて、そのインスタレーションから何らかのイメージを汲み取っていきたい作品です。
先にこのインスタレーションを『木々』や『蓮の葉』とも例えましたが、下から見上げると前者のイメージが、また上から見下ろすと蓮の葉の群れ、つまりは蓮池を見ているような印象を受けました。コンセプトからして極めてシンプルではありますが、意外にも居心地の良い空間が立ち上がっています。

『ある楽器』を是非、会場で確かめてみて下さい。3月2日までの開催です。
*関連エントリ
「窪田美樹 DESHADOWED - かげとり」
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
N響定期 「マーラー:交響曲第9番」他
NHK交響楽団 第1614回定期公演Cプログラム
メシアン:キリストの昇天
マーラー:交響曲第9番
指揮 チョン・ミュンフン
管弦楽 NHK交響楽団
2007/2/15 19:00~ NHKホール3階
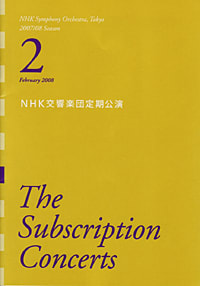
約8年ぶりとなるというチョン・ミュンフンの共演です。Cプロ初日に行ってきました。メシアンとマーラーの大作、交響曲第9番という重厚なプログラムです。
メインのマーラーについて端的に言ってしまうと、後半の第3、第4楽章が優れていたと思います。チョンの熱意もやや空回りしていた感のある前半部分とは異なって、非常に烈しいアレグロから一時の静寂、そしてほぼ弦楽合奏による濃厚な調べが、彼ならではのダイナミクスに長けた音楽によって表現されていました。金管も低調な、全体にもどこか冷めたN響を、特に第4楽章においてあれほど練り上げた彼の指揮は十分に賞賛に値するのではないでしょうか。率直なところ聴く前は、チョンとN響の組み合わせにあまり良いイメージが浮かびませんでしたが、滔々と流れながらも、それでいて情感豊かで芯も通ったアダージョを聴くと、彼がオーケストラに良い影響を与えたのは明らかだと思います。諦めを示すような極限のピアニッシモが続き、マーラーでさえ大き過ぎるホールに完全な静寂が訪れると、割れんばかりの拍手が鳴りわたりました。一階席では一部、スタンディングオベーションまで起きていたようですが、それはともかくも、まずは多く飛んでいたブラボーにも納得出来る演奏であったと思います。
チョンは音楽の横方向の流れを重視するのでしょうか。各フレーズを緩やかに繋ぎながら、時に爆発するように烈しくオケを鳴らしていました。その分、縦の線も要求される第一楽章ではやや揃わない印象が強く出てしまったわけですが、どこか吹っ切れたように飛ばした、まるでダンスミュージックのようなテンポをとる第3楽章が、それこそオーケストラに喝をあたえた格好になったのかもしれません。それ以降は、半ば目覚めたN響による充実した演奏を楽しむことが出来ました。
私自身、この曲には非常に思い入れがあるので、恥ずかしながらもそれが生で鳴るだけで感動してしまいますが、少なくとも初日の第4楽章は涙を誘うような感動的な演奏であったと思います。いわゆるうねりの有無等々、マーラー好きには賛否の分かれそうな部分もありましたが、まずは立ち直った後半部に、今後のチョンとN響とのコンビの可能性を見出したいところです。
メシアン:キリストの昇天
マーラー:交響曲第9番
指揮 チョン・ミュンフン
管弦楽 NHK交響楽団
2007/2/15 19:00~ NHKホール3階
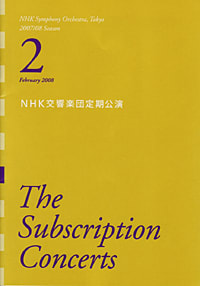
約8年ぶりとなるというチョン・ミュンフンの共演です。Cプロ初日に行ってきました。メシアンとマーラーの大作、交響曲第9番という重厚なプログラムです。
メインのマーラーについて端的に言ってしまうと、後半の第3、第4楽章が優れていたと思います。チョンの熱意もやや空回りしていた感のある前半部分とは異なって、非常に烈しいアレグロから一時の静寂、そしてほぼ弦楽合奏による濃厚な調べが、彼ならではのダイナミクスに長けた音楽によって表現されていました。金管も低調な、全体にもどこか冷めたN響を、特に第4楽章においてあれほど練り上げた彼の指揮は十分に賞賛に値するのではないでしょうか。率直なところ聴く前は、チョンとN響の組み合わせにあまり良いイメージが浮かびませんでしたが、滔々と流れながらも、それでいて情感豊かで芯も通ったアダージョを聴くと、彼がオーケストラに良い影響を与えたのは明らかだと思います。諦めを示すような極限のピアニッシモが続き、マーラーでさえ大き過ぎるホールに完全な静寂が訪れると、割れんばかりの拍手が鳴りわたりました。一階席では一部、スタンディングオベーションまで起きていたようですが、それはともかくも、まずは多く飛んでいたブラボーにも納得出来る演奏であったと思います。
チョンは音楽の横方向の流れを重視するのでしょうか。各フレーズを緩やかに繋ぎながら、時に爆発するように烈しくオケを鳴らしていました。その分、縦の線も要求される第一楽章ではやや揃わない印象が強く出てしまったわけですが、どこか吹っ切れたように飛ばした、まるでダンスミュージックのようなテンポをとる第3楽章が、それこそオーケストラに喝をあたえた格好になったのかもしれません。それ以降は、半ば目覚めたN響による充実した演奏を楽しむことが出来ました。
私自身、この曲には非常に思い入れがあるので、恥ずかしながらもそれが生で鳴るだけで感動してしまいますが、少なくとも初日の第4楽章は涙を誘うような感動的な演奏であったと思います。いわゆるうねりの有無等々、マーラー好きには賛否の分かれそうな部分もありましたが、まずは立ち直った後半部に、今後のチョンとN響とのコンビの可能性を見出したいところです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「熱狂の日」音楽祭2008 プログラム発表!
先週の金曜日の件ですが、今年のLFJのプログラムが発表されました。公式HPのタイムテーブルでは演奏者名が一覧出来ないので、pdfよりプリントアウトして見た方が分かり易そうです。

各日タイムテーブル
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
テーマは「シューベルトとウィーン」です。その要点を知るにはCLASSICAのブログ、もしくは公式HPの「10倍楽しむ方法」を参照するのがベストですが、ざっとそのプログラムに目を通しても、知名度の割には特定の曲ばかり演奏されるシューベルトとしては、かなり幅広いラインナップが用意されているように見えます。LFJの委嘱による現代作曲家の新作初演、または聞き慣れない宗教声楽曲、さらには当時のコンサートをそのまま再現するプログラムなど、優れた演奏者を安価に、しかもカジュアルな感覚で楽しむだけでない、LFJの奥深い魅力を知ることが出来る内容だと思いました。
全日、朝から晩まで張り付いてたくさんの公演を聴くことは私には出来ません。今年も昨年同様、2、3日通いながら、計6~7程度の公演を楽しむつもりです。これは是非という公演があれば教えていただけると嬉しいです。
チケットの発売までにはまだ少し時間があります。(会員先行2/23-、一般発売3/15-)去年の経験からいうと、ぴあ限定で手数料も何かとかかる会員先行発売のメリットはそれほどないような気もしましたが、ともかくも人気演奏家の公演は早々に完売となりそうです。発売までにプログラムと睨めっこして決めたいと思います。

各日タイムテーブル
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
テーマは「シューベルトとウィーン」です。その要点を知るにはCLASSICAのブログ、もしくは公式HPの「10倍楽しむ方法」を参照するのがベストですが、ざっとそのプログラムに目を通しても、知名度の割には特定の曲ばかり演奏されるシューベルトとしては、かなり幅広いラインナップが用意されているように見えます。LFJの委嘱による現代作曲家の新作初演、または聞き慣れない宗教声楽曲、さらには当時のコンサートをそのまま再現するプログラムなど、優れた演奏者を安価に、しかもカジュアルな感覚で楽しむだけでない、LFJの奥深い魅力を知ることが出来る内容だと思いました。
全日、朝から晩まで張り付いてたくさんの公演を聴くことは私には出来ません。今年も昨年同様、2、3日通いながら、計6~7程度の公演を楽しむつもりです。これは是非という公演があれば教えていただけると嬉しいです。
チケットの発売までにはまだ少し時間があります。(会員先行2/23-、一般発売3/15-)去年の経験からいうと、ぴあ限定で手数料も何かとかかる会員先行発売のメリットはそれほどないような気もしましたが、ともかくも人気演奏家の公演は早々に完売となりそうです。発売までにプログラムと睨めっこして決めたいと思います。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
「建築の記憶」 東京都庭園美術館
東京都庭園美術館(港区白金台5-21-9)
「建築の記憶 - 写真と建築の近現代 - 」
1/26-3/31

日本の建築物を、写真表現との関わりにおいて概観します。庭園美術館で開催中の「建築の記憶」へ行ってきました。
構成は7章立てです。建築写真、約400点ほどが出品されています。
1.「建築と写真の出会い」:日本の建築写真の原初。冨重利平「熊本城」(1872)。
2.「近代建築へのまなざし」:帝国議事堂、東京駅などの洋風建築。小川一眞「竹田宮邸」(1911)など。
3.「建築史学構築のための写真」:伊東忠太による建築調査。「北京宮城建築装飾」など。
4.「写真がとらえたモダンの相貌」:1930年以降、モダニズム建築を自由な写真表現で捉える。「現代住宅」(1933-40)。
5.「写真家の目、建築家の仕事」:前川國男と渡辺義雄、丹下健三と村井修。建築写真の確立。村井修「東京カテドラル」(1964)。
6.「日本建築の美」:桂離宮と伊勢神宮。石元泰博「桂離宮」(1981-82)。
7.「現代写真の建築」:杉本博司、畠山直哉、鈴木理策。

建築と写真の両表現を半ばクロスさせて見ていく展覧会です。幕末明治期、写真技術が流入するにあたって捉えられた江戸城の記録写真から、いつしか写真自体の表現に自主性が生まれ、例えば最近では杉本や理策など、対象を通した独自の美意識の露出する建築写真までの流れを見ることが出来ます。また、このような写真の立場ではなく、あくまでも建築の側、つまりは桂離宮から明治の洋風建築、そしてモダニズムから丹下、さらには青木淳の「青森県立美術館」というような、非常に大まかな一種の建築史を辿ることも可能です。もちろん展示物はあくまでも写真であるので、建築と写真とが客体と主体の関係にならざるを得ない部分はありますが、それでもその両者のスリリングなせめぎ合いを肌で感じることが出来ました。

興味深いのは、『建築のための写真』、例えば伊東忠太の調査取材や、前川建築の模型を捉えた渡辺の作品などです。どうも建築写真というと、例えば杉本作品の光の教会や、雪を驚くほど美しい質感で表現する理策などをイメージしてしまいますが、上に挙げた例の写真は、言わばその場の記憶をダイレクトに伝えています。北京城を写真におさめた伊東忠太は後、その詳細な意匠を木版に表して図版とした「北京宮城建築装飾」を手がけました。また前川のコンペ応募案の模型を捉えた「東京カテドラル応募案模型」(1962)は、実現し得なかったその空間を臨場感のある形で見るのに相応しい写真です。模型と写真とが共同して、まだ見ぬ建築物をそこに建てています。


時間差で桂離宮を捉えた二つのシリーズ、石元泰博の「桂」と「桂離宮」にも見応えがありました。まず50年代に写された「桂」では、全てモノクロームに還元された対象がさながら線と面とになって幾何学模様を描くのに対し、約30年の時を経て、修復後に撮影された「桂離宮」では、石畳や苔を含む趣き深い木造建築の気配が表されています。いつかは現地でじっくりと建物を拝見してみたいところです。

建築の展示は時に専門的過ぎて、私のような素人には難しいこともありますが、写真表現というフィルターを通すことでそうした要素を言わば低減させていました。構成は非常に意欲的なものですが、肩肘凝らずに楽しめます。
庭の梅もほころんでいました。3月末までの開催です。おすすめです。
「建築の記憶 - 写真と建築の近現代 - 」
1/26-3/31

日本の建築物を、写真表現との関わりにおいて概観します。庭園美術館で開催中の「建築の記憶」へ行ってきました。
構成は7章立てです。建築写真、約400点ほどが出品されています。
1.「建築と写真の出会い」:日本の建築写真の原初。冨重利平「熊本城」(1872)。
2.「近代建築へのまなざし」:帝国議事堂、東京駅などの洋風建築。小川一眞「竹田宮邸」(1911)など。
3.「建築史学構築のための写真」:伊東忠太による建築調査。「北京宮城建築装飾」など。
4.「写真がとらえたモダンの相貌」:1930年以降、モダニズム建築を自由な写真表現で捉える。「現代住宅」(1933-40)。
5.「写真家の目、建築家の仕事」:前川國男と渡辺義雄、丹下健三と村井修。建築写真の確立。村井修「東京カテドラル」(1964)。
6.「日本建築の美」:桂離宮と伊勢神宮。石元泰博「桂離宮」(1981-82)。
7.「現代写真の建築」:杉本博司、畠山直哉、鈴木理策。

建築と写真の両表現を半ばクロスさせて見ていく展覧会です。幕末明治期、写真技術が流入するにあたって捉えられた江戸城の記録写真から、いつしか写真自体の表現に自主性が生まれ、例えば最近では杉本や理策など、対象を通した独自の美意識の露出する建築写真までの流れを見ることが出来ます。また、このような写真の立場ではなく、あくまでも建築の側、つまりは桂離宮から明治の洋風建築、そしてモダニズムから丹下、さらには青木淳の「青森県立美術館」というような、非常に大まかな一種の建築史を辿ることも可能です。もちろん展示物はあくまでも写真であるので、建築と写真とが客体と主体の関係にならざるを得ない部分はありますが、それでもその両者のスリリングなせめぎ合いを肌で感じることが出来ました。

興味深いのは、『建築のための写真』、例えば伊東忠太の調査取材や、前川建築の模型を捉えた渡辺の作品などです。どうも建築写真というと、例えば杉本作品の光の教会や、雪を驚くほど美しい質感で表現する理策などをイメージしてしまいますが、上に挙げた例の写真は、言わばその場の記憶をダイレクトに伝えています。北京城を写真におさめた伊東忠太は後、その詳細な意匠を木版に表して図版とした「北京宮城建築装飾」を手がけました。また前川のコンペ応募案の模型を捉えた「東京カテドラル応募案模型」(1962)は、実現し得なかったその空間を臨場感のある形で見るのに相応しい写真です。模型と写真とが共同して、まだ見ぬ建築物をそこに建てています。


時間差で桂離宮を捉えた二つのシリーズ、石元泰博の「桂」と「桂離宮」にも見応えがありました。まず50年代に写された「桂」では、全てモノクロームに還元された対象がさながら線と面とになって幾何学模様を描くのに対し、約30年の時を経て、修復後に撮影された「桂離宮」では、石畳や苔を含む趣き深い木造建築の気配が表されています。いつかは現地でじっくりと建物を拝見してみたいところです。

建築の展示は時に専門的過ぎて、私のような素人には難しいこともありますが、写真表現というフィルターを通すことでそうした要素を言わば低減させていました。構成は非常に意欲的なものですが、肩肘凝らずに楽しめます。
庭の梅もほころんでいました。3月末までの開催です。おすすめです。
コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )
「日本の新進作家 vol.6 スティル/アライヴ」 東京都写真美術館
東京都写真美術館(目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)
「日本の新進作家 vol.6 スティル/アライヴ」
2007/12/22-2008/2/20

このシリーズを見るのは何年ぶりでしょうか。伊瀬聖子、屋代敏博、大橋仁、田中功起の4名のアーティストが、それぞれ思い思いに独自の表現を突き詰めます。写真美術館で開催中の「スティル/アライヴ」展へ行ってきました。

まず見入ったのは、先日、目黒区美で「銭湯」シリーズの印象深かった、屋代敏博のインスタレーションです。屋代といえば、時に繋がらない光景などを、縦の一線を軸に、左右へパノラマ的におさめてしまう写真が興味深いところですが、今回の「回転回LIVE!」シリーズでは、何とその中へ本人も含めた回転する人物を写し入れています。舞台は全国各地の学校です。これは屋代自身が現地に趣き、約2年ほどかけて学生、生徒の回転する様をフレームにおさめたそうですが、元々、グルリと一周して見やるような屋代の写真にさらなる動き、しかも今回は縦へのベクトルが加わっていて興味深く感じられました。また、回転する生徒たちが、静止した空間から駆け抜けていつの間にやら消えていく(卒業)とでもいえる、堅牢な学校(静止)とそれ(回転)との一種のズレが加わってもいます。それに、実際のプロジェクトを映したビデオも臨場感を高めていました。

美感に優れているという点でベストなのは、伊藤聖子の「スイミング・イン・クオリア」です。前方と左手に配された二枚の大型スクリーンに、同じ素材によりながらもイメージの異なる二つの映像を投影し、そこへさらに二種の音楽をシンクロさせています。異なった速度によって次々と移り変わる映像が、どこか重なりつつもありまた離れていくイメージの揺らぎを生み出し、またそれぞれに呼応するテンポの異なった音楽(一種はヘッドホンでの観賞。)が、時間と空間のリアルな感覚を喪失させていくような、夢見心地で幻想的な場を創出していました。映像と音楽とが半ば対角線上に交わる、明快なコンセプトも魅力の一つです。
最後の田中功起は、それこそ場の重みを解体してくれるような痛快なインスタレーションです。土地の記憶に依りながらも、用いられた素材と現実とのギャップを実にストレートな形で提示しています。ビール工場の映像が、ボーリングのピンを移動させる行程と重なって見えてなりません。映像内の工場より瓶を経由してのボーリング場、そしてさらに土地の記憶を経由しての美術館という空間の全てが、一本の糸で結ばれているような展示でもありました。
今月20日までの開催です。
「日本の新進作家 vol.6 スティル/アライヴ」
2007/12/22-2008/2/20

このシリーズを見るのは何年ぶりでしょうか。伊瀬聖子、屋代敏博、大橋仁、田中功起の4名のアーティストが、それぞれ思い思いに独自の表現を突き詰めます。写真美術館で開催中の「スティル/アライヴ」展へ行ってきました。

まず見入ったのは、先日、目黒区美で「銭湯」シリーズの印象深かった、屋代敏博のインスタレーションです。屋代といえば、時に繋がらない光景などを、縦の一線を軸に、左右へパノラマ的におさめてしまう写真が興味深いところですが、今回の「回転回LIVE!」シリーズでは、何とその中へ本人も含めた回転する人物を写し入れています。舞台は全国各地の学校です。これは屋代自身が現地に趣き、約2年ほどかけて学生、生徒の回転する様をフレームにおさめたそうですが、元々、グルリと一周して見やるような屋代の写真にさらなる動き、しかも今回は縦へのベクトルが加わっていて興味深く感じられました。また、回転する生徒たちが、静止した空間から駆け抜けていつの間にやら消えていく(卒業)とでもいえる、堅牢な学校(静止)とそれ(回転)との一種のズレが加わってもいます。それに、実際のプロジェクトを映したビデオも臨場感を高めていました。

美感に優れているという点でベストなのは、伊藤聖子の「スイミング・イン・クオリア」です。前方と左手に配された二枚の大型スクリーンに、同じ素材によりながらもイメージの異なる二つの映像を投影し、そこへさらに二種の音楽をシンクロさせています。異なった速度によって次々と移り変わる映像が、どこか重なりつつもありまた離れていくイメージの揺らぎを生み出し、またそれぞれに呼応するテンポの異なった音楽(一種はヘッドホンでの観賞。)が、時間と空間のリアルな感覚を喪失させていくような、夢見心地で幻想的な場を創出していました。映像と音楽とが半ば対角線上に交わる、明快なコンセプトも魅力の一つです。
最後の田中功起は、それこそ場の重みを解体してくれるような痛快なインスタレーションです。土地の記憶に依りながらも、用いられた素材と現実とのギャップを実にストレートな形で提示しています。ビール工場の映像が、ボーリングのピンを移動させる行程と重なって見えてなりません。映像内の工場より瓶を経由してのボーリング場、そしてさらに土地の記憶を経由しての美術館という空間の全てが、一本の糸で結ばれているような展示でもありました。
今月20日までの開催です。
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
「王朝の恋」 出光美術館
出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)
「描かれた伊勢物語 王朝の恋」
1/9-2/17

これなら伊勢物語の知識のない私でも楽しめます。主に宗達の「伊勢物語図色紙」にて恋物語を追いながら、それに取材した書画や工芸などを一堂に見る展覧会です。出光美術館の「王朝の恋」へ行ってきました。
この展覧会の対象が第一に伊勢物語ファンとされているのなら、第二は琳派ファンと言っても良いのではないでしょうか。実際、上記の宗達の色紙(約30点)をはじめ、伝宗達の「伊勢物語図屏風」、伝光琳、または抱一、芦舟の屏風絵など、かなり見応えのある琳派作品が揃っています。そしてそれらが集中して紹介されているのは、ちょうど展示の第三番目、「東下り」のセクションです。冒頭、「昔、男ありけり」で始まるかの有名な行が、琳派の絵師によって雅やかな絵画へと仕立てられています。

ある男が三河八橋の地に行き着き、そこで「かきつばた」の五文字を句にして歌に詠んだという八橋の主題では、酒井抱一の「八ッ橋図屏風」が白眉です。眩しいばかりの6曲1双の金屏風に配されているのは、右上から左下へと向かって進む橋に沿って繋がる燕子花の群れでした。ここでは、例えば光琳の燕子花に見るような逞しい造形美はなりを潜め、むしろその葉は水にそよぐ草のように、また花びらはあたかも蝶がとまるような姿にて穏やかに描かれています。また、ポスターカラーのような平面的な燕子花と、たらし込みを多用し、苔の緑も滲んだような瑞々しい橋の描写の対比も鮮やかでした。

抱一ではもう一点、光琳百図からそのモチーフを借りたとされる「宇津山図」も出品されています。駿河の宇津山にて男が修行者へ歌を託すという光景が、どこか乾山を思わせる軽妙なタッチにて描かれていました。またここで興味深いのは、伝宗達の「伊勢物語図屏風」との類似です。この屏風は宇津山や住吉行幸等々の場面を、図像的な雲霞によるそれこそ異時同図法にて巧みに表したものですが、宇津山の場面の構図が抱一の作とかなり似ています。ここに、伝宗達の元の屏風、光琳百図、そして抱一作の「宇津山図」と、いわゆる琳派の系譜を辿ることが出来るのかもしれません。

抱一の同名作も名高い、伝宗達の「月に秋草図屏風」も見応えがありました。殆ど地へ溶けて消えゆくかのような金色のすすきがか細く靡き、そこへに粉雪のような白い花々を付けた秋草が風雅に咲き乱れています。これと抱一作にどのような関連があるかは不明ですが、抱一のそれが、空と月を求めて秋草が大きく舞うという、どこか非現実的でシュールな秋の寂寞感を伝えるのに対し、宗達はもっと温かい眼差しを地に向けた、あたかも虫の声が聞こえ出すかのような秋の身近な情緒を巧みに示した作品とも言えるでしょう。見事な一枚でした。
会期末と、期間限定の「伊勢物語絵巻」(和泉市久保惣記念美術館所蔵)の展示が重なったからかもしれません。会場はかなり混雑していました。宗達の色紙の一角は行列です。
次の日曜日、17日まで開催されています。
「描かれた伊勢物語 王朝の恋」
1/9-2/17

これなら伊勢物語の知識のない私でも楽しめます。主に宗達の「伊勢物語図色紙」にて恋物語を追いながら、それに取材した書画や工芸などを一堂に見る展覧会です。出光美術館の「王朝の恋」へ行ってきました。
この展覧会の対象が第一に伊勢物語ファンとされているのなら、第二は琳派ファンと言っても良いのではないでしょうか。実際、上記の宗達の色紙(約30点)をはじめ、伝宗達の「伊勢物語図屏風」、伝光琳、または抱一、芦舟の屏風絵など、かなり見応えのある琳派作品が揃っています。そしてそれらが集中して紹介されているのは、ちょうど展示の第三番目、「東下り」のセクションです。冒頭、「昔、男ありけり」で始まるかの有名な行が、琳派の絵師によって雅やかな絵画へと仕立てられています。

ある男が三河八橋の地に行き着き、そこで「かきつばた」の五文字を句にして歌に詠んだという八橋の主題では、酒井抱一の「八ッ橋図屏風」が白眉です。眩しいばかりの6曲1双の金屏風に配されているのは、右上から左下へと向かって進む橋に沿って繋がる燕子花の群れでした。ここでは、例えば光琳の燕子花に見るような逞しい造形美はなりを潜め、むしろその葉は水にそよぐ草のように、また花びらはあたかも蝶がとまるような姿にて穏やかに描かれています。また、ポスターカラーのような平面的な燕子花と、たらし込みを多用し、苔の緑も滲んだような瑞々しい橋の描写の対比も鮮やかでした。

抱一ではもう一点、光琳百図からそのモチーフを借りたとされる「宇津山図」も出品されています。駿河の宇津山にて男が修行者へ歌を託すという光景が、どこか乾山を思わせる軽妙なタッチにて描かれていました。またここで興味深いのは、伝宗達の「伊勢物語図屏風」との類似です。この屏風は宇津山や住吉行幸等々の場面を、図像的な雲霞によるそれこそ異時同図法にて巧みに表したものですが、宇津山の場面の構図が抱一の作とかなり似ています。ここに、伝宗達の元の屏風、光琳百図、そして抱一作の「宇津山図」と、いわゆる琳派の系譜を辿ることが出来るのかもしれません。

抱一の同名作も名高い、伝宗達の「月に秋草図屏風」も見応えがありました。殆ど地へ溶けて消えゆくかのような金色のすすきがか細く靡き、そこへに粉雪のような白い花々を付けた秋草が風雅に咲き乱れています。これと抱一作にどのような関連があるかは不明ですが、抱一のそれが、空と月を求めて秋草が大きく舞うという、どこか非現実的でシュールな秋の寂寞感を伝えるのに対し、宗達はもっと温かい眼差しを地に向けた、あたかも虫の声が聞こえ出すかのような秋の身近な情緒を巧みに示した作品とも言えるでしょう。見事な一枚でした。
会期末と、期間限定の「伊勢物語絵巻」(和泉市久保惣記念美術館所蔵)の展示が重なったからかもしれません。会場はかなり混雑していました。宗達の色紙の一角は行列です。
次の日曜日、17日まで開催されています。
コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )
「田中麻記子 La deuxieme chambre」 高島屋東京店 美術画廊X
高島屋東京店6階 美術画廊X(中央区日本橋2-4-1)
「田中麻記子 La deuxieme chambre」
1/30-2/19

新宿高島屋に次ぐ『もう一つの部屋』は日本橋の高島屋です。巨大なウォールペインティングとともに、可愛らしくもシュールなドローイング数点が紹介されています。田中麻記子の個展です。
細密画と言っても良いのでしょうか。シャープペンシルを駆使して画面を埋め尽くすかのようにして描かれているのは、例えば人魚のような女性たちが登場する、どこか妖艶な趣の漂ったメルヘンの世界です。それが極めて細い線にて、それこそレースを重ねていくかのように、レイヤー状になって複層的に絡み合っています。大きく渦巻く空や、荒れ狂う海のような空間が連動して一つのダイナミックな場を作り出し、さらにそこへリボンなどの装飾的なモチーフが多元的に組合わさっていました。また細く、それに薄い木炭の感触に、限りなく仄かに施されたパステル色の水彩も魅力的ですが、全体を見ると、ドローイングというよりもコラージュ風のオブジェというような趣きが感じられます。実際、ミラーやリボンをそのまま用いた作品、及びネイルアートなども展示されていました。
年初に行われていた新宿の展示を見逃していたので助かりました。来週の火曜日、19日まで開催されています。
「田中麻記子 La deuxieme chambre」
1/30-2/19

新宿高島屋に次ぐ『もう一つの部屋』は日本橋の高島屋です。巨大なウォールペインティングとともに、可愛らしくもシュールなドローイング数点が紹介されています。田中麻記子の個展です。
細密画と言っても良いのでしょうか。シャープペンシルを駆使して画面を埋め尽くすかのようにして描かれているのは、例えば人魚のような女性たちが登場する、どこか妖艶な趣の漂ったメルヘンの世界です。それが極めて細い線にて、それこそレースを重ねていくかのように、レイヤー状になって複層的に絡み合っています。大きく渦巻く空や、荒れ狂う海のような空間が連動して一つのダイナミックな場を作り出し、さらにそこへリボンなどの装飾的なモチーフが多元的に組合わさっていました。また細く、それに薄い木炭の感触に、限りなく仄かに施されたパステル色の水彩も魅力的ですが、全体を見ると、ドローイングというよりもコラージュ風のオブジェというような趣きが感じられます。実際、ミラーやリボンをそのまま用いた作品、及びネイルアートなども展示されていました。
年初に行われていた新宿の展示を見逃していたので助かりました。来週の火曜日、19日まで開催されています。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
「横山大観 - 新たなる伝説へ - 」 国立新美術館
国立新美術館(港区六本木7-22-2)
「没後50年 横山大観 - 新たなる伝説へ - 」
1/23-3/3

仰々しい副題のついた展覧会です。初期より晩年の作、全75点にて大観の画業を概観します。国立新美術館での大観展へ行ってきました。

近代日本画の展示では必ず目にする大観ですが、このようなまとまった形で見るのは今回が初めてです。大観のコレクションでは聖地とも言える足立美術館をはじめ、東京藝大、東博、京博、その他、企業コレクションまで、全国各地より様々な作品が集まっています。そして大観が1904年、岡倉天心とともに訪れたアメリカでの作品(4点)が、史上初めて東京に『里帰り』していました。また昨年の東近美での特集展も記憶に新しい「生々流転」だけでなく、同じような長大な巻物形式(全長27メートル)をとる「四時山水」や、大倉集古館でもあまり出品されない「夜桜」などの大作群も紹介されています。一大回顧展に相応しいラインナップであるのは事実のようです。

作風、または画題も膨大な大観を一括りにするのは非常に困難ですが、私が一つ、彼の強い魅力として挙げたいのが水、または海の卓越した表現です。『大観ブルー』とも『海の大観』とでも称せるかもしれませんが、ともかく川や海が大観の手にかかると、実に瑞々しい美しさをたたえ、しかもそれが場面によって多様な表情を見せていきます。竹橋の常設展でもお馴染みの「南溟の夜」は傑作です。深い藍色をたたえて深淵に広がる海が、全てをのみ込むかのようにして陸地を洗っています。仄かに瞬く星屑と、海と一体となった大空も、どこか夢幻的なイメージを醸し出していました。


『海の大観』の美しさを見るには、「海潮四題」(1940)シリーズがベストかもしれません。これらの連作は、海景のみで四季を表すという、とても意欲的なものですが、例えば「冬」では凍り付く雪原のような寒々しい波を、また一変する「夏」では、岩場を襲いながら砕け散っていく波の様子が力強く示されています。そしてとりわけ充実しているのが、霞に包まれる大海原が広がる「春」です。清涼たる水色の海が光を浴び、その上にはあたかも春の到来を喜ぶかのような海鳥が舞っています。里帰り作品の一つ、初期の「月夜の波図」(1904)における透明感溢れる波の描写を見ても、大観が元々、海景に長けていたことが良く分かりますが、ともかく感心するのは、その染み渡るような水の色、そしてうねる波の美しさでした。

さて、展示で特に興味深いのは、先人たちとの対比という観点において、例えば光琳の「槇楓図屏風」と大観の「秋色」を一緒に紹介したセクションです。実際、大観はこの光琳作を見たのちに「秋色」を仕上げたということですが、私の目を通す限りにおいては、あまり両者に関連性があるようには感じられませんでした。光琳には木々にのびやかな動きのある、形態の面白さと型にはまらない奔放な構図の様子が見て取れますが、大観のそれは「夜桜」や「紅葉」などのような、画面をモチーフで埋め尽くす迫力の方が優先しています。また鹿の様子が描かれた左隻も、その余白の用い方においては光琳というよりも宗達に近いのではないでしょうか。この二点に関しては、大変失礼ながらも光琳作の方が『新しく』見えました。

大観と言えば富士ですが、やや食傷気味にも見えてしまうそれらの中で、ただ一点、とても惹かれた作品がありました。それがこの「霊峰十趣・夜」(1920)です。ここに描かれた富士は、有りがちな神々しさや威圧感を見るものとは異なり、どこか夜に微睡んで佇んでいるかのような、幻想を思う、優し気な表情をたたえています。スラッとした稜線を横にのばし、可愛らしくも照る三日月とあたかも話し合うかのような姿を見せてもいました。このような富士なら抵抗感はありません。
サブタイトルの『伝説』を汲み取るには、ただ展示作を眺めているだけでは足りないのかもしれません。作品には詳細なキャプションもなく、その謂れ等々に接するには、音声ガイド、または分厚い図録にあたるしかありませんでした。『伝説』を作るにしては、随分と構成が大味です。
集客は好調のようです。会場は相当混雑していました。3月3日まで開催されています。
「没後50年 横山大観 - 新たなる伝説へ - 」
1/23-3/3

仰々しい副題のついた展覧会です。初期より晩年の作、全75点にて大観の画業を概観します。国立新美術館での大観展へ行ってきました。

近代日本画の展示では必ず目にする大観ですが、このようなまとまった形で見るのは今回が初めてです。大観のコレクションでは聖地とも言える足立美術館をはじめ、東京藝大、東博、京博、その他、企業コレクションまで、全国各地より様々な作品が集まっています。そして大観が1904年、岡倉天心とともに訪れたアメリカでの作品(4点)が、史上初めて東京に『里帰り』していました。また昨年の東近美での特集展も記憶に新しい「生々流転」だけでなく、同じような長大な巻物形式(全長27メートル)をとる「四時山水」や、大倉集古館でもあまり出品されない「夜桜」などの大作群も紹介されています。一大回顧展に相応しいラインナップであるのは事実のようです。

作風、または画題も膨大な大観を一括りにするのは非常に困難ですが、私が一つ、彼の強い魅力として挙げたいのが水、または海の卓越した表現です。『大観ブルー』とも『海の大観』とでも称せるかもしれませんが、ともかく川や海が大観の手にかかると、実に瑞々しい美しさをたたえ、しかもそれが場面によって多様な表情を見せていきます。竹橋の常設展でもお馴染みの「南溟の夜」は傑作です。深い藍色をたたえて深淵に広がる海が、全てをのみ込むかのようにして陸地を洗っています。仄かに瞬く星屑と、海と一体となった大空も、どこか夢幻的なイメージを醸し出していました。


『海の大観』の美しさを見るには、「海潮四題」(1940)シリーズがベストかもしれません。これらの連作は、海景のみで四季を表すという、とても意欲的なものですが、例えば「冬」では凍り付く雪原のような寒々しい波を、また一変する「夏」では、岩場を襲いながら砕け散っていく波の様子が力強く示されています。そしてとりわけ充実しているのが、霞に包まれる大海原が広がる「春」です。清涼たる水色の海が光を浴び、その上にはあたかも春の到来を喜ぶかのような海鳥が舞っています。里帰り作品の一つ、初期の「月夜の波図」(1904)における透明感溢れる波の描写を見ても、大観が元々、海景に長けていたことが良く分かりますが、ともかく感心するのは、その染み渡るような水の色、そしてうねる波の美しさでした。

さて、展示で特に興味深いのは、先人たちとの対比という観点において、例えば光琳の「槇楓図屏風」と大観の「秋色」を一緒に紹介したセクションです。実際、大観はこの光琳作を見たのちに「秋色」を仕上げたということですが、私の目を通す限りにおいては、あまり両者に関連性があるようには感じられませんでした。光琳には木々にのびやかな動きのある、形態の面白さと型にはまらない奔放な構図の様子が見て取れますが、大観のそれは「夜桜」や「紅葉」などのような、画面をモチーフで埋め尽くす迫力の方が優先しています。また鹿の様子が描かれた左隻も、その余白の用い方においては光琳というよりも宗達に近いのではないでしょうか。この二点に関しては、大変失礼ながらも光琳作の方が『新しく』見えました。

大観と言えば富士ですが、やや食傷気味にも見えてしまうそれらの中で、ただ一点、とても惹かれた作品がありました。それがこの「霊峰十趣・夜」(1920)です。ここに描かれた富士は、有りがちな神々しさや威圧感を見るものとは異なり、どこか夜に微睡んで佇んでいるかのような、幻想を思う、優し気な表情をたたえています。スラッとした稜線を横にのばし、可愛らしくも照る三日月とあたかも話し合うかのような姿を見せてもいました。このような富士なら抵抗感はありません。
サブタイトルの『伝説』を汲み取るには、ただ展示作を眺めているだけでは足りないのかもしれません。作品には詳細なキャプションもなく、その謂れ等々に接するには、音声ガイド、または分厚い図録にあたるしかありませんでした。『伝説』を作るにしては、随分と構成が大味です。
集客は好調のようです。会場は相当混雑していました。3月3日まで開催されています。
コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ |









