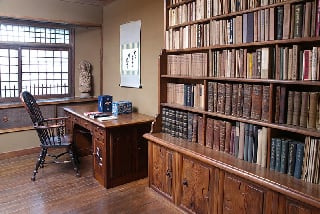20230704
ぽかぽか春庭アート散歩>2023アート散歩梅雨(2)近代の日本画 in 五島美術館
6月17日土曜日、五島美術館にお出かけしました。
6月18日で「近代の日本画」展が終わるので、駆け込み観覧です。
館所蔵品展示なので、あまり知られていない作品が多く、とても地味な展示ですが、初めての作品を見ることができました。
五島美術館の口上
館蔵の近代日本画コレクションから、「人物表現」を中心に、横山大観、下村観山、川合玉堂、上村松園、鏑木清方、松岡映丘、安田靫彦、前田青邨など、明治から昭和にかけての近代日本を代表する画家の作品約40点を選び展観します。
やはり目玉はポスターの図柄になっている上村松園『上臈図』でしょう。

安田幸彦「菊慈童」1939

近代の日本画は、洋画の技法を取り入れたり、従来の日本画とは異なる方向を目指した画家が多いように思います。新しい構図や筆遣いを求めながら自分自身の表現を目指してきた近代の日本画家の作品を眺めて歩きました。
女性画家伊藤小坡の『虫売』が出展されていました。美人画で上村松園と並び立った伊藤小坡でしたが、松園が女性初の文化勲章受章者となり、息子や孫も日本画家として高名を得ていることもあって今も人気が高いのに比べて、小坡の名は、たとえば、松園が中学高校の美術教科書に載っているほどの知名度はありません。伊勢猿田彦神社宮司の娘であったゆえ、出身地の伊勢には伊藤小坡美術館もありますが、広く知られた画家とは思えません。
「虫売」は、同じ画題で他の美術館にもあります。「虫売女」の着物の柄や虫を欲しがる子供のポーズの異なるものが何種類かある。人気の画題だったのでしょう。
展示室2は、棟方志功の特集。棟方は「五島慶太の追想」という本の装丁をしています。東急創始者の伝記とゆかりのあった人々が思い出を語った本。棟方が装丁を頼まれたのも、五島と深いかかわりがあったからでしょう。
夏日になる予想が出ていたので、暑くならないうちにと思って庭の散歩。日差しは強くても、庭内は木立に覆われているので、暑くはない。ゆったりと楽しい散歩でした。この日の歩数は9000歩。

<つづく>