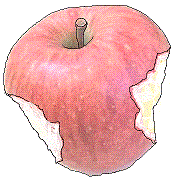
スティーヴン・シェイピンとサイモン・シャッファーの『リヴァイアサンと空気ポンプ ホッブズ、ボイル、実験的生活』(名古屋大学出版会)は、むずかしすぎて、読みづらい。
本書は、ホッブズとボイルの論争とその時代背景を扱ったものである。
ホッブズは、現在では、『リヴァイアサン』の著者、政治哲学者としか、一般には知られていない。ラッセルの『西洋哲学史』(みすず書房)によれば、王党派のホッブズは、数学や運動学・力学に精通した当時の教養人である。地動説のガリレオとも親交があった。
ボイルは、高校の教科書では、気体と圧力の法則を発見した実験家として描かれているが、原子論者で真空という概念の持ち主だった。
取り上げた時代は、自然科学が哲学から独立しようとしていたときだ。ボイルが、自然科学を、形而上学などの思弁から解放し、実験にもとづいた知識体系にしようとしたことを、もっと評価して良いと思う。
ボイルの217年後に生まれたニーチェは、『善悪の彼岸』(岩波文庫)の断章14で「物理学はそれなりに眼と指とをもち、それなりに明白さと平易さとをもっている。このことは賤民的な根本趣味をもつ時代に対して魅惑的に、説得的に作用する。」と言う。
また、断章204で「科学が余りにも長い間その「婢(はしため)」として仕えて来た神学から はなはだ幸運にも身を禦(ふせ)いで後は、科学は今では不遜となり無分別になって、ついには哲学に対して法則を与え、自己自らが今度は「主人」の役を――何ということだ!――すなわち哲学者の役を演じるに至っている」と言う。
ギリシア哲学者のアリストテレスは、哲学を物理学(physics)、論理学(logic)、形而上学(metaphysics)と分類した。昔の哲学者にとっては、自然哲学、自然科学、物理学は同じものをさす。
ニーチェは、自然科学は、「眼」(観察)と「指」(実験手段)をもち、大衆受けをするようになって、偉そうにしている、と怒っているのだ。すなわち、思弁を軽んじて、自然を観察したり、実験装置や測定装置を組み立てたりする人々を下賤だと言っているのだ。
しかし、プラトンやアリストテレスの方がおかしいのであって、自然哲学者アルキメデスは、技術者でもあって、浮力や滑車について研究し、いろいろな機械を開発した。
いっぽう、ホッブズは、ヨーロッパに亡命しており、1636年にガリレオに会っている。当時の最先端科学を知っているわけだ。
ガリレオの書いたものを読むと実験を重んじている。地球が回転しているのか、太陽が地球の周りをまわっているのか、どちらでも、昼と夜があることを説明できる。1つの自然現象に多様な説明ができるとき、その説明をする際の一連の原理(仮説)を実験で確かめていくしかない。
ガリレオの思考実験は、アインシュタインによって有名になっているが、本当の実験も行っている。斜面を使って、落下において速度がどんどん早くなることを実測している。斜面を使うと、重力の大部分が斜面からの抗力によって打ち消され、斜面を転がる球がゆっくりと加速していくのだ。ガリレオの実験は、ピザの斜塔の落下実験だけではないのだ。また、凹レンズと凸レンズとを組み合わせた望遠鏡を発明している。
ホッブズは、ガリレオに会ったにもかかわらず、思弁を重視している。
コミュニケーション能力がなく、発達障害で自閉症と思われてきた私としては、ボイルを応援したくなる。
ボイルは公開の実験や本による実験装置の公開も重視している。
シェイピンとシャッファーは本書で、「空気ポンプ」の再現性が、ボイルの本だけからの知識では難しかった、と指摘している。当時、「空気ポンプ」の制作は高価なものだった。ボイルはアイルランド貴族だったから「空気ポンプ」を制作できたと本書でいう。
装置の再現性の問題に関しては、私は次のように考える。当時、貴族が自分の手で装置を作ったのではなく、設計図を描くだけで、職人が実際にものを作ったから、知らないノウハウがあったのではないか。19世紀から20世紀にかけて、技術者と科学者との距離が近くなったのは、私は良いことだと思う。
いっぽうで、ボイルの16年後に生まれたニュートンの著作『Philosophiae Naturalis Principia Mathematica』(プリンキピア)は、その思弁性の成功のため、物理学は数学だという誤解を与えた。ニュートン自身は、実験もし、プリズムが光を多色に分けること(色差)を発見し、色差を抑える反射望遠鏡を考案した。
本書で、シェイピンとシャッファーは、むりやり、科学史を哲学史や政治史に結びつけようとしているように、思える。文体も変だ。例をあげよう。
「私たちの主題は実験である。私たちが理解したいのは、実験的な営みとその知的産物とは何か、そしてそれがどういう地位を有するかである。答えようと思う問いは以下のとおりである。実験とはなにか。実験はどのようにおこなわれるのか。実験はどのような仕方で事実を生みだすといわれうるのか。そして実験によって生みだされた事実と説明のために想定されることがら[説明のための理論]とのあいだにはどんな関係があるのか。どのようにして実験は成功したとされるのか、またどのようにして実験は成功したとされるのか、またどのようにして実験の成功と失敗は区別されるのか。この一連の問いの背景にはより一般的な問いが存在する。なぜ人は科学的真理に到達するために実験をするのか。自然に関する知識に合意によって到達するにあたって、実権は特権的な手段であるのか、あるいはなにか他の手段が可能なのか。科学において代わりとなりうる他の手法ではなく、実験的手法を勧めているものはなんなのか。」
本書が科学史のコミュニティで高く評価されるとは、私のような理系の人間と異なる人たちがコミュニティの主流をしめているように思える。









