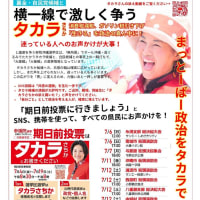沖縄平和市民連絡会は、11月20日、沖縄県と海砂採取問題について交渉を行った。辺野古新基地建設事業では、地盤改良工事等のために、800万㎥ほどの砂が必要になる。これは、沖縄の海砂採取量の4~5年分にもなり、このままでは沖縄沿岸部の環境は壊滅的に破壊されてしまう。
(現在の海砂採取の問題点については 10月27日のブログ 参照)

(図は、I.Yさん作成)
そのため、海砂採取の総量規制を制定し、さらに現行の運用方法を大幅に改善する必要がある。そのための県への要請だったが、いくつかの点で県は前向きな回答をした。
以下、県交渉の議事録(一部)である。
海砂採取問題に関する沖縄県との意見交換の記録 沖縄平和市民連絡会
・日時:2019.11.20
・出席者
●沖縄県土木建築部 照屋統括監、新崎海岸防災課長等
〇沖縄平和市民連絡会 共同代表ら7名
|
第1 海砂採取の運用面の問題について 1.業者の海砂採取量の申告を、どのような方法でチェックしているのか? 沖縄県海砂採取要綱(以下、「要綱」)では、業者は、毎日の採取量を県に月報で報告することとされている。しかし、業者が月報に記載した採取量が正しいのかどうか、県はどのような方法で確認しているのか? 海砂の採取料は現在、1立方メートル当たり128円と定められ、認可量をもとに納入されている。しかし、業者が認可量より多く採取した場合、県に納入される採取料金額が不足することとなるが、現状では業者の申告量が正しいかどうかの確認が行われていない。県の歳入額の根拠資料が不明確なまま処理されてよいはずはない。 長崎県では、「1採取毎の採取量計算書及び写真」を提出させ、報告された採取量が適正かどうかチェックを行っている。さらに、GPSを装備した船を県がチャーターし、実際の採取状況の監視を行っているという。沖縄県でもなんらかの確認方法を定めなければならない。 2.採取場所の確認ができているか? 沖縄での海砂採取は、「海岸線から1㎞以上離れ、且つ水深が15m以上の区域」に限られている(要綱)。しかし、月報には毎日の採取量は記載されているが、採取場所の記載は求めていない。 要綱には、「採取船には、位置確認のための測定機器を装備すること」と定めているのであるから、採取船のGPS情報の記録の提出を求めるべきである。長崎県では、「GPS記録紙及びポンプ稼働記録紙」等を提出させ、許可を受けた区域内で採取を行っているかどうかを県がチェックしている。 3.「深堀り」のチェックはどのような方法で行っているのか? さらに問題となるのは、環境への影響が大きい「深堀り」の規制である。要綱では、「部分的な深堀りをしてはならない」とされているが、その具体的な内容については要綱の定めはない。「海砂利採取に関する取扱いについて」で、「掘削深度は概ね2メートル程度とし、採取区域において平均2メートルとなるようにする」、「部分的な深堀りとは、2メートルから50%程度を超えた場合とする」とされているだけである。 実際の許可書にも、許可条件の一つに、「部分的な深堀りをしないこと」としているだけで、上記の「取扱い」の各数字は、許可条件としては明記されていない。 県は、これらの深堀りの規制が遵守されているかどうかをどのような方法で確認し ているのか? 海砂採取の許可申請には、等深線1メートルごとの深浅測量図を提出させているのであるから、採取後の深浅測量図の提出も求めるべきであろう。 また、「部分的な深堀りをしないこと」ではなく、「掘削深度は●メートル以内であること」と変更されたい。
|
<県の冒頭読上げ回答>
1.県は現在、採取量・採取位置について、写真等の提出を求めていません。日報等を提出させているだけです。採取位置については、海保にも情報提供しています。
深堀のチェックについては、事前の深浅測量の資料は提出させていますが、事後については提出を求めていません。
現在、これらについて、他府県の状況を調査しています。
採取量、採取場所については、他府県では事業者から航跡記録や、ポンプの稼働記録等を提出させているところもあいます。採取後の深浅測量も一部の県で行っています。
県としては、砂利採取組合とも意見交換した上で、彼らの負担が生じることもあるので、できることから取組を始めていきたい。
2.採取深度については、2m以内、部分的な深堀はその50%を超えないように規制しています。
<質疑応答>
〇現在の県のやり方では、業者が出す日報の採取量が正しいかどうか分からない。何故、採取量や採取位置の確認を行っていないのか?
●GPSの航跡記録の提出やポンプの稼働記録について、一部の砂利採取組合に聞いてみました。
紙データの出力をできる機器を備えていないという。また、ポンプの稼働記録についても、記録できるような設備が整っていないということだった。これらをやってもらうためには設備投資が必要になる。
今、できることは何かと話し合っている。一つひとつ改善に向けて取り組んでいきたい。
〇他府県ではそれらを実施しているところが多い。また、採取量は県に入る歳入額にもかかわることだから、その根拠資料は、当然、必要ではないか?
〇これらの設備も備えられないような業者に許可を出すこと自体がおかしい。
●組合とも意見交換しながら、できるだけ改善したい。
〇現在、採取している業者数は?
●組合の数は、11。組合に入っている業者数は100社程度だが、実施に申請しているのは最近3年間では6事業者です。
〇採取地は何処か?
●国頭村沖(安田沖等)、東村沖、大宜見村沖、伊是名島周辺、伊平屋島周辺、バン崎・天仁屋・安部沖、糸満沖、チリビシ周辺等です。
〇海砂の埋蔵量は無尽蔵なのか?
●それは把握できていません。
〇そうならもっと厳しくしていく必要がある。
〇第3者の検討会をつくって埋蔵量なども調査すべきだ。九州ではやっている県もある。
〇事業者と話しあうと言われているが、事業者は負担になることは同意しないだろう。第3者の検討会を設置すべきだ。
●航跡記録、ポンプの稼働記録、事後の深浅測量について、運用面の改善に向けて組合と話し合っていきたい。
〇要綱で、海砂採取を申請できるのは組合、もしくは組合員に限っているのは何故か? 広く、一般に機会を与えるべきではないか? 法的に問題はないか?
●以前は、一つの組合だけに許可をしていたが、まずいというので広く門戸を広げて、組合を作っていただいて、組合員であれば、OKしましょうということで門戸を広げた。要件を踏まえて組合を結成してもらっているので、組合員は能力がある業者ということになる。
ただ、この問題については、もう少し調べさせてください。
〇今日はあまりこの問題については触れないが、やはり特定の組合に限るというのは法的にも問題だろう。
(組合についての話、一部略)
●航跡記録やポンプの稼働記録を提出させることについては、改善に向けて取り組みます。総量規制については、各界の皆さんの意見も聞いて考えていきたい。
〇砂利採取事業協同組合が11月から海砂の値段を値上げした。そこでは、とくにSCP工法のための砂の価格が極端にあがっている。組合は、地盤改良工事で需要が増えることを見込んでいる。
〇県としての方向を早く打ち出さないとどんどん手遅れになる。県としての毅然とした対応を打ち出していく必要がある。
●航跡記録やポンプの稼働記録を提出させることについても、業者に対して設備投資を求めていきたい。ただ、組合の負担がでることでもあるので、すぐにはできないかもしれないが、できるだけ早く対応していただくよう求めていきます。
|
4.ジュゴンの生息地、海草藻場での海砂採取を規制すること 現在、沖縄県北部の安部(嘉陽)沖や、古宇利島沖等でも海砂の採取が行われている。 この付近は、ジュゴンが確認され、海草藻場が繁茂している地域であることから、沖縄県も海砂採取の許可にあたっては、その影響を危惧していたはずである。 今後、ジュゴンや海草への影響が危惧される海域では海砂採取を禁止されたい。
|
<県の冒頭読上げ回答>
要綱には許可基準があり、採取区域については他の法令(自然公園法、国定公園法等に抵触する場合は考慮するとなっている。
ジュゴンの生息地については、環境関連の法律が制定された際には対応したい。
<質疑応答>
(このやり取りについては、別紙)
|
5.「要綱」ではなく、条例・規則を制定すべきではないか? 現在、海砂採取の手続きについては、土木建築部長決裁の「沖縄県海砂採取要綱」しかない。法的拘束力のある、条例、若しくは規則を定めるべきではないか?
|
<県の冒頭読上げ回答>
条例・規則を制定すべきということだが、許可の際には条件を付している。許可も砂利採取法にもとづいてやっている。条件も法的な手続きでやっていると理解している。
違反した場合は、砂利採取法26条違反となり、許可の取消等となる。法的な義務を付していると理解している。
|
第2 海砂採取の総量規制について 前述のように、現在、環境面への影響を考慮し、海砂採取の全面禁止や、総量規制に踏み切っている県が多い。沖縄県でも早急に総量規制を行うことが求められている。 すぐに総量規制の条例化に踏み切ることができないとしても、まず、有識者による検討委員会を設置し、各県が海砂採取の全面禁止や総量規制に踏み切った背景等の調査、また、海砂採取による環境や水産資源への影響調査、沖縄沿岸域の海砂資源量の調査、今後の骨材の需要予測の調査等、具体的な取組を始めるべきではないか?
|
<県の冒頭読上げ回答>
海砂採取は、建築用の骨材・資材として需要性が高い。今後の持続的な確保をはかるという観点から、これからどうするかを考えていきたい。
総量規制の必要性については、今後の骨材・資材の安定的な供給について関係機関の意見も聞いて慎重に検討したい。
現在、他府県の状況、採取禁止の背景、総量規制に至った状況を調べている。全面禁止、総量規制を定めているところもある。組合とも意見交換して対応していきたい。
<質疑応答>
●総量規制については、組合の意見も聞くし、需要側の関係者や漁協等の意見も聞こうと考えている。ただ、過去の経緯もあるので。
●総量規制が必要ではないとは言っていません。
〇ヤマトの海砂は川から流れてきた砂だが、沖縄はサンゴ由来の砂だ。だから埋蔵量には限界がある。総量規制は急がなければならない。
●県も、総量規制が必要ないとは言っていません。
必要性については、関係者の意見を聞いたうえで方向性を考えていきたい。
〇関係者の話を聞くというが、業者は規制に反対するのは当たり前だ。聞くにしても、まず、県としての方向性を確認することが必要ではないか?
●組合だけではなく、漁協にも聞きます。
●海砂は沖縄では、コンクリートの骨材や建設資材として非常に重要です。今後の需要予測なども行って方向性を決めていきたい。
●かっては台湾などからも砂を持ってきたことがあったが、今はやっていない。
〇今、外国から砂は来ていませんか? 一時は、中国、台湾、フィリピンなどから宮古、石垣などに砂が履いていませんか?
●以前は来ていたが、今は来ていません。
〇それはきちんと把握できているのですか?
●調べてみます。
〇話を聞くということだが、環境面の専門家などにも話を聞くと約束できますか?
●それはやります。(注:これについては3回にわたって確認した。)
〇総量規制については、他府県でも、審査会などで5年に1回ぐらいごとに見直しをしている。最近の統計を見ても、沖縄では年間200万㎥で十分まかなえる。いったんそれで決めて、公共事業の動きなどで追い付かないということになったら、審査会などで見直せばよい。
●総量規制については、他府県でもほとんど実施しているという状況を踏まえて、沖縄県としても早い目に作業を進めていきたい。