
チベットというと、死ぬことに非常に重きをおいて、生の終わりに死があるというよりは、生とともに死があり、死者の弔いもとても意識的にていねいにおこなわれていたようです。
とはいえ、土がかたくて、ほぼ岩でできているので、埋めることができず、鳥葬が一般的です。
肉体よりも魂を重んじるチベット人らしいと言えると思いますが、ここでは、「高僧」と呼ばれ、特別にミイラとして死後も保存される死者について語られています。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
“化身”と呼ばれるような最高のラマ僧以外、チベットで死ぬすべての者は空葬によって葬される。
高僧たちは、お寺でよくみられるように、香油を塗られ、ガラス張りの箱に入れられるか、またはミイラにしてメッキされる。
この最後のやり方はひじょうに面白い。
わたしは何度もこの制作に立ち会った。
ある夕方、わたしは僧院長の前に呼ばれた。
「“化身”がまもなくその肉体を去られることになっている。
彼は今“野ばらの垣根”におられる。
君はそこへ行って,聖者をどのように保存するかを見たらよい」と、彼は言った。
そこでわたしは僧院に戻り、老僧院長の部屋に到着した。
彼の金色の霊気はまさに消滅せんとしており、そして約一時間後、彼は肉体から霊魂へとうつりかわった。
僧院長でありまた博学な人であったから、彼はバルド(死者が死後に通る道筋)を通る道案内をしてもらう必要はなかった。
さらに、私たちは〝通例の三日間"(死後のさまよいの3日間)を待つ必要もなかった。
その夜のうちに死体は蓮華座の姿勢に座らされ、一方ラマ僧たちはお通夜を続けた。
朝、最初の日の光とともに、私たちは儀式の行列をつくり、僧院の本堂をぬけおりた。
そして寺に入り、まれにしか使わぬ扉を通って秘密の地下へと降りていった。
先頭には二人のラマ僧が、遺体を籠に乗せて運んでいた。
それは蓮華座の姿勢のままだった。
僧たちの背後からは低い読経が響き、一同は赤い法衣を着、その上から黄色い袈裟をかけていた。
壁にはこれらの影が揺らめき踊り、バターランプと燃え盛るたいまつの光で異様に大きくなったり、ゆがんだりしていた。
私たちは、下に降りていった。下の秘密の場所へと。
最後に、地下20メートルほどで、封印された石の扉のところに着いた。

みんなは中に入った。
部屋は氷のように冷たかった。
僧たちは注意深く遺体を下ろし、それから2、3人のラマ僧とわたしを除いて、すべてが出ていっ
た。
数百のバターランプが輝き、どぎついぎらぎらする黄光を放っていた。
いよいよ遺体は衣服をはぎ取られ、そして注意深く洗われた。
体中の自然の穴から内臓は引き出され、大きなツボの中に入れられ、ツボは慎重に封印された。
体内はくまなく洗われた後乾かされ、そして特別なうるしがその中に流しこまれた。
これが体内で固いからを形作ることになるので、外見はまるで生きているようになるのだった。
漆で乾かし、そして固め、うつろな胴内には、形をこわさないように細心の注意を払って詰め物がされた。
腹部をしっかりさせるために、もっと多量のうるしを詰めものに浸み込ませ、堅くさせるよう中に流しこまれた。
体の外側の表面にもうるしが塗られ、乾かされた。
固くなった表面の上には、膜のように薄い絹の布地が何枚も糊付けされた。
まる一昼夜、それはそのまま動かされぬようにしておかれ、こうして最後に完全な乾燥がおこなわれ
た。
この期間が終わって、もう一度この部屋に戻ってみると、遺体はすっかり堅く、まっすぐに蓮華座を組んで座っていた。
私たちはそれを行列して下の別の部屋に運んだが、床は特殊な粉で厚く覆われていて、遺体はここ
の真ん中に置かれた。
下では僧たちがすでに火をつける用意をしていた。
注意深くこの部屋全体を、チベットの一地方から取れる特殊な塩とそれから薬草と薬石との混合物で隙間なく密閉した。
床から天井まで、部屋中に埋めものをしてから、みんな廊下の外に出て、部屋の扉を閉め、僧院のお札で封印した。
炉に点火するようにとの命令が与えられた。
まる一週間、火は下で燃え続けた。
七日目のおわりには、徐々に火は下火となり、燃え尽きていった。
おもい石の壁が、冷却するにつれて、きしりうねった。
封印をした日から11日目に、お札は破られ、扉が開かれ、彼ら僧たちは2日にわたってもろい塩の
混合物を、手で砕きながら掻き出し続けた。
ついに部屋は空になった。
真ん中の、いぜん蓮華座を組んだまま、屍衣に包まれた遺体をのぞいては。
私たちはそれを用心深くもちあげ、バターランプの光でもっとはっきり見えるようにと、別の部屋に
運んだ。
(引用ここまで・写真(下)は、著者が出版社に送ってきた近影))
*****
食料品店に行くと、「チベット産岩塩」を売っています。
海のないチベットに、どうして岩塩があるのか、これも興味深い問題です。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「日本のミイラ(1)・・自分でミイラになる方法」(6)まであり
「インカのミイラ・神々の好きなもの」(2)あり
「子供のミイラの仮面、生前そっくり・・5000年前、チリ先住民」
「エジプトのミイラ(1)・・バーとカーの戻る場所」(4)まであり
 「弥勒」カテゴリー全般
「弥勒」カテゴリー全般 「エジプト・イスラム・オリエント」カテゴリー全般
「エジプト・イスラム・オリエント」カテゴリー全般 「インカ・」カテゴリー全般
「インカ・」カテゴリー全般












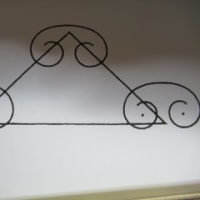


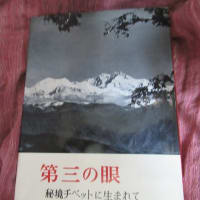







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます