
「ユダの福音書」、「マグダラのマリアによる福音書」と読んでみて、今度は「マタイによる福音書」を読んでみました。
「マタイによる福音書」には、4福音書中ただ一つ、イエスの誕生を知り、東方から祝福にやってくる「東方の三博士(マギ)」のことが書かれています。
この場面は、かいば桶の中で眠るイエスとともに、クリスマスカードの定番で、印象深く人々の心に浸透しています。
しかし、東方とはどこなのか、彼らがなぜやってきたのか、なぜ一つの福音書だけにそのことが書かれているのか。。
よく考えると、わからないことが多いようです。
エイドリアン・ギルバートという人は、「マギ・星の証言」という本において、東方の三博士(マギ)とキリスト教のかかわりについて述べています。
抜粋して少し引用してみます。
*****
(引用ここから)
マタイによる福音書には書かれている。
・・・・・・
イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。
そのとき占星術派の博士たち(マギ)が、東の方からエルサレムに来て、言った。
「ユダヤの王としてお生まれになった方はどこにおれられますか。
わたしたちは東方でその方の星を見たのです。」
ヘロデ王は占星術の博士たちをひそかに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。
そして「行って、そのことを詳しく調べ、みつかったら知らせてくれ。
わたしも行って拝もう」
と言って、彼らをベツレヘムに送り出した。
彼らが王の言葉を聞いて出かけると、かつて東方で見た星が先だって進み、ついに幼子(おさなご)のいる場所の上に止まった。
博士たちはその星を見て、よろこびにあふれた。
家に入ってみると、幼子はマリアと共におられた。
彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。
その後彼らは、「ヘロデの所に帰るな」と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国に帰っていった。
・・・・・・
マタイの記したイエスの生誕物語の中で、博士たちの役割は非常に謎めいている。
イエスの誕生に際し、博士たちの一人一人が贈り物を捧げる。
贈り物はそれぞれイエスの運命を象徴している。
黄金は王、乳香は祭司、没薬はヒーラーとしてのイエスの役割を示唆する。
この物語はマタイによるまったくの創作であるとする議論もあれば、マタイにはこの話を福音書に収めなくてはならない理由があったのだという見方もある。
いずれにしても、三博士の伝説には常軌を逸した、秘伝的な要素があるのは確かなのだ。
マギが幼子イエスに贈り物を届けにやってきた日を「救世公現祭」という。
これは1月6日に祝われる。
初期キリスト教会ではエピファニー、公現祭は聖なる日ではあったが、それはイエスの生誕とはまったく関係なかった。
むしろこの日はキリストがヨルダン川で洗礼を受けた日と考えられていた。
この日は「光の日」と呼ばれ、イエスの光、そしてヨルダン川に輝いた光と結びつけられている。
12月25日にクリスマスを祝うようになったのは、西暦353年、法王の宣言の後のことである。
それ以前、キリスト教最大の祭りは、キリストの洗礼であった。
これは1月6日に行われた。
キリストの洗礼という重要な祭りを行うのに、なぜこの日を選んだのか。
それは過去に、その元型となる習慣が1月6日に行われていた歴史によるらしい。
その習慣があったのは、エジプトであった。
ローマ時代、港町アレクサンドリアにコレイオンと呼ばれる非常に大きな神殿があった。
この神殿では1月6日に童子神アイオーンの誕生を祝っていた。
この異教の祭典が聖エピファニウス(西暦315-402)の時代になっても行われていたことは、その著書にも記されている。
エピファニウスは書いている。
・・・・・
アレクサンドリアの、いわゆる「処女の境内」とよばれる巨大な神殿コレイオンでは、人々は一晩中、音楽を奏で、偶像に祈りを捧げる。
夜が明けると、人々は灯りをもって地下聖堂におりて、輿の上にむき出しで横たわる木製の偶像を運び出す。
その額には金の十字架の刻印があり、両手や両膝にも同様な印がある。
これら五つの十字架の印は、いずれも金でできている。
人びとは偶像を抱えて一番奥の神殿の周りを、笛や太鼓を奏で、讃歌を歌いながら、7回まわる。
そして喜びの中、再び偶像を地下聖堂に運ぶ。
この秘儀の意味を問われると、彼らはこう答える。
「今日、この時刻、かの処女(コレ)がアイオーンを産んだ。」
(ミード編「三倍偉大なヘルメス」より)
・・・・・
これは「処女降誕」と公現祭、すなわち西洋で言う顕現祭、エピファニーとが結びついていたことを示す注目すべき証拠だ。
しかもそれは古代エジプトがマギの伝説の源泉の一つである可能性も示している。
これはみかけほど眉唾な見方ではない。
イエスの時代、アレクサンドリアはおそらく世界で最も文明の進んだ都市であったし、大きなユダヤ人共同体の本拠でもあった。
アレクサンドリアの最も偉大な哲学者フィロンもユダヤ人であり、また優秀な市民であった。
フィロンの膨大な著作は、当時をしのぶ最良の資料の一つである。
それは当時の賢者たちの信仰と習慣について多くのことを伝えてくれる。
その中には大勢のペルシャのマギが登場する。
彼らは真の知識の探求のために自然の営みを注意深く観察することによって沈思の中で、このうえなく明晰な(神秘的な)像を用いて神のような美徳をたたえた秘儀へと参入し、また自分たちの後にやってくる参入者を迎えるのであった。
フィロンは単に異国の宗教を観察していただけではない。
彼はそれらと密接に関わっていたようだし、おそらくはセラピスを崇拝する教団の一員であった。
セラピス崇拝の中心はアレクサンドリアの南にあった。
しかも面白いことに、フィロンがセラピス信者とその信仰について記していることの多くは、キリスト教を先取りしているのだ。
(引用ここまで)
*****
写真は「マギの礼賛・ローマの共同墓地にあるフレスコ画・3世紀前半」イアン・ウィルソン著「真実のイエス」より
 Wikipedia「公現祭」より
Wikipedia「公現祭」より
公現祭(こうげんさい、ギリシア語:エピファネイア( 現れ、奇跡的現象の意))は、人としてこの世に現れたイエス・キリストが神性を人々の前で表したことを記念するキリスト教の祭日。
本祭日は教派によって何を記念しているかについて違いがある。
西方教会(カトリック教会・聖公会・プロテスタント諸派)では幼子イエスへの東方の三博士の訪問と礼拝を記念する。
これに対し、正教会では神現祭(しんげんさい)もしくは洗礼祭(せんれいさい)と呼んでヨルダン川でのイエスの洗礼を記念し、三博士の礼拝は降誕祭で祭られている。
「公現節」「主の公現」「主顕節」などとも呼ばれる。
 Wikipedia「マギ」より
Wikipedia「マギ」より
マギ(ラテン語複数形 magi)は、本来、メディア王国で宗教儀礼をつかさどっていたペルシア系祭司階級の呼称。
本来のマギと意味の変遷
ヘロドトスの『歴史』には、「マギには、死体を鳥や犬に食いちぎらせたり、 アリや蛇をはじめその他の爬虫類などを無差別に殺す特異な習慣があった」と記されている。
これらの習慣はアヴェスターに記された宗教法と一致しており、彼らはゾロアスター教と同系の信仰を持っていたと考えられる。
一方、キリスト教世界では新約聖書、福音書の『マタイによる福音書』にあらわれる東方(ギリシア語でanatole。当時はペルシャのみならずエジプト北部などその範囲は広い)の三博士を指して言う場合が多い。
三人の王とも訳される。
直訳すれば星見すなわち占星術師であるが、マタイ福音書の文脈では、天文学者と推測される。
やがて、マギという言葉は 人知を超える知恵や力を持つ存在を指す言葉となり、英語のmagicなどの語源となった。
これはマギが行った奇跡や魔術が、現代的な意味での奇術、手品に相当するものだったと推定されるからである。
また磁石を意味するマグネットmagnet, マグネシウムmagnesiumの語源も、マギが奇跡のために使用したことに由来する、という説がある。
 Wikipedia「フィロン」より
Wikipedia「フィロン」より
アレクサンドリアのフィロン(20/30年? - 紀元後40/45年?)は、ローマ帝国ユリウス・クラウディウス朝時期にアレクサンドリアで活躍したユダヤ人哲学者。
豊かなギリシア哲学の知識をユダヤ教思想の解釈に初めて適用した。
ギリシア哲学を援用したフィロンの業績はユダヤ人には受け入れられず、むしろ初期キリスト教徒に受け入れられ、キリスト教思想のルーツの1つとなった。
 関連記事
関連記事
画面右上の「検索」を「ブログ内検索」にして
「キリスト」で15件
「十字」で13件(重複あり)あります。
「マタイによる福音書」には、4福音書中ただ一つ、イエスの誕生を知り、東方から祝福にやってくる「東方の三博士(マギ)」のことが書かれています。
この場面は、かいば桶の中で眠るイエスとともに、クリスマスカードの定番で、印象深く人々の心に浸透しています。
しかし、東方とはどこなのか、彼らがなぜやってきたのか、なぜ一つの福音書だけにそのことが書かれているのか。。
よく考えると、わからないことが多いようです。
エイドリアン・ギルバートという人は、「マギ・星の証言」という本において、東方の三博士(マギ)とキリスト教のかかわりについて述べています。
抜粋して少し引用してみます。
*****
(引用ここから)
マタイによる福音書には書かれている。
・・・・・・
イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。
そのとき占星術派の博士たち(マギ)が、東の方からエルサレムに来て、言った。
「ユダヤの王としてお生まれになった方はどこにおれられますか。
わたしたちは東方でその方の星を見たのです。」
ヘロデ王は占星術の博士たちをひそかに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。
そして「行って、そのことを詳しく調べ、みつかったら知らせてくれ。
わたしも行って拝もう」
と言って、彼らをベツレヘムに送り出した。
彼らが王の言葉を聞いて出かけると、かつて東方で見た星が先だって進み、ついに幼子(おさなご)のいる場所の上に止まった。
博士たちはその星を見て、よろこびにあふれた。
家に入ってみると、幼子はマリアと共におられた。
彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。
その後彼らは、「ヘロデの所に帰るな」と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国に帰っていった。
・・・・・・
マタイの記したイエスの生誕物語の中で、博士たちの役割は非常に謎めいている。
イエスの誕生に際し、博士たちの一人一人が贈り物を捧げる。
贈り物はそれぞれイエスの運命を象徴している。
黄金は王、乳香は祭司、没薬はヒーラーとしてのイエスの役割を示唆する。
この物語はマタイによるまったくの創作であるとする議論もあれば、マタイにはこの話を福音書に収めなくてはならない理由があったのだという見方もある。
いずれにしても、三博士の伝説には常軌を逸した、秘伝的な要素があるのは確かなのだ。
マギが幼子イエスに贈り物を届けにやってきた日を「救世公現祭」という。
これは1月6日に祝われる。
初期キリスト教会ではエピファニー、公現祭は聖なる日ではあったが、それはイエスの生誕とはまったく関係なかった。
むしろこの日はキリストがヨルダン川で洗礼を受けた日と考えられていた。
この日は「光の日」と呼ばれ、イエスの光、そしてヨルダン川に輝いた光と結びつけられている。
12月25日にクリスマスを祝うようになったのは、西暦353年、法王の宣言の後のことである。
それ以前、キリスト教最大の祭りは、キリストの洗礼であった。
これは1月6日に行われた。
キリストの洗礼という重要な祭りを行うのに、なぜこの日を選んだのか。
それは過去に、その元型となる習慣が1月6日に行われていた歴史によるらしい。
その習慣があったのは、エジプトであった。
ローマ時代、港町アレクサンドリアにコレイオンと呼ばれる非常に大きな神殿があった。
この神殿では1月6日に童子神アイオーンの誕生を祝っていた。
この異教の祭典が聖エピファニウス(西暦315-402)の時代になっても行われていたことは、その著書にも記されている。
エピファニウスは書いている。
・・・・・
アレクサンドリアの、いわゆる「処女の境内」とよばれる巨大な神殿コレイオンでは、人々は一晩中、音楽を奏で、偶像に祈りを捧げる。
夜が明けると、人々は灯りをもって地下聖堂におりて、輿の上にむき出しで横たわる木製の偶像を運び出す。
その額には金の十字架の刻印があり、両手や両膝にも同様な印がある。
これら五つの十字架の印は、いずれも金でできている。
人びとは偶像を抱えて一番奥の神殿の周りを、笛や太鼓を奏で、讃歌を歌いながら、7回まわる。
そして喜びの中、再び偶像を地下聖堂に運ぶ。
この秘儀の意味を問われると、彼らはこう答える。
「今日、この時刻、かの処女(コレ)がアイオーンを産んだ。」
(ミード編「三倍偉大なヘルメス」より)
・・・・・
これは「処女降誕」と公現祭、すなわち西洋で言う顕現祭、エピファニーとが結びついていたことを示す注目すべき証拠だ。
しかもそれは古代エジプトがマギの伝説の源泉の一つである可能性も示している。
これはみかけほど眉唾な見方ではない。
イエスの時代、アレクサンドリアはおそらく世界で最も文明の進んだ都市であったし、大きなユダヤ人共同体の本拠でもあった。
アレクサンドリアの最も偉大な哲学者フィロンもユダヤ人であり、また優秀な市民であった。
フィロンの膨大な著作は、当時をしのぶ最良の資料の一つである。
それは当時の賢者たちの信仰と習慣について多くのことを伝えてくれる。
その中には大勢のペルシャのマギが登場する。
彼らは真の知識の探求のために自然の営みを注意深く観察することによって沈思の中で、このうえなく明晰な(神秘的な)像を用いて神のような美徳をたたえた秘儀へと参入し、また自分たちの後にやってくる参入者を迎えるのであった。
フィロンは単に異国の宗教を観察していただけではない。
彼はそれらと密接に関わっていたようだし、おそらくはセラピスを崇拝する教団の一員であった。
セラピス崇拝の中心はアレクサンドリアの南にあった。
しかも面白いことに、フィロンがセラピス信者とその信仰について記していることの多くは、キリスト教を先取りしているのだ。
(引用ここまで)
*****
写真は「マギの礼賛・ローマの共同墓地にあるフレスコ画・3世紀前半」イアン・ウィルソン著「真実のイエス」より
 Wikipedia「公現祭」より
Wikipedia「公現祭」より 公現祭(こうげんさい、ギリシア語:エピファネイア( 現れ、奇跡的現象の意))は、人としてこの世に現れたイエス・キリストが神性を人々の前で表したことを記念するキリスト教の祭日。
本祭日は教派によって何を記念しているかについて違いがある。
西方教会(カトリック教会・聖公会・プロテスタント諸派)では幼子イエスへの東方の三博士の訪問と礼拝を記念する。
これに対し、正教会では神現祭(しんげんさい)もしくは洗礼祭(せんれいさい)と呼んでヨルダン川でのイエスの洗礼を記念し、三博士の礼拝は降誕祭で祭られている。
「公現節」「主の公現」「主顕節」などとも呼ばれる。
 Wikipedia「マギ」より
Wikipedia「マギ」より マギ(ラテン語複数形 magi)は、本来、メディア王国で宗教儀礼をつかさどっていたペルシア系祭司階級の呼称。
本来のマギと意味の変遷
ヘロドトスの『歴史』には、「マギには、死体を鳥や犬に食いちぎらせたり、 アリや蛇をはじめその他の爬虫類などを無差別に殺す特異な習慣があった」と記されている。
これらの習慣はアヴェスターに記された宗教法と一致しており、彼らはゾロアスター教と同系の信仰を持っていたと考えられる。
一方、キリスト教世界では新約聖書、福音書の『マタイによる福音書』にあらわれる東方(ギリシア語でanatole。当時はペルシャのみならずエジプト北部などその範囲は広い)の三博士を指して言う場合が多い。
三人の王とも訳される。
直訳すれば星見すなわち占星術師であるが、マタイ福音書の文脈では、天文学者と推測される。
やがて、マギという言葉は 人知を超える知恵や力を持つ存在を指す言葉となり、英語のmagicなどの語源となった。
これはマギが行った奇跡や魔術が、現代的な意味での奇術、手品に相当するものだったと推定されるからである。
また磁石を意味するマグネットmagnet, マグネシウムmagnesiumの語源も、マギが奇跡のために使用したことに由来する、という説がある。
 Wikipedia「フィロン」より
Wikipedia「フィロン」より アレクサンドリアのフィロン(20/30年? - 紀元後40/45年?)は、ローマ帝国ユリウス・クラウディウス朝時期にアレクサンドリアで活躍したユダヤ人哲学者。
豊かなギリシア哲学の知識をユダヤ教思想の解釈に初めて適用した。
ギリシア哲学を援用したフィロンの業績はユダヤ人には受け入れられず、むしろ初期キリスト教徒に受け入れられ、キリスト教思想のルーツの1つとなった。
 関連記事
関連記事
画面右上の「検索」を「ブログ内検索」にして
「キリスト」で15件
「十字」で13件(重複あり)あります。











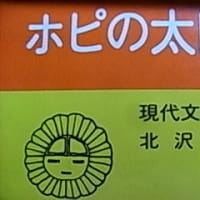

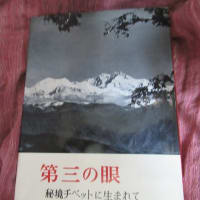










○様
コメントをどうもありがとうございました。
お返事がおそくなりまして、申し訳ございません。
3という数字に神秘を感じる文化があったのではないでしょうか。
たしかに4人でも5人でも10人でもいいですよね。
そして、もっといろいろな供物を持ってきたとしても、全然おかしくないですし。。
どうしても3がいいと考える理由があったのではないでしょうか。
② 真のイエス:カエサルとクレオパトラの子
③ ローマで死んだのは、赤いトーガの『A』
④ カエサリオンは、日本で生まれた。・・・
⑤ カエサル3度目世界一周旅荒苦雷墓参
。。。
⑥ 新約聖書記載劇=ベツレヘム.マリア。
⑦ 処女懐胎=劇を示唆。乳母マリア自然
⑧ ジョセフは?・・イエスを預かってきた人
ゴブラン織り。 荒神山古墳被葬者不明。荒苦雷尊では
カエサル31~32まで学生。。 。 タミル文字熟知。。
。 諸子百家教説も。。 。 。。 。 。。 。
ユダヤ教徒&ゾロアスター教徒。。 。 &マニ教徒
ジョセフは秀忠
真父=信康、英国で出生火坂雅志氏そう書きたかった
② 殺ったのは、安東守就&竹中半兵衛等.雪斎.寿圭尼
南渓.守就.利三.半兵衛.見性庵.北方様.佐吉.お福.皆:
英国留学。・・・
天武天皇=天智天皇(中大兄皇子)大海人皇子
白村江の戦い戦没。
・・ ・ ・・ ・ ・・ ・
『 星=☆。何故に人麻呂 春の月 』
。。 。 。。 。 。。 。 。。 。
歴史好き家康、見抜いていた!・・三成=信康
状況証拠=満載。・・・ 『 桃配り山腰掛石 』
頭巾、杖、彦根屏風。。 。 。。 。 。。 。
コメントをどうもありがとうございます。
たくさんのお言葉をお書きくださり、どのようにお返事すればよいのかわからないのですが、
わたしは、世界史の中で、キリストが過度に重視されているというように感じています。
キリストは、ユダヤ人だったので、もう少しユダヤ教の中で解釈したらどうかと思っております。
キリストで歴史に切れ目を入れたのは、ローマ帝国で、そこから、西洋という概念が確立されて、世界を東西に分けて考える習慣が一般化されたのではないかと思います。
しかし、現実の世界は、ローマ帝国の外側にも、はてしなく広く存在していたわけで、ローマ帝国の外側にあたかもなにもなかったように歴史を見るのは、おかしなことですよね。
西洋と東洋は、たとえお上がどう言おうとも、あいまいなまま、混在し続けていたのであったと思います。
キリストくらいの人物は、古今東西、人類の歴史の中にはたくさんいたと思います。
中近東に生きている人々は、中近東を世界の真ん中だと思って生きています。
日本人は日本が一番よく分かるので、日本文化を世界に伝えることを、もっと自信をもって行ってよいと思います。