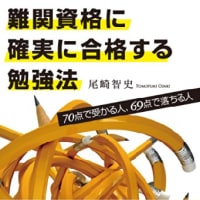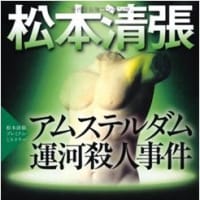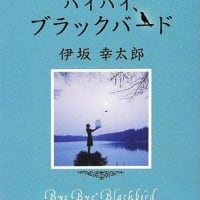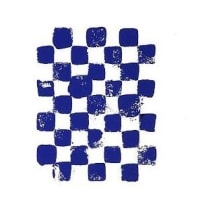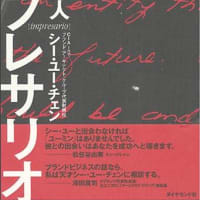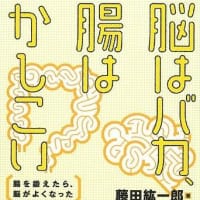<目次>
第一章 多読・少読・広読・狭読
セイゴオの本棚/本は二度読む/たまには違ったものを食べてみる/生い立ちを振り返える
第二章 多様性を育てていく
母からのプレゼント/親友に薦められた『カラマーゾフの兄弟』/文系も理系もこだわらない
第三章 読書の方法をさぐる
雑誌が読めれば本は読める/三割五分の打率で上々/活字中毒になってみる/目次をしっかり読む/本と混ってみる/本にどんどん書き込む/著者のモデルを見極める
第四章 読書することは編集すること
著者と読者の距離/編集工学をやさしく説明する/ワイワイ・ガヤガヤの情報編集/言葉と文字とカラダの連動/マッピングで本を整理する/本棚から見える本の連関
第五章 自分に合った読書スタイル
お風呂で読む・寝転んで読む/自分の「好み」を大切にする
第六章 キーブックを選ぶ
読書に危険はつきもの/人に本を薦めてもらう/本を買うこと/キーブックとは何か/読書しつづけるコツ/本に攫われたい
第七章 読書の未来
鳥の目と足の目/情報検索の長所と短所/デジタルvs読書/読書を仲間と分ち合う/読書は傷つきやすいもの
あとがき「珈琲を手にとる前に」
<筑摩書房 多読術 / 松岡 正剛 著>
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480688071/
私が松岡正剛さんを知ったのはいつの頃であったろうか。おそらく何かのテレビ番組ではなかったかと思いますが、著作としては「日本流」(朝日新聞社、2000)、「日本数寄」(春秋社、2000)を読んでいますので、だいたい10年ぐらい前の頃だと推察します。松岡さんの日本文化に対する幅広い知識と深い洞察に、私が敬愛している加藤周一さんの系譜を見、以来、勝手にポスト加藤周一の名をつけています。
それが5、6年ほど前、私の前職の会社案内に松岡さんが、文化ジャーナリスト、エッセイストである山田美也子さんがインタビュアーになった「間」に関する記事で登場されたのです。山田さんは、かつて1971年に、太田裕美さんらと「NHKステージ101」に出演された歌手、タレントでもありますが、とあるご縁で前職の会社とのお付き合いが始まり、何度かご一緒したことがありました。

お二人のご関係について山田さんにお尋ねしたことはありませんが、岐阜県主催で、戦国時代の偉人古田織部に倣い、創造的事業に尽力した人物、グループを顕彰する国際賞である織部賞の審査員を松岡さんが務め、第四回から司会を山田さんが務めておられることから、このご縁だったんだろうと思います。
そして、私がブログを書くようになって、取り上げる人物や話題をネットで調べていると、そこに松岡さんの「千夜千冊」が度々登場するのです。評論家、編集工学者としての認識はあったものの、松岡さんのこのブログを見るにつけ、その読書量に驚かされたものです。そんな松岡さんの読書術が本書で披露されます。また、本書によって「松岡正剛」の知の成り立ちを垣間見ることもできるのです。松岡さんは読書について次のように語ります。
~読書を神聖なものだとか、有意義なものだとか、特別なものだと思わないほうがいい。読書はもともと多様なものだ、だから、本は「薬」にもなるが「毒」にもなるし、毒にも薬にもならないことも少なくない。読書はつねにリスクを伴うと思ったほうがいい。読書を愉快にさせるのは、読み手次第なのである。書き手だって、いい本を書いているとはかぎらない。~
~だからといって、著者の責任と読者の責任が半々なのではない。著者三割、読者三割、制作・販売三割、のこり偶然が一割という相場だろう。それゆえ本を読むにあたっては、読者自身が自分自身が自分の得意な作法に照らし合わせ、会得しやすい柔軟な方法を身につけることをススメたい。それにはむしろ最初から多読的に遊んでみるほうがおもしろいうはずなのだ。~
「いい本」にめぐり会うために東大の推薦図書を参考にするのはどうかという質問に対し、あまりピンとこなかったという松岡さんは、注目すべき人物の選び方として次のように述べています。
~あのね。狩野亨吉(かのうこうきち)という熊本五高で漱石と一緒に教鞭をとっていた人物がいるんです。この人は安藤昌益の「自然真営道」の発見者であって、一高の校長とも、京都帝国大学の文化科の学長ともなった傑物ですが、ものすごい読書量の持ち主で、幸田露伴が「あの人ほどに本を読んでいると、宗教なんかバカバカしくなるだろう」と言ったほどだった。京都に西田幾多郎や内藤湖南を招聘したのも、この人です。漱石が死んだときの友人代表の弔辞も読んだ。~
~そこで、この狩野亨吉があまりにすばらしいというので、時の皇太子の教育掛に推挙されたんです。ところが本人は、これを断った。「ぼくは危険人物だ」というんですね。そして、大学をさっさとやめると、好色本のコレクションと書画骨董の鑑定をやりはじめた。~
~それでいて、時の知識人たち、たとえば長谷川如是閑(にょぜかん)が「これからの日本における自由とはどういうものだと思うか」と尋ねると、「自由なんてものはキリスト教がつくったフィクションだ。日本人は日本のネッセサリーをもっと複雑にしていけばいいんだ」と言ってのけたりもする。大賛成ですよ、社会派弁護士として有名だった正木ひろしが、「狩野先生こそ本当の国宝的人物です」とのちに述懐していますが、こういう人の推薦図書こそ、東大はめざすべきなんです。~

<狩野亨吉 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%A9%E9%87%8E%E4%BA%A8%E5%90%89
<ISIS>
http://www.isis.ne.jp/isis/
<編集工学研究所>
http://www.eel.co.jp/
<松岡正剛 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E6%AD%A3%E5%89%9B

1944年、京都生まれ。編集工学研究所所長。東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を経て、現在イシス編集学校校長。おもな著書は、『空海の夢』『知の編集工学』『情報の歴史を読む』『外は、良寛。』『日本流』『日本数寄』『フラジャイル』『花鳥風月の科学』『日本という方法』『17歳のための世界と日本の見方』『誰も知らない世界と日本のまちがい』ほか多数。インターネット上にブックナビゲーション「千夜千冊」を展開。2006年、『松岡正剛千夜千冊』(全7巻)を刊行。
「知の巨人」と呼ばれる松岡さん、きっと脳科学者・茂木健一郎さんと対談したら面白いだろうなと思って、何気なく検索していたら、2006年、もうすでに実現していたんですね。それも那須で12時間に及ぶ対談だったそうです。
<「セイゴオちゃんねる」>
http://www.eel.co.jp/seigowchannel/archives/2006/11/
<松岡正剛の千夜千冊 『脳とクオリア』茂木健一郎>
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0713.html
<茂木健一郎 クオリア日記: 脳と日本人 増刷>
http://kenmogi.cocolog-nifty.com/qualia/2007/12/post_db01.html
<備忘録>
「世の中でうまくいっていないことの多くは、実は当人の言葉の使い方によっている」(P41)、「雲水、ドストエフスキー、埴谷雄高」(P44)、「セイゴウの青春時代」(P54)、「ヘッドラインはサビ」(P65)、「読書の醍醐味~無知から未知へ」(P69)、「読書の前戯としての三分間目次読書」(P71)、「ヘルマン・ワイル~味蕾(みらい)と対話形式~」(P74)、「音読と黙読」(P105-110)、「読書の3R(リスペクト、リスク、リコメンデーション)(P140、146)、「自己形成と一抹の非自己化」(P142)、「柔らかい束」(P154)、「狩野亨吉」(P173)
第一章 多読・少読・広読・狭読
セイゴオの本棚/本は二度読む/たまには違ったものを食べてみる/生い立ちを振り返える
第二章 多様性を育てていく
母からのプレゼント/親友に薦められた『カラマーゾフの兄弟』/文系も理系もこだわらない
第三章 読書の方法をさぐる
雑誌が読めれば本は読める/三割五分の打率で上々/活字中毒になってみる/目次をしっかり読む/本と混ってみる/本にどんどん書き込む/著者のモデルを見極める
第四章 読書することは編集すること
著者と読者の距離/編集工学をやさしく説明する/ワイワイ・ガヤガヤの情報編集/言葉と文字とカラダの連動/マッピングで本を整理する/本棚から見える本の連関
第五章 自分に合った読書スタイル
お風呂で読む・寝転んで読む/自分の「好み」を大切にする
第六章 キーブックを選ぶ
読書に危険はつきもの/人に本を薦めてもらう/本を買うこと/キーブックとは何か/読書しつづけるコツ/本に攫われたい
第七章 読書の未来
鳥の目と足の目/情報検索の長所と短所/デジタルvs読書/読書を仲間と分ち合う/読書は傷つきやすいもの
あとがき「珈琲を手にとる前に」
<筑摩書房 多読術 / 松岡 正剛 著>
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480688071/
私が松岡正剛さんを知ったのはいつの頃であったろうか。おそらく何かのテレビ番組ではなかったかと思いますが、著作としては「日本流」(朝日新聞社、2000)、「日本数寄」(春秋社、2000)を読んでいますので、だいたい10年ぐらい前の頃だと推察します。松岡さんの日本文化に対する幅広い知識と深い洞察に、私が敬愛している加藤周一さんの系譜を見、以来、勝手にポスト加藤周一の名をつけています。
それが5、6年ほど前、私の前職の会社案内に松岡さんが、文化ジャーナリスト、エッセイストである山田美也子さんがインタビュアーになった「間」に関する記事で登場されたのです。山田さんは、かつて1971年に、太田裕美さんらと「NHKステージ101」に出演された歌手、タレントでもありますが、とあるご縁で前職の会社とのお付き合いが始まり、何度かご一緒したことがありました。

お二人のご関係について山田さんにお尋ねしたことはありませんが、岐阜県主催で、戦国時代の偉人古田織部に倣い、創造的事業に尽力した人物、グループを顕彰する国際賞である織部賞の審査員を松岡さんが務め、第四回から司会を山田さんが務めておられることから、このご縁だったんだろうと思います。
そして、私がブログを書くようになって、取り上げる人物や話題をネットで調べていると、そこに松岡さんの「千夜千冊」が度々登場するのです。評論家、編集工学者としての認識はあったものの、松岡さんのこのブログを見るにつけ、その読書量に驚かされたものです。そんな松岡さんの読書術が本書で披露されます。また、本書によって「松岡正剛」の知の成り立ちを垣間見ることもできるのです。松岡さんは読書について次のように語ります。
~読書を神聖なものだとか、有意義なものだとか、特別なものだと思わないほうがいい。読書はもともと多様なものだ、だから、本は「薬」にもなるが「毒」にもなるし、毒にも薬にもならないことも少なくない。読書はつねにリスクを伴うと思ったほうがいい。読書を愉快にさせるのは、読み手次第なのである。書き手だって、いい本を書いているとはかぎらない。~
~だからといって、著者の責任と読者の責任が半々なのではない。著者三割、読者三割、制作・販売三割、のこり偶然が一割という相場だろう。それゆえ本を読むにあたっては、読者自身が自分自身が自分の得意な作法に照らし合わせ、会得しやすい柔軟な方法を身につけることをススメたい。それにはむしろ最初から多読的に遊んでみるほうがおもしろいうはずなのだ。~
「いい本」にめぐり会うために東大の推薦図書を参考にするのはどうかという質問に対し、あまりピンとこなかったという松岡さんは、注目すべき人物の選び方として次のように述べています。
~あのね。狩野亨吉(かのうこうきち)という熊本五高で漱石と一緒に教鞭をとっていた人物がいるんです。この人は安藤昌益の「自然真営道」の発見者であって、一高の校長とも、京都帝国大学の文化科の学長ともなった傑物ですが、ものすごい読書量の持ち主で、幸田露伴が「あの人ほどに本を読んでいると、宗教なんかバカバカしくなるだろう」と言ったほどだった。京都に西田幾多郎や内藤湖南を招聘したのも、この人です。漱石が死んだときの友人代表の弔辞も読んだ。~
~そこで、この狩野亨吉があまりにすばらしいというので、時の皇太子の教育掛に推挙されたんです。ところが本人は、これを断った。「ぼくは危険人物だ」というんですね。そして、大学をさっさとやめると、好色本のコレクションと書画骨董の鑑定をやりはじめた。~
~それでいて、時の知識人たち、たとえば長谷川如是閑(にょぜかん)が「これからの日本における自由とはどういうものだと思うか」と尋ねると、「自由なんてものはキリスト教がつくったフィクションだ。日本人は日本のネッセサリーをもっと複雑にしていけばいいんだ」と言ってのけたりもする。大賛成ですよ、社会派弁護士として有名だった正木ひろしが、「狩野先生こそ本当の国宝的人物です」とのちに述懐していますが、こういう人の推薦図書こそ、東大はめざすべきなんです。~

<狩野亨吉 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%A9%E9%87%8E%E4%BA%A8%E5%90%89
<ISIS>
http://www.isis.ne.jp/isis/
<編集工学研究所>
http://www.eel.co.jp/
<松岡正剛 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E6%AD%A3%E5%89%9B

1944年、京都生まれ。編集工学研究所所長。東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を経て、現在イシス編集学校校長。おもな著書は、『空海の夢』『知の編集工学』『情報の歴史を読む』『外は、良寛。』『日本流』『日本数寄』『フラジャイル』『花鳥風月の科学』『日本という方法』『17歳のための世界と日本の見方』『誰も知らない世界と日本のまちがい』ほか多数。インターネット上にブックナビゲーション「千夜千冊」を展開。2006年、『松岡正剛千夜千冊』(全7巻)を刊行。
「知の巨人」と呼ばれる松岡さん、きっと脳科学者・茂木健一郎さんと対談したら面白いだろうなと思って、何気なく検索していたら、2006年、もうすでに実現していたんですね。それも那須で12時間に及ぶ対談だったそうです。
<「セイゴオちゃんねる」>
http://www.eel.co.jp/seigowchannel/archives/2006/11/
<松岡正剛の千夜千冊 『脳とクオリア』茂木健一郎>
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0713.html
<茂木健一郎 クオリア日記: 脳と日本人 増刷>
http://kenmogi.cocolog-nifty.com/qualia/2007/12/post_db01.html
<備忘録>
「世の中でうまくいっていないことの多くは、実は当人の言葉の使い方によっている」(P41)、「雲水、ドストエフスキー、埴谷雄高」(P44)、「セイゴウの青春時代」(P54)、「ヘッドラインはサビ」(P65)、「読書の醍醐味~無知から未知へ」(P69)、「読書の前戯としての三分間目次読書」(P71)、「ヘルマン・ワイル~味蕾(みらい)と対話形式~」(P74)、「音読と黙読」(P105-110)、「読書の3R(リスペクト、リスク、リコメンデーション)(P140、146)、「自己形成と一抹の非自己化」(P142)、「柔らかい束」(P154)、「狩野亨吉」(P173)