
<目次>
はじめに
第1部 先人からの伝言~しきたりに込められたメッセージ
しきたりは先人からの贈り物
暮らしの中のカミサマ
カミサマと向き合うときの作法
カミサマを待つ“まつり"
季節の節目のおまつり
人生の節目のおまつり
暦が教えてくれること
第2部 ときどき旧暦で暮らす「アエノコト」
食べ物に感謝してこれからの季節に備える
冬至 甦りの日
人日 七種( 草)粥を食す日
上巳 桃の節供「桃」と「雛」と「蛇」
端午 梅雨の邪気を祓う日
七夕 罪穢れを清め技芸上達を願う日
重陽 九が重なるおめでたい日
おわりに
付録:旧暦カレンダー
著者は、民族情報工学研究家。民族情報工学について著者は次のように述べています。
~聞き慣れない言葉ですよね。・・・具体的には、日本各地に息づいた風習や伝承を拾い集め、分析していく。なぜそんな場所にそういうことが生じたのか、その意味を読み解いていく研究です。重要なのはそこで得た先人の智恵、メッセージを受け継ぎ、未来へと生かすこと。~
この「民族情報工学」という言葉を聞いたとき、私は、日本の編集者、著述家で日本文化研究者の松岡正剛さんが提唱する「編集工学」を連想しました。松岡さんは、「編集工学について次のように語っています。
~編集によって文章や表現の意味が「がらっと」かわることを経験。会話や思考など普段、人が無意識に行っている行為も「編集」という観点で捉え直すようになる。そして「編集」をひとつの方法論にまで高め、単一的なモノの見方では見えてこなかった意味をあぶりだす「編集工学」を生み出した。~
この松岡さんの言葉を借りれば、民族情報工学とは、「日本各地に息づいた風習や伝承を拾い集め、分析し、『民族情報』をひとつの方法論にまで高め、単一的なモノの見方では見えてこなかった意味をあぶりだす学問。
本書には、著者がこれまで重ねてきた民族情報に関するフィールドワークで得られた知見が随所に散りばめられています。そして、日本人が古からこれまで、「カミサマ」といかに寄り添いながら暮らしてきたのかをやさしい語り口でこんな風に解き明かしてくれます。
~元気で暮らせているのは、自分に以外のまわりのおかげ様の力。自分以外のすべてのなかに、このおかげ様のもとになるものがあります。言葉にすると、カミサマのおかげ、ご先祖様のおかげ、家族のおかげ・・・・。「わたし、あるいは人間を取り巻くすべてのもの」という意味合いに近いかもしれません。
昔の人は、その陰のチカラに感謝して過ごすことで、常に自分たちの暮らしは守られる、そう信じて生きていたのではないかと思います。~
さらに、そのカミサマを年の節目で待つという意味での「マツリ」に、著者の筆は躍動します。それは、各地の盆踊りにも及び、その成り立ちとしきたりについてこんな風に教えてくれます。
~日本各地で行なわれる盆踊りの踊り方には、パターンがあります。まず手で天の気を受け、地の気を受け、自分に引き寄せて祓う。どれもみな、基本パターンが同じです。
動作のなかには、いわゆる中国の気功のような意味合いがあり、人間と死者との区別があります。死者は自然の気を受けられないし、体をもっていません。
生きているわたしたちは、死者が戻るときに、つい寂しくなって連れていきたくなる想いを断ち切り、あの世へ持っていかれないよう、自然の力を体いっぱいにいただいてしっかり踊るのです。
それから足の運び方にも独特のパターンがあります。行ってちょっと戻る、またちょっと行って半歩戻る。行きつ戻りつ、エネルギーを溜めて踊ります。~
私はこれまで、日本の阿波踊り、ハワイのフラに代表される手の動きは前者が潮のみちひき、後者は波のゆらめきを表わしていると理解していましたが、手の払いだけではなく、足の運び方にもちゃんと理由があったんですね。
<日本音楽の成立ち(4)/團伊玖磨の講演録「創るということ」から>
http://blogs.yahoo.co.jp/asongotoh/25834579.html
本書には、四季折々にカミサマを迎えてもてなす食「アエノコト」がレシピ付で紹介されています。是非お母様方に読んでいただきたい一冊です。

著者プロフィール:
民俗情報工学研究家。1964年北海道北見市生まれ。國學院大學卒業後、株式会社リクルート フロムエーへ入社、営業職を経て退職。現在、多摩美術大学の非常勤講師として教鞭を執る傍ら、日本全国をまわって、先人の受け継いできた各地に残る伝統儀礼、風習、歌謡、信仰、地域特有の祭り、習慣、伝統技術などについて民俗学的な視点から、その意味と本質を読み解き、現代に活かすことを目的とする活動を精力的に続けている。最近では、ホテルや温泉施設、化粧品会社の商品などのコンセプト、デザイン、ネーミングなどに携わるほか、映画やオペラ、アニメなどの時代考証、アドバイザーも務めている。「Back to future Japan(日本の未来に還ろう)」をコンセプトに、人間国宝や職人、科学者、神社界・仏教界の重鎮たちをネットワークし、伝統技術の継承にも積極的に関わっている。










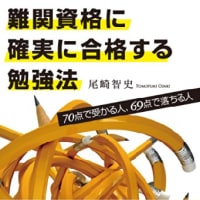
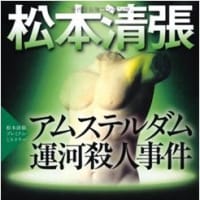
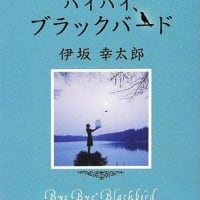

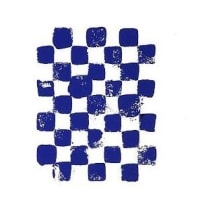
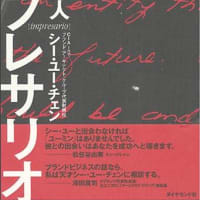



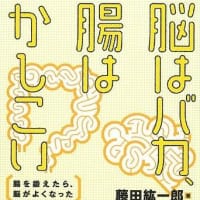
見えません。残念。いいね!ポチ