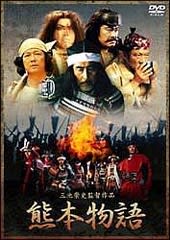
監督:三池崇史
第一部:「隧穴幻想 トンカラリン夢伝説」(1998年)
第二部:「鞠智城物語 防人たちの唄」(2000年)
第三部:「おんな国衆一揆」(2002年)
いや、内容はわかりやすいんですよ。わからないのは、この映画が製作された経緯、監督、俳優陣のキャスティングについてなんです。熊本を舞台にした映画はこの10年間で見ても、「英二」(1999年/黒土三男監督)、「ボクの、おじさん THE CROSSING(2000年/東陽一監督)、「女帝 Super Queen」(2001年/金澤克次監督)、「黄泉がえり」(2003年/塩田明彦監督)、「聞こゆるや」(2004年/山田武監督)などがありますが、この作品はちょっと異質です。で、調べてみました。
第一部の「隧穴幻想 トンカラリン夢伝説」には平幹二朗さん、大杉漣さん。第二部:「鞠智城物語 防人たちの唄」には江守徹さん、根津甚八さん、ナレーターに竹中直人さん。第三部の「おんな国衆一揆」には原田芳雄さん、竹中直人さん、石橋蓮司さん、大杉漣さん、布施博さん、遠藤憲一さん、あべ静江、青田典子そして、北村一輝さん。ナレーターに竹下景子さん。
豪華でしょ?おまけに、なんと塩谷義子(1939年4月5日-)熊本県知事が北の政所・ねねを演じています。さらに、この三部作を通じて全て主演格で登場するのが、はた三恵という女優さんなんですが、よく知りません。熊本出身の方なのでしょうか?全体の配役陣からすると、ちょっと奇異な配役です。そう言えば数年前、熊本空港であべ静江さんを見かけ、市内の小料理屋で竹中直人さんに出くわしましたが、この映画の関係だったのかと思い起こします。
この映画、上映は熊本県限定だったとか。制作は、「隧穴幻想 トンカラリン夢伝説」が玉名郡菊水町、「鞠智城物語 防人たちの唄」が熊本県立装飾古墳館、「おんな国衆一揆」は「財団法人・日本宝くじ協会」の助成事業で、制作が玉名郡三加和町となっています。この辺で制作背景がわかりました。
要は、熊本県立装飾古墳館が本締めさんなんですね。「くまもとアートポリス事業」の一環として建築家の安藤忠雄さんが設計されたくらいを知っている程度です。私はまだ訪れたことがないのですが、次のようなところです。

「文化庁が1979年に提唱した『風土記の丘』設置構想の一環として、熊本県が菊池川流域の山鹿市・鹿本郡鹿央町(現・山鹿市)・玉名郡菊水町(現・和水町)の3地区を指定し、『肥後古代の森』として整備を進めた。ここ熊本県立装飾古墳館は、その中心施設として1992年に開館した」。
さらに、この古墳館には、次ぎの二つのアニメ作品が所蔵されています。
『山鹿灯籠』
山鹿市の「山鹿灯籠」の成り立ちを描いた物語。実写を交えた切り絵によるアニメ映画です。
監督:三池崇史、声の出演:古谷一行、ナレーター:はた三恵
『松尾敬宇とその母』
激動の昭和に生きた山鹿市出身の一青年、松尾敬宇海軍中佐と戦後を生きた母の物語。不戦の誓いと平和の尊さを訴えたアニメ映画です。
監督:三池崇史、声の出演:萩原聖人、藤村俊二、松坂慶子、ナレーター:勝野洋
やはり凄いキャスティングです。そしてはた三恵さんも登場します。三池崇史さんは大阪出身なので、どういう経緯でここまでこの古墳館にコミットされているのか知りたいところです。
さて、内容ですが、「時代劇映画感想文集」というサイトに詳細なコメントがありましたので、そちらから引用させてもらいます。
<第一部:「隧穴幻想 トンカラリン夢伝説」(1998年 33分)>
熊本県北部にトンネル遺跡があり、地元ではトンカラリンと呼んでいる。トンネルは全長数百mほどもあり自然にこんな洞窟ができることはありえないから、明らかに人間が作ったものである。しかし、どんな人たちが何の目的で作ったものかは皆目わからず、諸説がある。そこを脚本家のイマジネーションで一種の神話ファンタジーに仕上げた作品。
1500年前、トンカラリンを神の通り道として祀っている村を、ヤマトの兵が襲ってくる。村人の多くは隣の山に逃げたが、神穴を守る巫女と戦士(平幹二朗)は村に残って最後まで戦う。二人の命が尽きたとき、穴から龍の姿をした神が現れ、二人の魂を運び去った。(終)
まず見所は、平幹二朗の鬼気迫る頑張りぶりであろう。本来、村の戦士は若者の設定で平の実年齢からしたらかなりの無理がある役なのだが、歌舞伎のような隈取りメイクと切れのいい体の動きでカバー。途中からメイクだけでなく芝居自体が歌舞伎っぽくなってくるのだが、この辺は舞台俳優としての平幹二朗の真骨頂で、ケレン味溢れた大熱演。昔、築地本願寺で見た「オイディプス王」(蜷川幸雄演出)を思い出した。古代劇はこの人、大得意なのだ。そして大仰な演技も、三池映画のカラーにもよく合っているように思う。
時代考証なしの自由な発想で作られた衣装も、注目していいところだと思う。ヤマトの兵士達は黒尽くめでマントを羽織っていて、「ロードオブザリング」の黒い騎士みたいだ。戦士の衣装も巫女の衣装も何度か変わるが、シルエットがきれいでなかなかいいでき。
映像はときどきいかにも低予算風になるところが、気になる。背景が書割りで床にはスモーク、とか。あと巫女が踊りだすとシュボっと音をたてて神具に火が灯るところの安っぽさには、思わず苦笑。
<第二部:「鞠智城物語 防人たちの唄」(2000年 29分)>
鞠智城は、大和朝廷が国防拠点として作った砦のひとつ。いわゆる朝鮮式山城で、白村江の戦い後、朝鮮半島から亡命してきた百済の人たちから伝えられた。
平和に妻子と暮らす男(根津甚八)は、家族と別れ防人として鞠智城での兵役に付いた。毎日見張りだけで飽きてしまった男に、朝鮮からの亡命者(江守徹)が祖国が滅びたときのつらい思い出を話し、国や家族を守ることの大事さを諭した。3年の任期も終わり、男が故郷に帰れると喜んでいると、突然大地震が来た。亡命者は男を庇って亡くなった。男は亡命者の形見を手に故郷に帰った。(終)
映画公開時は一部3D映像だったらしい。3Dつっても「スパイ・キッズ3D」みたいな赤青メガネをかけるやつね。DVDでは普通の映像。大部分はブルーバック合成画像だと思う。ひまわり畑はきれいだが、空の色が不自然なのが気になる。
中大兄皇子役の大杉漣、藤原鎌足役の石橋蓮司が並ぶと、なんか悪党が二人で悪企みという感じになりそうなものだが、全然古代人の雰囲気はないものの、異国人風だった。

根津甚八(1947年12月1日-)は、「山梨県都留市出身の日本の男性俳優。本名は、根津透(ねづ とおる)。ユマニテ所属。芸名は、真田十勇士の一人根津甚八に由来する。劇団『状況劇場』所属時に、苗字の「根津」に合う芸名として唐十郎に命名された」。
「歯科医師の家の三男として生まれる。日本大学第三高等学校卒業、獨協大学外国語学部フランス語学科中退。演出家・劇作家の唐十郎主催の状況劇場に入団、1969年から79年まで在籍した。1978年にはNHK制作の大河ドラマ『黄金の日日』に石川五右衛門役で出演、翌年には同局制作の『失楽園'79』、映画『その後の仁義なき戦い』などで主演した」。
「黒澤明監督の映画にも何度か主要な登場人物役で出演している(1980年の『影武者』、1985年の『乱』)。2007年現在、ユマニテに所属。2002年頃から右目下直筋肥大という顔面の病気を患い活動を縮小していた。2004年7月に交通事故を起こし、被害者を死亡させた。その後しばらくの間活動を停止していたが、2006年5月よりブログを運営している」。(ウィキペディア)
<第三部:「おんな国衆一揆」(2002年 60分)
国衆(地元豪族)が肥後領主の佐々成政に起こした肥後国衆一揆。鎮圧にてこずった佐々は秀吉の不興を買い,切腹。後任は加藤清正。
一揆の知らせに秀吉(竹中直人)は怒って茶会を中止した。豊臣の大軍が領主の佐々成政(石橋蓮司)の助成に向かい、国衆一揆はほとんど鎮圧されたが、名だたる大名軍に取り囲まれても和仁一族が篭った田中城だけは、どうしても落ちなかった。しかし内部の裏切りにより、田中城もついに落ちた。(終)
和仁一族というのは、原田芳雄、布施博、遠藤憲一の実の3兄弟と、兄弟の妹の夫・北村一輝が主要メンバーだが、やけにみんなかっこいい。裏切るのは北村一輝。どこが「おんな」なのかが、よくわからない。たしかに「おんな」にところどころコメントさせているが、全体の視点は男中心のように思える。「時代劇映画感想文集」(http://www.bekkoame.ne.jp/i/django/index.html)
「SABU」(2002)、「着信アリ」(2004)、先月公開された「クローズZERO」」のあの三池崇史監督が本作を撮ったということ、この経緯だけはちょっとわかりませんでした。

三池崇史(1960年8月24日-)は、「三重県尾鷲市出身の板金工の父の下に、大阪府八尾市で生まれる。日本映画学校卒業。今村昌平、恩地日出夫に師事。1991年のVシネマ『突風!ミニパト隊』で監督デビュー、1995年の『新宿黒社会』で初の劇場用オリジナル作品を手掛けた。コメディ、バイオレンス、ホラーなど多岐に渡るジャンルで映画制作を続ける」。
「1998年に、米『TIME』誌上よりこれから活躍が期待される非英語圏の監督としてジョン・ウーと並び10位に選出。作品はクエンティン・タランティーノ監督に影響を与える(『殺し屋1』など)。『極道恐怖大劇場 牛頭』はVシネマとして初めてカンヌ国際映画祭に出品された。旧名は三池モバ。多作である」。
「その映画制作スタイルは、鮮烈な暴力描写を伴うため、しばしば論争を巻き起こすものの、海外での評価は高い。2001年のトロント国際映画祭での『殺し屋1』の上映時には、エチケット袋を観客に配り、暴力描写が自分の持ち味であることをアピールした。海外での受賞は『極道戦国志 不動』でファンタスボルト国際映画祭審査員特別賞」。
「『オーディション』でロッテルダム国際映画祭で国際批評家連盟賞とオランダジャーナリズム連盟賞。『カタクリ家の幸福』でジェルミナーレ国際ファンタスティック映画祭審査員特別賞。『牛頭』で第36回シッチェス・カタロニア国際映画祭審査員特別ビジュアルエフェクト賞など多数。フランシス・コッポラやウェイ・ワンがアジア人監督作品をプロデュースする企画に日本から参加が発表されるなど、ハリウッドからの引き合いは数年前からあった」。
「2006年にはアメリカのケーブルテレビ局Showtimeが企画した、ホラー映画の巨匠13人によるオムニバステレビシリーズ『マスターズ・オブ・ホラー』の第1シーズンに、日本人唯一の参加を果たした。しかし、実際に三池が製作した『インプリント ~ぼっけえ、きょうてえ~』(原作・岩井志麻子)は比較的緩いといわれるケーブルテレビの放送コードにさえ引っ掛かってしまう内容のもので、北米での放映は見送られることとなり、話題となった」。
「また、日本では角川ヘラルド・ピクチャーズ配給で映画館公開も計画されていたが、映倫が審査を拒否したため、映倫の審査が必要ないシアター・イメージフォーラムで単館上映した。2007年11月、米『TIME』誌の調査による「Top 25 Horror Movies(ホラー映画ベスト25)」に唯一の日本映画として『オーディション』が選出された」。(ウィキペディア)
第一部:「隧穴幻想 トンカラリン夢伝説」(1998年)
第二部:「鞠智城物語 防人たちの唄」(2000年)
第三部:「おんな国衆一揆」(2002年)
いや、内容はわかりやすいんですよ。わからないのは、この映画が製作された経緯、監督、俳優陣のキャスティングについてなんです。熊本を舞台にした映画はこの10年間で見ても、「英二」(1999年/黒土三男監督)、「ボクの、おじさん THE CROSSING(2000年/東陽一監督)、「女帝 Super Queen」(2001年/金澤克次監督)、「黄泉がえり」(2003年/塩田明彦監督)、「聞こゆるや」(2004年/山田武監督)などがありますが、この作品はちょっと異質です。で、調べてみました。
第一部の「隧穴幻想 トンカラリン夢伝説」には平幹二朗さん、大杉漣さん。第二部:「鞠智城物語 防人たちの唄」には江守徹さん、根津甚八さん、ナレーターに竹中直人さん。第三部の「おんな国衆一揆」には原田芳雄さん、竹中直人さん、石橋蓮司さん、大杉漣さん、布施博さん、遠藤憲一さん、あべ静江、青田典子そして、北村一輝さん。ナレーターに竹下景子さん。
豪華でしょ?おまけに、なんと塩谷義子(1939年4月5日-)熊本県知事が北の政所・ねねを演じています。さらに、この三部作を通じて全て主演格で登場するのが、はた三恵という女優さんなんですが、よく知りません。熊本出身の方なのでしょうか?全体の配役陣からすると、ちょっと奇異な配役です。そう言えば数年前、熊本空港であべ静江さんを見かけ、市内の小料理屋で竹中直人さんに出くわしましたが、この映画の関係だったのかと思い起こします。
この映画、上映は熊本県限定だったとか。制作は、「隧穴幻想 トンカラリン夢伝説」が玉名郡菊水町、「鞠智城物語 防人たちの唄」が熊本県立装飾古墳館、「おんな国衆一揆」は「財団法人・日本宝くじ協会」の助成事業で、制作が玉名郡三加和町となっています。この辺で制作背景がわかりました。
要は、熊本県立装飾古墳館が本締めさんなんですね。「くまもとアートポリス事業」の一環として建築家の安藤忠雄さんが設計されたくらいを知っている程度です。私はまだ訪れたことがないのですが、次のようなところです。

「文化庁が1979年に提唱した『風土記の丘』設置構想の一環として、熊本県が菊池川流域の山鹿市・鹿本郡鹿央町(現・山鹿市)・玉名郡菊水町(現・和水町)の3地区を指定し、『肥後古代の森』として整備を進めた。ここ熊本県立装飾古墳館は、その中心施設として1992年に開館した」。
さらに、この古墳館には、次ぎの二つのアニメ作品が所蔵されています。
『山鹿灯籠』
山鹿市の「山鹿灯籠」の成り立ちを描いた物語。実写を交えた切り絵によるアニメ映画です。
監督:三池崇史、声の出演:古谷一行、ナレーター:はた三恵
『松尾敬宇とその母』
激動の昭和に生きた山鹿市出身の一青年、松尾敬宇海軍中佐と戦後を生きた母の物語。不戦の誓いと平和の尊さを訴えたアニメ映画です。
監督:三池崇史、声の出演:萩原聖人、藤村俊二、松坂慶子、ナレーター:勝野洋
やはり凄いキャスティングです。そしてはた三恵さんも登場します。三池崇史さんは大阪出身なので、どういう経緯でここまでこの古墳館にコミットされているのか知りたいところです。
さて、内容ですが、「時代劇映画感想文集」というサイトに詳細なコメントがありましたので、そちらから引用させてもらいます。
<第一部:「隧穴幻想 トンカラリン夢伝説」(1998年 33分)>
熊本県北部にトンネル遺跡があり、地元ではトンカラリンと呼んでいる。トンネルは全長数百mほどもあり自然にこんな洞窟ができることはありえないから、明らかに人間が作ったものである。しかし、どんな人たちが何の目的で作ったものかは皆目わからず、諸説がある。そこを脚本家のイマジネーションで一種の神話ファンタジーに仕上げた作品。
1500年前、トンカラリンを神の通り道として祀っている村を、ヤマトの兵が襲ってくる。村人の多くは隣の山に逃げたが、神穴を守る巫女と戦士(平幹二朗)は村に残って最後まで戦う。二人の命が尽きたとき、穴から龍の姿をした神が現れ、二人の魂を運び去った。(終)
まず見所は、平幹二朗の鬼気迫る頑張りぶりであろう。本来、村の戦士は若者の設定で平の実年齢からしたらかなりの無理がある役なのだが、歌舞伎のような隈取りメイクと切れのいい体の動きでカバー。途中からメイクだけでなく芝居自体が歌舞伎っぽくなってくるのだが、この辺は舞台俳優としての平幹二朗の真骨頂で、ケレン味溢れた大熱演。昔、築地本願寺で見た「オイディプス王」(蜷川幸雄演出)を思い出した。古代劇はこの人、大得意なのだ。そして大仰な演技も、三池映画のカラーにもよく合っているように思う。
時代考証なしの自由な発想で作られた衣装も、注目していいところだと思う。ヤマトの兵士達は黒尽くめでマントを羽織っていて、「ロードオブザリング」の黒い騎士みたいだ。戦士の衣装も巫女の衣装も何度か変わるが、シルエットがきれいでなかなかいいでき。
映像はときどきいかにも低予算風になるところが、気になる。背景が書割りで床にはスモーク、とか。あと巫女が踊りだすとシュボっと音をたてて神具に火が灯るところの安っぽさには、思わず苦笑。
<第二部:「鞠智城物語 防人たちの唄」(2000年 29分)>
鞠智城は、大和朝廷が国防拠点として作った砦のひとつ。いわゆる朝鮮式山城で、白村江の戦い後、朝鮮半島から亡命してきた百済の人たちから伝えられた。
平和に妻子と暮らす男(根津甚八)は、家族と別れ防人として鞠智城での兵役に付いた。毎日見張りだけで飽きてしまった男に、朝鮮からの亡命者(江守徹)が祖国が滅びたときのつらい思い出を話し、国や家族を守ることの大事さを諭した。3年の任期も終わり、男が故郷に帰れると喜んでいると、突然大地震が来た。亡命者は男を庇って亡くなった。男は亡命者の形見を手に故郷に帰った。(終)
映画公開時は一部3D映像だったらしい。3Dつっても「スパイ・キッズ3D」みたいな赤青メガネをかけるやつね。DVDでは普通の映像。大部分はブルーバック合成画像だと思う。ひまわり畑はきれいだが、空の色が不自然なのが気になる。
中大兄皇子役の大杉漣、藤原鎌足役の石橋蓮司が並ぶと、なんか悪党が二人で悪企みという感じになりそうなものだが、全然古代人の雰囲気はないものの、異国人風だった。

根津甚八(1947年12月1日-)は、「山梨県都留市出身の日本の男性俳優。本名は、根津透(ねづ とおる)。ユマニテ所属。芸名は、真田十勇士の一人根津甚八に由来する。劇団『状況劇場』所属時に、苗字の「根津」に合う芸名として唐十郎に命名された」。
「歯科医師の家の三男として生まれる。日本大学第三高等学校卒業、獨協大学外国語学部フランス語学科中退。演出家・劇作家の唐十郎主催の状況劇場に入団、1969年から79年まで在籍した。1978年にはNHK制作の大河ドラマ『黄金の日日』に石川五右衛門役で出演、翌年には同局制作の『失楽園'79』、映画『その後の仁義なき戦い』などで主演した」。
「黒澤明監督の映画にも何度か主要な登場人物役で出演している(1980年の『影武者』、1985年の『乱』)。2007年現在、ユマニテに所属。2002年頃から右目下直筋肥大という顔面の病気を患い活動を縮小していた。2004年7月に交通事故を起こし、被害者を死亡させた。その後しばらくの間活動を停止していたが、2006年5月よりブログを運営している」。(ウィキペディア)
<第三部:「おんな国衆一揆」(2002年 60分)
国衆(地元豪族)が肥後領主の佐々成政に起こした肥後国衆一揆。鎮圧にてこずった佐々は秀吉の不興を買い,切腹。後任は加藤清正。
一揆の知らせに秀吉(竹中直人)は怒って茶会を中止した。豊臣の大軍が領主の佐々成政(石橋蓮司)の助成に向かい、国衆一揆はほとんど鎮圧されたが、名だたる大名軍に取り囲まれても和仁一族が篭った田中城だけは、どうしても落ちなかった。しかし内部の裏切りにより、田中城もついに落ちた。(終)
和仁一族というのは、原田芳雄、布施博、遠藤憲一の実の3兄弟と、兄弟の妹の夫・北村一輝が主要メンバーだが、やけにみんなかっこいい。裏切るのは北村一輝。どこが「おんな」なのかが、よくわからない。たしかに「おんな」にところどころコメントさせているが、全体の視点は男中心のように思える。「時代劇映画感想文集」(http://www.bekkoame.ne.jp/i/django/index.html)
「SABU」(2002)、「着信アリ」(2004)、先月公開された「クローズZERO」」のあの三池崇史監督が本作を撮ったということ、この経緯だけはちょっとわかりませんでした。

三池崇史(1960年8月24日-)は、「三重県尾鷲市出身の板金工の父の下に、大阪府八尾市で生まれる。日本映画学校卒業。今村昌平、恩地日出夫に師事。1991年のVシネマ『突風!ミニパト隊』で監督デビュー、1995年の『新宿黒社会』で初の劇場用オリジナル作品を手掛けた。コメディ、バイオレンス、ホラーなど多岐に渡るジャンルで映画制作を続ける」。
「1998年に、米『TIME』誌上よりこれから活躍が期待される非英語圏の監督としてジョン・ウーと並び10位に選出。作品はクエンティン・タランティーノ監督に影響を与える(『殺し屋1』など)。『極道恐怖大劇場 牛頭』はVシネマとして初めてカンヌ国際映画祭に出品された。旧名は三池モバ。多作である」。
「その映画制作スタイルは、鮮烈な暴力描写を伴うため、しばしば論争を巻き起こすものの、海外での評価は高い。2001年のトロント国際映画祭での『殺し屋1』の上映時には、エチケット袋を観客に配り、暴力描写が自分の持ち味であることをアピールした。海外での受賞は『極道戦国志 不動』でファンタスボルト国際映画祭審査員特別賞」。
「『オーディション』でロッテルダム国際映画祭で国際批評家連盟賞とオランダジャーナリズム連盟賞。『カタクリ家の幸福』でジェルミナーレ国際ファンタスティック映画祭審査員特別賞。『牛頭』で第36回シッチェス・カタロニア国際映画祭審査員特別ビジュアルエフェクト賞など多数。フランシス・コッポラやウェイ・ワンがアジア人監督作品をプロデュースする企画に日本から参加が発表されるなど、ハリウッドからの引き合いは数年前からあった」。
「2006年にはアメリカのケーブルテレビ局Showtimeが企画した、ホラー映画の巨匠13人によるオムニバステレビシリーズ『マスターズ・オブ・ホラー』の第1シーズンに、日本人唯一の参加を果たした。しかし、実際に三池が製作した『インプリント ~ぼっけえ、きょうてえ~』(原作・岩井志麻子)は比較的緩いといわれるケーブルテレビの放送コードにさえ引っ掛かってしまう内容のもので、北米での放映は見送られることとなり、話題となった」。
「また、日本では角川ヘラルド・ピクチャーズ配給で映画館公開も計画されていたが、映倫が審査を拒否したため、映倫の審査が必要ないシアター・イメージフォーラムで単館上映した。2007年11月、米『TIME』誌の調査による「Top 25 Horror Movies(ホラー映画ベスト25)」に唯一の日本映画として『オーディション』が選出された」。(ウィキペディア)










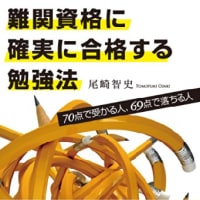
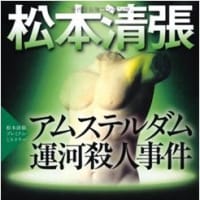
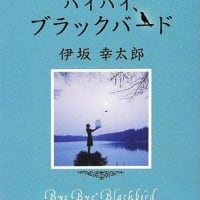

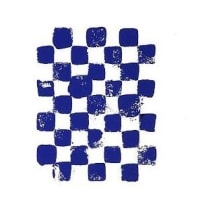
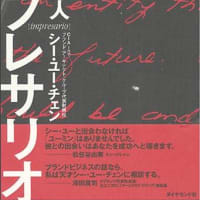



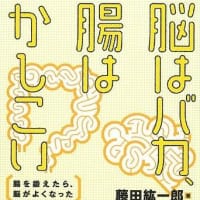
この世界は「お金」よりも強い「人脈」というものが存在します。
これだけのメンバーを揃えることができる大物が仕切っているのです。
もう一度スタッフリストを見てみれば誰がキーマンか分かるはずです。
金にまみれた芸能界のイメージがありますが、
みたいな、義理人情にあふれた面もあるのです。
いまは皆大物ですが、若い頃は・・・。
苦労を分かち合った人達の友情作品ともいえるのではないでしょうか