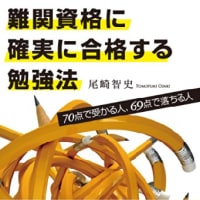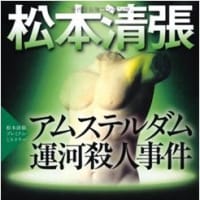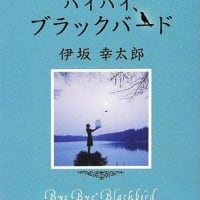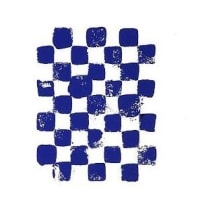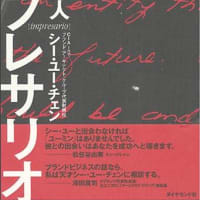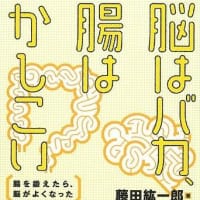~『乃木希典』で明治という時代の宿命と矛盾を背負った軍神の実像を提示した筆者が、今度は山下奉文を通して昭和の悲劇を浮き彫りにします。大英帝国の拠点シンガポールを攻略してヨーロッパのアジア植民地支配を打ち破りながら、マニラで絞首刑に処された軍人の末路にこそ、昭和の本質が凝縮されているのではないでしょうか。乃木や、同時代を生きた東條英機との比較を通してより重厚な山下像を描き出した、傑作軍人評伝シリーズ第二弾です。(文芸春秋/TA)~
<目次>
一 英雄(大杉のもとに宿った二つの運命、徹底した合理主義が生んだ「特攻の思想」、貧困を眺めながら育った少年期)
二 組織(何故、皇道派に加担したのか、山下・パーシバル会談の真相、保田與重郎の山下観)
三 粛清(疑わしきは罰す、「死んだ兵隊のために動いてはナラン」、「恐怖」によって辛うじて保たれていた中立、井伏鱒二の筆による「マレーの虎」の横顔)
四 敗北(セクショナリズムの病弊、大西瀧治郎の二〇〇〇万人特攻論、退却と飢餓、屈辱に満ちた降伏調印式、終焉の地ロス・バニョス)
前回取り上げた「あっぱれ日本兵」の著者ケネス・ハリソンがオーストラリア兵として戦ったマレー半島の日本軍の指揮官が本著の主人公、山下奉文(ともふみ)。この稀有の軍人、山下奉文の人となりについて概要をまとめてみると、大雑把には次のようになります。
・明治18年(1885年)11月8日、高知生まれ。第二次世界大戦当時の陸軍大将。陸軍大学校28期生で、一年先輩に東條英機。
・1936年の二・二六事件で皇道派の幹部として決起部隊に理解を示し、陸軍大臣と侍従武官長を通じて、彼らの自決に立ち会う侍従武官の差遣を昭和天皇に願い出たため天皇の不興を買う。
・1941年、第25軍司令官として1941年12月マレー作戦を指揮し、日本のマスコミからは「マレーの虎」と呼ばれた
・1944年、第14方面軍司令官として起用され、日本軍が占領していたフィリピンの防衛戦を指揮する事になり、1945年9月3日フィリピンのバギオにて降伏。
・1946年2月23日、マニラ郊外ロス・バニョスで絞首刑に処される。
1942年初頭から日本軍とイギリス軍、英印軍、オーストラリア軍の間で激戦が繰り広げられたマレー作戦とシンガポールの戦い。ミャンマー、タイ、マレーシア、シンガポールという国々から構成されるマレー半島で、35,000名を擁する山下奉文司令官、対するは88,600名の頂点に立つアーサー・パーシバル中将。
この大東亜戦争緒戦のシンガポール攻略時にパーシバルに「イエスかノーか」と強圧的に降伏交渉を行ったとされ、これが、日露戦争で旅順の司令官だった乃木希典がステッセルとの会見で武士道をもって遇したことに対比されて、その対応が武士の情けを知らないのではないかと批判する識者もいるそうです。
この点について、本書で著者の福田さんは当時の副官やメディアの伝え方に触れ、その真相に迫っていますが、結論的な言辞は避けて、「新聞記者が談話まで捏造することは考え難いから、やはりこのように語ったのだろう。もちろん、山下がいたわりの言葉を語ったを語ったけれども、それが活字にならなかった可能性はある」としながら、山下の次の談話を引用しています。
~敵は往生際が悪かった、イギリスは往生際が悪いと同時にマレーの経営を搾取的にやっていたことをつくづく感じた又退却するにも掠奪しながらだ、敵第一線には印度兵、次に豪州兵、最後にイギリス本国兵といふ徹底した横着なやり方だ、そんなことでは戦に勝てるものかね(朝日新聞 昭和17年3月2日)~
山下奉文の生涯は、二つの木に象徴されます。それは、杉とマンゴの木。著者は本書の冒頭で次のように記しています。

~「マレーの虎」山下奉文は、杉の足元で育ち、杉を仰ぎ、杉に参り、杉に誓って、人となった。自らを号して「巨杉」と称した。~
この杉は高知県大豊町に屹立する「杉の大杉」のこと。最古の昔に須佐之男命(すさのおみこと)が植えられたと伝えられる推定樹齢3000年の巨木。美空ひばりの聖地としても高名。
そして、マンゴの木。フィリピンでは、絞首刑はマンゴの木の下で執り行われるそうです。山下奉文終焉の地となったロス・バニョスのマンゴの木で山下も処刑されました。この処刑についてサイトで次のような解説がありました。

~山下大将は昭和20年9月3日に降伏し、戦争犯罪者として起訴されました。裁判は10月29日に始まり真珠湾攻撃の前日にあたる12月7日に絞首刑の判決。そして昭和21年2月11日、紀元節の日にマッカーサーから処刑執行命令が出され、2月23日の初代アメリカ大統領ワシントンの誕生日であるワイントン・デーにマンゴーの木に作られた簡易処刑場で絞首刑にされます。
迅速だけの復讐裁判です。命からがらフィリピンより部下を捨てて逃げ出したマッカーサーはこの間にも裁判を急げとせき立てます。自らの恥辱を晴らさんと復讐に燃えるマッカーサーにより、山下大将は軍人でありながら軍服を禁ぜられ、カーキ色のシャツ、ズボン姿で敵軍である米軍の作業帽をかぶせられ、欧米では一番恥ずべきものとされる絞首刑により処刑されました。そして、その遺体の埋葬場所は秘密にされたままです。~
<米軍による戦犯遺体処理について>
http://www.tamanegiya.com/beigunnsennpannitaisyori.html
将来を嘱望された大日本帝国陸軍の超エリートは、今から74前の2月26日のクーデターに理解を示したことで、華やかなりき出世のレールから降ろされることになりました。そして、以降も軍部という組織の中で役割を全うし、「マレーの虎」として表舞台に復活した後も、戦火が沖縄、本土に及ぶことを少しでも遅らせるための戦略を講じながらも組織からの支援は得られず、軍人としての矜持を捨てられるように絞首刑によってその生涯を閉じました。
敗戦から65年後の今、バンクーバーでは殺戮のない、スポーツマンシップに則った戦いが平和裏に競われています。日本選手団の健闘を称えつつも、半世紀以上前に国家を守るために死闘を演じた同年代の英霊たちの想いに感謝することを忘れてはなりませんね。

<山下奉文 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%8B%E5%A5%89%E6%96%87

<アーサー・パーシバル- Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%90%E3%83%AB
<河村参郎 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E6%9D%91%E5%8F%82%E9%83%8E

<福田和也 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%92%8C%E4%B9%9F
<「あの戦争になぜ負けたのか」(半藤一利他共著/文春新書刊)>
http://blog.goo.ne.jp/asongotoh/e/6f2bffb6e5870d44892c4ec9399fb12d
<「大丈夫な日本」(福田和也著/文春新書刊)>
http://blog.goo.ne.jp/asongotoh/e/cb19d735a3d73aaa193dc78218ef1600
<備忘録>
バーデンの誓い(P42)、草莽崛起(吉田松陰の思想/「草莽」は『孟子』においては草木の間に潜む隠者を指し、転じて一般大衆を指す。「崛起」は一斉に立ち上がることを指す。“在野の人よ、立ち上がれ”の意)。(P58)、山下が主催した慰霊祭(P78)、華僑たちの義勇軍(P91)、大西覚(P97)、河村参郎警備司令官(P87、94)、沼田真蔵(P120)、ベンゲッド道路の伝説~バギオ高地の道路開削工事~(P163)
<目次>
一 英雄(大杉のもとに宿った二つの運命、徹底した合理主義が生んだ「特攻の思想」、貧困を眺めながら育った少年期)
二 組織(何故、皇道派に加担したのか、山下・パーシバル会談の真相、保田與重郎の山下観)
三 粛清(疑わしきは罰す、「死んだ兵隊のために動いてはナラン」、「恐怖」によって辛うじて保たれていた中立、井伏鱒二の筆による「マレーの虎」の横顔)
四 敗北(セクショナリズムの病弊、大西瀧治郎の二〇〇〇万人特攻論、退却と飢餓、屈辱に満ちた降伏調印式、終焉の地ロス・バニョス)
前回取り上げた「あっぱれ日本兵」の著者ケネス・ハリソンがオーストラリア兵として戦ったマレー半島の日本軍の指揮官が本著の主人公、山下奉文(ともふみ)。この稀有の軍人、山下奉文の人となりについて概要をまとめてみると、大雑把には次のようになります。
・明治18年(1885年)11月8日、高知生まれ。第二次世界大戦当時の陸軍大将。陸軍大学校28期生で、一年先輩に東條英機。
・1936年の二・二六事件で皇道派の幹部として決起部隊に理解を示し、陸軍大臣と侍従武官長を通じて、彼らの自決に立ち会う侍従武官の差遣を昭和天皇に願い出たため天皇の不興を買う。
・1941年、第25軍司令官として1941年12月マレー作戦を指揮し、日本のマスコミからは「マレーの虎」と呼ばれた
・1944年、第14方面軍司令官として起用され、日本軍が占領していたフィリピンの防衛戦を指揮する事になり、1945年9月3日フィリピンのバギオにて降伏。
・1946年2月23日、マニラ郊外ロス・バニョスで絞首刑に処される。
1942年初頭から日本軍とイギリス軍、英印軍、オーストラリア軍の間で激戦が繰り広げられたマレー作戦とシンガポールの戦い。ミャンマー、タイ、マレーシア、シンガポールという国々から構成されるマレー半島で、35,000名を擁する山下奉文司令官、対するは88,600名の頂点に立つアーサー・パーシバル中将。
この大東亜戦争緒戦のシンガポール攻略時にパーシバルに「イエスかノーか」と強圧的に降伏交渉を行ったとされ、これが、日露戦争で旅順の司令官だった乃木希典がステッセルとの会見で武士道をもって遇したことに対比されて、その対応が武士の情けを知らないのではないかと批判する識者もいるそうです。
この点について、本書で著者の福田さんは当時の副官やメディアの伝え方に触れ、その真相に迫っていますが、結論的な言辞は避けて、「新聞記者が談話まで捏造することは考え難いから、やはりこのように語ったのだろう。もちろん、山下がいたわりの言葉を語ったを語ったけれども、それが活字にならなかった可能性はある」としながら、山下の次の談話を引用しています。
~敵は往生際が悪かった、イギリスは往生際が悪いと同時にマレーの経営を搾取的にやっていたことをつくづく感じた又退却するにも掠奪しながらだ、敵第一線には印度兵、次に豪州兵、最後にイギリス本国兵といふ徹底した横着なやり方だ、そんなことでは戦に勝てるものかね(朝日新聞 昭和17年3月2日)~
山下奉文の生涯は、二つの木に象徴されます。それは、杉とマンゴの木。著者は本書の冒頭で次のように記しています。

~「マレーの虎」山下奉文は、杉の足元で育ち、杉を仰ぎ、杉に参り、杉に誓って、人となった。自らを号して「巨杉」と称した。~
この杉は高知県大豊町に屹立する「杉の大杉」のこと。最古の昔に須佐之男命(すさのおみこと)が植えられたと伝えられる推定樹齢3000年の巨木。美空ひばりの聖地としても高名。
そして、マンゴの木。フィリピンでは、絞首刑はマンゴの木の下で執り行われるそうです。山下奉文終焉の地となったロス・バニョスのマンゴの木で山下も処刑されました。この処刑についてサイトで次のような解説がありました。

~山下大将は昭和20年9月3日に降伏し、戦争犯罪者として起訴されました。裁判は10月29日に始まり真珠湾攻撃の前日にあたる12月7日に絞首刑の判決。そして昭和21年2月11日、紀元節の日にマッカーサーから処刑執行命令が出され、2月23日の初代アメリカ大統領ワシントンの誕生日であるワイントン・デーにマンゴーの木に作られた簡易処刑場で絞首刑にされます。
迅速だけの復讐裁判です。命からがらフィリピンより部下を捨てて逃げ出したマッカーサーはこの間にも裁判を急げとせき立てます。自らの恥辱を晴らさんと復讐に燃えるマッカーサーにより、山下大将は軍人でありながら軍服を禁ぜられ、カーキ色のシャツ、ズボン姿で敵軍である米軍の作業帽をかぶせられ、欧米では一番恥ずべきものとされる絞首刑により処刑されました。そして、その遺体の埋葬場所は秘密にされたままです。~
<米軍による戦犯遺体処理について>
http://www.tamanegiya.com/beigunnsennpannitaisyori.html
将来を嘱望された大日本帝国陸軍の超エリートは、今から74前の2月26日のクーデターに理解を示したことで、華やかなりき出世のレールから降ろされることになりました。そして、以降も軍部という組織の中で役割を全うし、「マレーの虎」として表舞台に復活した後も、戦火が沖縄、本土に及ぶことを少しでも遅らせるための戦略を講じながらも組織からの支援は得られず、軍人としての矜持を捨てられるように絞首刑によってその生涯を閉じました。
敗戦から65年後の今、バンクーバーでは殺戮のない、スポーツマンシップに則った戦いが平和裏に競われています。日本選手団の健闘を称えつつも、半世紀以上前に国家を守るために死闘を演じた同年代の英霊たちの想いに感謝することを忘れてはなりませんね。

<山下奉文 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%8B%E5%A5%89%E6%96%87

<アーサー・パーシバル- Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%90%E3%83%AB
<河村参郎 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E6%9D%91%E5%8F%82%E9%83%8E

<福田和也 - Wikipedia>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%92%8C%E4%B9%9F
<「あの戦争になぜ負けたのか」(半藤一利他共著/文春新書刊)>
http://blog.goo.ne.jp/asongotoh/e/6f2bffb6e5870d44892c4ec9399fb12d
<「大丈夫な日本」(福田和也著/文春新書刊)>
http://blog.goo.ne.jp/asongotoh/e/cb19d735a3d73aaa193dc78218ef1600
<備忘録>
バーデンの誓い(P42)、草莽崛起(吉田松陰の思想/「草莽」は『孟子』においては草木の間に潜む隠者を指し、転じて一般大衆を指す。「崛起」は一斉に立ち上がることを指す。“在野の人よ、立ち上がれ”の意)。(P58)、山下が主催した慰霊祭(P78)、華僑たちの義勇軍(P91)、大西覚(P97)、河村参郎警備司令官(P87、94)、沼田真蔵(P120)、ベンゲッド道路の伝説~バギオ高地の道路開削工事~(P163)