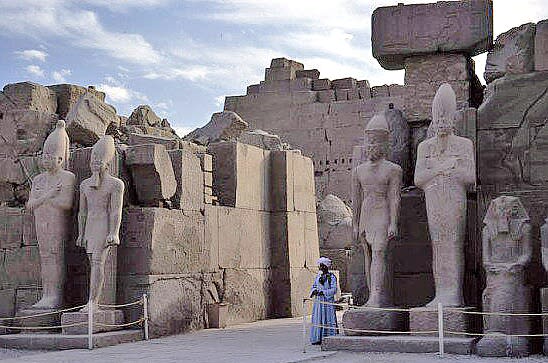挨拶 古井由吉散文訳・「詩への小路」より。
――いえ、まだ何物でもありません。このシャンペンではないが、泡みたいなもの、あるいはすでに渦巻く海の泡でもありますか。とにかく無色透明なるこの詩は、このグラスに喩えるなら、中身はさておき、輪郭つまり形ばかりを定めたものであります。空の器は空の器でもしかし、遠くの海でセイレーンの群れがこれを耳にしたら、術を破られ、多くはのけざまに海中に沈む、とそれほどのものかと自負しております。
さて出航だ。多士済々の友よ。わたしは船尾に立った、諸兄は雷の轟く冬の荒海を押し分ける華麗な船首に就かれよ。すでに美酒に酔った心で、縦揺れにも怖じず、別れの挨拶をまっすぐに唱える。「孤独、暗礁、星辰」と。世に通るまいと知ったことか。われらが帆の、白い憂慮をここに掲げる。
頌(たたえごと) 加藤美雄訳・「マラルメ詩集」より。
華麗で、混濁したインドを越えて
航海のひたすらな願いへと――この挨拶
現代の使者、あなたの船尾(とも)が
回りつつある岬はささげられる
あたかも、帆船とともに水くぐる
なにかの低い帆桁のうえで
跳ね回りつつ、新しい陶酔の鳥が
ただ一羽、飛沫(しぶき)を浴びるように
舵柄(かじ)の方向(むき)が変わらぬうちは
この鳥の単調な鳴き声が
ひとつの無用な方角、夜、絶望
そして宝石類を訴えていた
蒼白いヴァスコの微笑まで
映しだされたその歌声によって。
同じマラルメの1編の詩の翻訳も、翻訳者の捉え方によってこのように変わるものですねぇ。
1498年、「ヴァスコ・ダ・ガマ」の喜望峰回りのインド航路の発見から、カルカッタに至るまでの航海の400周年を記念して、出版されたアルバム(1898年4月20日刊)に掲載されたマラルメの作品です。マラルメは同年9月9日に亡くなっていますので、おそらくこの作品が最期の作品と思われます。
インド航路開拓以降の400年は、インドにとっては植民地支配、産業革命、市民革命、科学技術の発達などなど、大きな歴史の動きに揺り動かされ、翻弄された時代でもあったのではないでしょうか?ヴァスコ・ダ・ガマの非常に困難な航海は、実は今なお続いているのではないでしょうか?海底にはいったい何艘の破船が沈んでいることでしょうか?
しかし、この偉大な400年前の航海者を讃えつつ、若き詩人たちにこれからの難路を示し、不安で蒼白であったかもしれぬヴァスコ・ダ・ガマの頬の色のような乾杯を捧げつつ、激励するのだった。詩の遠征のために。
祝杯(トースト) 加藤美雄訳
虚無(リヤン)、この泡、処女(おとめ)なる詩
ただ盃をさししめすのみ。
はるかかなたに、一群の人魚
あまたみだれ、溺れんとす。
わが友人(ともだち)よ、船こぎいでて
われすでに、船尾(とも)にあり
君たちは栄華に耽る船首にありて、
轟く真冬の怒濤(あらなみ)を押しわける。
すばらしき酔(えい)の虜とはなりつつ
縦揺れに惧れもみせず
この挨拶を、立ちてささげん。
孤独、暗礁、星影、
わが帆の素白(ましろ)き苦しみを
あたえしすべてのものに。
1893年に書かれた、このソネット「祝杯」は、1898年にヴァスコ・ダ・ガマに捧げられた「頌」と深く繋がっているようです。このソネットは雑誌「ペン=ラ・プリユーム」の第7回の会合の折に、マラルメ自身が朗読したとのことです。この時マラルメは「ペン」の主幹となる時でもありました。若き詩人たちの前途を祝福するとともに、その多難をも甘受しようとしたようです。
* * *
しかし、古井由吉の散文訳は名文だなぁ。原文にはない言葉で補強したと思われますが、お見事ですね。金羊毛を探しに航海に出た「アルゴ遠征隊」の1人である「オルフォイス」と「セイレーン」との歌合戦にも繋がったイメージとなっています。