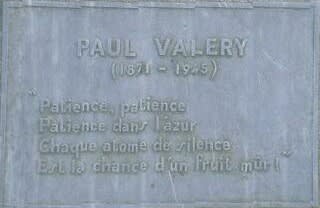歌え わが心よ、おまえの知らぬ園々を、ガラスの器に
注ぎこまれた園にも似て 澄みきった 達しえぬそれら。
イスパハンやシラスの水と薔薇、
歌え それらを歓び深く、称えよ それらをたぐいなく。
示せ わが心よ、おまえがそれらの園なしでいた時のなかったことを。
それらが、そこで熟れてゆく無花果が、おまえを想っていることを。
そこの花咲く枝々のあいだを その顔が見えるほど
昂揚してそよいでいる風と おまえが交わっていることを。
存在することへの すでに生じたこの決意にとって
欠乏があると思うような 迷誤を遠ざけよ!
絹の糸よ おまえは 織物のなかへ歩みいったのだ。
どの図様におまえが内部で織りこまれていようとも
(たとえそれが苦悩の生の1こまであろうとも)
感じるがよい、称賛すべき絨毯の全体が想われていることを。
(田口義弘訳)
うたえ、わが心よ、おまえの知らぬ庭々を。ガラスに
鋳こまれたように透明で、とどきえぬ園を。
イスパハン、またシラスの園の水と薔薇、
それらの至福を歌え、頌めたたえよ、たぐいない声で。
示せ、わが心よ、それらはるかな園が、たえずおまえに応じたことを。
そこに稔るいちじくがおまえを想ってくれようことを。
その園の花咲く枝のあわいを吹く、さながらに眼に見えるほど
高まる風と、おまえが交わっていることを。
すでに生まれたこの決意、在ろうとする決意にとって
欠乏があろうとなどとは誤ってはならぬ!
絹糸よ、おまえは存在の織目にはいったのだ。
絵柄のどれに内部では織り入れられているにせよ、
(よしんばそれが苦痛の生の一瞬であろうとも)、
感じるがよい、頌むべき絨毯の全容が意図されてあることを。
(生野幸吉訳)
イスパハン(イスファハン)はイランの都市。同市にあるアパス大王によって建てられたモシューには水の流れる庭園があります。シラスもイランの都市ですが、ここには名高い薔薇の庭園があります。ここには詩人ハーフィスの墓所もあります。また「薔薇水」や「絨毯」の産地でもあります。
ハーフィスはゲーテ(リルケと間違って書いているのではありませぬ。笑。)に大きな影響を与えた詩人であり、これによって「西東詩集」が生まれています。
さまざまな遠い呼びかけの場所として、リルケはそこを「園」と名付けています。「園」は人間と関連しつつ、しかしこの地上にある身としては、そこに至ることはできない。ただその領域を感じつつ歌い続けるのみなのだ。ここを「イスパハン」と「シラス」の園に重ねています。そのはるかな場所から風が届いている。その風と交わることによって自らの存在を知るのでしょう。
第3節から、リルケのこのソネットによくみられるように、「園」から「絹」「絨毯」への急展開が行われています。リルケの言う「全体」とは「生」と「死」を合わせ持つ統一世界であり、さらに現実と創造(想像?)との双方を合わせ持つ世界なのでしょう。
自らの存在が絹の糸の1本が織り込まれたような存在であったとしても、「絨毯」という全体のなかにおいて、自らもまたその全体に関わり、織り込まれているのだと。
《追記》
アンテピレマ(語りかけ三たび) ゲーテ 柴田翔訳
敬虔なる眼差しで
永遠なる織女の傑作を見よ。
足をひとたび踏めば千の糸が動き
左へ右へ杼(ひ)が飛び
糸と糸とが出会い流れる。
ひとたび筬(おさ)を打てば千の織り目が詰められる。
織女はそれを物乞いして集めたのではない
彼女は経糸を太古の昔から機に張っていた
永遠の巨匠が横糸を
安んじて投げることができるようにと。
注ぎこまれた園にも似て 澄みきった 達しえぬそれら。
イスパハンやシラスの水と薔薇、
歌え それらを歓び深く、称えよ それらをたぐいなく。
示せ わが心よ、おまえがそれらの園なしでいた時のなかったことを。
それらが、そこで熟れてゆく無花果が、おまえを想っていることを。
そこの花咲く枝々のあいだを その顔が見えるほど
昂揚してそよいでいる風と おまえが交わっていることを。
存在することへの すでに生じたこの決意にとって
欠乏があると思うような 迷誤を遠ざけよ!
絹の糸よ おまえは 織物のなかへ歩みいったのだ。
どの図様におまえが内部で織りこまれていようとも
(たとえそれが苦悩の生の1こまであろうとも)
感じるがよい、称賛すべき絨毯の全体が想われていることを。
(田口義弘訳)
うたえ、わが心よ、おまえの知らぬ庭々を。ガラスに
鋳こまれたように透明で、とどきえぬ園を。
イスパハン、またシラスの園の水と薔薇、
それらの至福を歌え、頌めたたえよ、たぐいない声で。
示せ、わが心よ、それらはるかな園が、たえずおまえに応じたことを。
そこに稔るいちじくがおまえを想ってくれようことを。
その園の花咲く枝のあわいを吹く、さながらに眼に見えるほど
高まる風と、おまえが交わっていることを。
すでに生まれたこの決意、在ろうとする決意にとって
欠乏があろうとなどとは誤ってはならぬ!
絹糸よ、おまえは存在の織目にはいったのだ。
絵柄のどれに内部では織り入れられているにせよ、
(よしんばそれが苦痛の生の一瞬であろうとも)、
感じるがよい、頌むべき絨毯の全容が意図されてあることを。
(生野幸吉訳)
イスパハン(イスファハン)はイランの都市。同市にあるアパス大王によって建てられたモシューには水の流れる庭園があります。シラスもイランの都市ですが、ここには名高い薔薇の庭園があります。ここには詩人ハーフィスの墓所もあります。また「薔薇水」や「絨毯」の産地でもあります。
ハーフィスはゲーテ(リルケと間違って書いているのではありませぬ。笑。)に大きな影響を与えた詩人であり、これによって「西東詩集」が生まれています。
さまざまな遠い呼びかけの場所として、リルケはそこを「園」と名付けています。「園」は人間と関連しつつ、しかしこの地上にある身としては、そこに至ることはできない。ただその領域を感じつつ歌い続けるのみなのだ。ここを「イスパハン」と「シラス」の園に重ねています。そのはるかな場所から風が届いている。その風と交わることによって自らの存在を知るのでしょう。
第3節から、リルケのこのソネットによくみられるように、「園」から「絹」「絨毯」への急展開が行われています。リルケの言う「全体」とは「生」と「死」を合わせ持つ統一世界であり、さらに現実と創造(想像?)との双方を合わせ持つ世界なのでしょう。
自らの存在が絹の糸の1本が織り込まれたような存在であったとしても、「絨毯」という全体のなかにおいて、自らもまたその全体に関わり、織り込まれているのだと。
《追記》
アンテピレマ(語りかけ三たび) ゲーテ 柴田翔訳
敬虔なる眼差しで
永遠なる織女の傑作を見よ。
足をひとたび踏めば千の糸が動き
左へ右へ杼(ひ)が飛び
糸と糸とが出会い流れる。
ひとたび筬(おさ)を打てば千の織り目が詰められる。
織女はそれを物乞いして集めたのではない
彼女は経糸を太古の昔から機に張っていた
永遠の巨匠が横糸を
安んじて投げることができるようにと。