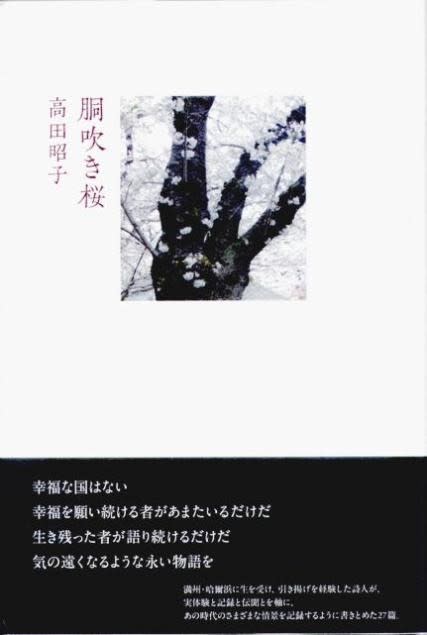「ゆずり葉」 河井酔茗
子供たちよ。
これは譲り葉の木です。
この譲り葉は
新しい葉が出来ると
入り代わつてふるい葉が落ちてしまふのです。
これは譲り葉の木です。
この譲り葉は
新しい葉が出来ると
入り代わつてふるい葉が落ちてしまふのです。
こんなに厚い葉
こんなに大きい葉でも
新しい葉が出来ると無造作に落ちる
新しい葉にいのちを譲つてー 。
こんなに大きい葉でも
新しい葉が出来ると無造作に落ちる
新しい葉にいのちを譲つてー 。
子供たちよ
お前たちは何を欲しがらないでも
凡てのものがお前達に譲られるのです。
太陽の廻るかぎり
譲られるものは絶えません。
お前たちは何を欲しがらないでも
凡てのものがお前達に譲られるのです。
太陽の廻るかぎり
譲られるものは絶えません。
輝ける大都会も
そつくりお前たちが譲り受けるのです。
読みきれないほどの書物も
みんなお前たちの手に受取るのです。
幸福なる子供たちよ
お前たちの手はまだ小さいけれどー 。
そつくりお前たちが譲り受けるのです。
読みきれないほどの書物も
みんなお前たちの手に受取るのです。
幸福なる子供たちよ
お前たちの手はまだ小さいけれどー 。
世のお父さん、お母さんたちは
何一つ持つてゆかない。
みんなお前たちに譲つてゆくために
いのちあるもの、よいもの、美しいものを、
一生懸命に造つてゐます。
何一つ持つてゆかない。
みんなお前たちに譲つてゆくために
いのちあるもの、よいもの、美しいものを、
一生懸命に造つてゐます。
今、お前たちは気が附かないけれど
ひとりでにいのちは延びる。
鳥のやうにうたひ、花のやうに笑ってゐる間に
気が附いてきます。
ひとりでにいのちは延びる。
鳥のやうにうたひ、花のやうに笑ってゐる間に
気が附いてきます。
そしたら子供たちよ。
もう一度譲り葉の木の下に立って
譲り葉を見るときが来るでせう。
もう一度譲り葉の木の下に立って
譲り葉を見るときが来るでせう。
近所の小学校では新学期。
上級生が先頭を歩いて、その後には下級生が列を組んで歩いている光景が見られる。
その道の脇に「ゆずり葉」が、新しい葉をのぞかせています。
小学校の校庭にも「ゆずり葉」があります。
上級生が先頭を歩いて、その後には下級生が列を組んで歩いている光景が見られる。
その道の脇に「ゆずり葉」が、新しい葉をのぞかせています。
小学校の校庭にも「ゆずり葉」があります。
我が子たちも、小学校の教科書で読んだはず。覚えているかしら?、


その木の下では、ウマゴヤシが咲き出しました。