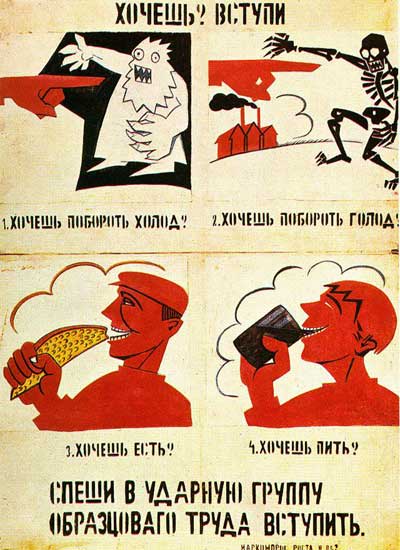ご紹介します2篇の詩は、戦後南方の島々において、戦死者とそこに茂る木々との詩です。
死者は島の土に眠り、その土から育つ木のすさまじい生命力が書かれています。
この2篇ともが、女性詩人によって書かれています。
木の実 茨木のり子
高い梢に
青い大きな果実が ひとつ
現地の若者は するする登り
手を伸ばそうとして転り落ちた
木の実と見えたのは
苔むした一個の髑髏(どくろ)である
ミンダナオ島
二十六年の歳月
ジャングルのちっぽけな木の枝は
戦死した日本兵のどくろを
はずみで ちょいと引掛けて
それが眼窩(がんか)であったか 鼻孔であったかはしらず
若く逞しい一本の木に
ぐんぐん成長していったのだ
生前
この頭を
かけがえなく いとおしいものとして
掻抱いた女が きっと居たに違いない
小さな顳顬(こめかみ)のひよめきを
じっと視ていたのはどんな母
この髪に指からませて
やさしく引き寄せたのは どんな女(ひと)
もし それが わたしだったら・・・・・・
絶句し そのまま一年の歳月は流れた
ふたたび草稿をとり出して
褒めるべき終行 見出せず
さらに幾年かが 逝く
もし それが わたしだったら
に続く一行を 遂に立たせられないまま
(茨木のり子詩集 『自分の感受性くらい』 2005年 花神社より)
たしかに言葉はない。
優しい手に抱かれて、故郷の墓地に埋められることもなく、
誰の髑髏ともわからない深い寂しさ。
こんな悲しい埋葬はあってはならない。
ダガンダガンは何故蒔かれたか 高田敏子
ダガンダガンは何故蒔かれたか
ダガンダガンは何故茂ったか
ネムに似たその木は
私のめぐった南方の島々に茂り
熱帯樹の間を埋めて
丘にも平地にも バスの走る国道の両側にも
茂りに茂り 地をおおい
枝に垂れ下がる実を割ると
黒褐色の種がこぼれた
艶やかな黒褐色の種を手のひらに遊ばせながら
木の名を尋ねる私に
「ダガンダガン」と 裸の土民は答え
彼もまた腕をのばして頭上の枝から種をとり
手のひらにこぼして見せた
──この種は戦争が終るとすぐ
米軍の飛行機が空から蒔いた
島全体に 蒔いていった
土民は種を手のひらから払い落すと
空いっぱいに両手をひろげて説明した
ダガンダガンは何故蒔かれたか
ダガンダガンは何故茂ったか
ダガンダガンの種は首飾りや花びん敷になって
土産物屋に売られている
一ドル五十セントの首飾りを二十本も求めたのは
この島サイパンで兄一家を失い 慰霊のために訪れたと語る中年の夫婦だった
テニヤン ヤップ ロタ
どの島々にもダガンダガンは茂りに茂り 地をおおい
島の旅から帰って二カ月ほど過ぎた日
硫黄島に戦友の遺骨収集に行った元工兵の記事が目にとまった
──島はギンネムのジャングルにおおわれ
昔の地形を思い出すのに 困難をきわめた。
山刀でギンネムのジャングルを切り倒しながら進み
ようようにしてかつての我々の壕を発見し 目的を果たすことができた。
これは全く死者の霊に導かれたと思うほかはない──
このギンネムとはダガンダガンに違いない
ダガンダガンは何故蒔かれたか
ダガンダガンは何故茂ったか
南の島々に蒔かれた種が 急速に成長し
茂り 隠したものの姿が 突然に私の目に浮かんだ
ダガンダガンは何故蒔かれたか
首飾りを求めた夫婦はそれについて何んの疑問も持たなかった
ダガンダガンの首飾りは若い娘の胸にゆれて
どこかの町を歩いているだろう
ダガンダガンは何故茂ったか
(高田敏子詩集『砂漠のロバ』1971年 サンリオ出版 より)
「ダカンダカン」はおそらくは「ギンネム」のことではないだろうか?
野生化した本種を指す場合「ギンネム」と呼ばれ、園芸樹木としては「ギンゴウカン=銀合歓」と呼ばれる。
強烈な繁殖力を持った樹木である。在来固有種の存続を脅かすほどに。
沖縄戦で焦土と化した島の土壌流出防止用として、
米軍がハワイ産種の種子を空中散布したという事実もある。
何故撒かれたか?焦土と多くの死者を覆い隠すためではないか?
ベトナムの枯葉剤散布を思い出すことは行き過ぎか?
「ギンネムの画像はこちらで見られます。