仲俣暁生が猛烈な勢いで、雑誌についての論考を公開している。あとわずか高みに登り俯瞰の範囲を広げる必要もあるし、いつものように強引な一点突破の部分も多いけれど、さすがに雑誌のことだけあって問題提起としては面白い。いっそのこと文芸なんかのことは忘れちゃって、この得手な方向に邁進すればよいのに、と思うが、それはさておき、ぼくも少し雑誌についての考えを書きとめておきたくなってきた。
というのも、ここ2週間ばかり本を買っていないのだけれど、気がつけばそのぶん雑誌を買っていて、仲俣とは違い、思慮浅くいまだにその面白さに沸き立つ自分に気付いたからだ。きっと、雑誌の判定に対するハードルが相当低いからなんだろうけれど、この点取り占いにも劣らないスコアの甘さは批評精神の欠如に起因するのか、少し確かめてみたくなった。まず、最近の購入履歴。
▶
『STUDIO VOICE 2008年07月号 特集:本は消えない!』

深夜に、うろが来ている状態でローソンに入ったのがまずかった。ああ、文学フリマの話なんかものっているし、イカした海外の雑誌なんかも紹介されているとの幻覚により、ほとんど中身も確かめずにレジに直行。夢からさめたとたんに、これはもうおっさんの読む雑誌じゃないなあ、と痛感した次第。
まず、タイポグラフィ。著しくリーダビリティを欠いていて老いさらばえた目にはたいへん厳しい。なかにはいくらなんでもこりゃないだろうと思えるあきらかな印刷事故もある。そして、なによりのウィークポイントは一部のテキストに見られる品質管理の甘さだ。このことは、常々言われていることだと思うが、テキストの量が多い号ほど荒さが目立つところをみると、きっと編集の現場はたいへんなことになっているんだろうなあ、と思う。
しかし、これら含めて、いやこんな不遜な態度こそが『STUDIO VOICE』であるともいえ、こんなおっさんを何度もだまくらかす「雑誌としての」パワーはいちおう残存しているのではないかと思える。心構えとかその「雑」感はなかなかのものだし、想定されたセグメントには直球であり、そういった意味では雑誌の基本型であるともいえる。
▶
『群像 7月号』

編集長には申し訳ないが今月は『新潮』をパスした。3年振りぐらいだろうか。さいわい『群像』がキャッチーだったので選んだわけだが、このところ文芸誌は全般的に驚きがなくなってきている。というか、読みたいものが各誌に分散されるクールに入ってきた。文芸誌を90年代から追っかけてみるとコンドラチェフの波のようなものが確実にあって、いまはそういったリセッションの時期かもしれない。新しい作家が生まれていないという考えの一方で過渡的な充電のための蛹時代という見方もできる。いずれにしても、M&Aをあらためてプレゼンテーションできるチャンスが再び訪れたというわけだ。
そんな7月号において、『群像』は、きわめて個人的な嗜好に寄るが訴求力はあった。内容はともかくとして、舞城王太郎はほんとうに久しぶりだし、岡田利規や大澤真幸など最近言及したISBNはやはり気になる(ただし、『群像』は対談の編集やライティングがどうもしっくりこない)。つまり、あるレベルでテキスト好きのセグメントにとっては、毎月・全誌はかなわないとしても、文芸誌はそこそこのバリューは発揮している。
▶『SANKEI EXPRESS 06/09』
もちろん新聞である。しかし、新聞休刊日にも発行されるこれは、じゃあ雑誌とどう違うのか?と問われると答えるのがむずかしい。いまこういった体裁をしたフリーペーパーは確実に増えている。そもそも、MSN産経ニュースやZAKZAKのテキストをふんだんにマルチユースしているあたりからして、記事に、量はもとより深みや複眼的な視点がなく、新聞というには何かが足りない。一方で、大判の写真を中心とした「自然エネルギー」の特集があったり、オバマの勝利と関連づけたロバート・F・ケネディの興味深いコラムもあったり、新聞とは異なる側面もある。そういった雑誌の視点でみると、競合は『AERA』ということになる。こんなこと言ったら『AERA』が激怒するな。しかし、月曜の朝の新幹線の車中では、身体がいまの『AERA』の主軸となっている記事にみられるような、押しの強いものは勘弁願いたい、と訴えるときもあるのですよ。
▶
『CASA BRUTUS No.100』

「日本の美術館・世界の美術館100」。100号記念の特別保存版だけあって網羅的で、記事のバリエーションも豊かである。これもすでに各方面で言われていることだが、いまやアダルトな『平凡』と化し、失速している本体『BRUTUS』に比べると格段に読みどころがある。アダルトな『平凡』もたとえば、2号ほど前、恒例の「居住空間学」なんかはまだまだ活きているし、次号「井上雄彦」特集のように期待をもたせるテーマアップはうまいんだけどなあ。
▶
『CASA BRUTUS 特別編集』
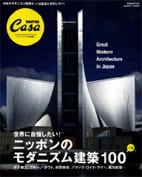
「ニッポンのモダニズム建築100+α」。2004年版のリ・イッシュー。パラパラ眺めていると、発売当時は気付かなかった「古江台の展望台」や「千里中央センタービル」、「エキスポタワー」、「希望が丘の青年の塔(とうもろこしタワー)」の写真が目に留まる。記憶の建築。一枚の建築物の写真から一挙にあまたの追想があふれ出る。これは、モノとしてアーカイブしておく必要があるとの思いに駆られ落掌した。
あらためて読み出すと、いまさらながら建築物は見ていて飽きないものだ、ということがわかってきた。これはモダン建築に限った話なのかもしれないが、「それでも建っているという絶妙の美しいバランス」「工夫のデザイン」そして「バックグラウンドへのイマジネーション」が、誰もがもつ創造の心とか「なにかを垂直に立ち上げたい」という本能のようなものを引っ張りだしてくるのだろうか。一方で、モダン建築といわれるカテゴリーのデザインが、自分の中でも確実に記憶のなかのものとなりつつあるのにはいささかの驚きを禁じえない。
ともあれ、写真とテキストの豊潤なバランスで「2000円」には少し足りない1500円。ボリウム層が買うような雑誌ではないが、そういった層にもおすすめしたいコストパフォーマンスの高さだ。ただ、さすがにMOOKだけあって、雑誌というより書籍に近い。では、本と雑誌を画するものはなにか。
▶『ROCKS』

深夜2時まで店を開いているセレクト書店(という定義はどうやら正しくなさそうだが)「SHIBUYA PUBLISHING & BOOK SELLERS」には、それこそ深夜、一度だけ足を運んだことがある(そのときはたぶん4時まで開いていたはずだ)。そのセレクトはたとえば90年代ぐらいまでなら垂涎のものだったろうが、ここまで書店のバリエーションが拡がったいまとなっては、月並みのものなのかもしれない。しかし、店舗兼編集スタジオとしての知的創造空間/現場は充分に魅力的で、本が好きな人間なら一度はこんな仕事場で労働にいそしみたいと感じるところじゃないだろうか。
『ROCKS』は、そのSPBSが、編集・創刊したオリジナル雑誌。巻頭言の気骨に感じるものがあり、なかば祝儀として購入。
<「ROCKS」(=生き様の変わらない人たち、の意)は、
安易なプロモーション主義と決別した雑誌だ。
表現したい人だけが集い、新たな価値観がうまれていく場所である。
……(中略)
おそらく広告が、最も入りにくい雑誌の一つだろう。
でも、私は頑張って営業する。
一生懸命に営業する。
だって、この雑誌が好きだから。
でも、やっぱり無理かな……。
どなたか、広告を入れていただけませんか?>
中略の部分でも気概の強いメッセージと現在の雑誌のあり方についての問題提起が続く。もし、ぼくがアラブの王様だったら確実に広告をいれてあげるのだが。
しかし、
「"流行り廃り"と決別した20人のROCKSたちが、思い思いに自らの「現在」を表現」というわりには、以下のメンツを見る限りは、決別とまではいっていないように思える。この精神をもってして号を重ねることで、洗練されていくことを期待したい。
[contents]
□創刊特集「気骨の活字」 □芥川賞作家・川上未映子による書きおろし短編小説。 □詩人・谷川俊太郎 × 田中健太郎(イラストレーター)の異色コラボレート。 □映画監督、作家・森達也の語りおろし+取材現場の撮りおろし写真。
[ROCKSによる豪華連載「ROCKS×17」]
鈴木寛(民主党議員)/新井敏記(スイッチパブリッシング社長) /松原隆一郎(東京大学教授)/浅野忠信(俳優 )/ 岡田武史(サッカー日本代表監督)/渡辺一志(映画監督)×泉谷しげる(俳優・ミュージシャン)/古田敦也 (東京ヤクルト前監督)/ 中井美穂(アナウンサー)/野口美佳(ピーチ・ジョン社長)/若木信吾(写真家)/小林紀晴(写真家・小説家)/ 岡沢高宏(cycle代表)/石渡進介(弁護士)/来栖けい(美食の王様)/幅允孝(ブックディレクター)/ドクター・セブン/野口卓也(小説家)/TNP
▶その他
◎『Inter Communication』の最終号は、買っていないし、たぶん買うことはないだろうと思う。期ごとに編集コンセプトと体裁を変えてきたインコミは、とりわけ直近のリニューアル以降、「編集」という意志が働いていないように思えてほとんど読むことはなくなっていた。最終号ぐらいは、と思ったが、それでも読んでおきたいと思える記事がなく手が伸びない。これも特定のセグメントには響くのだろうが、少しアブストラクトになりすぎた。
◎『港のひと』という美しい装丁の出版社PR誌をみつけた。その名のとおり「港の人」という鎌倉にある出版社の出版案内で、すでに5号となっている。自社で創った北村太郎という詩人の『光が射してくる 未刊行詩とエッセイ 1946-1992』の各メディアに掲載された書評を集め再編集するなど(たとえば、週刊朝日に掲載された荒川洋治のもの、毎日新聞に掲載された堀江敏幸のものなど)、ローコスト精神旺盛ではあるが、未知の読者にとってはうれしい、とてもていねいな仕事だ。わずかなページの小冊子ではあるが、ぼくに対しての役目は、立派な書評誌となった。
◎ブックガイドという観点では、東大出版会の『UP 6月号』では、恒例の豊崎由美の「上半期ガイブンおすすめ市」も掲載されていて、短いながらも愉しめる。やはり『ラナーク』と『終わりの街の終わり』なんかは抑えておきたいと読書意欲を喚起された。
こうしてみると、そのビジネスモデルはともかくとして、雑誌というメディアはかくも豊かである。しかし、最後の『港のひと』『UP』に見られるように、もはや金を出して買うものではない、という脅威もある。そして、なによりの本質問題は、今の世界では、雑誌を読むことに費やすような時間は圧倒的に減ってしまったということかもしれない。雑誌について大きな関心を寄せているぼくのようなものでも、買ったは良いが10分ほど斜め読みしてあとは放置せざるをえない雑誌が山積みになっているといった状況だ。
こういった現象に対して、ぼくはなにか素晴らしいアイデアを提言できるほどの知見をもっていない。しかし、雑誌について、話したいことは山ほどある。手始めとして雑誌の記憶を手繰ってみようと思う。
 』佐々木敦 P31)
』佐々木敦 P31)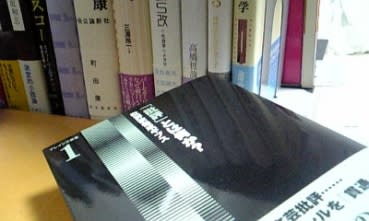
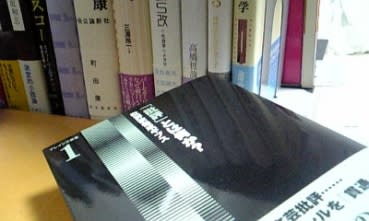














 東大合格者のノートは美しい。最後までテンションが落ちない。その“ノート術”を科目別、性格別に紹介、解説した全く新しい参考書
東大合格者のノートは美しい。最後までテンションが落ちない。その“ノート術”を科目別、性格別に紹介、解説した全く新しい参考書

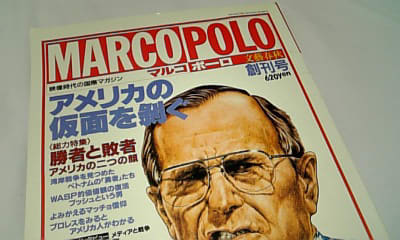

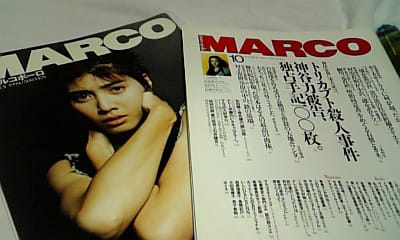

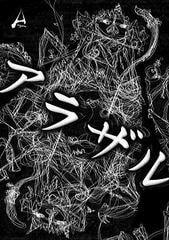
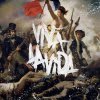 ▶いくつかの音源をリッピング。『The Best of Radiohead』、『誰がために鐘は鳴るver2』浜田省吾、『Golden Grapefruit』LOVE PSYCHEDELICO、『Toxicity』System Of A Down、『Zooropa』U2、『The Dream Of The Blue Turtles』Sting。しかし、いまは、ほぼ100%といっていいくらいColdplayの『Viva La Vida or Death And All His Friends』だけをヘビーにローテーション。陽気とか命脈のようなものが加わることで迎えたこの新しいフェイズを手放しで礼賛したい。そして、なにより感嘆すべきなのは、すべてに貫かれた「二重の思想」。Viva La Vidaと感じてもいいし、Death And All His Friendsと感じてもいい。Lovers In Japan とReign Of Loveはつながる。LOST!もあるしLOST?もある。それは光と影なのかもしれないし、二つで一つということかもしれないし、ディアローグ、ディアレクティーク、アンチテーゼということかもしれない。そんなに深い考えのないたんなる形式という話かもしれない。しかし、たとえそうであっても、オルタナティブは重要だ。すばらしい。
▶いくつかの音源をリッピング。『The Best of Radiohead』、『誰がために鐘は鳴るver2』浜田省吾、『Golden Grapefruit』LOVE PSYCHEDELICO、『Toxicity』System Of A Down、『Zooropa』U2、『The Dream Of The Blue Turtles』Sting。しかし、いまは、ほぼ100%といっていいくらいColdplayの『Viva La Vida or Death And All His Friends』だけをヘビーにローテーション。陽気とか命脈のようなものが加わることで迎えたこの新しいフェイズを手放しで礼賛したい。そして、なにより感嘆すべきなのは、すべてに貫かれた「二重の思想」。Viva La Vidaと感じてもいいし、Death And All His Friendsと感じてもいい。Lovers In Japan とReign Of Loveはつながる。LOST!もあるしLOST?もある。それは光と影なのかもしれないし、二つで一つということかもしれないし、ディアローグ、ディアレクティーク、アンチテーゼということかもしれない。そんなに深い考えのないたんなる形式という話かもしれない。しかし、たとえそうであっても、オルタナティブは重要だ。すばらしい。 深夜に、うろが来ている状態でローソンに入ったのがまずかった。ああ、文学フリマの話なんかものっているし、イカした海外の雑誌なんかも紹介されているとの幻覚により、ほとんど中身も確かめずにレジに直行。夢からさめたとたんに、これはもうおっさんの読む雑誌じゃないなあ、と痛感した次第。
深夜に、うろが来ている状態でローソンに入ったのがまずかった。ああ、文学フリマの話なんかものっているし、イカした海外の雑誌なんかも紹介されているとの幻覚により、ほとんど中身も確かめずにレジに直行。夢からさめたとたんに、これはもうおっさんの読む雑誌じゃないなあ、と痛感した次第。 編集長には申し訳ないが今月は『新潮』をパスした。3年振りぐらいだろうか。さいわい『群像』がキャッチーだったので選んだわけだが、このところ文芸誌は全般的に驚きがなくなってきている。というか、読みたいものが各誌に分散されるクールに入ってきた。文芸誌を90年代から追っかけてみるとコンドラチェフの波のようなものが確実にあって、いまはそういったリセッションの時期かもしれない。新しい作家が生まれていないという考えの一方で過渡的な充電のための蛹時代という見方もできる。いずれにしても、M&Aをあらためてプレゼンテーションできるチャンスが再び訪れたというわけだ。
編集長には申し訳ないが今月は『新潮』をパスした。3年振りぐらいだろうか。さいわい『群像』がキャッチーだったので選んだわけだが、このところ文芸誌は全般的に驚きがなくなってきている。というか、読みたいものが各誌に分散されるクールに入ってきた。文芸誌を90年代から追っかけてみるとコンドラチェフの波のようなものが確実にあって、いまはそういったリセッションの時期かもしれない。新しい作家が生まれていないという考えの一方で過渡的な充電のための蛹時代という見方もできる。いずれにしても、M&Aをあらためてプレゼンテーションできるチャンスが再び訪れたというわけだ。 「日本の美術館・世界の美術館100」。100号記念の特別保存版だけあって網羅的で、記事のバリエーションも豊かである。これもすでに各方面で言われていることだが、いまやアダルトな『平凡』と化し、失速している本体『BRUTUS』に比べると格段に読みどころがある。アダルトな『平凡』もたとえば、2号ほど前、恒例の「居住空間学」なんかはまだまだ活きているし、次号「井上雄彦」特集のように期待をもたせるテーマアップはうまいんだけどなあ。
「日本の美術館・世界の美術館100」。100号記念の特別保存版だけあって網羅的で、記事のバリエーションも豊かである。これもすでに各方面で言われていることだが、いまやアダルトな『平凡』と化し、失速している本体『BRUTUS』に比べると格段に読みどころがある。アダルトな『平凡』もたとえば、2号ほど前、恒例の「居住空間学」なんかはまだまだ活きているし、次号「井上雄彦」特集のように期待をもたせるテーマアップはうまいんだけどなあ。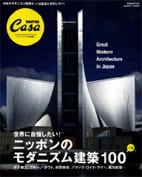 「ニッポンのモダニズム建築100+α」。2004年版のリ・イッシュー。パラパラ眺めていると、発売当時は気付かなかった「古江台の展望台」や「千里中央センタービル」、「エキスポタワー」、「希望が丘の青年の塔(とうもろこしタワー)」の写真が目に留まる。記憶の建築。一枚の建築物の写真から一挙にあまたの追想があふれ出る。これは、モノとしてアーカイブしておく必要があるとの思いに駆られ落掌した。
「ニッポンのモダニズム建築100+α」。2004年版のリ・イッシュー。パラパラ眺めていると、発売当時は気付かなかった「古江台の展望台」や「千里中央センタービル」、「エキスポタワー」、「希望が丘の青年の塔(とうもろこしタワー)」の写真が目に留まる。記憶の建築。一枚の建築物の写真から一挙にあまたの追想があふれ出る。これは、モノとしてアーカイブしておく必要があるとの思いに駆られ落掌した。 深夜2時まで店を開いているセレクト書店(という定義はどうやら正しくなさそうだが)「SHIBUYA PUBLISHING & BOOK SELLERS」には、それこそ深夜、一度だけ足を運んだことがある(そのときはたぶん4時まで開いていたはずだ)。そのセレクトはたとえば90年代ぐらいまでなら垂涎のものだったろうが、ここまで書店のバリエーションが拡がったいまとなっては、月並みのものなのかもしれない。しかし、店舗兼編集スタジオとしての知的創造空間/現場は充分に魅力的で、本が好きな人間なら一度はこんな仕事場で労働にいそしみたいと感じるところじゃないだろうか。
深夜2時まで店を開いているセレクト書店(という定義はどうやら正しくなさそうだが)「SHIBUYA PUBLISHING & BOOK SELLERS」には、それこそ深夜、一度だけ足を運んだことがある(そのときはたぶん4時まで開いていたはずだ)。そのセレクトはたとえば90年代ぐらいまでなら垂涎のものだったろうが、ここまで書店のバリエーションが拡がったいまとなっては、月並みのものなのかもしれない。しかし、店舗兼編集スタジオとしての知的創造空間/現場は充分に魅力的で、本が好きな人間なら一度はこんな仕事場で労働にいそしみたいと感じるところじゃないだろうか。