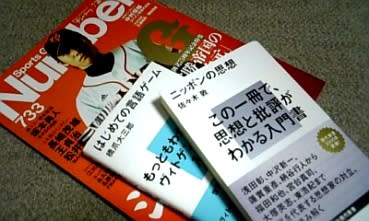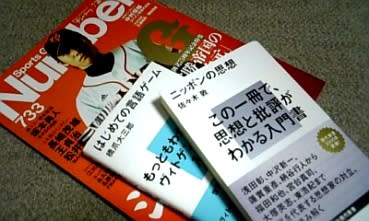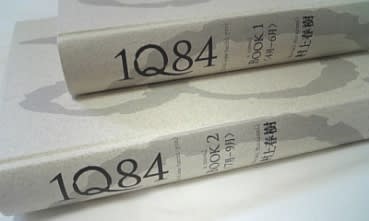どこの書店に行っても、カズオ・イシグロの新刊が平積みになっている。アマゾンでもたいていはベスト10以内。
『1Q84』に隠れて見えにくくなっているけれど、意外な出現率。この現象はいったいなんなのだろう。というのは、
『夜想曲集~音楽と夕暮れをめぐる五つの物語』は、平積みのポジションを獲得している他の小説と比べ、いっさいエキセントリックなところも、アクロバティックなところも、スキャンダラスなところもなく、もちろんスリルもどんでん返しもほぼない、おだやかな落陽の日常を切り出しただけの小説だからであり、その小説が、『1Q84』や『告白』や『ダ・ヴィンチ・コード』や『東京タワー』やら『ハリーポッターと死の秘宝 上下巻セット』などコントラストのはっきりした小説と陣取りを興じている様は、どう考えても解せない。感動気狂いと呼ばれるだれかが、『夜想曲集』を求めているのだろうか。
『わたしを離さないで』の勢いをかった、本屋大賞の中の人たちどうしの企て、というのは、ひとつの仮説としては成り立つが、たとえそうだとしても、この小説が万人に受け入れられるとは信じがたい。居ても立ってもいられなくなった俺は、書店員にちょっと訊いてみることにした。そうだ、いつも行く青山ブックセンターで、ずっと気になっていたあの娘だ。いっさいの疚しさがないきわめて正当な理由で、声を掛けられるまたとないチャンス。
#
おお
『Number #733』はジャイアンツ特集!なんて雑誌コーナーを横目にみながらたどり着いた文芸書の平台のあたりをぶらぶらすること5分。予想外の早いタイミングで、彼女が近づいてきた。NEW BALANCEのあまりみたことのないタイプの、センスのよいデザインのスニーカーをはいた、いつもどおり精悍なしょうゆ顔の彼女だ。あくまでしゅっとしてる。
アップダイクの『クーデタ』を入荷しだした彼女の横で、俺はあわてて『夜想曲集』を手に取り、いかにもカズオ・イシグロの愛読者です、これまでの作品は全部読んでます、といわんばかりのゼスチャーでページを開く。そして、あわや「モールバンヒルズ」を再読しそうになるのを抑えて、中空の視線でつぶやいてみる。「これって、どうなんですかねえ」。
「?……ああ、カズオ・イシグロの短篇ですね。いいですよ。ぜひ、読んでみてください。刺激とかそんなのないし、エンターテイメントとも違うんですけど、なんかいい小説なんですよお」
その的を得た、しかもなんともいえないチャーミングな回答を聞いた瞬間、俺はもうカズオのことなんかどうでもよくなって、彼女とならきっと『1Q84』とか、
『ヘブン』とか
『ドーン』とか
『終の住処』の話ができるんじゃないか、場合によってはどこかでお茶でも飲みながらパワーズの話なんかも……と足も体も浮きそうになったわけだが、そこまでの関係を一足飛びに詰めるのはどう考えても無理やり感がある、と冷静さをとり戻し、まずは、とりあえず、当初のミッションを全うすることにした。
「どこの本屋さんでも、だいたいプッシュされて平積みになっているようなのですが、そんなに人気があるのでしょうか?」
「ああ、そうなんですか。ほかの本屋さんのことはよくわからないんですけど、ここでは、お買い求めになるお客さまは多いです。イシグロは、そもそも人気はあるんですけど、たぶん『わたしを離さないで』で、裾野が広がったんじゃないですかね。もしかしたら、最近の村上春樹さんの影響とかかもしれないです…」
「なるほど…」村上春樹か。それにちなんでチェーホフ?そういえば、エッセイに書いていたなあ。カズオ・イシグロのこと。あれ、なんだったっけ…『monkey business』だった?あ、『monkey business』といえば、そろそろ
「箱号」もでているはずだ、たしかパワーズがなんか書いてるんだよなあ、なんて思いをめぐらせていると、彼女の言葉が続いた。
「でも……」
「でも?」
「そう、ベストセラーになるような小説じゃないかもしれませんね。うちのような本屋で、2日とか3日に1冊ぐらいのペースで、だけど1年ぐらいはずっと誰かが買っていくような、そんなちょっと地味な小説。わたしは好きなんですけどね、おすすめしますよ」
……この小説をまだ読んでいないことになっている俺はつらかった。ほんとうのところは、「いやあ、僕もカズオ・イシグロはずっと読んでいて…」とかなんとかいいながら、今回のやつはインパクトこそないけど巧みな状況設定とか面白いですよねえ、文章だけで翳りのイメージを見せるなんてさすが、でもこの手の話ならひょっとしたら堀江敏幸のほうがうまいかもしんないですねえ、読んでます?
『おぱらばん』とか?なんて話を発展させて、次の展開に持ち込みたかったのだが、いまさらそんなことはできない。痛恨の作戦ミス。
だから話はここで終わる。まるで、イシグロの短篇のように。
ということなんで
『ニッポンの思想』、
『はじめての言語ゲーム』、
『偽アメリカ文学の誕生』、
『村上春樹『1Q84』をどう読むか』、
『費用対効果が見える広告 レスポンス広告のすべて』、
『AERA english』、
『Web PRのしかけ方』、
『技術への意志とニヒリズムの文化―21世紀のハイデガー、ニーチェ、マルクス』、
『思考する言語〈上〉』、
『Newton 太陽光発電』、
『ディアスポリス#13』なんかをみつくろってABCを後にする。
今度、会ったとき、「あ、どうも」ぐらいは言えればよいのだけれど。