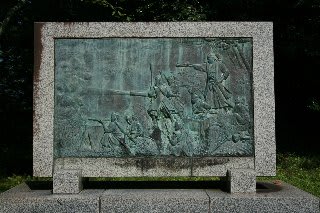(東山温泉)

旅館向瀧
宇都宮における戦闘で脚を負傷した土方歳三が、湯治のために東山温泉を訪れたといわれる。土方が逗留した清水屋旅館から東山温泉までは、徒歩で歩くとかなりの距離がある。脚の悪い土方がこの距離を移動できたのか疑問が残るが、東山温泉には、土方が入ったとされる源泉が複数存在している。「旅館向瀧」の前身は「きつね湯」と称し、会津藩士の保養所だったという歴史を持っている。土方が藩の勧めによって、ここの敷地内で入湯した可能性がある。また、会津藩の共同湯があったとされる「瀧の湯」の場所には、現在「庄助の宿・瀧の湯」という旅館が建っているが、ここも土方が使った可能性のある温泉である。

庄助の宿 瀧の湯
(院内御廟)

忠誠霊神碑
容保の諡号である忠誠霊神は、孝明天皇から賜った御宸翰からとったという。
東山の院内御廟には、二代藩主松平(保科)正経以降の歴代藩主の墓がある。入口付近に「冬場は足もとが悪いのでご注意ください」と書かれていたが、夏場でも階段は半ば小川のような状態であり、十分足場は悪かった。
森閑とした木立の中に歴代藩主の墓が聳える様は圧巻である。
九代藩主松平容保の墓が一番奥まった場所にある。三代以降の歴代藩主は、いずれも神式で葬られている。亀型をした石(亀趺)の上に建てられた碑石が前面にあり、対の石灯籠の奥に表石、さらにその奥に土を盛った塚の上に八角形の鎮石が置かれている。

正三位松平容保之墓

松平容保之墓
あの悲惨な会津戦争を回避できたとすれば、藩主容保が首を差し出すことしかなかったであろう。戦争前夜、仙台藩、米沢藩が戦争回避のために奔走した。両藩は会津藩の家老の首を差し出すことで妥協を図った。しかし、新政府軍はその提案を拒否し、飽くまで容保の首と、城の開け渡し、領地の没収を要求した。容保にしてみれば、自分が命を奪われるほど悪業を犯したか、という思いもあったに違いない。御所に発砲した長州藩でさえ、藩主の首までは奪われなかったではないか。前将軍である慶喜が、恭順の姿勢をとることで一命を保全されているというのに、その将軍の命に従って忠実に職務を遂行した会津藩主が首を取られなくてはいけないのは納得がいかないだろう。会津藩士にしてみても、君主に死んでもらって、自分たちが生き延びようとは武士道に悖る行為である。天地がひっくりかえっても飲める条件ではなかった。結果、薩長の思惑とおり、戦争に突入し、多くの会津藩士の命が奪われた。戊辰戦争を通じた会津藩士の犠牲者は、約五千とも言われる。言わば、容保一人の命と引き換えに五千の命が差し出された。自分の命と引き換えにそれだけの命が救えるのであれば、その方がずっと気は楽だったに違いない。容保は、自ら命を絶つわけにもいかず、戦後二十年余りを生きることになった。この間、容保はあの時代のことを語ることも少なく、自らの主張について書き残すこともなく、まるで存在を消した如き半生を送った。容保の心境を察する材料としては、死ぬまで身に付けていたとされる竹筒の中に収められていた、文久年間に孝明天皇から下賜された「御宸翰」だけである。容保にしてみれば、自分は天皇の信任を得ていた。間違ったことはしていないという強い思いがあったに違いない。

松平家之墓
松平家の墓には、容保の養子で十代会津藩主を継いだ松平喜徳(のぶのり)、容保の長男で斗南藩知事を務めた容大(かたはる)とその夫人、容保の五男で海軍少将、貴族院議員を務めた保男夫妻が葬られている。喜徳は、水戸藩の徳川斉昭の十九男で、容保とともに降伏の儀式に出たときまだ十三歳であった。明治二十四年(1891)三十七歳で世を去っている。
(会津武家屋敷)

会津武家屋敷
東山温泉入口の会津武家屋敷は、再現された会津藩家老西郷頼母邸や中畑村の旗本松平軍次郎の代官屋敷などを移築した一種のテーマパークである。中畑陣屋の裏手に、戊辰戦争戦没者供養塔と、見廻組佐々木只三郎の墓がある。

戊辰戦争戦没者供養塔

徳川家臣 佐々木只三郎源高城墓
傍らの説明によると、昭和五十年(1975)八月、作家早乙女貢氏らの好意により墓石をこの地に移したとあるが、私は四~五年ほど前に和歌山の紀三井寺で佐々木只三郎の墓と対面している。墓に刻まれた石は、全く同じ「徳川家臣 佐々木只三郎源高城墓」であった。どちらかが複製だろうか。
(天寧寺)

天寧寺
天寧寺は、葦名氏の菩提寺として隆盛を誇ったが、葦名氏が伊達政宗に追われた際、天寧寺も戦火にあって焼失した。天寧寺は、周囲の人たちの手によりその後再建された。長い歴史を持つ天寧寺は、広大な墓地を有しており、ここに近藤勇の墓もある。

会津士魂碑
「会津士魂」は会津藩士の血を引く作家早乙女貢氏が昭和六十年(1985)から執筆を始め、平成十三年(2001)に上梓。四半世紀をかけて全二十一巻を完成した。まさに早乙女貢氏のライフワークともいうべき作品である。まだ私は読んだことがないが、これだけの作品を読破するには、かなりの時間と覚悟が要る。

報國院殿公道了忠居士
紫雲院殿鏡光妙心大姉
(萱野権兵衛夫妻の墓)

郡長正之墓
天寧寺には、萱野権兵衛とその子、郡長正の墓がある。

酒井伊佐美之墓
酒井伊佐美も、白虎隊の生き残りで、自刃から蘇生した飯沼貞吉の証言を聞いた一人である。白虎隊の最期の様子を伝えることになった。

酒井安平之墓
南摩家の墓所である。南摩家といえば、南摩綱紀(通称八之丞、雅号は羽峯)を生んでいる。南摩家でも勝子以下四人が八月二十三日に自決している。

勇進院殿忠山誠劒居士
(南摩弥佐衛門の墓)
自宅で自刃した家族の名簿は以下のとおりである。(星亮一『会津戦争全史』より転載)
北原采女(二千八百石) 母が西郷刑部の家族とともに
西郷刑部(七百石) 家族五人
井上丘隅(六百石) 妻子二人を刺し自刃
木村兵庫(五百石) 家族九人
多賀谷勝之進(四百五十石) 家族七人ほかに親籍二人
永井左京(四百石) 家族七人
小山田伝四郎(四百石) 家族四人
中沢志津馬(三百石) 家族四人
柴太助(百五十石) 家族三人
中野慎之丞(百五十石) 家族六人
和田勇蔵(百石) 家族三人
高木豊次郎(百石) 家族三人
岡田又五郎(百石) 妻一人
野中此右衛門(七十五石) 家族六人
樋口多司馬(七十石) 妻一人
赤塚藤内(二十八石) 家族一人
八月二十三日だけで自刃した藩士の家族は二百三十名以上にのぼるという。これだけの数の非戦闘員が自ら命を絶ったという戦争は、会津城下だけである。「女子は敵の辱めを受けない」と徹底的に教えこまれた結果かもしれないが、それにしても凄まじい。

南摩勝子 節 寿 辛 墓
砲兵一番組頭の南摩弥三右衛門の母勝子、妻ふさ子、弟の寿(八歳)と辛(四歳)、そして長男萬之助と生まれたばかりの次男の六人は坂下勝方寺にたどり着いた。ここで落城の報に接し、勝子は、ふさ子と幼い子を城下に返し、自らの手で寿と辛とを刺し、その血に染まった刃で我が胸を突いたと伝えられる。

田中玄清墓
(田中土佐の墓)

田中玄光墓
南摩家の墓所からさらに登ると、草むらの中に田中家の墓所がある。ここに家老田中土佐(玄清)の墓がある。
田中家は代々会津藩の家老を務める家である。文久二年(1862)、藩主容保が京都守護職に任じられると、西郷頼母とともに上京して辞退を説いた。会津戦争では主戦派の一人として甲賀口の守備に就いた。このときの戦闘で重傷を負い、戦火が城下に迫るに及んで、神保内蔵助と刺し違えて死んだ。四十九歳であった。
玄光は、田中土佐の長男である。

貫天院殿純忠誠義大居士
(近藤勇の墓)
新選組局長、近藤勇の墓である。近藤の墓は、これ以外にも三鷹の龍源寺、斬首された板橋、京都三条河原で晒された首を密かに隠したと伝えられる岡崎法蔵寺にもある。会津天寧寺の墓は、やはり近藤の首をこの地に埋葬したもので、土方歳三が建てたものという。ただし、土方の建墓ということは事実かもしれないが、戦火の迫る会津城下まで首を持ちこむことが現実的に可能だったかどうか。
傍らには盟友、土方歳三の慰霊碑が建てられている。

歳進院殿誠山義豊大居士
(土方歳三慰霊碑)

近藤勇辞世歌碑
近藤勇の有名な辞世の漢詩が刻みこまれている。
(愛宕神社)

愛宕神社

松平容保公之像

武信神霊
信忠神霊
(窪田伴次の墓)
鳥羽伏見の戦争で、唐御門前の合戦で一番槍だったという窪田伴次の墓がある。
愛宕神社の本殿周辺を歩いてみたが、どこにも墓らしきものが見当たらない。付近にある宮司さんが住んでいると思しき民家を訪ねて在り処を確認すると、社殿北側の藪の中にあるという。
「ほら、あそこに頭が見えているでしょう」
と、宮司さんが指さす方向をみると、わずかにそれらしいものが確認できた。
クマザサのおい茂る藪をかきわけてようやく窪田伴次の墓に行き着くことができた。
(大龍寺)

大龍寺
慶山にある臨済宗大龍寺は、天正年間(1573~1593)に建立された桂山寺を起淵とし、初代会津藩主保科正之によって中興された。本堂の前に大龍寺戊辰戦争殉難殉節供養碑があり、大龍寺にゆかりがある戊辰戦争で戦死した会津藩士と唐津藩士の名前が刻まれている。

沼澤七郎之墓
沼澤七郎は、会津藩士沼沢弘通の二男である。兄明通が禁門の変で戦死したため七郎が家督を相続した。戊辰戦争のとき七郎十五歳であった。母道子が一族を集めて一隊を編成、七郎を隊長として越後口を守った。六十里越、大内村で奮戦し遊撃隊長となった。維新後、上京して大学南校に学び、のちに岩手、福島、香川、秋田県に勤務した。

林氏合葬之墓
林安儀(又三郎の墓)
林家の当主は、代々「権助(ごんすけ)」の名を継いだ。もっとも有名な林権助は、幕末会津藩の大砲奉行であった林安定であろう。林権助は、槍や剣術に優れていたが、西洋の砲術を積極的に学び、保守的な藩論を西洋式に変更することに尽力した。文久三年(1863)の禁門の変では大砲隊を率いて真木和泉らを天王山に追い込む活躍を見せた。慶応四年(1868)の鳥羽伏見の戦争で被弾して、江戸に向かう船中にて死亡した。六十三歳であった。この戦闘では息子又三郎も戦死している。又三郎の墓も、林氏合葬墓の左手に建てられている。
林権助奮戦の様子を「会津戊辰戦史」では次のように伝えている。
――― 歳六十余にして長髯白麻のごとし。大いに怒って号令を下し、大砲三門を発射して、これに応ず。その距離わずかに数間に過ぎず。権助令して槍をいれしむ。
衆奮進、弾雨をおかして戦う。彼は地物により、我はしからず。組頭中沢常左衛門弾に当たりてまず斃る。

林安定(林権助の墓)

斎藤幸元墓
斎藤幸元は、松本良順に学んだ藩医である。維新後は、会津若松市内で開業したが、野口英世の手の手術を担当したことで知られる。

小田磯之助之墓
小田磯之助は、剣術師範。藩校日新館武術教授を務めた。

神戸民治 岩蔵 墓
神戸民治は、九月十七日、一ノ堰で交わされた西軍(薩摩・佐土原・土佐・米沢・芸州・新発田)との激戦で戦死した。この戦闘での戦死は東軍四名に対し、会津藩は三十四名という甚大な被害を被り、一ノ堰以北の地は完全に西軍に掌握されることになり、唯一の城外との連絡路も断たれた。

籾山充盛墓

畑五郎左衛門墓

大龍寺戊辰戦争殉難殉節供養碑
(井上浄光寺)

井上浄光寺

藤森家之墓
藤森八太郎の墓である。藤森八太郎は、寄合組白虎一番中隊に所属し、津川口にてよく西軍の進攻を防いだが、石筵口が敗れ西軍が城下に迫っているとの情報を受け、会津方面への撤退を余儀なくされた。このときの戦闘で藤森八太郎は戦死。十六歳であった。
津川は、現在の新潟県東蒲原郡阿賀町津川。福島との県境に近い場所である。
(御薬園)

御薬園

御茶屋御殿
御茶屋御殿は、元禄九年(1696)に建てられたもので、主に藩主の休息の場として利用された。戊辰戦争の際には、西軍の療養所として利用され、戦後は容保の住まいとしても使われた。明治十年(1877)、この地で容保の六男として松平恒雄が生まれている。松平恒雄は、駐英大使、駐米大使を務めたあと、宮内大臣、初代参議院議長となった。
(浄光寺)

浄光寺
今泉岫雲は会津藩士。幼時から日新館に入り文武を修め、藩中の子弟に漢学を教えた。子弟は多く、その中に山川健次郎・赤羽四郎(のちのオランダ特命全権公使)・高嶺秀夫(東京師範学校校長、東京美術学校校長など)らがいる。維新後も漢学を教授した。

今泉岫雲墓

勝見裔 日向家代々之墓
(日向勝見の墓)
日向勝見は、白虎士中一番隊に所属。

日向氏之墓
(日向左衛門の墓)
日向左衛門は、八月二十三日、若松大町通加須屋左近邸内で戦死したと伝えられる。左衛門の娘日向ユキは、斗南に移住したのち北海道に嫁した。その頃の体験をのちに「萬年青(おもと)」としてまとめた。「萬年青」は「ある明治女人の記録」と称され、評価の高い作品である。現在、なかなか入手するのは困難である。どこか出版してもらえないものだろうか。

海老名リン像
海老名リンは、会津藩士日向新介の娘である。幼児教育・女子教育の先駆者といわれる。海老名季昌に嫁ぎ、夫の留守中の一家を支えた。明治五年(1872)警視庁に入った季昌に従い上京した。のち季昌が山形・福島郡長になったあと警視庁課長として再度上京した際キリスト教に接し熱心な信者となった。社会活動家として麻布に共立幼稚園を創立し、保母の資格を取る。夫の帰国を機に明治二十六年(1893)会津に私立若松幼稚園(現在の若松第一幼稚園)と私立若松女子高(現在の会津女子高校)を創立した。
(天寧寺町土塁)

天寧寺町土塁
鶴ヶ城は会津戦争で砲撃の対象となったこともあり、ほとんど当時の遺構が残っていない。数少ない現存する遺構の一つが、天寧寺町土塁である。
予想外に早く甲賀口門が破られ、危機が迫ったことに対し、中山口に布陣していた会津藩砲兵第二中隊と青竜一番寄合中隊は、急ぎ城下に引き返した。八月二十三日、午後二時頃、両隊は背炙山を超えて天寧寺口にたどり着いた。そのとき酒蔵の前には波々と酒をたたえた酒樽が並んでいた。両中隊の兵は嬉々としてそれを呑み、三の丸から無事入城することができた。
両中隊から遅れること二時間。小原宇右衛門率いる砲兵第一中隊は、同じく天寧寺口に迫ったが、ここで敵兵の攻撃を受け二十名余りが戦死した。わずかな時間の差で入城が困難になっていた。