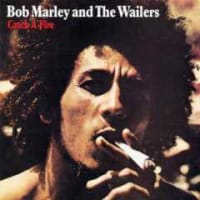オルタナティブ・ロックというのは、ニューウェープに比べると、余りきちんと分類がなされていないが、それはオルタナという意味の定義からして、明確棲み分けを諭すものでないからかもしれない。なので、このクリードというバンドに関しては、ミュージック・ショップへ行っても、余り「オルタナティブ」というコーナー分けは殆どないから、大概がロック・アーティストのところにタン列されているが、稀に「ヘヴィ・メタ」のコーナーにあったりもする。無論、クリードにハードな要素があるということに関しては否定しないが、それはハード・オルタナであって、決してへヴィメタではない。この辺りは、日本はハード・ロックとヘヴィ・メタルの境をはっきり設けていない現れである。
クリードはアメリカ・フロリダ州出身の4人組である。オルタナティブ・ロックはそもそもアメリカでメジャー音楽への反発から1970年代以前への音楽への回帰ということを志向しているのであるが、このクリードを聴いているとオト的にはメジャーっぽさを感じる。特に前述したが、へヴィ・メタと分類されても致し方ないのは、この作品の発表された1999年は、まさにポップ音楽シーンの中心はへヴィ・メタであった。商業音楽の中心にいるへヴィ・メタの面々よりも、ずっとメジャーな音作りをしているところに、このクリードというバンドの本質、底力を強く印象づけられるのは、私だけでは無い筈である。ただ、不思議なことにこのバンドは日本では中々ヒットしなかった。特にこのアルバムは全世界で2000万枚ものセールスを誇った作品なのだが、日本では今一つであった理由は私にもよく分からないが、敢えてあげるとしたら、スコット・スタップのヴォーカルなのかもしれない。ハード系バンドのヴォーカリストというのは伝統的にリード・ギターの音色に同化する声質が好まれる。例えば、ディープ・バーブルの名曲、「ストレンジ・カインド・ウーマン」の様に、重厚なバック演奏と一体化する声質であり、かつ、リードギターとの掛け合いも楽器の如くやって退けてしまうパターン。ロバート・プラントの全盛期も音楽の中でまるでひとつの楽器の様に同化をしていながら、かつ存在感がある。ところが、クリードの場合はどちらかというと重厚な演奏も、スコットありきの作りになっているところがあり、実はこの辺がヘヴィ・メタではなく、オルタナなのである。それは型にはまらないという彼らの音楽性でもあり、同時に対メジャーを意識したインディーズ出身色が非常に強い。だか、そもそもの音楽性は高いから時ととしてこんなビックなアルバムを作ってしまうのではないか。シングルカットされた「ハイヤー」や「ウィズ・アームス・ワイド・オープン」などはまさに後世に残る名曲と言ってもよく、このバンドの出自がなにであろうと全く関係ない、音楽性の高さを表現しているのである。
1970年代以降、日本の音楽シーンはアメリカ一色だったし、日本のミュージシャンも皆アメリカナイズされていたが、所謂、リスナーの中心層がイチゴ世代という団塊世代二世に移ってから、何故か突然Jポップと輸入音楽は垣根を作ったようにそれぞれの音楽形態を推し進めた。従ってこれ以降Jポップは全くつまらないものに変わって来たし、同時にアメリカの音楽がなんでもすんなりと受け入れらる時代ではなくなってしまった。クリードはそんな佳境にデビューしたことが、唯一、日本で高い評価を受けない理由なのかもしれない。だが、良く考えてみれば、こんなに独自の音楽性を持っているバンドが日本の音楽界に居るかというえば、残念ながら答えはNoであり、もっとこういう音楽を聴いて欲しいと思うのである。
こちらから試聴できます