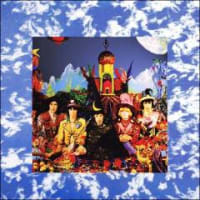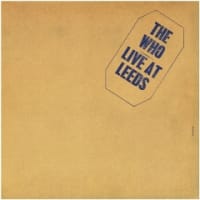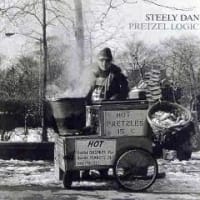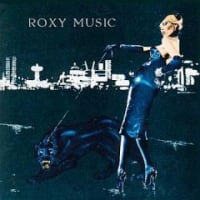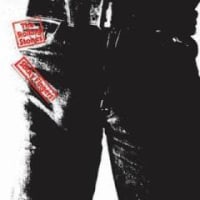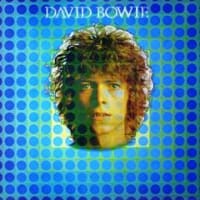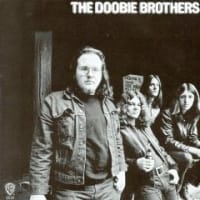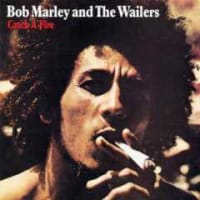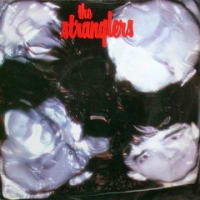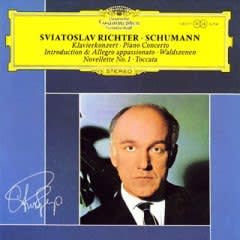
このところピアノ協奏曲の鑑賞ばかり書いているが、やはりこういうものって連鎖して色々聴き続けたいものなのかもしれない。私がそれぞれの楽曲に知り合った時期というのは勿論区々であるから、その時々の感動というものがある一方で、纏めてひとつのジャンルを聴き続けて比べてみるという行為も、新たな発見に繋がるのだと思う。かといって、音楽評論家ではないからそこそこ専門的なことは書けないが、ピアノを筆頭に幾つかの楽器を奏でたり、素人で作曲してきたレベルでの物言いであることはご勘弁頂きたい。
シューマンはなぜか、ピアノ協奏曲を1曲しか書いていない。まずもってこのことが大変な驚きであるが、それはショパンが2曲しか書いていないことにも通じるのかもしれない。恐らく、シューマンがもう少し早く、そう、ベートーヴェンの時代に生きていたのなら、多分、モーツァルトに継ぐ数のピアノ協奏曲を書いたのではないかと、これは、ショパンにも同様に言えると思う。もう、この時代は、「ピアノ協奏曲」なんて仰々しいものを欲していなかったのである。一方でシューマンは常に自分の音楽を求めていた時代であった。クララと結婚した前後がシューマンが最も活動的に音楽と向き合った時代であるが、躁鬱の持病があった彼は、更にそれとも戦っていた。だから、当初、シューマンにはピアノ協奏曲の構想が幾つかあった。しかし、そのうちのいくつかは交響曲や幻想曲に変わってしまい、唯一残ったのが、このイ短調ピアノ協奏曲である。1845年、シューマンは丁度この頃から精神的に不安に兆候が出始め、この曲を書き終えた後、交響曲第2番を完成するまでの間が、最初の大変辛い時期だったようだ。しかし運命とは皮肉なもので、恐らく、シューマンの曲の中で最高傑作であろうと思うこの「ピアノ協奏曲イ短調(OP.54)」完成の後に精神の病になってしまった。
この楽曲は、既に1841年に書かれた「ピアノと管弦楽のための幻想曲」を第1楽章として、後に、間奏曲とフィナーレを書いて完成させた。この曲がとても優れていると思うのは、悪戯にピアノの技巧に走らなかったことにある。ご存知の通りシューマンは「ピアノ曲」の作曲家といっても過言ではない。しかし、その本質はショパンとも違うし、また、リストとは全然違う。シューマンはもともと「音楽評論家」であった。彼は音楽作品より先に、音楽雑誌を発表しているのであるが、その話は別なところで書く。だからかもしれないが、私は彼の楽曲はどれをとっても全体の「構成」が素晴らしいと思う、音楽的な構成というよりも、それはひとつの作品の概念をしっかり持っていて、それをどのように表現するかという、ごく一般的言い方の「構成」である。前述した既に出来上がっていた幻想曲を協奏曲に変えてしまう辺りの発想も、当時、他の音楽家には考えられない。また、この協奏曲も、交響曲もそうだが、ソナタ形式を自由に扱っている点は、西洋音楽の新しい着想であり、マーラーなどにも受け継がれている。要するに、リストやワーグナーの前に、既にこういう音楽着想を持っていたということが、その後、絶対音楽と標題音楽に分かれる以前に双方を合一させた音楽理念を構築していたことを尊敬するのである。この辺りは流石ドイツ音楽の王道を継承しているのである
聴けば聞くほど良さがわかる楽曲である。
こちらから試聴できます