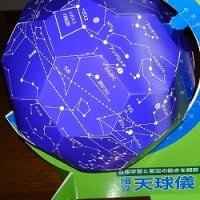「末期の目」というのは、芥川龍之介が自殺する前の「ある友へ送る手記」の中に書かれていた言葉だそうだ。ただし僕はそれが実際に手紙なのかそれとも創作なのかは知らない。この手記の中には、あの有名な、「(自殺する)動機は…ただぼんやりした不安である」という言葉も書かれている。ただ、芥川の遺書や上記の手記に対しては、今となっては大きな違和感を持たざるを得ない。
また、「末期の目」という言葉をさらにメジャーにしたのは、川端康成が文学論の中でそれを展開してからだそうだ。ぼくはそれをさしあたって確かめる必要を感じていない。ぼくには川端の美的感覚はいささか気持ち悪く感じられる。ぼくが芥川や川端の感じ方にシンパシーを感じているわけではない。
…と断ったうえで、「手記」の該当の個所を引用してみる。
「…君は自然の美しいのを愛し、しかも自殺しようとする僕の矛盾を笑ふであらう。けれども自然の美しいのは僕の末期の目に映るからである…」
さて、比較社会学者の真木悠介氏が、「交響するコミューン」の中でこんなことを書いている。
「敗戦後東南アジアの現地で処刑されたB・C級戦犯の手記などを読むと、ふしぎにたがいに符合する一つの回心のパターンをみることができる。現地の収容所からつれ出されて裁判をうける建物に行き、そこで死刑の判決をうけてまた収容所にもどる。そのもどり道で、光る小川や木の花や茂みのうちに、かつて知ることのなかった鮮烈な美を発見する。彼らはそこに来るときもこの道をとおってきたし、すでに幾週かをこの島で戦ってきたはずなのに、彼らの目はかつてこのような、小川にも木の花にも茂みにも出会うことがなかった。これらの風景や瞬間は、今はじめて突然のように彼らをおそい、彼らを幻惑し魅了する」
これは、「末期の目」について書いているのだと思う。
ぼくたちは誰もが皆、死にゆく存在である。死に行く存在であることを知るがゆえに、ぼくたちの目に映る世界は、いっそう美しい。
桜の花があんなに美しいのは、ほんの一週間ばかりの間にあざやかに咲いて散ってしまうから、だけでなく、桜を見るぼくたちも短い時を生きる存在だからなのだ。
だから桜は年々、いっそう美しい。
時が急いで過ぎていくことを、ぼくたちがこの世界をすぐに通り過ぎてゆくことを、残念に思わなくて良い。通り過ぎてゆくからこそぼくたちは、自然を、日々を、いっそう美しいと感じることができる。
念のために書くが、自死を肯定しているわけではない。滅びゆくものは美しいといっているわけではない。
ぼくは今、散歩の途中で花を見るのが楽しくてしょうがない。心地よい音楽を聴くのが、気心の知れた友達と話すのが、楽器の練習をするのが、読書をするのが、楽しくてしょうがない。
そうはいってもすぐ疲れるのだし、今は仕事をやめたゆえの開放感、ということもあるのだろうが、これは一種、「末期の目」なのだと思う。ぼくが地上を離れる日まで、ぼくはその目を持って生きたい。
また、「末期の目」という言葉をさらにメジャーにしたのは、川端康成が文学論の中でそれを展開してからだそうだ。ぼくはそれをさしあたって確かめる必要を感じていない。ぼくには川端の美的感覚はいささか気持ち悪く感じられる。ぼくが芥川や川端の感じ方にシンパシーを感じているわけではない。
…と断ったうえで、「手記」の該当の個所を引用してみる。
「…君は自然の美しいのを愛し、しかも自殺しようとする僕の矛盾を笑ふであらう。けれども自然の美しいのは僕の末期の目に映るからである…」
さて、比較社会学者の真木悠介氏が、「交響するコミューン」の中でこんなことを書いている。
「敗戦後東南アジアの現地で処刑されたB・C級戦犯の手記などを読むと、ふしぎにたがいに符合する一つの回心のパターンをみることができる。現地の収容所からつれ出されて裁判をうける建物に行き、そこで死刑の判決をうけてまた収容所にもどる。そのもどり道で、光る小川や木の花や茂みのうちに、かつて知ることのなかった鮮烈な美を発見する。彼らはそこに来るときもこの道をとおってきたし、すでに幾週かをこの島で戦ってきたはずなのに、彼らの目はかつてこのような、小川にも木の花にも茂みにも出会うことがなかった。これらの風景や瞬間は、今はじめて突然のように彼らをおそい、彼らを幻惑し魅了する」
これは、「末期の目」について書いているのだと思う。
ぼくたちは誰もが皆、死にゆく存在である。死に行く存在であることを知るがゆえに、ぼくたちの目に映る世界は、いっそう美しい。
桜の花があんなに美しいのは、ほんの一週間ばかりの間にあざやかに咲いて散ってしまうから、だけでなく、桜を見るぼくたちも短い時を生きる存在だからなのだ。
だから桜は年々、いっそう美しい。
時が急いで過ぎていくことを、ぼくたちがこの世界をすぐに通り過ぎてゆくことを、残念に思わなくて良い。通り過ぎてゆくからこそぼくたちは、自然を、日々を、いっそう美しいと感じることができる。
念のために書くが、自死を肯定しているわけではない。滅びゆくものは美しいといっているわけではない。
ぼくは今、散歩の途中で花を見るのが楽しくてしょうがない。心地よい音楽を聴くのが、気心の知れた友達と話すのが、楽器の練習をするのが、読書をするのが、楽しくてしょうがない。
そうはいってもすぐ疲れるのだし、今は仕事をやめたゆえの開放感、ということもあるのだろうが、これは一種、「末期の目」なのだと思う。ぼくが地上を離れる日まで、ぼくはその目を持って生きたい。