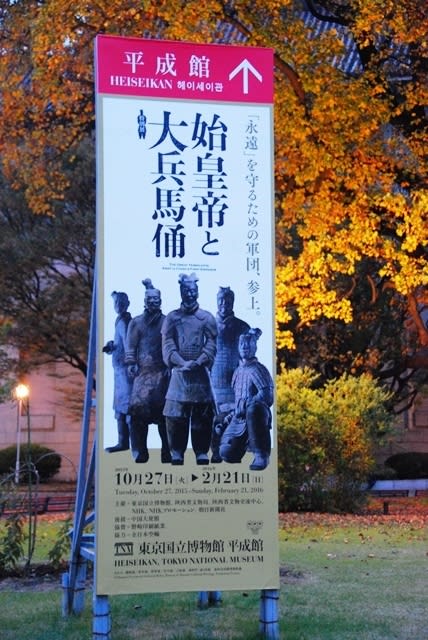美術展巡りはまだまだ続きます。
第3弾は丸の内の三菱一号美術館で開催中の「プラド美術館展」


大きな作品というよりはキャビネットサイズの作品の数々。
ゴヤやベラスケス等の名前もありました。
スペインの国力を感じる展覧会でした。
この展覧会に合わせて、日銀に勤める友人の情報により、最近リニューアルをした貨幣博物館へ。

ちょうどこの日はリニューアル記念講座「お金の使われ方―和同開珎から日本銀行券まで―」があるとのことで、参加。
大昔の木簡や通い帳、または浮世絵などから分かるそれぞれの時代の貨幣についての講義は面白く、
それを聴いてからの資料室の閲覧は興味深いものとなりました。
1,000両箱の重さや、1億円の重さなど実際体験出来たり、
天長菱大判(今は本物が展示)、藩札や西郷札などほほーと思いながら貨幣について知識を深めました~
なんだかお金の神様が下りてきた気分になり、当たれば10億円の宝くじを購入したのでした。
当たりますように!
第3弾は丸の内の三菱一号美術館で開催中の「プラド美術館展」


大きな作品というよりはキャビネットサイズの作品の数々。
ゴヤやベラスケス等の名前もありました。
スペインの国力を感じる展覧会でした。
この展覧会に合わせて、日銀に勤める友人の情報により、最近リニューアルをした貨幣博物館へ。

ちょうどこの日はリニューアル記念講座「お金の使われ方―和同開珎から日本銀行券まで―」があるとのことで、参加。
大昔の木簡や通い帳、または浮世絵などから分かるそれぞれの時代の貨幣についての講義は面白く、
それを聴いてからの資料室の閲覧は興味深いものとなりました。
1,000両箱の重さや、1億円の重さなど実際体験出来たり、
天長菱大判(今は本物が展示)、藩札や西郷札などほほーと思いながら貨幣について知識を深めました~
なんだかお金の神様が下りてきた気分になり、当たれば10億円の宝くじを購入したのでした。
当たりますように!