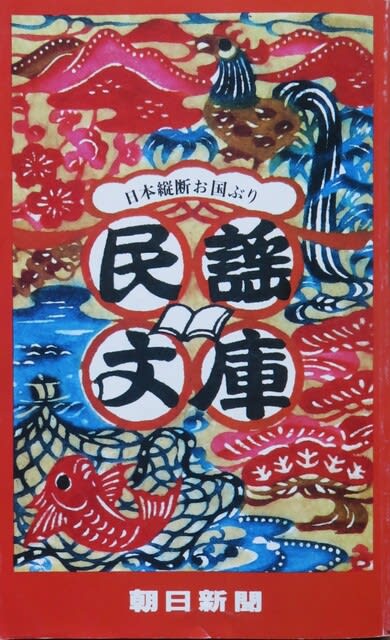今日の早朝散歩・ウオーキングの途中で見掛けて、撮ってきた花の写真の中に、やはり、初めて見るような花で、花名知らず分からず、「君の名は?」だったが花が有り、スマホの無料アプリ「GreenSnap」の「調べる」で、「花名、教えて下さい!」したところ、早速、コメントが有り、どうも、「サラサウツギ」の花であることが分かった。
記憶力無し、教えていただいてもそのそばから忘れてしまう爺さん、すっかり思い出せなくなる前に、ブログ・カテゴリー「爺さんの備忘録的花図鑑」に、書き留め置くことにする。
草花に詳しい人からは、「なーんだ、そんな花も知らなかったの?」と笑われそうだが、爺さんにとっては、新情報、新知識。今度見掛けた時等に、確認したりするのに役に立つ存在になる。
花名を調べたり、知ったところで、ナンボになる分けでも無しだが、脳トレ、ボケ防止の一助になるかも知れない等と、勝手に思い込みながら・・・



サラサウツギ(更紗空木)
アジサイ科(ユキノシタ科)、ウツギ属、落葉低木、
日本に有る10種以上の「ウツギ(空木)」の1種、
別名 「ヤエウツギ(八重空木)」、「ツカサウツギ(司空木)」
原産地・分布 日本、中国、朝鮮半島等、
樹高 1m~2m、
花色 内側白色、外側淡紅紫色、
八重咲き、
枝先に、横向き、下向きに咲く、
開花時期 5月頃~6月頃、
花言葉 「気品」「品格」「謙虚」「古風」「風情」「秘密」
(蛇足)
和名「ウツギ(空木)」は、幹の中が空洞になっていることから名付けられたとされている。
また、卯月(旧暦の4月)頃に、白い花を咲かせることから、「ウノハナ(卯の花)」と呼ばれ、古くから初夏のシンボルとして愛されてきた。
俳句等でも盛んに詠まれており、季語は、「初夏」
卯の花やくらき柳の及び腰 松尾芭蕉
卯の花や水の明りになく蛙 小林一茶
卯の花にかくるる庵の夜明哉 正岡子規
「卯の花」という言葉から、ふっと連想してしまうのは、童謡・唱歌「夏は来ぬ」、
「夏は来ぬ」 (YouTubeから共有)
ウツギ属の「ウツギ(空木)」の品種には、「サラサウツギ」「サクラウツギ」「ヒメウツギ」「シトバナヤエウツギ」「ウラジロウツギ」等が有るが、
見た目「ウツギ」っぽい樹木で、「ウツギ」の名が付いているが、分類上、ウツギ属でない樹木も沢山有る。
スイカズラ科・「タニウツギ」、「ハコネウツギ」、「ツクバネウツギ」等
フジウツギ科・「フジウツギ」等
バラ科・「コゴメウツギ」等
アジサイ科・「バイカウツギ」、「ノリウツギ」等
ミツバウツギ科・「ミツバウツギ」等
草木に超疎い爺さん、今更になって、「へー!、そうだったの」・・・・、
目から鱗・・・、である。