作家五木寛之の講演。
「慈のこころ、悲のこころ」
1932年生まれ、83歳。
福岡生まれ。
龍谷大学で仏教史を学んだこともある。
「TARIKI」は、ニューヨークでBOOK OF YEAR
スピリチュアル部門で銅賞の経歴も。
昭和7年組ということで、いろいろ著名人の名前が
でた。石原新太郎と生年月日が同じ。・・・
(このあたりはちょっと前説的な雑談が長いなあという
印象だった。)
価値判断というのは、時代によっていろいろ変わってくる。
ジョギングは体にいいといわれているが、
実は悪いという説もあったり、水は飲んだほうがよいと
言われるが、飲みすぎると腎臓に悪いとかいう説もある。
年齢に応じて、信心も変わってくる。
青年、壮年は、「生」を考えるべき、
ある年齢に達したら、以後は「死」を考えるべき。
かつては、自分も若いときは、五木レーシングという
レーシングチームを作ったこともあった。
(五木さんがドライバーだったのかは不明)
車の運転のほうは、60歳でやめた。運転できるが
運転能力が衰える。危ない。
今パイロットは不足している。
65歳定年だが、70歳まで延長しようかという
動きもある。
体だけでなく、信心も年齢によって変わってくる。
キリスト教、イスラム教、仏教は三大宗教と
言われているが、・・・
キリストは30代で死んでいる。
そこから、キリスト教は青年の宗教というイメージがある。
イスラム教は、社会人の規範が組み込まれているという印象。
仏教は、生老病死というところから、
高齢者の宗教というイメージ。
文化とかも年齢を重ねると嗜好がかわってくる。
ガンは早期発見がよいと一般的に言われるが、
必ずしもいいとは、いえないかもしれない。人による。
政治経済を語る人は、最近は宗教を語らないで
意見することが難しくなってきている。
真宗では、ブッダのお堂より、阿弥陀如来の
お堂のほうが大きい。
もともとの仏教は、順化していき、それぞれの国、土地の
仏教に変化していっている。
日本では、日本仏教といえる。
スリランカではスリランカ仏教。
チベットならチベット仏教・・・
インドでは、カースト制度廃絶したいという背景があり、
ニューブッディズムといわれる信仰も起きている。
仏教徒も増えている。
国勢調査で、ヒンディーと書いたりするが、実際には
仏教徒である場合もある。
これは、江戸時代に真宗が禁止された地域の隠れ念仏と
似たようなところがある。
宮沢賢治、もとは真宗の門徒。
後に、法華経の日蓮宗に変えた。
宮沢賢治が書いた書物は、宗教観を伝えるために
書いたものもある。
有名な、雨にも負けず・・・のくだりの文章は、
宮沢賢治の死後、整理していたときにでてきた。
この文章には、実は、南無妙法蓮華経ということば
が入っていた。しかし、世の中には
公表されず、宗教的部分が消された。
宮沢賢治は、なぜ日蓮宗へ変えたのだろうか。
今、この世の中を変えたいという気持ちが
強かったのだろうか。
真宗では、念仏を唱えて成仏する。
そして、またこの世に戻って、慈悲の心で、
他の人を救う。
宮沢賢治には、理解できなかったのだろうか。
真宗では、熱心な人は、七五三は祝わない。
クリスマスとかやらない。門松はかざらない。
ある真宗のお寺の住職は、
お寺に入ってくる車に、神社のお守りが
つられているのを見つけると、お寺に入るのを
拒否するという極端な住職もいる。
かつて、企画で、百寺巡礼というものをやった。
お寺に行くと、お寺の中に、神社があるという
こともある。しかたなく手を合わせる。
不思議なことに、神社で般若心経を
唱える人もいる。
ある記者から、親鸞の思想について、聞かせて
もらえませんかといわれる。
いつのときの親鸞についてですか?
・・・のとき?、・・・のとき?
関東に来て・・・のとき?、
島流しにあったとき?・・・
(数限りないくらいの親鸞の時代が出てきて
親鸞おたくっぽいところが見られた。)
親鸞には、その時その時で、いろんな思想がある。
「親鸞」という本も書いたことがある。
沖縄には、仏教の信仰はなかった。
琉球新報に、親鸞について、
連載記事を載せたら、けっこう関心が強かった。
(個人的に思うが、浄土宗の僧侶が琉球で
浄土宗を広めたとともに、
エイサーの基礎となったとも言われる踊り念仏
を広めたとも言われている。
そこから浄土宗と親戚の浄土真宗に感心を
もったのかもしれない)
歎異抄(たんにしょう)の現代訳の本も出版したことがある。
このたんにしょうは、親鸞自身が書いたものではない。
教行信証(きょうぎょうしんしょう)という本は、
親鸞が書いた。
れんにょ上人が、蔵の中から
ばらばらになった書を見つけた。
その書をまとめて、たんにしょうとして世に出した。
たんにしょうは、いくらかは、
れんにょ上人の思いが入っているのかもしれない。
キリストのバイブル。
キリスト自身は書いていない。
論語も孔子自身が書いていない。
周りの人が書いた。
本人が書くより、周りの人が書くほうが
よりきびしく、客観的に書くだろう。
仏典もブッダが書いていない。
ブッダの言葉は、歌として引き継がれたという面もある。
ブッダの教えを聞いた弟子たちが、町に出て
ほらを吹く。ほらを吹くと、何事かと人が集まってくる。
人が集まったところで、太鼓やら笛でもって、
ブッダの教えを歌にして広めていった。
ほらを吹くとは、うそをつくときに使われる言葉だが、
このときは、真実のことを言っているのであって、
今の意味とは逆の意味になってしまっている。
ブッダの死後、何百年後に文字になった。
聖書も、論語も、仏教も、言い伝えで
世の中に受け継がれてきた。
(つまり書物から理解するよりも
むしろ、いい伝え聞くことで教えが
伝わるという大切さがある。)
(ちょっと余談のようで)
中国のお寺、だるま大師にゆかりのあるお寺。
座禅が始まる。日本とはまるで違う、
最初は雑談からはじまり、自然に会話が
なくなり、なんとなくはじまる。日本のように
、棒でたたくということなどしない。
食事のとき、合掌してから食事という日本のような
ことはしない。
ちょっと、びっくりした。
真宗は、本を読むより、面と向かって
直接法話を聞くということに重きを置く。
親鸞が書いた教行信証は難しい。
読解しても難しい。
結局、たんにしょうに行き着く。
親鸞は、和讃(わさん)を老年期によく書いた。
わさんには、メロディがつく。
人が集まって歌うと味がある。
活字としてみただけでは味気ない。
わさんは七五調。
当時、地獄、極楽がはやった時代。
疫病や、地震も多かった。
法然、親鸞が、念仏を唱えれば
救われると説いた。
さらに、この教えを広めたいということで、
歌うことを考えて、当時の流行にあわせて
わさんという形をとった。
ブッダの時代も歌でも教えは広まった。
教えは、聞くということで広まってきた。
後記:
さすがに有名な作家ともなると、
立て板に水のごとく、よくしゃべる。
ちょっと難しい言葉がでたりするところは
ちょっとわからなかったりした。
今日は、目からうろこ的なことも多かった。
文章の他、言い伝えて伝わる大事さを感じた。
真宗が推進している法話、聴聞の大切さを
実感した。
個人的にも、法話の聴聞に数多く触れられる
というのはありがたいことだ。
「慈のこころ、悲のこころ」
1932年生まれ、83歳。
福岡生まれ。
龍谷大学で仏教史を学んだこともある。
「TARIKI」は、ニューヨークでBOOK OF YEAR
スピリチュアル部門で銅賞の経歴も。
昭和7年組ということで、いろいろ著名人の名前が
でた。石原新太郎と生年月日が同じ。・・・
(このあたりはちょっと前説的な雑談が長いなあという
印象だった。)
価値判断というのは、時代によっていろいろ変わってくる。
ジョギングは体にいいといわれているが、
実は悪いという説もあったり、水は飲んだほうがよいと
言われるが、飲みすぎると腎臓に悪いとかいう説もある。
年齢に応じて、信心も変わってくる。
青年、壮年は、「生」を考えるべき、
ある年齢に達したら、以後は「死」を考えるべき。
かつては、自分も若いときは、五木レーシングという
レーシングチームを作ったこともあった。
(五木さんがドライバーだったのかは不明)
車の運転のほうは、60歳でやめた。運転できるが
運転能力が衰える。危ない。
今パイロットは不足している。
65歳定年だが、70歳まで延長しようかという
動きもある。
体だけでなく、信心も年齢によって変わってくる。
キリスト教、イスラム教、仏教は三大宗教と
言われているが、・・・
キリストは30代で死んでいる。
そこから、キリスト教は青年の宗教というイメージがある。
イスラム教は、社会人の規範が組み込まれているという印象。
仏教は、生老病死というところから、
高齢者の宗教というイメージ。
文化とかも年齢を重ねると嗜好がかわってくる。
ガンは早期発見がよいと一般的に言われるが、
必ずしもいいとは、いえないかもしれない。人による。
政治経済を語る人は、最近は宗教を語らないで
意見することが難しくなってきている。
真宗では、ブッダのお堂より、阿弥陀如来の
お堂のほうが大きい。
もともとの仏教は、順化していき、それぞれの国、土地の
仏教に変化していっている。
日本では、日本仏教といえる。
スリランカではスリランカ仏教。
チベットならチベット仏教・・・
インドでは、カースト制度廃絶したいという背景があり、
ニューブッディズムといわれる信仰も起きている。
仏教徒も増えている。
国勢調査で、ヒンディーと書いたりするが、実際には
仏教徒である場合もある。
これは、江戸時代に真宗が禁止された地域の隠れ念仏と
似たようなところがある。
宮沢賢治、もとは真宗の門徒。
後に、法華経の日蓮宗に変えた。
宮沢賢治が書いた書物は、宗教観を伝えるために
書いたものもある。
有名な、雨にも負けず・・・のくだりの文章は、
宮沢賢治の死後、整理していたときにでてきた。
この文章には、実は、南無妙法蓮華経ということば
が入っていた。しかし、世の中には
公表されず、宗教的部分が消された。
宮沢賢治は、なぜ日蓮宗へ変えたのだろうか。
今、この世の中を変えたいという気持ちが
強かったのだろうか。
真宗では、念仏を唱えて成仏する。
そして、またこの世に戻って、慈悲の心で、
他の人を救う。
宮沢賢治には、理解できなかったのだろうか。
真宗では、熱心な人は、七五三は祝わない。
クリスマスとかやらない。門松はかざらない。
ある真宗のお寺の住職は、
お寺に入ってくる車に、神社のお守りが
つられているのを見つけると、お寺に入るのを
拒否するという極端な住職もいる。
かつて、企画で、百寺巡礼というものをやった。
お寺に行くと、お寺の中に、神社があるという
こともある。しかたなく手を合わせる。
不思議なことに、神社で般若心経を
唱える人もいる。
ある記者から、親鸞の思想について、聞かせて
もらえませんかといわれる。
いつのときの親鸞についてですか?
・・・のとき?、・・・のとき?
関東に来て・・・のとき?、
島流しにあったとき?・・・
(数限りないくらいの親鸞の時代が出てきて
親鸞おたくっぽいところが見られた。)
親鸞には、その時その時で、いろんな思想がある。
「親鸞」という本も書いたことがある。
沖縄には、仏教の信仰はなかった。
琉球新報に、親鸞について、
連載記事を載せたら、けっこう関心が強かった。
(個人的に思うが、浄土宗の僧侶が琉球で
浄土宗を広めたとともに、
エイサーの基礎となったとも言われる踊り念仏
を広めたとも言われている。
そこから浄土宗と親戚の浄土真宗に感心を
もったのかもしれない)
歎異抄(たんにしょう)の現代訳の本も出版したことがある。
このたんにしょうは、親鸞自身が書いたものではない。
教行信証(きょうぎょうしんしょう)という本は、
親鸞が書いた。
れんにょ上人が、蔵の中から
ばらばらになった書を見つけた。
その書をまとめて、たんにしょうとして世に出した。
たんにしょうは、いくらかは、
れんにょ上人の思いが入っているのかもしれない。
キリストのバイブル。
キリスト自身は書いていない。
論語も孔子自身が書いていない。
周りの人が書いた。
本人が書くより、周りの人が書くほうが
よりきびしく、客観的に書くだろう。
仏典もブッダが書いていない。
ブッダの言葉は、歌として引き継がれたという面もある。
ブッダの教えを聞いた弟子たちが、町に出て
ほらを吹く。ほらを吹くと、何事かと人が集まってくる。
人が集まったところで、太鼓やら笛でもって、
ブッダの教えを歌にして広めていった。
ほらを吹くとは、うそをつくときに使われる言葉だが、
このときは、真実のことを言っているのであって、
今の意味とは逆の意味になってしまっている。
ブッダの死後、何百年後に文字になった。
聖書も、論語も、仏教も、言い伝えで
世の中に受け継がれてきた。
(つまり書物から理解するよりも
むしろ、いい伝え聞くことで教えが
伝わるという大切さがある。)
(ちょっと余談のようで)
中国のお寺、だるま大師にゆかりのあるお寺。
座禅が始まる。日本とはまるで違う、
最初は雑談からはじまり、自然に会話が
なくなり、なんとなくはじまる。日本のように
、棒でたたくということなどしない。
食事のとき、合掌してから食事という日本のような
ことはしない。
ちょっと、びっくりした。
真宗は、本を読むより、面と向かって
直接法話を聞くということに重きを置く。
親鸞が書いた教行信証は難しい。
読解しても難しい。
結局、たんにしょうに行き着く。
親鸞は、和讃(わさん)を老年期によく書いた。
わさんには、メロディがつく。
人が集まって歌うと味がある。
活字としてみただけでは味気ない。
わさんは七五調。
当時、地獄、極楽がはやった時代。
疫病や、地震も多かった。
法然、親鸞が、念仏を唱えれば
救われると説いた。
さらに、この教えを広めたいということで、
歌うことを考えて、当時の流行にあわせて
わさんという形をとった。
ブッダの時代も歌でも教えは広まった。
教えは、聞くということで広まってきた。
後記:
さすがに有名な作家ともなると、
立て板に水のごとく、よくしゃべる。
ちょっと難しい言葉がでたりするところは
ちょっとわからなかったりした。
今日は、目からうろこ的なことも多かった。
文章の他、言い伝えて伝わる大事さを感じた。
真宗が推進している法話、聴聞の大切さを
実感した。
個人的にも、法話の聴聞に数多く触れられる
というのはありがたいことだ。











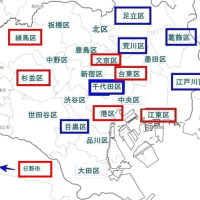












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます