慶應大学教育課程センター公開研究会に参加していただいた皆さん、ごくろうさまでした。夜の時間帯にも関わらず、30人を超える方々が参加してくださいました。公開研は3回目になります。ロールプレイングの練習がありましたので、16:00前には大学へ到着して、前回と同じ場所でやるのだろうなと勝手に自分で思い込んで、広場の喫煙所で、のんびりとしていたのですが、16:00を過ぎても誰とも出会わないし、ひょっとして場所間違えたかな?という不安になり、パソコンを開いてネットで調べようとして電源をつけると、電池切れ・・・・「あ~、えらいことやー」とパニックになってしまいました。教職課程センターへ「会場はどこでしょう?」と訊きに行くと、今回の事務連絡をしてくれていた谷内さんが、親切にも遠く離れた会場まで連れていってくれたのです。「よかった-」谷内さんに助けていただきました。何しろ練習がどれくらい時間がかかるのか演者の方と出会ってみなければわからないので、1分でも惜しいような状態でしたから。
ということころから始まった私の公開研でした。私の研修は基本的には「講演」ではなくファシリテーションなので、参加者の皆さんの素の姿やパワーの上にのっかってなりたっています。で、小さくても深い気づき(これは、人それぞれ違いますし、感じる深さも違ってきます)を得ることができれば、参加者の皆さんも、私自身もクオリティーが高まる、というものなのです。理論的な支柱は「『依存的なあり様』から『主体的なあり様』」なのです。今日の研修はそこまで行き着くことができませんでした。そもそも、私の基礎研修は6時間のプログラムなので、3時間×2回ということで進めていきます。その最後に「『依存的なあり様』から『主体的なあり様』」というワークショップに至って完成というものですので、今日の2時間30分の設定では、すっ飛ばしたところも多く、最後の所は論文を読んでおいてくださいね。ということで閉めてしまったので、「物足りない」と感じた方もおられるでしょう。ごめんなさい。
ロールプレイングに入ったところで、教員をめざす学生さんだったら、ここを少し深めておいた方がいいだろうと感じまして、アサーションとそのDESC法に時間を割きました。アサーションは「スキル」と呼ばれることが多いのですが、ほんとうは、「あり様」なのです。自分を大切にする、相手のことを想像する、お互いの折り合いをつけるためのWin&Winの解決策・プランを創造する、という段取りをとります。このような、生産的な行為は、単なる「スキル」では無理なのですね。ですから、そんなあり様へ到達していくためのヒントだけを、本日提示させてもらったということなのです。声を出したり、身体を動かしたり、気づきを交流したり、騙されたり、自己開示したりしましたね。どうでした? 心地よかったですか? もし、そうなっていただいたら、実は、それが「いじめ」や「不登校」などを乗り越える力になっていくのです。それを、教育課程に取り入れて学校で実践しているのが、松原第七中学校区の小学校・中学校なのです。私の知る限りでは、このような校区はこの国にはここ以外にありません。「認知」→「行動」→「評価」のプラスのスパイラルを教育課程に組み込み、子どもの成長を9年間支援している校区は、ここしか無いのです。だから、私は、教員を退職し、今日のような研修をしています。気づきを交流してもらう情報ツールとして、HPとブログを立ち上げました。決して、松原第七中学校区と同じものでなくても構いません。みなさんが今日感じていただいたことを、自分に流し込み、自分が取り組んでみる(生活レベルから)。そして、それを教員として実践してみる。仲間を増やし、相乗的な効果をめざす。これが、「いじめ」「不登校」を乗り越える力になると私は思っています。
こづえさんも3回目になるのに、来て下さいました。竹村先生、伊藤先生、今回の公開研を企画していただいてありがとうございました。私自身にとって、今日は良い日でした。参加された皆さん、感謝しています。
お約束しましたように、メールで住所を教えていただければ、松原第七中学校の人間関係学科プログラム最新版とふり返り掲示物の画像が入っているCDをプレゼントさせていただきます。送料も何もいりません。ぜひとも、教員になられたときには、参考にしていただいて、人間関係づくりの授業に生かしてください。
***************************************************************************************
あいあいネットワーク of HRS
ホームページURL:http://aiainet-hrs.jp/
学校の先生119番URL:http://aiainet-hrs.jp/10sensei119/index.htm
(mail:info@aiainet-hrs.jp)
(コメント欄のメールアドレスとURLは必須ではありません。)


















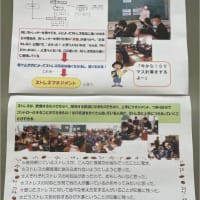








実体験型のような感じでわかりやすく、とても楽しい研究会でした!ありがとうございました。
一人一人認知が違う、という考えのもと話そうとすると、少し楽な気持ちで話せると感じました。
ロールプレイング2-4のまなみさんへの回答も、それに基づいたものだったのだとわかりました。
すごろくも自分の回より、他の人の答えに質問をしてるときの方が楽しく感じました。
教師になってからは、友人と話す以上に、相手をセンターにの考えが重要だと思います。
今日学んだことを生かして、自分なりの方法を考えていきます。
ロールプレイングは、言われてみれば当たり前だけれど普段私たちが見落としがちな気遣いや他人との接し方が表現されていて、改めて気づかされる部分も多かったです。
「悩みの相談」の場面は、以前ある本で同様の話を読んだことがあるので、また読み返そうと思いました。
本日はありがとうございました。
何か、慶應生なのにこんな簡単な計算も出来ないのかということ
に気づかされたら、益々自信をなくしてしまいそう。
だから、中断してもらってほっとしました。
このタイプは、ストレスを溜め込んでしまうタイプだそうで、
先々不安になってしまいました。
何とか上手い対処法、探していきたいです。
一つ、質問があります。
ストレッサーを受けたあと、“評価”によって、
感じ方が変わるとありましたが、その“評価”
とは、例えばどのようなものが挙げられるのでしょうか。
お手数をおかけ致しますが、宜しくお願いします。
(深美です・・・アンジーさん。私の説明不足だと思います。まず、「ストレスを溜めるタイプ」とありますが、それは「計算」jという分野においては「そうだ」ということだけなのです。分野が違えばそうはならないことがありますよね。問題は、ストレスを溜めてそれがストレスを増加させるような対処をしてしまうということが問題です。そういう、マイナスのスパイラルを止める「対処」が必要になるのです。
「評価」のことですが、私は「評価」というものを人間が持つ「評価システム」と位置づけています。「人間としての枠組み」ということと同義で使っています。今日の研修で言えば、「いやだと感じる枠組み」「ようし、やってやろうという枠組み」なのですね。というように感じ方が違うということなのです。「評価」から「認知」に至るものが「ふりかえり」にあたります。ふりかえりとは、気づきや感情を言語化し、それを次の認知へ積み上げていくということです。すると、前の「認知」より今の「認知」は少しだけクオリティーが上がります。実は、これが教育だと思うのです。)
改めてお話をお伺い致しまして、新鮮な気持ちで「深美ワールド」にハマらせて頂き、本当にワクワクしました。
偏見や錯覚、共感や寛容、訊く姿勢…様々なポイントを具体的に想起でき、実践に移しやすい形で提示して頂けて、スッと入ってくる講演に、毎度魅了されています。
あのロールプレイ、今回「メール」での解決について触れられていましたが、今度は例えば…親が絡んでくるとか、他の先生との指導方針の食い違いだとか…入れて頂けると嬉しいです!
私がちょっと不安なのは、保護者対応ですので。
宜しくご検討下さい。
本日は、ありがとうございました。
(深美です・・・完全に思い出していましたよ。服部くんのことも同時に思い出していました。こづえさんは院に行かれたのではなかったですか? 今、現場におられるのですか? ご要望がすごくしっかりしているので、成長されたのですね。時間の経過を感じます。でも、おっとりしているところは同じなので、少し笑ってしまいます。確かに、保護者対応というものは現場で要求されるのですが、モデルとしては対処的なものが多いのだと思います。具体的な相談という事のほうが適切だと思いますから、ブログにアドレスいただきましたので大阪に帰ったらメールします。)
その中でもいかに評価を重視する必要があるかを強く感じました。
今後、自分が教員になったときのヒントが沢山得られた研究会となりました。
ありがとうございました。
(深美です・・・ペンギンさんのこの気持ちに、研修の最中に気づかなかった私はファシリテータとしてまだまだですね。すごく反省しています。遅ればせながら、お返事をさせていただきます。
「いじめ」「不登校」の未然防止に一番必要な事は、実は「受けとめる力」「認める力」なのですね。残念ながら、これは書籍では手に入れる事ができません。理屈はわかっても身体が動かないのです。頭ではわかっているだけでは心で感じることができることにはならないのです。ここが一番教育現場で困難が生じる要因となるところとなってきます。それに気づき、行動を起こそうと感じることが今日のファシリテーションにおいて一番の目的でした。今日の皆さんのふりかえりで言いますと、はじめのほうにある「ぶっちー」さんのふりかえりです。ぶっちーさんの心の動きと次の行動を感じませんか? 「いじめ」「不登校」を未然に防ぐためには、一刻を争う迅速な支援が必要になります。そして、それを可能にするのは、子どもの心の動きをしっかりつかむことです。他者の心の動きや変化をつかむためには、まず、教員は自分の心の動きと変化をつかむことができなければなりません。で、この力は、残念ながら啓発書を読んだだけで身につけることはできないのです。でも、逆に言うと、啓発書を読んだだけで、それが出来る人は、研究者の方を除いてその啓発書を読む必要はありません。時間がもったいないです。
それと、一般的な啓発書ということにふれます。啓発書という概念では、何をさしておられるのかよくわかりませんが、私自身の事で言わせてもらいますと、読み手の主体を育てるものが啓発書だと思っています。もってかえっていただいた論文はもうお読みになりましたか? その中の『「依存的なあり様」から「主体的なあり様」へ』というものは、「いじめ」「不登校」に関わる当事者を成長のプロセスとして見ていこう! 支援していこう!ということを訴えています。多くの「いじめ研究者」が支持しているゼロ・トレランスの考えと対極をなすものです。
私がこの考えに至ることができたのは、実用書・ビジネス書の分野に位置づけられているフランクリン・R・コビーが書いた「7つの習慣」のおかげです。コビーは、主体的×反応的という概念づけをしています。それと日本のアサーションの始祖である平木典子さんの著書です。平木さんは攻撃的×非主張的×アサーティブという三極構造で説明をしました。実は、コビーが言っている「反応的」とは平木さんが言っている「攻撃的+非主張的」のことなのですね。私は、これを成長のプロセスとして考え、成長を「依存的」→「主体的」と規定しました。つまり、2極構造であり、それはその成長プロセスに教育が関わることによって、「主体的」に育てていくということなのです。成長のプロセスに乗っ取った教育ですから、三極構造ではすごくわかりにくいのですね。どこから、どこへ行くのかよくわからないからです。「依存的」から「主体的」というベクトルを示したということです。コビーの「反応的」という言葉も、実際には「主体的」という言葉の対極には「反応的」という言葉は来ません。一昨年出された文科省の生徒指導提要ですら「主体的」という言葉の対極には「客体的」と書いています。これも、非常に理解しづらい言葉なのですね。人間は生まれたときは、100%人間の力を頼らなければならないほど完全「依存的」な状態なのです。そして、心のなかみがしっかり詰まり、大きくなっていくことで人間は「主体的」になっていきます。俗に言う「自立」という概念を超えたものになります。本来は「自立」という概念はそうだったと思うのですが、実際的には「自立」という言葉は多くの場合「生活の自立」を表しています。決して、主体的であるとうことを表しているのではないのです。「就職できてよかったね」ということにとどまっているのが現実です。今の社会は「成長社会」から「成熟社会」へ移行したと言われています。簡単に言うと、世の中を囲っていた大きな枠組みが崩れ去った時代が「成熟社会」と言われるものなのです。ですから、教員や保護者や地域の大人は、子どもが「主体的」になることを望まなければいけないような社会になってきます。まあ、こんなことを理解していただきたかったわけですね。まだまだ還しておきたいことはたくさんあるのですが、これである程度は理解していただけましたでしょうか?
お返事をコメント欄にいただければ、また、フィードバックいたします。よろしくお願いいたします。)
自分自身もソーシャルスキルトレーニングを企画・運営することもありますが、きょうの研修を通じて感じたのは「何をやるか」よりも「その人らしさ」ということなのかなということです。たとえば、「友だちともっと仲良くなれるコミュニケーションのワザを身につける!」というテーマとして、取り上げるスキル自体は同じだとしても、トレーナーの「その人らしさ」次第で受ける側の印象はかなり変わるよな~と。布袋さん(深美先生)のキャラクターというか、個性というのかな? そこが大きかったように思います。=きょうの原稿どおりに自分が話しても、たぶん「ビミョー」な感じになるわけで。「自分らしさ」をもっと深めていきたいなー!