
「自己肯定感を高める三要素」 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
「自己肯定感を高める三要素」・・・その3
「②相乗効果を得る」・・スキルのレベル
人間の活動の喜びとしてあげられるもののひとつに、他者との協働があります。他者との協働で得られるもっとも大きなものが相乗効果です。相乗効果は、独りで成しえる仕事の何倍もの成果を生み出し、そこから生まれる成果や他者との信頼関係が、より自己肯定感を高めていきます。プロジェクトの中で自分がなくてはならない存在であることを実感できるからです。
WHOやOECD、そして様々なグループアプローチ(構成的グループエンカウンターなど)は、多様な成長のためのスキルを提唱しています。その中で、私が相乗効果のための根幹スキルをあげるとすれば、迷いなく「自己管理」と「思いやり」を挙げます。「自己管理」は、ストレスマネジメントを基礎にして感情対処や時間管理などのスキルに発展していきます。
ワークショップのなかで、私は「100マス計算」を使い参加者の方にストレスをかけるのですが、100マス計算という刺激に対し、「(計算するのが)いやだ」という感情を持たれた方は、「悪い結果がでたら、恥ずかしいな...!?」「計算は自信ないから、ここから逃げ出したい!」というような妄想に支配され、最悪のケースを想像します。
一方、「いやだ」と感じた方でも、計算をするという事実を受け止め、一旦「心のスペース」を確保できた場合は、「自信はないけど、自分がどれだけできるかやってみようかな!?」という前向きな姿勢に変換することができます。これが「リフレーミング」です。つまり、後ろ向きの姿勢だったものを前向きな姿勢に変えることができたわけです。
このリフレーミングは、「認知→行動→評価のスパイラル」を促進させ、評価から認知にいたるまでの、自己対話・シェアリング・イメージングへの道を開きます。「思いやり」は、「相手のことを思う」ということですが、これは「共感性」と呼ばれ、共感性が低い・高いというものは自己肯定感が低い・高いというレベルにほぼリンクしています。
つまり、自己肯定感が低い場合は共感性が低い(他者の気持ちを想像できない)、自己肯定感が高い場合は共感性が高い(他者の気持ちを想像できる)ということになります。さらに、共感性の向上に欠かせないものは自己開示です。自己開示は他者の自己開示を引き出します。自己防御している不安や恐怖から抜け出せるツールになります。自己と他者との相互の自己開示は信頼と安心を生み出します。
しかし、共感性というものは常に不十分なものですから、相手のことが理解できずに感情的な対応をして、攻撃的になってしまうことがあります。そこで「心のスペース」を確保することが大切なのです。そこで「くりかえす(相手の言葉をそのまま返す)」という技法などを使います。A「宿題やってない、見せて!」、B「そうか、宿題やってないのか、それで見せてほしいんだね。」と心のスペースを作りだせば、「なぜ?」という余裕ができます。そこで「訊いて、聴く」というスキルが生かされるのです。
「訊いて、聴く」ことにより「あ~、そうなんだ」という他者理解につながり、自己の主張をするという段階に移ることができます。このようにして積み上げられたコミュニケーションは、アサーティブネスと呼ばれています。時間は非常にかかるのですが、最終的には他者との折り合いをつけることが可能になります。共感性や自己開示のない自己と他者との関係性は、二者の共通する少しの部分しか成果が上がりません。それに比べて、共感性と自己開示にあふれた関係性は、二者の共通する部分はもちろん、二者がもつ能力すべてを引き出します。
そしてさらに、不安や恐怖は人を遠ざけますが、信頼と安心は人を呼びよせます。つまり、二者に呼びよせられた人々の力までも合体させてしまう力をもっているのです。これでプロジェクトがうまくいかないわけがありません。相乗効果は成功体験や達成感をさらに向上させるのです。
***
 |
いじめ・不登校を防止する人間関係プログラム |
| 深美隆司 価格:¥ 2,000(+税) | |
| 学事出版 |
 |
子どもと先生がともに育つ人間力向上の授業 |
| 深美隆司 価格:¥ 1,800(+税) | |
| 図書文化社 |
あいあいネットワーク of HRS
ホームページURL:http://aiainet-hrs.jp/


















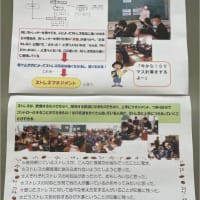







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます