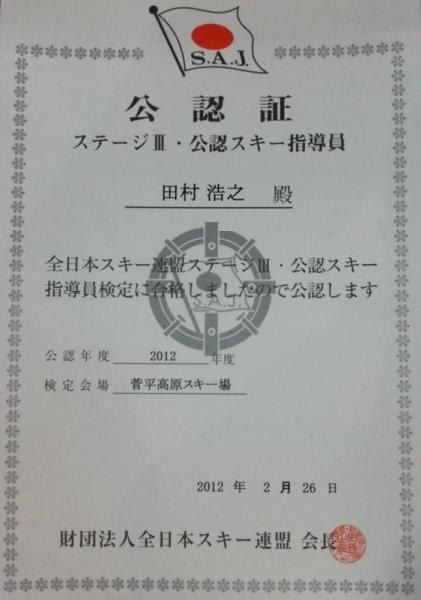1/4(日)の午前に行われた指導者研修会の後、午後には検定員のクリニックがありましたので参加してきました。
私は準指導員資格を取ったときに併せてC級検定員という資格を取りました。正指導員になるとB級検定員資格が取れます。
検定員資格はスキー検定などのジャッジを行うのに必要な資格です。C級はスキーバッジテストの級別テスト(1級~5級)とジュニアテスト、B級はこれに加えて準指導員検定、全日本スキー技術選手権大会の予選会が検定できます。その上のA級になると全日本スキー技術選手権大会の本選、正指導員検定ができるようになります。
検定員になると、2年に一度はクリニックと呼ばれる行事に参加して検定技術の維持向上を図らなければなりません。
というのがお題目で、実際のクリニックでは実際のスキーヤーの滑りを見て採点し、講師の先生方による模範採点と自分の採点とを比較してそのギャップを反省(?)する、という内容です。外れまくっても資格剥奪ということがないので少し気が楽です。一応模範点と±3点以内が許容範囲なのでなかなか外れることはありませんが、合否を間違えるのは避けたいところです。
さてクリニックは開会式で始まりました。水落亮太デモ、佐藤秀明デモ、新潟県連の先生方の挨拶で始まり始まり。出席者は約40名くらい。正指と準指が半々で、準指の方がちょっと多いくらいの割合。

検定員クリニックの開会式。
昨シーズンに都連で受けたクリニックでは、ビデオをみて採点するという形式でした。実際にスキー場で行われるバッジテストや検定会を見て採点し模範点と比較するという本番さながらの臨場感溢れるクリニックもあるようです。今回は二班に分かれて、片方が演技して滑り、もう片方がそれを採点するという形式でした。レベルはバッジテスト一級(合格点70点以上)を想定。種目は大回りと小回り。
今回行われた演技では、スタート地点で滑り方をいろいろ指示されます。「普通に滑って下さい」という指示の他に、例えば「横ずれの多い滑り」とか「上下動を多く」とか「ローテーションを強く」とか。
逆に見ると、こういう風に検定員は滑りを見るんだなーということが改めて分かって大変勉強になりました。
それにしても演技される方々が実にユニークに演技しながら滑って来るので、思わず笑ってしまうことも多かったです。

演技滑走と採点風景。(右の後ろ姿はk2hiko先生)
私の採点結果はちょっと外れ気味。4点以上外したのはなかったのですが、3点離れてしまったものがあり、もっと見る目を鍛えなければ・・・。
k2hikoさんの演技に73点(模範点は72点)付けたら「付けすぎです」と言われてしまいました。始め80点付けて消したことは口が裂けても言えない(大汗)。
私自身の演技では「横ずれの多い小回り」という指示がありましたので、思いっきりずれずれにずらしながら滑ってみました。模範採点は67点。ちょっと極端に演技しすぎたかなー。1級っぽいが横ずれがちょっと強い、69点くらいになるように滑った方がよかったかなあと反省しました。
普段どおりに滑ったら何点付くだろう・・・と試したい誘惑に一瞬駆られましたが、70点に届かなかったら再起できなくなる怖れがあるので止めておきました(爆)。
以上で研修会とクリニックの報告を終わります。これまで雲の上の存在だったスキースクールの先生方に混じって研修を受けられたことは本当にうれしくて誇らしく、かつ大変勉強になりました。自分自身のレベルに対する自信も少し深めることができました。研修会に参加された講師・先生の皆様、そしてお誘い下さったk2hikoさん、本当にありがとうございました。_(^o^)_