魚眼図バージョン(2009年4月21日北海道新聞夕刊掲載)
釘の十字架
かつての西ベルリンの中心に、廃墟となった教会が建っている。第二次世界大戦中、このヴィルヘルム王記念教会はイギリス軍を主力とする連合軍の空爆によって破壊された。戦後は、戦争に対する警鐘の意味を込めて、崩れ落ちた姿のまま保存されることになった。
その内側の片隅に、釘をつなぎ合わせて作られた十字架が立っている。これを「コヴェントリーの釘の十字架」と言う。コヴェントリーはイギリスの都市で、やはり同じ大戦中、ドイツ軍の空襲を受けて多数の犠牲者を出し、由緒ある大聖堂も破壊された。間もなくその祭壇にハワード司祭が「父よ赦したまえ」と刻み込んだ。そして焼け跡から見つかった大釘で十字架が作られた。
イギリス軍の空襲被害を受けたドイツの都市に、戦後、このコヴェントリーから釘の十字架が「和解のシンボル」として贈られるようになった。その一つがベルリンのヴィルヘルム王記念教会にあるものだ。今ではドイツだけでなく、東欧、中東、アジア、アフリカ、アメリカなど世界の教会や団体に釘十字が贈られ、これらの釘十字センターが和解のネットワークを形成している。
そして司祭が刻んだ「父よ赦したまえ」の言葉から「和解の祈り」が作られ、イギリス時間で毎週金曜日の正午に、世界の釘十字センターで同時に唱えられている。
廃墟の中の古い釘から作られた十字架。それがかつての「敵」と「敵」とを結びつけ、関係を平和なものに変える和解のシンボルとなる。和解の仕事がいかに多様なやり方でなされるものかをこの釘十字のケースから学ぶことができる。
(小田博志・北大准教授=文化人類学)
* * * * * *
かつての西ベルリンの中心に、廃墟となった教会が立っています。ヴィルヘルム王記念教会です。
第2次世界大戦中、この教会は連合軍の空爆によって破壊されました。戦後は、戦争に対する警鐘の意味を込めて、崩れ落ちた姿のまま保存されることになりました。(その点で、広島の「原爆ドーム」と共通しています。)教会としての機能を持つ新しい建物が後に併設されています。
先日、その新しい方の中で、ある掲示に目が留まりました。
「毎週金曜日13時:コヴェントリーの釘の十字架にて平和と和解のための祈り」
と書かれています。
これがヴィルヘルム王記念教会に置かれた釘の十字架です。
コヴェントリーはイギリス中部の都市で、やはり第2次世界大戦のときに、ドイツ軍の空襲を受け、多数の犠牲者を出しました。さらに大聖堂も破壊されてしまいました。
では、コヴェントリーの釘の十字架とは何でしょうか。それがどうして当時の敵国ドイツの教会にあるのでしょうか。
空襲の後、ハワード司祭は焼け落ちた教会の中で、天井部分に使われていた大釘を見つけます。そしてそれを組み合わせて十字架を作りました。これが最初の「釘の十字架」です。そして祭壇の壁面に「父よ赦したまえ」と、のみで刻みました。この破壊をもたらした者にも赦しを、との思いを込めたのだそうです。
戦後、イギリス軍の空襲で破壊されたドイツの都市に、コヴェントリーから「和解のシンボル」として釘十字が贈られるようになります。最初に受け取ったのはキールで、1947年のことでした。それからコヴェントリーと釘十字を受け取った教会や組織の間で、「コヴェントリー釘十字コミュニティ」というネットワークが結ばれるようになります。
ドイツではすでに50以上の教会と団体がこのネットワークに入っています。そのひとつがベルリンのヴィルヘルム記念教会だったのです。
ハワード司祭が刻んだ「父よ赦したまえ」の言葉から「和解の祈り」が生まれ、毎週金曜日の12時(イギリス時間)に、釘十字コミュニティに入っている各国の教会で唱えられています。
ベルリンでは他に、アレクサンダー広場のマリア教会にもコヴェントリーの釘の十字架があります。
和解の仕事がいかに多様なやり方でなされるものかが、この釘十字のケースからわかります。廃墟の中から拾い出した釘を使って作られた十字架。それがかつての「敵」と「敵」とを結びつけ、関係を平和なものに変える和解のシンボルとなる。ここには人間の創造性が表れています。
今度の金曜日には和解の祈りに参加したいものです。














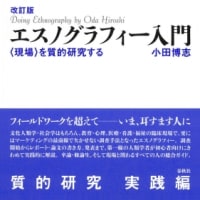







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます