「言葉」という言葉は不思議だ。なぜ葉っぱの「葉」が付くのだろう。
『古語辞典』(大野晋ほか編、岩波書店)を紐解(ひもと)いてみると、次のように説明されている。口でいうコト(言)と出来事のコト(事)はもともと未分化だった。しかし時代が下ると両者が区別され、事の一端を示すに過ぎない発言や、口先だけの表現もあることから、コトのハ(端)、すなわちコトバというようになった。
これに対して、北大で言語学を講じた津曲敏郎先生は、「コトノハ考」という論文で、コトバの積極的な意味を指摘された。つまりコトバはたんなる「端っこ」ではなくて、意味される内容(事 こと)と意味する媒体(端 は)との結びつきを示す点で、世界の諸言語の中でもユニークである、と。
それでもなお残る謎は、なぜ「葉」なのかということだ。葉(は)には端(は)の当て字以上のものがある、と私は考えている。
木の端っこにある葉っぱ。そんな一枚の葉っぱを引っぱると枝がしなるだろう。枝は幹につながり、幹をたどると地面の中にもぐって根っことなる。その根っこは土中に広がり水を吸い上げ、微生物と共生して養分をやりとりしている。上空に目を転ずると、降り注ぐ日光を葉っぱが浴びて光合成をし、また空中の酸素で呼吸している。一枚の葉っぱは、天地の間の森羅万象が関わり合っているということの一つの表れである。
この葉っぱのイメージが「言葉」という言葉には移されている。一つの言葉は一見小さくてはかない。しかしその向こうには、それを発した人の人生のみならず、その人と縁あるあらゆる人々と物事の無限のつながりが広がっている。 (北海道新聞夕刊<魚眼図>2023年9月4日掲載)
『古語辞典』(大野晋ほか編、岩波書店)を紐解(ひもと)いてみると、次のように説明されている。口でいうコト(言)と出来事のコト(事)はもともと未分化だった。しかし時代が下ると両者が区別され、事の一端を示すに過ぎない発言や、口先だけの表現もあることから、コトのハ(端)、すなわちコトバというようになった。
これに対して、北大で言語学を講じた津曲敏郎先生は、「コトノハ考」という論文で、コトバの積極的な意味を指摘された。つまりコトバはたんなる「端っこ」ではなくて、意味される内容(事 こと)と意味する媒体(端 は)との結びつきを示す点で、世界の諸言語の中でもユニークである、と。
それでもなお残る謎は、なぜ「葉」なのかということだ。葉(は)には端(は)の当て字以上のものがある、と私は考えている。
木の端っこにある葉っぱ。そんな一枚の葉っぱを引っぱると枝がしなるだろう。枝は幹につながり、幹をたどると地面の中にもぐって根っことなる。その根っこは土中に広がり水を吸い上げ、微生物と共生して養分をやりとりしている。上空に目を転ずると、降り注ぐ日光を葉っぱが浴びて光合成をし、また空中の酸素で呼吸している。一枚の葉っぱは、天地の間の森羅万象が関わり合っているということの一つの表れである。
この葉っぱのイメージが「言葉」という言葉には移されている。一つの言葉は一見小さくてはかない。しかしその向こうには、それを発した人の人生のみならず、その人と縁あるあらゆる人々と物事の無限のつながりが広がっている。 (北海道新聞夕刊<魚眼図>2023年9月4日掲載)












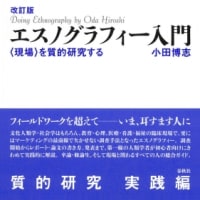








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます