・掲載する文献をここでは「書籍」に限っています。
・各カテゴリーでの掲載順は、当該書籍の「版」の発行年によっています(そのため翻訳の発行が新しければ、海外の古典でも後ろの方にきたりしています)。
・複数の見出しカテゴリーに関わる本は、重複表示をすることがあります。
I.質的研究の概説書と研究例
[質的研究の概説書]
[質的研究の倫理]
[研究デザイン]
[質的研究とコンピュータ]
[フィールドワーク/エスノグラフィーの概説書]
[フィールドワーク/エスノグラフィーにおける視聴覚データ/マルチメディア]
[エスノグラフィー論]
[人類学的エスノグラフィーの実例]
[社会学的エスノグラフィーの実例]
[カルチュラル・スタディーズ的エスノグラフィーの実例]
[法学的エスノグラフィーの実例]
[経済・経営学的エスノグラフィーの実例]
[教育学的エスノグラフィーの実例]
[心理学的エスノグラフィーの実例]
[看護学的エスノグラフィーの実例]
[言語学的エスノグラフィーの実例]
[歴史学的エスノグラフィーの実例]
[民俗学研究/民俗誌]
[グラウンデッド・セオリー・アプローチの概説書]
[グラウンデッド・セオリー・アプローチの研究例]
[ライフヒストリー/ライフストーリー研究の概説書]
[オーラル・ヒストリーの概説書]
[ライフヒストリー/ライフストーリー/オーラル・ヒストリー研究の実例]
[ナラティブ研究の実例]
[エスノメソドロジーと会話分析]
[談話・ディスコース分析]
[グループインタビューの概説書]
[解釈学的現象学の概説書]
[アクション・リサーチの概説書]
[その他の手法]
I.質的研究の概説書と研究例
[質的研究の概説書]
北澤毅、古賀正義(編)1997『〈社会〉を読み解く技法:質的調査法への招待』福村出版
J・ロフランド、L・ロフランド (進藤雄三、宝月誠 訳)(1997)『社会状況の分析:質的観察と分析の方法』恒星社厚生閣
U・フリック(小田博志、山本則子、春日常、宮地尚子 訳)2002『質的研究入門:〈人間の科学〉のための方法論』春秋社
S・B・メリアム(堀薫夫、久保真人、成島美弥 訳)2004『質的調査法入門:教育における調査法とケース・スタディ』ミネルヴァ書房
波平恵美子、道信良子 2005『質的研究Step by Step―すぐれた論文作成をめざして』医学書院
N・K・デンジン、Y・S・リンカン(平山満義 監訳、岡野一郎、古賀正義 編訳)2006『質的研究ハンドブック 1巻―質的研究のパラダイムと眺望』北大路書房
N・K・デンジン、Y・S・リンカン(平山満義 監訳、藤原顕 編訳)2006『質的研究ハンドブック 2巻―質的研究の設計と戦略』北大路書房
N・K・デンジン、Y・S・リンカン(平山満義 監訳、大谷 尚、伊藤 勇 編訳)2006『質的研究ハンドブック 3巻―質的研究資料の収集と解釈』北大路書房
秋田喜代美・能智正博 監修、能智正博・川野健二(編)2007『はじめての質的研究法 臨床・社会編』東京図書
秋田喜代美・能智正博 監修、高橋都・会田薫子(編)2007『はじめての質的研究法 医療・看護編』東京図書
秋田喜代美・能智正博 監修、秋田喜代美・藤江康彦(編)2007『はじめての質的研究法 教育・学習編』東京図書
秋田喜代美・能智正博 監修、遠藤利彦・坂上裕子(編)2007『はじめての質的研究法 生涯発達編』東京図書
西條剛央 2007『ライブ講義 質的研究とは何か SCQRMベーシック編』新曜社
グレッグ美鈴 他(編)2007『よくわかる質的研究の進め方・まとめ方―看護研究のエキスパートをめざして』医歯薬出版
萱間真美 2007『質的研究実践ノート-研究プロセスを進めるclueとポイント』医学書院
Lyn Richards, Janice M. Morse(小林奈美 監訳)2007『はじめて学ぶ質的研究』医歯薬出版
佐藤郁哉 2008『質的データ分析法―原理・方法・実践』新曜社
西條剛央 2008『ライブ講義 質的研究とは何か SCQRMアドバンス編』新曜社
北澤毅・古賀正義(編)2008『質的調査法を学ぶ人のために』世界思想社
北 素子、谷津裕子 2009 『質的研究の実践と評価のためのサブストラクション』医学書院
リチャーズ、リン(大谷順子、大杉卓三 訳)2009 『質的データの取り扱い』北大路書房
ブレア、マイケル/ウッド、フィオナ(上淵 寿 監訳)2009 『質的研究法キーワード』金子書房
シュワント、トマス・A(伊藤勇、徳川直人、内田健 訳)2009 『質的研究用語事典』北大路書房
谷富夫・芦田徹郎(編著)2009『よくわかる質的社会調査 技法編』ミネルヴァ書房
伊藤哲司 2009『みる きく しらべる かく かんがえる――対話としての質的研究』北樹出版
サトウ タツヤ 2009『TEMではじめる質的研究』 誠信書房
Barbara L. Paterson, Sally E. Thorne, Connie Canam, Carol Jillings(石垣和子・宮崎美砂子・北池正・山本則子 監訳)2010『質的研究のメタスタディ実践ガイド』医学書院
工藤保則・宮垣元・寺岡伸悟(編)2010『質的調査の方法―都市・文化・メディアの感じ方』法律文化社
谷富夫・山本努(編著)2010『よくわかる質的社会調査 プロセス編』ミネルヴァ書房
波平恵美子(語り手)、小田博志(聞き手) 2010『質的研究の方法―いのちの〈現場〉を読みとく』春秋社
得丸さと子 2010『ステップ式質的研究法―TAEの理論と応用』海鳴社
高木廣文 2010『質的研究を科学する』医学書院
フリック、ウヴェ(小田博志 監訳、小田博志、山本則子、春日常、宮地尚子 訳)2011『新版 質的
研究入門:〈人間の科学〉のための方法論』春秋社
山浦晴男 2012『質的統合法入門: 考え方と手順』医学書院
萱間真美 2013『質的研究のピットフォール: 陥らないために/抜け出るために』医学書院
サンデロウスキー,M.(谷津裕子・江藤裕之訳)2013『質的研究をめぐる10のキークエスチョン: サンデロウスキー論文に学ぶ』医学書院
[質的研究の倫理]
宮本常一・安渓遊地 2008『調査されるという迷惑―フィールドに出る前に読んでおく本』みずのわ出版
[研究デザイン]
G・キング、R・O・コヘイン、S・ヴァーバ(真渕 勝 監訳) 2004『社会科学のリサーチ・デザイン―定性的研究における科学的推論』勁草書房
John W. Creswell(操 華子・森岡 崇訳)2007『研究デザイン――質的・量的そしてミックス法』日本看護協会出版会
J.W.Creswell,V.L. Plan Clark(大谷順子 訳)2010『人間科学のための混合研究法―質的・量的アプローチをつなぐ研究デザイン』北大路書房
[質的研究とコンピュータ]
佐藤郁哉 2006『定性データ分析入門:QDAソフトウェア・マニュアル』新曜社
佐藤郁哉 2008『QDAソフトを活用する 実践 質的データ分析入門』(『定性データ分析入門』改定新版)新曜社
[フィールドワーク/エスノグラフィーの概説書]
川喜田二郎 1967『発想法―創造性開発のために』中央公論新社
デル・H・ハイムズ(唐須教光 訳)1979『ことばの民族誌 ― 社会言語学の基礎』紀伊国屋書店
杉本尚次 1983『フィールドワークの方法』講談社
宮本常一 1986『宮本常一著作集第31巻 旅にまなぶ』未来社
佐藤郁哉 1992『フィールドワーク―書を持って街へ出よう』新曜社
原ひろ子 1993『観る・集める・考える』カタツムリ社
J・G・クレイン、M・V・アグロシーノ(江口信清 訳)1994『人類学フィールドワーク入門』昭和堂
R・エマーソン、R・フレッツ、L・ショウ(佐藤郁哉、好井裕明、山田富秋 訳)1998『方法としてのフィールドノート:現地取材から物語作成まで』新曜社
箕浦康子(編著)1999『フィールドワークの技法と実際―マイクロ・エスノグラフィー入門』ミネルヴァ書房
L・シャッツマン、A・ストラウス(川合隆男 監訳)1999『フィールド・リサーチ―現地調査の方法と調査者の戦略』慶應義塾大学出版会
好井裕明、桜井 厚(編)2000『フィールドワークの経験』せりか書房
住原則也、箭内匡、芹澤知広 2001『異文化の学びかた・描きかた―なぜ、どのように研究するのか』世界思想社
佐藤郁哉 2002『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説を鍛える』新曜社
好井裕明、山田富秋(編)2002『実践のフィールドワーク』せりか書房
J・M・Roper, J・Shapira(麻原きよみ、グレッグ美鈴 訳)2003『エスノグラフィー』(看護における質的研究1)日本看護協会出版会
柴山真琴 2006『子どもエスノグラフィー入門―技法の基礎から活用まで』新曜社
菅原和孝 2006『フィールドワークへの挑戦―〈実践〉人類学入門』世界思想社
原尻英樹 2006 『フィールドワーク教育入門―コミュニケーション力の育成』玉川大学出版部
佐藤郁哉 2006『フィールドワーク―書を持って街へ出よう(増訂版)』新曜社
井上 真(編)2006『躍動するフィールドワーク―研究と実践をつなぐ』世界思想社
武田 丈, 亀井 伸孝(編) 2008『アクション別フィールドワーク入門』世界思想社
李仁子、金谷美和、佐藤和久(編)2008『はじまりとしてのフィールドワーク―自分がひらく、世界がわかる』昭和堂
箕浦康子(編著)2009『フィールドワークの技法と実際II分析・解釈編』ミネルヴァ書房
西川麦子 2010 『フィールドワーク探求術―気づきのプロセス、伝えるチカラ』ミネルヴァ書房
小田博志 2010『エスノグラフィー入門―〈現場〉を質的研究する』春秋社
ジェイムズ P.スプラッドリー(田中美恵子、麻原きよみ監訳)2010『参加観察法入門』医学書院
金井壽宏、佐藤郁哉、ギデオン・クンダ、ジョン・ヴァン‐マーネン 2010 『組織エスノグラフィー』有斐閣
新原道信 2011『旅をして、出会い、ともに考える―大学で初めてフィールドワークをするひとのために』中央大学出版部
日本文化人類学会(監修)、鏡味治也他(編)2011『フィールドワーカーズ・ハンドブック』世界思想社
佐藤知久 2013『フィールドワーク2.0―現代世界をフィールドワーク』 (京都文教大学文化人類学ブックレット No. 8)風響社
藤田結子、北村文(編)2013『現代エスノグラフィー: 新しいフィールドワークの理論と実践』新曜社
2013-16「フィールドワーク選書」(全20巻)臨川書店
椎野若菜・白石壮一郎(編)2014『フィールドに入る』(FENICS 100万人のフィールドワーカーシリーズ1)古今書房
増田研・梶丸岳・椎野若菜(編)2015『フィールドの見方』(FENICS 100万人のフィールドワーカーシリーズ2) 古今書房
木村周平・杉戸信彦・柄谷友香(編)2014『災害フィールドワーク論』(FENICS 100万人のフィールドワーカーシリーズ5) 古今書房
佐藤靖明・村尾るみこ(編)2014『衣食住からの発見』(FENICS 100万人のフィールドワーカーシリーズ11)古今書房
[フィールドワーク/エスノグラフィーにおける視聴覚データ/マルチメディア]
川田順造 1988『サバンナの音の世界』白水社(白水カセットブック)
大森康宏(編)1996『ジプシー・マヌーシュの生活』エスパ(ビデオブック)
石黒広昭(編)2001『AV機器をもってフィールドへ:保育・教育・社会的実践の理解と研究のために』新曜社
山中速人(編)2002『マルチメディアでフィールドワーク』有斐閣(CD-ROM付き)
北村皆雄 他(編)2006『見る、撮る、魅せるアジア・アフリカ!―映像人類学の新地平』新宿書房(DVD付き)
分藤大翼・川瀬慈・村尾静二(編)2015『フィールド映像術』(FENICS 100万人のフィールドワーカーシリーズ15)古今書房
[エスノグラフィー論]
G・マーカス,M・フィッシャー(永渕康之 訳)1989 『文化批判としての人類学―人間科学における実験的試み』紀伊国屋書店
J・クリフォード、G・マーカス(春日直樹 他訳)1996 『文化を書く』紀伊国屋書店(原著1986年)
C・ギアーツ(森泉弘次 訳)1996『文化の読み方/書き方』岩波書店
J・ヴァン‐マーネン(森川渉 訳)1999『フィールドワークの物語:エスノグラフィーの文章作法』現代書館
茂呂雄二(編著)2001『実践のエスノグラフィ』金子書房
松田素二、川田牧人(編著)2002『エスノグラフィー・ガイドブック』嵯峨野書院
J・クリフォード(太田好信 他訳)2003『文化の窮状―二十世紀の民族誌、文学、芸術』世界思想社(原著1988年)
[人類学的エスノグラフィーの実例]
B・マリノフスキー(寺田和夫、増田義郎 訳)1972『西太平洋の遠洋航海者』中央公論社(原著1922年)
H・ライヘル=ドルマトフ(寺田和夫、友枝啓泰 訳)1973『デサナ―アマゾンの性と宗教のシンボリズム』岩波書店(原著1968年)
飯島茂 1973『祖霊の世界―アジアのひとつの見方』日本放送出版協会
コリン・M.ターンブル(幾野 宏 訳)1974『ブリンジ・ヌガグ―食うものをくれ』筑摩書房
コリン・M.ターンブル(藤川玄人 訳)1976『森の民』筑摩書房
M・ミード(畑中幸子、山本真鳥 訳)1976『サモアの思春期』蒼樹書房(原著1928年)
J・F・エンブリー(植村元覚 訳)1978『日本の村―須恵村』日本経済評論社(原著1939年)
J・A・ピット=リバーズ(野村雅一 訳)1980『シエラの人びと―スペイン・アンダルシア民俗誌』弘文堂(原著1954年)
P・ラビノー(井上順孝 訳)1980『異文化の理解―モロッコのフィールドワークから』岩波書店(原著1977年)
大貫恵美子 1985『日本人の病気観―象徴人類学的考察』岩波書店
J・オークリー 1986『旅するジプシーの人類学』晶文社(原著1983年)
R・J・スミス、E・L・ウィスウェル(河村望、斉藤尚文 訳)1987『須恵村の女たち―暮らしの民俗誌』御茶の水書房
長島信弘 1987『死と病いの民族誌―ケニア・テソ族の災因論』岩波書店
小川了1987『サヘルに暮らす―西アフリカ・フルベ民族誌』日本放送出版協会
山下晋司 1988『儀礼の政治学―インドネシア・トラジャの動態的民族誌』弘文堂
川田順造 1988『サバンナの音の世界』白水社(白水カセットブック)
S・フェルド(山口修 他訳)1988『鳥になった少年―カルリ社会における音・神話・象徴』平凡社(原著1982年)
原ひろ子 1989『ヘヤー・インディアンとその世界』平凡社
清水展 1990『出来事の民族誌―フィリピン・ネグリート社会の変化と持続』九州大学出版会
M・レーナルト(坂井信三訳)1990『ド・カモ―メラネシア世界の神話と人格』せりか書房(原著1947年)
C・ギアーツ(小泉潤二 訳)1990『ヌガラ―19世紀バリの劇場国家』みすず書房(原著1980年)
M・ブロック(田辺繁治、秋津元輝 訳)1990『祝福から暴力へ―儀礼における歴史とイデオロギー』法政大学出版会(原著1986年)
福井勝義 1991『認識と文化―色と模様の民族誌』東京大学出版会
土屋健治 1991『カルティニの風景』めこん
吉田憲司 1992『仮面の森―アフリカ・チェワ社会における仮面結社、憑霊、邪術』講談社
E・R・リーチ(関本照夫 訳)1995『高地ビルマの政治体系』弘文堂(原著1954年)
E・E・エヴァンズ=プリチャード(向井元子 訳)1995『ヌアー族の宗教』(上・下)平凡社(原著1956年)
大貫恵美子 1995『コメの人類学―日本人の自己認識』岩波書店
関根康正 1995『ケガレの人類学―南インド・ハリジャンの生活世界』東京大学出版会
V・W・ターナー(富倉光雄 訳)1996『儀礼の過程』新思索社(原著1969年)
谷泰 1996『牧夫フランチェスコの一日―イタリア中部山村生活誌』平凡社(初版1976年)
栗本英世 1996 『民族紛争を生きる人びと―現代アフリカのマイノリティ』世界思想社
松田素二 1996『都市を飼い慣らす―アフリカの都市人類学』河出書房新社
山本 泰・山本真鳥 1996『儀礼としての経済―サモア社会の贈与・権力・セクシュアリティ』弘文堂
大森康宏(編)1996『ジプシー・マヌーシュの生活』エスパ(ビデオブック)
森山工 1996 『墓を生きる人々:マダガスカル、シハナカにおける社会的実践』 東京大学出版会
E・E・エヴァンズ=プリチャード(向井元子 訳)1997『ヌアー族』平凡社(原著1940年)
M・グリオール(坂井信三・竹沢尚一郎 訳)1997『水の神―ドゴン族の神話的世界』せりか書房(原著1948年)
細谷広美 1997『アンデスの宗教的世界―ペルーにおける山の神信仰の現在性』明石書店
P・ラビノウ(渡辺政隆 訳)1998『PCRの誕生―バイオテクノロジーのエスノグラフィー』みすず書房
岸上伸啓 1998『極北の民カナダ・イヌイット』弘文堂
菅原和孝 1998『語る身体の民族誌―ブッシュマンの生活世界(1)』京都大学学術出版会
菅原和孝 1998『会話の人類学―ブッシュマンの生活世界(2)』京都大学学術出版会
小川了 1998『可能性としての国家誌―現代アフリカ国家の人と宗教』世界思想社
F・バルト(麻田 豊 監修、子島 進 訳)1998『スワート最後の支配者』勁草書房
森明子 1999『土地を読みかえる家族―オーストリア・ケルンテンの歴史民族誌』新曜社
松田素二 1999『抵抗する都市─ナイロビ移民の世界から』岩波書店
タキエ・スギヤマ・リブラ(竹内洋、井上義和、海部優子 訳)2000『近代日本の上流階級―華族のエスノグラフィー』世界思想社
佐々木重洋 2000『仮面パフォーマンスの人類学―アフリカ、豹の森の仮面文化と近代』世界思想社
高倉浩樹 2000『社会主義の民族誌―シベリア・トナカイ飼育の風景』東京都立大学出版会
鈴木裕之 2000『ストリートの歌―現代アフリカの若者文化』世界思想社
金基淑 2000『アザーンとホラ貝ーーインド・ベンガル地方の絵語り師の宗教と生活戦略』明石書店
鷹木恵子 2000『北アフリカのイスラーム聖者信仰―チュニジア・セダダ村の歴史民族誌』刀水書房
E・リーボウ(吉川徹 監訳)2001『タリーズコーナー:黒人下層階級のエスノグラフィ』東信堂
G・ベイトソン、M・ミード(外山昇 訳)2001『バリ島人の性格:写真による分析』国文社
E・E・エヴァンズ=プリチャード(向井元子 訳)2001『アザンデ人の世界―妖術・託宣・呪術』みすず書房(原著1937年)
C・レヴィ=ストロース(川田順造訳)2001『悲しき熱帯』(I,II)中央公論社(原著1955年)
川田順造 2001『無文字社会の歴史―アフリカ・モシ族の事例を中心に』岩波書店(初版1976年)
川田順造2001(1992)『口頭伝承論』平凡社(河出書房新社)
川上郁雄 2001『越境する家族―在日ベトナム系住民の生活世界』明石書店
春日直樹 2001『太平洋のラスプーチン―ヴィチ・カンバニ運動の歴史人類学』世界思想社
浜本満 2001『秩序の方法―ケニア海岸地方の日常生活における儀礼的実践と語り』弘文堂
河合利光 2001『身体と形象―ミクロネシア伝承世界の民族誌的研究』風響社
白川千尋 2001『カストム・メレシン―オセアニア民間医療の人類学的研究』風響社
西井凉子 2001『死をめぐる実践宗教―南タイのムスリム・仏教徒関係へのパースペクティヴ』世界思想社
H.アルロ・ニモ(西重人訳)2001『漂海民バジャウの物語―人類学者が暮らしたフィリピン・スールー諸島』現代書館
名和克郎 2002『ネパール、ビャンスおよび周辺地域における儀礼と社会範疇に関する民族誌的研究―もうひとつの「近代」の布置』三元社
ヤコブ・ラズ(高井宏子訳)2002『ヤクザの文化人類学―ウラから見た日本』岩波書店(岩波現代文庫)
エドワード・ファウラー(川島めぐみ訳)2002『山谷ブルース』新潮社(新潮OH!文庫)
K.ガードナー(田中典子訳)2002『河辺の詩―バングラデシュ農村の女性と暮らし』風響社
大貫恵美子 2003『ねじ曲げられた桜―美意識と軍国主義』岩波書店
中谷文美 2003『女の仕事のエスノグラフィー―バリ島の布・儀礼・ジェンダー』世界思想社
田口理恵 2003『ものづくりの人類学―インドネシア・スンバ島の布織る村の生活誌』風響社
外川昌彦 2003『ヒンドゥー女神と村落社会―インド・ベンガル地方の宗教民俗誌』風響社
シンジルト 2003『民族の語りの文法―中国青海省モンゴル族の日常・紛争・教育』風響社
坂井信三 2003『イスラームと商業の歴史人類学―西アフリカの交易と知識のネットワーク』世界思想社
風間計博 2003『窮乏の民族誌―中部太平洋・キリバス南部環礁の社会生活』大学教育出版
古谷嘉章 2003『憑依と語り―アフロアマゾニアン宗教の憑依文化』九州大学出版会
渡辺 公三 2003『司法的同一性の誕生―市民社会における個体識別と登録』言叢社
川田牧人 2003『祈りと祀りの日常知―フィリピン・ビサヤ地方バンタヤン島民族誌』九州大学出版会
松田素二 2003『呪医の末裔─東アフリカ・オデニョー族の20世紀』講談社
デボラ・B・ローズ 2003『生命の大地―アボリジニ文化とエコロジー』平凡社
森谷 裕美子 2004『ジェンダーの民族誌―フィリピン・ボントックにおける女性と社会』九州大学出版会
中田友子 2004『南ラオス村落社会の民族誌―民族混住状況下の「連帯」と闘争』明石書店
王向華 2004『友情と私利―香港一日系スーパーの人類学的研究』風響社
奥野克巳 2004『「精霊の仕業」と「人の仕業」―ボルネオ島カリス社会における災い解釈と対処法』春風社
渡辺 靖 2004『アフター・アメリカ―ボストニアンの軌跡と〈文化の政治学〉』慶應義塾大学出版局
藤原久仁子 2004『「聖女」信仰の成立と「語り」に関する人類学的研究』すずさわ書店
菅原 和孝 2004『ブッシュマンとして生きる―原野で考えることばと身体』中央公論新社
加藤恵津子 2004『”お茶”はなぜ女のものになったか―茶道から見る戦後の家族』世界思想社
花渕馨也 2005『精霊の子供―コモロ諸島における憑依の民族誌』春風社
清水郁郎 2005『家屋とひとの民族誌―北タイ山地民アカと住まいの相互構築誌』風響社
青木恵理子 2005『生を織りなすポエティクス―インドネシア・フローレス島における詩的語りの人類学』世界思想社
M・ロック(江口重幸、山村宜子、北中淳子 訳)2005『更年期―日本女性が語るローカル・バイオロジー』みすず書房
野元美佐 2005『アフリカ都市の民族誌―カメルーンの「商人」バミレケのカネと故郷』明石書店
米山リサ(小沢弘明 他訳)2005『広島―記憶のポリティクス』岩波書店
田川泉 2005『公的記憶をめぐる博物館の政治性―アメリカ・ハートランドの民族誌』明石書店
福井勝義(編)2005『社会化される生態資源―エチオピア絶え間なき再生』京都大学学術出版会
渋谷 努 2005『国境を越える名誉と家族―フランス在住モロッコ移民をめぐる「多現場」民族誌』東北大学出版会
H.アルロ・ニモ(西重人訳)2005『フィリピン・スールーの海洋民―バジャウ社会の変化』現代書館
R・F・マーフィー(辻 信一 訳)2006『ボディ・サイレント』平凡社(平凡社ライブラリー)
大貫恵美子 2006『学徒兵の精神誌―「与えられた死」と「生」の探求』岩波書店
飯田淳子 2006『タイ・マッサージの民族誌―「タイ式医療」生成過程における身体と実践』明石書店
亀井伸孝 2006『アフリカのろう者と手話の歴史』明石書店
岸上伸啓 2007『カナダ・イヌイットの食文化と社会変化』世界思想社
テオドル・ベスター(和波雅子・福岡伸一 訳)2007『築地』木楽舎
林 史樹 2007『韓国サーカスの生活誌―移動の人類学への招待』風響社
金谷美和 2007『布がつくる社会関係―インド絞り染め布とムスリム職人の民族誌』思文閣出版
伊藤泰信 2007『先住民の知識人類学 ― ニュージーランド=マオリの知と社会に関するエスノグラフィ』世界思想社
鷹木恵子 2007『マイクロクレジットの文化人類学 ― 中東・北アフリカにおける金融の民主化にむけて』世界思想社
石井美保 2007『精霊たちのフロンティア―ガーナ南部の開拓移民社会における“超常現象”の民族誌』世界思想社
松村圭一郎 2008『所有と分配の人類学―エチオピア農村社会の土地と富をめぐる力学』世界思想社
春日直樹(編)2008『人類学で世界をみる―医療・生活・政治・経済』ミネルヴァ書房
板垣竜太 2008『朝鮮近代の歴史民族誌―慶北尚州の植民地経験』明石書店
竹沢尚一郎 2008『サバンナの河の民―記憶と語りのエスノグラフィ』世界思想社
田辺繁治 2008『ケアのコミュニティ―北タイのエイズ自助グループが切り開くもの』岩波書店
藤田渡 2008『森を使い森を守る―タイの森林保護政策と人々の暮らし』京都大学学術出版会
金明美 2009『サッカーから見る日韓のナショナリティとローカリティ―地域スポーツ実践の場への文化人類学的アプローチ』御茶の水書房
西 真如 2009『現代アフリカの公共性―エチオピア社会にみるコミュニティ・開発・政治実践』昭和堂
長坂格 2009『国境を越えるフィリピン村人の民族誌―トランスナショナリズムの人類学』明石書店
速水洋子 2009『差異とつながりの民族誌―北タイ山地カレン社会の民族とジェンダー』世界思想社
岩谷彩子 2009『夢とミメーシスの人類学―インドを生き抜く商業移動民ヴァギリ』明石書店
北村 毅 2009『死者たちの戦後誌―沖縄戦跡をめぐる人びとの記憶』御茶の水書房
立川陽仁 2009『カナダ先住民と近代産業の民族誌―北西海岸におけるサケ漁業と先住民漁師による技術的適応』御茶の水書房
B・マリノフスキ(増田義郎 訳)2010『西太平洋の遠洋航海者』講談社(講談社学術文庫)
丸山淳子 2010『変化を生きぬくブッシュマン―開発政策と先住民運動のはざまで』 世界思想社
亀井伸孝 2010『森の小さな〈ハンター〉たち―狩猟採集民の子どもの民族誌』京都大学学術出版会
藤原潤子 2010『呪われたナターシャ―現代ロシアにおける呪術の民族誌』人文書院
田辺繁治 2010『「生」の人類学』岩波書店
大川真由子 2010『帰還移民の人類学―アフリカ系オマーン人のエスニック・アイデンティティ』明石書店院
金子守恵 2011『土器つくりの民族誌―エチオピア女性職人の地縁技術』昭和堂
ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ 2011『懐かしい未来 ラダックから学ぶ』懐かしい未来の本
栗田和明 2011『アジアで出会ったアフリカ人―タンザニア人交易人の移動とコミュニティ』昭和堂
佐川 徹 2011『暴力と歓待の民族誌:東アフリカ牧畜社会の戦争と平和』昭和堂
平井京之介 2011『村から工場へ―東南アジア女性の近代化経験』NTT出版
金子守恵 2011『土器つくりの民族誌―エチオピア女性職人の地縁技術』昭和堂
小川さやか 2011『都市を生きぬくための狡知―タンザニアの零細商人マチンガの民族誌』世界思想社
常田夕美子 2011『ポストコロニアルを生きる―現代インド女性の行為主体性』世界思想社
笹岡正俊 2012『資源保全の環境人類学―インドネシア山村の野生動物利用・管理の民族誌』コモンズ
高倉浩樹 2012『極北の牧畜民サハ―進化とミクロ適応をめぐるシベリア民族誌』昭和堂
大野哲也 2012『旅を生きる人々―バックパッカーの人類学』世界思想社
木村周平 2013『震災の公共人類学―揺れとともに生きるトルコの人びと』世界思想社
田村うらら 2013『トルコ絨毯が織りなす社会生活 ― グローバルに流通するモノをめぐる民族誌』世界思想社
高橋絵里香 2013『老いを歩む人々ー高齢者の日常からみた福祉国家フィンランドの民族誌』勁草書房
清水展 2013『草の根グローバリゼーション―世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略』京都大学学術出版会
山本達也 2013『舞台の上の難民―チベット難民芸能集団の民族誌』法藏館
ジェームズ・C・スコット 2013『ゾミア―脱国家の世界史』みすず書
田辺繁治 2013『精霊の人類学―北タイにおける共同性のポリティクス』岩波書店
鈴木晋介 2013『つながりのジャーティヤ―スリランカの民族とカースト』法藏館
大村敬一 2013『カナダイヌイトの民族誌』大阪大学出版会
馬場淳 2014『この子は俺の未来だ―パプアニューギニア&ケニア“つながり”の文化人類学』佼成出版社
山口未花子 2014『ヘラジカの贈り物―北方狩猟民カスカと動物の自然誌』春風社
浜本満 2014『信念の呪縛―ケニア海岸地方ドゥルマ社会における妖術の民族誌』九州大学出版会
松川恭子 2014『「私たちのことば」の行方―インド・ゴア社会における多言語状況の文化人類学』風響社
中村かれん 2014『クレイジー・イン・ジャパン―べてるの家のエスノグラフィ 』医学書院
北中 淳子 2014『うつの医療人類学』日本評論社
松嶋健 2014『プシコナウティカ―イタリア精神医療の人類学』世界思想社
箕曲在弘 2015『フェアトレードの人類学―ラオス南部ボーラヴェーン高原におけるコーヒー栽培農村の生活と協同組合』めこん
久保明教 2015『ロボットの人類学―二〇世紀日本の機械と人間』世界思想社
山崎吾郎 2015『臓器移植の人類学―身体の贈与と情動の経済』世界思想社
牛山美穂 2015『ステロイドと「患者の知」-アトピー性皮膚炎のエスノグラフィー』新曜社
佐藤斉華 2015『彼女達との会話―ネパール・ヨルモ社会におけるライフ/ストーリーの人類学』三元社
菅原和孝 2015『狩り狩られる経験の現象学―ブッシュマンの感応と変身』京都大学学術出版会
磯野真穂 2015『なぜふつうに食べられないのか: 拒食と過食の文化人類学』春秋社
竹村嘉晃 2015『神霊を生きること、その世界―インド・ケーララ社会における「不可触民」の芸能民族』風響社
戸田美佳子 2015『越境する障害者―アフリカ熱帯林に暮らす障害者の民族誌』明石書店
伊藤千尋 2015『都市と農村を架ける―ザンビア農村社会の変容と人びとの流動性』新泉社
マリリン・ストラザーン 2015『部分的つながり』水声社
エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ 2015『食人の形而上学―ポスト構造主義的人類学への道』 洛北出版
中川加奈子 2016『ネパールでカーストを生きぬく―供犠と肉売りを担う人びとの民族誌』世界思想社
比嘉夏子 2016『贈与とふるまいの人類学: トンガ王国の〈経済〉実践』京都大学学術出版会
中谷文美、宇田川妙子(編)2016『仕事の人類学 ― 労働中心主義の向こうへ』世界思想社
田川玄、慶田勝彦、花渕馨也(編)2016『アフリカの老人 ― 老いの制度と力をめぐる民族誌』九州大学出版会
伊東未来 2016『千年の古都ジェンネ―多民族が暮らす西アフリカの街』昭和堂
吉松久美子 2016『移動するカレン族の民族誌―フロンティアの終焉』東京外国語大学出版会
金縄初美 2016『つながりの民族誌―中国モソ人の母系社会における「共生」への模索』春風社
鈴木佑記 2016『現代の〈漂海民〉―津波後を生きる海民モーケンの民族誌』めこん
ケイトリン・コーカー 2019『暗黒舞踏の身体経験:アフェクトと生成の人類学』京都大学学術出版会
石原真衣 2020『〈沈黙〉の自伝的民族誌(オートエスノグラフィー):サイレント・アイヌの痛みと救済の物語』北海道大学出版会
S・ミンツ(川北稔、和田光弘 訳)2021『甘さと権力―砂糖が語る近代史』筑摩書房(ちくま学芸文庫)
[社会学的エスノグラフィーの実例]
佐藤郁哉 1984『暴走族のエスノグラフィー:モードの叛乱と文化の呪縛』新曜社.
E・ゴッフマン(石黒毅訳)1984『アサイラム:施設被収容者の日常世界』誠信書房
R・S・リンド、H・M・リンド(中村八郎 訳)1990『ミドゥルタウン』青木書店
H・S・ベッカー(村上直之 訳)1993(新装版)『アウトサイダーズ―ラベリング理論とは何か』新泉社
鵜飼正樹 1994『大衆演劇への旅―南条まさきの一年二ヶ月』未来社
N・S・ハイナー(田島淳子 訳)1997『ホテル・ライフ』(シカゴ都市社会学古典シリーズ1)ハーベスト社
ハーベイ・W・ゾーボー(吉原直樹・桑原司・奥田憲昭・高橋早苗 訳)1998『ゴールド・コーストとスラム』(シカゴ都市社会学古典シリーズ2)ハーベスト社
C・R・ショウ(玉井真理子、池田寛 訳)1998『ジャック・ローラー―ある非行少年自身の物語』東洋館出版社
佐藤郁哉 1999『現代演劇のフィールドワーク―芸術生産の文化社会学』東京大学出版会
N・アンダーソン(広田康生 訳)1999、2000『ホーボー:ホームレスの人たちの社会学』(上、下)(シカゴ都市社会学古典シリーズ3)ハーベスト社
W・F・ホワイト(奥田道大、有里典三 訳)2000『ストリート・コーナーソサエティ』有斐閣
イライジャ・アンダーソン(奥田道大・奥田啓子 訳)2003『ストリート・ワイズ:人種/階層/変動にゆらぐ都市コミュニティに生きる人びとのコード』ハーベスト社
小熊英二・上野陽子 2003『〈癒し〉のナショナリズム―草の根保守運動の実証研究』慶応義塾大学出版会
渡戸一郎他(編)2003『都市的世界/コミュニティ/エスニシティ』明石書店
黒坂愛衣(コメンテーター:福岡安則)2003, 2004『黒坂愛衣のとちぎ発と人権のエスノグラフィー』(Part 1, 2, 3)創土社
藤田結子 2008『文化移民―越境する日本の若者とメディア』新曜社
鶴田幸恵 2010 『性同一性障害のエスノグラフィ:性現象の社会学』 (質的社会研究シリーズ 4)ハーベスト社
宮内泰介 2011『開発と生活戦略の民族誌―ソロモン諸島アノケロ村の自然・移住・紛争』新曜社
ロイック・ヴァカン(田中研之輔、倉島哲、石岡丈昇 訳)2013『ボディ&ソウル: ある社会学者のボクシング・エスノグラフィー』新曜社
[カルチュラル・スタディーズ的エスノグラフィーの実例]
P・E・ウィリス(熊沢誠、山田潤 訳)1996『ハマータウンの野郎ども』筑摩書房 (ちくま学芸文庫)
小笠原祐子 1998『OLたちの〈レジスタンス〉―サラリーマンとOLのパワーゲーム』中央公論社(中公新書)
韓 東賢 2006『チマ・チョゴリ制服の民族誌―その誕生と朝鮮学校の女性たち』双風舎
[法学的エスノグラフィーの実例]
明石照久 2002『自治体エスノグラフィー―地方自治体における組織変容と新たな職員像』信山社
[経済・経営学的エスノグラフィーの実例]
村井吉敬 1978『スンダ生活誌―変動のインドネシア社会』日本放送出版協会(再刊2014『インドネシア・スンダ世界に暮らす』岩波書店)
ヘンリー・ミンツバーグ(奥村哲史、須貝栄 訳)1993『マネジャーの仕事』白桃書房
青山和佳 2006『貧困の民族誌―フィリピン・ダバオ市のサマ生活』東京大学出版会
平井京之介 2011『村から工場へ―東南アジア女性の近代化経験』NTT出版
中田英樹 2013『トウモロコシの先住民とコーヒーの国民―人類学が書きえなかった「未開」社会』有志舎
[教育学的エスノグラフィーの実例]
結城恵 1998『幼稚園で子どもはどう育つか―集団教育のエスノグラフィ』有信堂高文社
渋谷真樹 2001『「帰国子女」の位置取りの政治―帰国子女教育学級の差異のエスノグラフィ』勁草書房
柴山真琴 2002『行為と発話形成のエスノグラフィー―留学生家族の子どもは保育園でどう育つのか』東京大学出版会
野津 隆志 2005『国民の形成―タイ東北小学校における国民文化形成のエスノグラフィー』明石書店
森田京子 2007『子どもたちのアイデンティティー・ポリティックス―ブラジル人のいる小学校のエスノグラフィー』新曜社
[心理学的エスノグラフィーの実例]
伊藤哲司 2001『ハノイの路地のエスノグラフィー:関わりながら識る異文化の生活世界』ナカニシヤ出版
松嶋秀明 2005『関係性のなかの非行少年―更生保護施設のエスノグラフィーから』新曜社
土屋由美 2007『生によりそう「対話」―医療・介護現場のエスノグラフィーから』新曜社
落合美貴子 2009『バーンアウトののエスノグラフィー―教師・精神科看護婦の疲弊』(シリーズ・臨床心理学研究の最前線 2)ミネルヴァ書房
[看護学的エスノグラフィーの実例]
松澤和正 2008『臨床で書く―精神科看護のエスノグラフィー』医学書院
[言語学的エスノグラフィーの実例]
窪田光男 2005『第二言語習得とアイデンティティ ― 社会言語学的適切性のエスノグラフィー的ディスコース分析』ひつじ書房
[歴史学的エスノグラフィーの実例]
E・ル・ロワ・ラデュリ (井上 幸治、波木居 純一、渡辺 昌美訳)1990, 1991 『モンタイユー―ピレネーの村 1294~1324』(上、下)刀水書房
T・フジタニ(米山リサ 訳)1994『天皇のページェント―近代日本の歴史民族誌から』日本放送出版協会
板垣竜太 2008『朝鮮近代の歴史民族誌―慶北尚州の植民地経験』明石書店
[民俗学研究/民俗誌]
柳田國男(初出1910)1989「遠野物語」『柳田國男全集4』所収 筑摩書房(ちくま文庫)
折口信夫(初出1917)1999「身毒丸」『死者の書・身毒丸』所収 中央公論新社(中公文庫)
宮本常一(初出1960)1984『忘れられた日本人』岩波書店(岩波文庫)
亀井好恵 2000『女子プロレス民俗誌―物語のはじまり』雄山閣出版
杉本 仁 2007『選挙の民俗誌―日本的政治風土の基層』梟社
六車由美 2012『驚きの介護民俗学』医学書院
[グラウンデッド・セオリー・アプローチの概説書]
B・グレイザー、A・ストラウス(後藤隆、大出春江、水野節夫 訳)1996『データ対話型理論の発見:調査からいかに理論をうみだすか』新曜社
A・ストラウス,J・コービン(南裕子 監訳)1999『質的研究の基礎―グラウンデッド・セオリーの技法と手順』医学書院
木下康仁 1999『グラウンデッド・セオリー・アプローチ:質的実証研究の再生』弘文堂
木下康仁 2003『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践』弘文堂
A・ストラウス,J・コービン(操華子, 森岡崇 訳)2004『質的研究の基礎―グラウンデッド・セオリー開発の技法と手順(第2版)』医学書院
木下康仁(編著)2005『分野別実践編 グラウンデッド・セオリー・アプローチ』弘文堂
戈木クレイグヒル滋子 2005『質的研究方法ゼミナール―グラウンデッドセオリーアプローチを学ぶ』医学書院
戈木クレイグヒル滋子 2006『グラウンデッド・セオリー・アプローチ』新曜社
木下康仁 2007『ライブ講義M‐GTA実践的質的研究法―修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチのすべて』弘文堂
戈木クレイグヒル滋子 2008『実践 グラウンデッド・セオリー・アプローチ―現象をとらえる』新曜社
戈木クレイグヒル滋子(編) 2008『質的研究方法ゼミナール―グラウンデッドセオリーアプローチを学ぶ』(増補版)医学書院
キャシー・シャーマズ(抱井尚子、末田清子 監訳)2008『グラウンデッド・セオリーの構築―社会構成主義からの挑戦』ナカニシヤ出版
戈木クレイグヒル滋子(編) 2010『グラウンデッド・セオリー・アプローチ 実践ワークブック』日本看護協会出版部
A・ストラウス,J・コービン(操華子, 森岡崇 訳)2012『質的研究の基礎―グラウンデッド・セオリー開発の技法と手順 (第3版)』医学書院
戈木クレイグヒル滋子(編) 2013『質的研究法ゼミナール―グラウンデッド・セオリー・アプローチを学ぶ』(第2版)医学書院
戈木クレイグヒル滋子(編著) 2014『グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いたデータ収集法』新曜社
戈木クレイグヒル滋子(編) 2014『グラウンデッド・セオリー・アプローチ 分析ワークブック(第2版)』日本看護協会出版会
戈木クレイグヒル滋子 2016『グラウンデッド・セオリー・アプローチ―理論を生み出すまで(改訂版)』新曜社
[グラウンデッド・セオリー・アプローチの研究例]
A・ストラウス 他(編)(南裕子 監訳)1987『慢性疾患を生きる:ケアとクォリティー・ライフの接点』医学書院
B・グレイザー、A・ストラウス(木下康仁 訳)1988『死のアウェアネス理論と看護:死の認識と終末期ケア』医学書院
ピエール・ウグ(編)(黒江ゆり子 他訳)1995『慢性疾患の病みの軌跡―コービンとストラウスによる看護モデル』医学書院
三毛美予子 2003 『生活再生に向けての支援と支援インフラ開発―グラウンデッド・セオリー・アプローチに基づく退院援助モデル化の試み』相川書房
[ライフヒストリー/ライフストーリー研究の概説書]
K・プラマー(原田勝弘、川合隆男、下田平裕身 訳)1991『生活記録の社会学:方法としての生活史研究案内』光生館
N・K・デンジン(関西現象学的社会学研究会 編訳)1992『エピファニーの社会学――解釈的相互作用論の核心』マグロウヒル出版
L・L・ラングネス、G・フランク(米山俊直、小林多寿子 訳)1993『ライフヒストリー研究入門:伝記への人類学的アプローチ』ミネルヴァ書房
中野卓、桜井厚(編)1995『ライフヒストリーの社会学』弘文堂
水野節夫 2000 『事例分析への挑戦』 東信堂
桜井厚 2002『インタビューの社会学:ライフストーリーの聞き方』せりか書房
D・ベルトー(小林多寿子 訳)2003『ライフストーリー:エスノ社会学的パースペクティブ』ミネルヴァ書房
桜井厚・小林多寿子 2005『ライフストーリー・インタビュー―質的研究入門』せりか書房
大久保孝治 2009『ライフストーリー分析―質的調査入門』 (早稲田社会学ブックレット―社会調査のリテラシー) 学文社
ロバート・アトキンソン(塚田 守 訳)2006『私たちの中にある物語―人生のストーリーを書く意義と方法』ミネルヴァ書房
小林 多寿子(編著)2010『ライフストーリー・ガイドブック―ひとがひとに会うために』 嵯峨野書院
桜井厚 2012『ライフストーリー論』 (現代社会学ライブラリー7)弘文堂
[オーラル・ヒストリーの概説書]
御厨 貴 2002『オーラル・ヒストリー―現代史のための口述記録』中央公論新社
P・トンプソン(酒井順子 訳)2002『記憶から歴史へ―オーラル・ヒストリーの世界』青木書店
御厨 貴(編)2007『オーラル・ヒストリー入門』岩波書店
[ライフヒストリー/ライフストーリー/オーラル・ヒストリー研究の実例]
石田 忠(編著)1973『反原爆:長崎被爆者の生活史』未来社
中野 卓 1977『口述の生活史:或る女の愛と呪いの日本近代』御茶の水書房
中野 卓 1981, 1982『離島トカラに生きた男』(I、II)御茶の水書房
W・トマス、F・ズナニエツキ(桜井厚 訳)1983『生活史の社会学:ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民』お茶の水書房
V・クラパンザーノ(大塚和夫 他訳)1991『精霊と結婚した男:モロッコ人トゥハーミの肖像』紀伊国屋書店
反差別国際連帯解放研究所しが(編)1995『語りのちから:被差別の生活史から』弘文堂
谷富夫(編)1996『ライフ・ヒストリーを学ぶ人のために』世界思想社
小林多寿子 1997『物語られる「人生」:自分史を書くということ』学陽書房
平松幸三(編)2001『沖縄の反戦ばあちゃん』刀水書房
O・ルイス(高山智博 他 訳)2003『貧困の文化』筑摩書房(ちくま学芸文庫)
桜井厚(編)2003『ライフストーリーとジェンダー』せりか書房
蘭由岐子 2004『「病いの経験」を聞き取る―ハンセン病者のライフヒストリー』皓星社
保苅 実 2004『ラディカル・オーラル・ヒストリー―オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』御茶の水書房
桜井厚 2005『境界文化のライフストーリー』せりか書房
田垣正晋 2007『中途肢体障害者における「障害の意味」の生涯発達的変化―脊髄損傷者が語る
ライフストーリーから』ナカニシヤ出版
小熊英二・姜尚中(編)2008『在日一世の記憶』集英社
[ナラティブ研究の実例]
A・クラインマン(江口重幸、五木田紳、上野豪志 訳)1996『病いの語り:慢性の病いをめぐる臨床人類学』誠信書房
やまだようこ(編)2000『人生を物語る』ミネルヴァ書房
T・グリーンハル、B・ハーウィッツ(編)(斎藤清二他監訳)2001『ナラティブ・ベイスト・メディスン:臨床における物語りと対話』金剛出版
斎藤清二、岸本寛史 2003『ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践』金剛出版
能智正博(編)2006『〈語り〉と出会う―質的研究の新たな展開に向けて』ミネルヴァ書房
江口重幸、斎藤清二・野口直樹(編)2006『ナラティヴと医療』金剛出版
伊藤智樹 2010 『セルフヘルプ・グループの自己物語論: アルコホリズムと死別体験を例に』(質的社会研究シリーズ 2)ハーベスト社
[エスノメソドロジーと会話分析]
H・ガーフィンケル 他(山田富秋 他 訳)1987『エスノメソドロジー:社会学的思考の解体』せりか書房
K・ライター(高山眞知子 訳)1987『エスノメソドロジーとは何か』新曜社
山田富秋、好井裕明 1991『排除と差別のエスノメソドロジー』新曜社
好井裕明(編)1992『エスノメソドロジーの現実』世界思想社
D・サドナウ(岩田啓靖、志村哲郎、山田富秋 訳)1992『病院でつくられる死―「死」と「死につつあること」の社会学』せりか書房
G・サーサス、H・ガーフィンケル、E・シェグロフ 他(北澤裕、西阪仰 訳)1995『日常性の解剖学:知と会話』マルジュ社
A・クロン(山田富秋、水川喜文 訳)1996『入門エスノメソドロジー』せりか書房
山崎敬一・西阪 仰(編)1997『語る身体・見る身体』(〈附論〉ビデオデータの分析法)ハーベスト社
山田富秋、好井裕明(編著)1998『エスノメソドロジーの想像力』せりか書房
好井裕明、山田富秋、西阪仰(編)1999『会話分析への招待』世界思想社
好井裕明 1999『批判的エスノメソドロジーの語り』新曜社
ルーシー A.サッチマン(佐伯 胖 監訳)1999『プランと状況的行為―人間‐機械コミュニケーションの可能性』産業図書
山田富秋 2000『日常性批判』せりか書房
西阪 仰 2001『心と行為:エスノメソドロジーの視点』岩波書店
山崎敬一 2004『実践エスノメソドロジー入門』有斐閣
前田泰樹、水川喜文、岡田光弘(編)2007『エスノメソドロジー―人びとの実践から学ぶ』新曜社
鈴木聡志 2007『会話分析・ディスコース分析―ことばの織りなす世界を読み解く』新曜社
山崎敬一 2010 『美貌の陥穽:セクシュアリティーのエスノメソドロジー』(第2版)(質的社会研究シリーズ 1)ハーベスト社
[談話・ディスコース分析]
茂呂雄二(編)1997『対話と知―談話の認知科学入門』新曜社
M・クールタード(吉村昭市 他 訳)1999『談話分析を学ぶ人のために』世界思想社
窪田光男 2005『第二言語習得とアイデンティティ―社会言語学的適切性のエスノグラフィー的ディスコース分析』ひつじ書房
鈴木聡志 2007『会話分析・ディスコース分析―ことばの織りなす世界を読み解く』新曜社
[グループインタビューの概説書]
高山忠夫、安塩勅江 1998『グループインタビュー法の理論と実際:質的研究による情報把握の方法』川島書店
S・ヴォ―ン、J・S・シューム、J・M・シナグブ (井下 理 監訳)1999『グループインタビューの技法』慶應義塾大学出版会
安梅勅江 2001『ヒューマン・サービスにおけるグループインタビュー法:科学的根拠に基づく質的研究法の展開』医歯薬出版
安梅勅江 2003『ヒューマン・サービスにおけるグループインタビュー法〈2〉活用事例編:科学的根拠に基づく質的研究法の展開』医歯薬出版
[解釈学的現象学の概説書]
Marlene Zichi Cohen, David L. Kahn, Richard H. Steeves(大久保功子 訳)2005『解釈学的現象学による看護研究―インタビュー事例を用いた実践ガイド』(看護における質的研究2)日本看護協会出版会
パトリシア・ベナー(編)(相良-ローゼマイヤーみはる 監訳)2006『ベナー解釈的現象学 健康と病気における 身体的・ケアリング・倫理』医歯薬出版
[アクション・リサーチの概説書]
佐野正之(編著)2000『アクション・リサーチのすすめ―新しい英語授業研究』大修館書店
佐野正之(編著)2005『はじめてのアクション・リサーチ―英語の授業を改善するために』大修館書店
内山研一2007『現場の学としてのアクション・リサーチ―ソフトシステム方法論の日本的再構築』白桃書房
イアン・パーカー(八ッ塚一郎訳)2008『ラディカル質的心理学―アクション・リサーチ入門』ナカニシヤ出版
矢守克也 2010『アクション・リサーチ―実践する人間科学』新曜社
武田丈2015『参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践―社会変革のための研究方法論』世界思想社
[その他の手法]
武田 尚子 2009『質的調査データの2次分析―イギリスの格差拡大プロセスの分析視角』 (質的社会研究シリーズ 3) ハーベスト社
景山佳代子 2010『性・メディア・風俗:週刊誌「アサヒ芸能」からみる風俗としての性』(質的社会研究シリーズ 5)ハーベスト社
アンディ・アラシェフスカ(川浦康至・田中敦 訳)2011『日記とはなにか―質的研究への応用』誠信書房












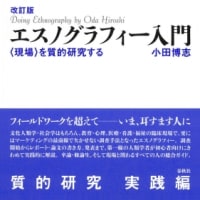








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます