明治22(1889)年8月に紀伊半島を大水害が襲いました。それは奈良県十津川村に壊滅的な被害をもたらし、家屋と土地を失った村民2,489人が故郷を離れ、北海道に入植することになりました。
熊野古道・小辺路を私が2年前に歩いたとき、その歴史を記した説明板に十津川山中でたまたま出くわしました。十津川の被災者はこの険しい山道を数日かけて徒歩で越え、神戸から船で北海道に向かったーーそれを知り、心が揺さぶられました。北海道に着いたのは10月。はじめて過ごす冬は、十津川村民にとって想像を絶するものだったでしょう。
その苦難を乗り越えて現在の新十津川町の発展へとつながる「開拓」の物語は、「母村」と言われる十津川村の歴史民俗資料館でも展示され、また『新十津川物語』という小説とそのTVドラマ化でも知られることになりました。
しかし、ここで気になるのが、入植先にはアイヌ民族がいたのではないか、その人たちはどうなったのか、ということです。
それを知る手がかりとなる石碑が、新十津川町にあると知り、先日、訪れました。
新十津川にさしかかると、稲穂が金に色づく水田の風景が広がっていました。その中心部から国道451号線を10数キロ西に行った「吉野橋」の隣にその石碑はありました。
これは岩見沢の杉山四郎氏を中心とするアイヌ語教室によって、2015年9月23日に建立されたものです。
この石碑がある地点から、ワッカウェンペッという川を遡った山中に、アイヌ・コタンがあったと記しています。もともと石狩川沿いに住んでいたアイヌを、十津川村民の入植のためにこの辺りへ移住させたということのようです。
石碑からコタンがあったされる場所へは、無舗装の山道を通って、かなり奥地に分け入ります。そこはワッカウェンペッ(水の悪い川)という名前が表すように、とてもよい環境とは思えませんでした。
石碑の文面を以下に転載しておきます。
正面
中空知 コタン(集落)跡地入口
右側
ここよりワッカウェンペッ川上流約五キロの地域に、一九〇七・明治四〇年頃から一九七五・昭和五〇年頃までの約七〇年間、コタン(「アイヌ給与地」)が存在した。名取武光氏・平田角平氏らが詳細な記録を残している。
左側
北・中空知に先住していたアイヌ民族は和人の入植により、移住を余儀なくされた。が、その地域にコタンを創り、文化を育み紡ぎ、空知の開拓と文化向上に寄与した。コタンへの入口に「道標」を建て、存在を後世に伝える。
背面
二〇一五(平成二十七)年九月十九日
私塾「アイヌ語教室」(岩見沢市)建立
この石碑建立の経緯については杉山四郎氏が著書『続アイヌモシㇼ・北海道の民衆史』(中西出版、2016年)で述べておられます。
またこのコタンの沿革は『新十津川町史』や『新十津川百年史』に詳しいので、後日改めてここで書きたいと思います。
北海道はどこもそうですが、この新十津川は歴史を複眼でみることが試される場所です。「開拓」史観によって、アイヌの歴史は見えなくされています。それをいかに見えるようにするかが問われています。
このことで個々の十津川からの移民を責める意図はまったくありません。逆に、そのご苦労を思うと、深く畏敬の念を抱きます。
問題はもっと大きな植民地主義という文脈です。自らの苦難の裏に別の苦難があったかもしれない。そう複眼で記憶し、想像できるようになる道はないものでしょうか。
石碑についてご教示いただいた紀國聡さま、そして現地をご案内いただいた石井ポンぺ・エカシに感謝申し上げます。
熊野古道・小辺路を私が2年前に歩いたとき、その歴史を記した説明板に十津川山中でたまたま出くわしました。十津川の被災者はこの険しい山道を数日かけて徒歩で越え、神戸から船で北海道に向かったーーそれを知り、心が揺さぶられました。北海道に着いたのは10月。はじめて過ごす冬は、十津川村民にとって想像を絶するものだったでしょう。
その苦難を乗り越えて現在の新十津川町の発展へとつながる「開拓」の物語は、「母村」と言われる十津川村の歴史民俗資料館でも展示され、また『新十津川物語』という小説とそのTVドラマ化でも知られることになりました。
しかし、ここで気になるのが、入植先にはアイヌ民族がいたのではないか、その人たちはどうなったのか、ということです。
それを知る手がかりとなる石碑が、新十津川町にあると知り、先日、訪れました。
新十津川にさしかかると、稲穂が金に色づく水田の風景が広がっていました。その中心部から国道451号線を10数キロ西に行った「吉野橋」の隣にその石碑はありました。
これは岩見沢の杉山四郎氏を中心とするアイヌ語教室によって、2015年9月23日に建立されたものです。
この石碑がある地点から、ワッカウェンペッという川を遡った山中に、アイヌ・コタンがあったと記しています。もともと石狩川沿いに住んでいたアイヌを、十津川村民の入植のためにこの辺りへ移住させたということのようです。
石碑からコタンがあったされる場所へは、無舗装の山道を通って、かなり奥地に分け入ります。そこはワッカウェンペッ(水の悪い川)という名前が表すように、とてもよい環境とは思えませんでした。
石碑の文面を以下に転載しておきます。
正面
中空知 コタン(集落)跡地入口
右側
ここよりワッカウェンペッ川上流約五キロの地域に、一九〇七・明治四〇年頃から一九七五・昭和五〇年頃までの約七〇年間、コタン(「アイヌ給与地」)が存在した。名取武光氏・平田角平氏らが詳細な記録を残している。
左側
北・中空知に先住していたアイヌ民族は和人の入植により、移住を余儀なくされた。が、その地域にコタンを創り、文化を育み紡ぎ、空知の開拓と文化向上に寄与した。コタンへの入口に「道標」を建て、存在を後世に伝える。
背面
二〇一五(平成二十七)年九月十九日
私塾「アイヌ語教室」(岩見沢市)建立
この石碑建立の経緯については杉山四郎氏が著書『続アイヌモシㇼ・北海道の民衆史』(中西出版、2016年)で述べておられます。
またこのコタンの沿革は『新十津川町史』や『新十津川百年史』に詳しいので、後日改めてここで書きたいと思います。
北海道はどこもそうですが、この新十津川は歴史を複眼でみることが試される場所です。「開拓」史観によって、アイヌの歴史は見えなくされています。それをいかに見えるようにするかが問われています。
このことで個々の十津川からの移民を責める意図はまったくありません。逆に、そのご苦労を思うと、深く畏敬の念を抱きます。
問題はもっと大きな植民地主義という文脈です。自らの苦難の裏に別の苦難があったかもしれない。そう複眼で記憶し、想像できるようになる道はないものでしょうか。
石碑についてご教示いただいた紀國聡さま、そして現地をご案内いただいた石井ポンぺ・エカシに感謝申し上げます。













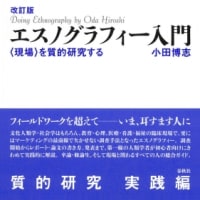








この方達の両親は、内浦ハウサンケとシルケシュマです。
母親の古里であるウラシナイ・コタンに住んだのですが、後に新十津川のウシスベツ給与地に移ります。
この土地は騙し取られてしまうのですが、これなければ、貧困に苦しまないですんだと推定できます。
このことについての詳細なデーターがあります。
また、空知のコタンとその住人についての情報もあります。