著書 小田博志2023『改訂版 エスノグラフィー入門――〈現場〉を質的研究する』春秋社. 山口未花子・ケイトリン・コーカー・小田博志 2023『生きる智慧はフィールドで学んだ:現代人類学入門』ナカニシヤ出版(担当:第9章 生命, pp.135-148,第10章 言葉, pp.151-161, 第11章 平和, 163-177,第12章 エスノグラフィー,pp.179-194)。 小田博志・関雄二(編著)2014『平和の人類学』法律文化社。 波平恵美子、小田博志 2010『質的研究の方法―いのちの〈現場〉を読みとく 』春秋社(2023新装版)。 小田博志 2010『エスノグラフィー入門―〈現場〉を質的研究する 』春秋社。 Oda H 2001 Spontanremissionen bei Krebserkrankungen aus der Sicht des Erlebenden . Beltz. 論文 小田博志2024「大地の存在論:岩田慶治と密教的人類学の展望」『密教文化研究所紀要』37:98-118。 小田博志 2023「根源的自発性の生命論:木村敏と空海との対話から」『高野山大学論叢』58:61-80。 小田博志 2021「いのちの網の目の平和学」『平和研究』56:1-26(DOI:https://doi.org/10.50848/psaj.56002)。 小田博志2021「北海道を脱植民地化する」松本ますみ・清末愛砂(編)『北海道で考える平和:歴史的視点から現代と未来を探る』法律文化社:111-120。 小田博志 2019「トラウマと歓待——ホロコースト生存者の声を聴くことと当事者性」田中雅一・松嶋健 編『トラウマを共有する』(トラウマ研究2)京都大学学術出版会:21-53。 小田博志 2019「ドイツから「移管」されたあるアイヌの遺骨と脱植民地化」松島泰勝・木村朗(編著)『大学による盗骨―研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』耕文社:137-152。 小田博志 2018「骨から人へ:あるアイヌ遺骨のrepatriationと再人間化 」『北方人文研究』11:73-94。 小田博志 2017「記憶の当事者性と植民地主義の忘却 」『立命館言語文化研究』18(3):115-123。 小田博志 2016「生命的自発性と生きた自然の人類学」『臨床精神病理』37(3):191-197。 小田博志 2016「戦後和解と植民地後和解のギャップ―ドイツ‐ナミビア間の遺骨返還を事例に」『平和研究』47(脱植民地化のための平和学):45-65。 小田博志 2016「「窓拭き」と「聴く耳」-「行動・償いの印・平和奉仕」とインフォーマルな和解』石田勇治・福永美和子(編)『現代ドイツへの視座I 想起のグローバル市民社会』勉誠出版:305-336。 H. Oda, 2015, Unearthing the history of minshū in Hokkaido: the case study of the Okhotsk People’s History Workshop. In: P. Seaton (ed.): Local History and War Memories in Hokkaido . Routledge: 129-145. 小田博志 2015「小池喜孝―〈痛み〉からはじまる民衆史運動」テッサ・モーリス=スズキ(編)『ひとびとの精神史 第2巻 朝鮮の戦争―1950年代』岩波書店:313-339。 小田博志、福武慎太郎 2015「巻頭言 <生きる場〉と地域研究からの平和論」『平和研究 第44号 地域・草の根から生まれる平和』:i-xiii。 小田博志 2014「歴史の他者と出会い直す:ナチズム後の「和解」のネットワーク形成」小田博志・関雄二(編著)『平和の人類学』法律文化社:70-91。 小田博志 2014「平和の人類学 序論」小田博志・関雄二(編著)『平和の人類学』法律文化社:1-23。 小田博志 2013「ハンス・パーシェと日本―国境を越えたつながりの物語」日独交流史編集委員会(編)『日独交流150年の軌跡』雄松堂書店:204-209。 29.Oda, H., 2012, Ethnography of Relationships among Church Sanctuary Actors in Germany. In: Randy Lippert and Sean Rehaag (eds.) Sanctuary Practices in International Perspectives: Migration, Citizenship and Social Movements . Routledge: 148-161. 小田博志 2012「足もとからの平和―北海道の「民衆史掘りおこし運動」から学ぶ」越田清和(編)『アイヌモシリと平和―〈北海道〉を平和学する!』法律文化社:73-98。 小田博志 2012「エスノグラフィー教育の現場から 」(連載 質的研究シリーズ)『感性工学』11(1): 29-32。 Oda, H., 2011, Japan und Hans Paasche: Ein pazifistischer Wanderer zwischen den Welten. In: Curt-Engelhorn-Stiftung für die Reiss-Engelhorn-Museen und Verband der Deutsch-Japanischen Gesellschaften (Hrsg.), Ferne Gefährten: 150 Jahre deutsch-japanische Beziehungen . Schnell und Steiner: S. 212-215. 小田博志 2010「よみがえる朝鮮通信使―対馬をめぐる記憶の技法のエスノグラフィー」『エスノグラフィー入門―〈現場〉を質的研究する』春秋社:305-329。 小田博志 2009「エスノグラフィーとナラティヴ」野口裕二(編)『ナラティヴ・アプローチ』勁草書房:27-52。 小田博志 2009「「現場」のエスノグラフィー 」波平恵美子(編)『健康・医療・身体・生殖に関する医療人類学の応用学的研究』(『国立民族学博物館調査報告』85):11-34。 小田博志 2008「難民―現代ドイツの教会アジール」春日直樹(編)『人類学で世界をみる』ミネルヴァ書房:149-168。 小田博志 2007「ナラティヴと現場性」『日本保健医療行動科学会年報』22: 27-37。 Oda, H., 2007 Peacebuilding from Below: Theoretical and Methodological Considerations toward an Anthropological Study on Peace . Journal of the Graduate School of Letters , Hokkaido University . Vol.2: 1-16. 小田博志 2006「ナラティヴの断層について」江口重幸・斎藤清二・野村直樹(編)『ナラティヴと医療 』金剛出版:49-69。 小田博志 2006「Salutogenesisと意味に基づく医療」『全人的医療』7(1): 84-91。 Oda, H., 2006, "Because We Are a Community of Refugees": An Ethnographic Study on Church Asylum in Germany . Journal of the Graduate School of Letters , Hokkaido University . Vol.1: 17-29. 小田博志 2005「スピリチュアリティと健康」『子どもの心とからだ』14(1):25-32。 小田博志 2005「エスノグラフィーの知をめぐって―マリノフスキーと他者性の認識」『こころと文化』4(2):112-117。 小田博志 2004「質的研究とミーニング・ベイスト・メディスン」『心身医学』44(4):257-262。 小田博志 2002「質的研究におけるナラティブ」『看護技術』48(1): 89-94。 Oda H, Scherg H, Verres R, Wilke S, Jonasch K, Egerer G, Karcher A, 2001, Erlebte Genesungsgeschichten: Eine qualitative Studie über Spontanremissionen bei Krebserkrankungen (Recovery stories: a qualitative study on spontaneous remission of cancer). Zeitschrift für Medizinische Psychologie (German Journal of Medical Psychology) 10(1): 33-40. 小田博志 2000「サリュートジェネシス論の概観と展望」河野友信・山岡昌之・石川俊男・一條智康(編)『最新心身医学』三輪書店: 141-146。 小田博志 2000「ストレスとサリュートジェネシス:コヒアレンス感概念を理解する」『ストレス科学』15(1): 89-95。 小田博志 1999「サリュートジェネシスと心身医学」『心身医学』39: 507-513。 小田博志 1999「ドイツ語圏における質的健康研究の現状 」『日本保健医療行動科学会年報』14: 223-239。 小田博志 1999「ストレスと健康生成」現代のエスプリ 別冊 『ストレスの臨床』 39-49。 Oda H, Jonasch K, 1998, Salutogeneseforschung bei unerwarteten Genesungen. In: Heim M, Schwarz R (Hrsg.): Spontanremissionen in der Onkologie . Schattauer Verlag: 145-154. クラウス・ヨナシュ,小田博志,吾郷晋浩 1997「健康とサリュートジェネシス」『現代のエスプリ』361: 69-78。 小田博志 1996「健康生成パースペクティヴ 」『日本保健医療行動科学会年報』11: 261-267。 小田博志,中田光紀,川村則行 1995「自然退縮から学ぶもの」河野博臣(編) 『サイコオンコロジー入門』日本評論社: 105-109。 小田博志 1994「がんの自然退縮」吾郷晋浩(監修)・川村則行(編)『がんは「気持ち」で治るのか!?――精神神経免疫学の挑戦』三一書房: 70-108。 小田博志 1992「癒しの存在論 : 現象学的シャマニズム研究の試み」『年報人間科学』13:113-127。 研究報告書 ジェフ・ゲーマン,小田博志(編)2017,『シンポジウム「アイヌ民族の遺骨返還の意義と研究倫理―心のこもった返還のために」報告書』,北海道大学メディア・コミュニケーション研究院 共同研究助成事業「大学と地域の先住民族・マイノリティの対話と連携に基づいたエンパワーメントに関する研究」(2016年7月14日開催) ジェフ・ゲーマン,小田博志,カイリー・マーティン(編)2014,『国際シンポジウム「多文化共生と大学─対話と連携に基づいた負の遺産の克服へ」報告書』,北海道大学メディア・コミュニケーション研究院 共同研究助成事業(2013年12月14日開催) 小田博志 2012「物語のタペストリー 」村松邦子(編)『共同対人援助モデル研究 5(人間科学と平和教育~体験的心理学を基盤とした歴史・平和教育プログラム開発の視点から) 』立命館大学人間科学研究所:142-147。 小田博志 2011「南京と「和解」―歴史の深遠に橋をかける 」村松邦子(編)『共同体人援助モデル研究 3(歴史のトラウマの世代間連鎖と和解修復の試み:国際セミナー「南京を思い起こす2011の記録) 』立命館大学人間科学研究所:70-85。 小田博志 2011「フォーラムとしての「平和の人類学」―共同研究:平和・紛争・暴力に関する人類学的研究の可能性(2008-2011)」『民博通信』133:18-19。 小田博志 2010「平和の人類学」を実践する―共同研究:平和・紛争・暴力に関する人類学的研究の可能性(2008-2011)」『民博通信』130:26-27。 小田博志 2010「「平和の人類学」を構想する―共同研究:平和・紛争・暴力に関する人類学的研究の可能性」『民博通信』128:18-19。 小田博志 2004「医学・医療系教育におけるエスノグラフィーの知」医療人類学ワーキンググループ編『公益信託澁澤民族学振興基金 民族学振興プロジェクト助成 ワークショップ 医学・医療系教育における医療人類学の可能性』医療人類学ワーキンググループ:73‐76。 小田博志 2001「ドイツにおける難民のメンタル・ヘルスとそのケア」金吉晴編『平成12年度研究報告書 外傷ストレス関連障害の病態と治療ガイドラインに関する研究』国立精神神経センター精神保健研究所: 65-70。 小田博志 2000「サリュートジェネシス・モデルに関するレポート」,長谷川敏彦(編)『平成10年度 健康科学総合研究事業 健康日本21計画の基本概念と推進手段に関する計画』国立医療・病院管理研究所: 45-56。 小田博志 2000「ドイツ語圏における主観的健康観研究に関するレポート」,長谷川敏彦(編)『平成10年度 健康科学総合研究事業 健康日本21計画の基本概念と推進手段に関する計画』国立医療・病院管理研究所: 35-44。 教科書 小田博志 2021「質的研究とエスノグラフィー」波平恵美子(編)『文化人類学』(第4版)医学書院:27-54。 小田博志 2011「文化人類学と質的研究」波平恵美子(編)『文化人類学』(第3版)医学書院:25-49。 辞典・事典項目 小田博志2023「生命と平和」日本平和学会 編『平和学事典』丸善, pp.570-573. 小田博志 2009「難民と庇護」日本文化人類学会(編)『文化人類学事典』丸善:326-327。 小田博志 2005「健康生成」河野友信・石川俊男(編)『ストレスの事典』朝倉書店:231-234。 小田博志 1999「質的データ」日本保健医療行動科学会(監修)『保健医療行動科学事典』メヂカルフレンド社:146-147。 小田博志 1999「参与観察」日本保健医療行動科学会(監修)『保健医療行動科学事典』メヂカルフレンド社:123-124。 書評 小田博志 2017「『質的研究 step by step(第2版)』波平恵美子著: 研究を具体的な生の現場に取り戻そう―質的研究がイメージできる好著 」『週刊医学界新聞』第3250号,医学書院:7。 小田博志 2013「『未開の戦争、現代の戦争』 戦争の人類学から平和の人類学の再創造へ」日本平和学会(編)『平和を考えるための100冊+α』法律文化社:72-73。 翻訳 ウヴェ・フリック(著),小田博志(監訳)、小田博志・山本則子・春日常・宮地尚子(訳) 2011『新版 質的研究入門:〈人間の科学〉のための方法論 』春秋社。(原書:Flick, U., 2007, Qualitative Sozialforschung , Rowohlt./ 2009, Introduction to Qualitative Research (4th edition), Sage.) ウヴェ・フリック(著),小田博志・山本則子・春日常・宮地尚子(訳) 2002『質的研究入門 』春秋社。(原書:Flick U., 1995, Qualitative Forschung , Rowohlt) ロルフ・ヴェレス著, 小田博志・二村‐エッケルト敬子(訳)1999『がんを超えて生きる――生きる意味の再発見 』人文書院。 (原書: Verres R., 1991, Die Kunst zu leben: Krebsrisiko und Psyche . Piper.) コラム〈魚眼図〉 2024/10/29「自発的治癒 」北海道新聞朝刊〈魚眼図〉 2024/4/16「カンタ!ティモール 」北海道新聞朝刊<魚眼図> 2023/9/4「言葉はことのは 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2023/2/14 「大地のケア 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2022/9/9 「水の巡り 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2022/6/28 「高野山大学 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2022/3/15 「殺すなかれ 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2021/12/7 「ニュートンからリンゴへ 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2021/9/13 「スペルト小麦 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2021/6/21 「森の教え 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2021/2/26 「小川隆吉エカシ 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2020/10/30 「オンライン授業の長短 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2020/9/5 「土の時間 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2020/1/23 「「治す」から「治る」へ 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2019/11/20 「アンデスのサルワ村 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2019/7/10 「生きている世界 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2019/4/17 「いのちへの信頼 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2019/2/7 「歓待がつなぐ世界」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2018/11/30 「ラダックで足るを知る」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2018/9/21 「タネを受け継ぐ」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2018/7/5 「学恩」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2018/5/7 「種のいのち」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2017/7/25 「森のイスキア」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2017/5/30 「札幌にコタンがあった」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2016/12/14 「森のような畑」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2016/07/20 「内なる力」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2016/05/12 「ファストファッションの向こうで」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2016/02/03 「ワタが世界を変える」北海道新聞夕刊<魚眼図><道新ぷらす 夕刊な人びと>魚眼図*研究者の知見発信 」北海道新聞朝刊 2015/09/18 「自然に合わせる」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2015/08/28 「久高オデッセイ」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2015/07/31 「積極的平和主義とは」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2015/04/28 「痛みの平和論」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2014/12/18 「水俣の祈りのこけし」北海道新聞<魚眼図> 2014/09/16 「カキは森の恵み」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2014/05/13 「インドネシアの里海」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2014/04/11 「森の水産業」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2014/02/07 「ワタリガラスの神話」北海道新聞<魚眼図> 2014/01/15 「敬意をもって」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/11/27 「ひとつらなりのいのち」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/10/24 「平和は一人から」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/09/24 「中国で信頼を植える」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/08/29 「シリエトクと人間」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/08/13 「未来世代への責任」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/07/30 「“好期”高齢者が活躍する町」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/05/23 「二風谷で木を植える」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/04/24 「ナミビアの夏」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/03/29 「久高島と比嘉康雄 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/02/26 「円空のオリジナリティー」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/02/21 「葉っぱで町おこし」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/02/01 「瀬戸内国際芸術祭」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2013/01/07 「宮古島のドイツ」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/12/10 「戦争を起こすには」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/11/20 「アイヌモシリと平和」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/10/18 「ドクメンタ13」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/09/14 「人権博物館の危機」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/08/24 「ほたるの里」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/07/27 「ウランはどこから」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/06/28 「樹の上のお坊さん」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/05/29 「西行花伝」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/04/25 「歩きたくなる道」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/03/27 「エスノグラフィー」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/03/01 「命こそ宝」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2012/02/01 「西森茂夫さんと草の家」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2011/12/22 「360万年前の足跡」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2011/10/28 「ウガリの味」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2011/10/14 「カシューナッツの木」北海道新聞<魚眼図> 2010/02/15 「ラドヴァンスキーさん」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2010/01/18 「ハンス・パーシェ」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2009/08/11 「伝えるという仕事」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2009/04/21 「釘の十字架」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2008/10/02 「ツィレ美術館」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2008/06/24 「市民がつくる和解と平和」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2007/11/26 「クラとよそ者」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2007/05/01 「民衆の憲法」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/11/29 「麦の穂をゆらす風」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/11/02 「平和を実践し続ける」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/10/23 「ガーダ ―パレスチナの詩―」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/07/26 「北海道から平和をつくる」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/06/19 「テッサさんの講演会」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/05/29 「小さいものの力」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/04/28 「共存の記憶」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/03/08 「白バラの祈り」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/02/24 「他者のための教会」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2006/01/13 「島国日本 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2005/10/28 「パスポート 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2005/08/26 「景観への責任 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2005/08/03 「高野山の明神様 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2005/06/08 「テューテ・ビッテ! 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2005/04/13 「受難曲の季節 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2005/03/09 「バッハをきいて 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2004/12/02 「クリスマス市 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2004/10/18 「一枚の写真から 」北海道新聞夕刊 <魚眼図> 2004/08/06 「和解というテーマ 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2004/07/27 「スロー・サイエンス 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2004/06/25 「イサム・ノグチとその向こう 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2004/04/28 「不思議な場所 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2004/03/22 「平和報道 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2004/01/23 「場所への感性 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2003/09/11 「平和作りの現場で 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2003/07/01 「教会アジール 」北海道新聞夕刊<魚眼図> 2003/03/31 「神田カブール食堂 」北海道新聞夕刊<魚眼図> コラム・エッセイ・その他 小田博志2024「大地の平和 」『生協九条の会北海道 会報』78: 2. 小田博志2023「川の供養に――北海道大学の風景を脱植民地化する」北海道教区宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要委員会 編『北海道 ヤウンモシリ 歴史と今を学ぶ』北海道教区宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要委員会, pp.12-13. 小田博志 (構成:原 健一 )2021「文化人類学の視点からコロナ禍を読み解く~「古くて新しいものの見方から「いのち育む経済」へ~ 」いいね!Hokudai(北海道大学の魅力を発信するウェブマガジン)CoSTEP. 小田博志 2021「北海道を脱植民地化する」松本ますみ・清末愛砂(編)『北海道で考える〈平和〉』法律文化社:。 小田博志 2020「コロナ後の「生類の平和」のために 」平和学会、平和フォーラム「コロナ危機に立ち向かう」。 小田博志 2020「新型コロナウィルス感染症と文化人類学 」北海道大学文化人類学研究室ウェブサイト。 小田博志 2019「研究倫理違反 戒めと学びの場に 」朝日新聞朝刊道内版(2019年12月15日)。 安積遊歩・小田博志(対談)2019「優生思想に傷つけられた心を癒したもの―平和学の視点から」(社会を変える対話―優生思想を遊歩する 第十二回(終))『福祉労働』163:121-128。 小田博志 2019「まえがき」北大ACMプロジェクト(編)『北海道大学もうひとつのキャンパスマップ』寿郎社:8-12。 小田博志 2019「あるアイヌ遺骨のふるさと」北大ACMプロジェクト(編)『北海道大学もうひとつのキャンパスマップ』寿郎社:14-21。 小田博志 2019「古河講堂と足尾銅山鉱毒事件」北大ACMプロジェクト(編)『北海道大学もうひとつのキャンパスマップ』寿郎社:89-95。 小田博志 2018「平和の人類学をめざして 」『知のフロンティア 北海道大学の研究者は、いま』第4号。 小田博志 2017「共謀罪と大学のあり方 」『きぼうの虹』第371号、北海道大学生活協同組合。 小田博志 2017「歴史文化論講座の輝き 」歴史文化論講座ウェブサイト。 小田博志 2017「国民国家を超える歓待の世界」清末愛砂他(編)『緊急事態条項で暮らし・社会はどうなるか』現代人文社:96-99。 小田博志 2016「アイヌ遺骨問題と北海道大学」清末愛砂・松本ますみ編『北海道で生きるということ』法律文化社:84-86。 小田博志 2015「草の根の人々はどのように安全を保障し、平和をつくってきたのでしょうか 」日本平和学会(編)『安全保障100の論点』。 小田博志 2015「大河原孝一さんに捧げる言葉」『中帰連 : 戦争の真実を語り継ぐ』56:36-39。 小田博志 2011「平和の人類学への道」、『北海道民族学』第7号(講演会等報告):93-94。 小田博志 2010「平和の人類学がめざすもの」渡邊直樹(編)『宗教と現代がわかる本2010』平凡社:106-109。 小田博志 2007「他者との関係性への想像力」公共的良識人 第189号: 3。 小田博志 2007「スピリチュアリティの人類学―がんの自然寛解と下からの平和づくり」Mind-Body Science No.17: 2-7。 小田博志 2006「授業アンケートによるエクセレント・ティーチャーズ(平成17年度)・文系部局 」北海道大学。 小田博志,上野圭一(インタビュアー)2004「がんの自然寛解から平和の実践へ―鍵を握るスピリチュアリティの役割」地球人 No.4: 2-25。 小田博志 2004「Asyl(アジール)とヨーロッパ人類学 」ECHO 20、DAAD(ドイツ学術交流会)友の会。 小田博志 2003「生命力のシンボル――ミステル 」カムネット通信第19号:p.1 & 6。 小田博志 2002「平和の種子を育てる 」映画「プロミス」・コメント集、アップリンク、http://www.uplink.co.jp/film/promises/top.html 。 小田博志 2002「[講演録] ナラティブ志向の質的研究―「がんの自然寛解」の研究プロセスを例に」(後編)『Healthかうんせりんぐ』5(5): 93-100。 小田博志 2002「[講演録] ナラティブ志向の質的研究―「がんの自然寛解」の研究プロセスを例に」(前編)『Healthかうんせりんぐ』5(4): 40-48。 小田博志 2000「戦場のフィールドワーク―コソボからの報告」『春秋』415: 14-17。 小田博志 1997「がんの例外的回復が指し示すいのち観」『ホリスティックマガジン』97 : 20-25。 Oda, H., 1996, Wenn man das Leben als Wunder erkennt. Signal 15: 6-8. その他の出版(オンライン含む)による業績 2022/3/24- ウェブサイト「脱植民地化のためのポータル 」の制作監修と公開(コンテンツ:1 ペルー アヤクチョ 武力紛争で奪われた家族の記憶、2 カナダ ユーコン 大学と先住民族との共働=葛西奈津子制作、3 日本 サッポロ アイヌ・コタンのある風景と遺骨の帰還)。 小田博志・笹岡正俊 2017「北海道大学もう一つのキャンパスマップ 」(日本平和学会2017年春季研究大会・連動企画)。 「市民がつくる和解と平和」実行委員会(編)2008『国際シンポジウム 市民がつくる和解と平和 資料集』「市民がつくる和解と平和」実行委員会(編集責任者)。 2007年浅茅野調査チーム(編)2008『2007年浅茅野調査報告書―北海道浅茅野飛行場、朝鮮人強制動員の歴史を掘り起こす』強制連行・強制労働犠牲者を考える北海道フォーラム(編集責任者)。












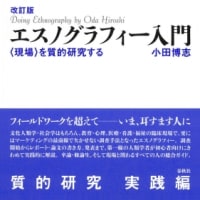








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます