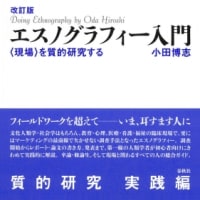コロナ後の「生類の平和」のために
小田博志
「人間はちっとも偉くない。森や川、空や大地の声に耳を傾けよ。その全部に精霊が宿り、沢山の事を教えてくれて、それに従う。人間の都合だけで判断する事は間違っている。お前たちの社会は目先の事しか考えず、目に見えるものしか信じない。森が無くなれば、インディオも死ぬ。でもお前たちも滅びることを忘れてはならない。」(アマゾン・カヤポ民族の長老ラオーニ) 1)
新型コロナウィルス感染症(以下COVID-19と表記)が世界に大きな影響を与えている。この事態は「コロナ危機」とも呼ばれる。しかしそれは何の「危機」なのだろうか?むしろこれまでのようではない「もうひとつのこの世」2) を構想し、生み出していく好機とも言えるのではないだろうか?このパンデミックが私たち平和を探求する者に何を問いかけているのだろうか?ここではこうした問いについて、私がこの2月から3月にかけて、パンデミック状況に巻き込まれながらたどった旅の中で感じ、考えたことに基づいて書いていきたい。
アンデスのサルワ村
今年2月26日に日本を出た私は、カナダを経由してペルーに入った。その当時はむしろ日本の方が危険視されていた。カナダの感染者は少なく、南米にいたっては「ブラジルで南米初の感染者確認」とのニュースが流れた段階で、私の心配事は日本からの入国がカナダの空港で拒否されるかもしれないということだった。
しかしそれは杞憂に終わり、ペルーのリマ空港でも「最近、中国に行きましたか?」と聞かれただけですんなり入国できた。COVID-19はまだどこか他人事の風情だった。
ペルーでの目的の一つは、アンデス山中の村で調査をすることだった。アヤクーチョ県の県都ワマンガから、車で3時間かけて山道を縫うように進み、そのサルワ村に到着する。ここにはケチュア語話者の先住民族が2000人ほど暮らしている。この村の訪問は昨年に続いて二度目だ。ここに来ると、からだの底から安心感と穏やかさを感じる。村の通りをカラフルな民族衣装の人だけでなく、ロバや羊たちが行き交い、その表情はとてもゆったりしている。慎ましい家々が立ち並ぶ村の向こうには、アンデスの斜面を切り開いた段々畑が広がる。パチャママ(大地の神)とアプ(山の神)に祈りを捧げながら、ジャガイモ、トウモロコシ、キヌア、ソラマメ、ムギ類を栽培し、山の向こうの高原で羊、牛などの家畜を飼う。昨年の訪問で聞いたある男性の話。「村のほとんどの若者はいったん都会に出て行く。自分も首都のリマに出て商売をしていた。しかし嫌になって戻ってきた。ここにいると生きていくには困らない。2年分の食料の備蓄はある。」そう言って、納屋にある豊富なジャガイモとトウモロコシの蓄えを見せてくれた。

サルワ村の段々畑(2020年3月5日、小田撮影)
一見、この村は歴史の変化と隔絶しているかに映る。だがそうではない。二度目の訪問でわかったのは、数百年前のインカ帝国の支配、スペイン人の侵略だけでなく、1980年代に極左組織センデロ・ルミノソと国軍との間で勃発した内戦といった歴史の荒波を、この村も受けてきたということだ。最近では若者の都市への流出も多い。これらのことにも関わらず、この村の人たちは、貨幣経済にほとんど頼らない自給自足の暮らしを主体的に選び取り、あの穏やかな雰囲気を保っているのだ。食料のみならず、衣類は羊毛から自分たちで糸を紡いで織り上げ、住居も日干しレンガで建てられる。上述の男性は、今回の訪問でこう語った。「この村まで道路が開通したのは1980年頃だ。その前の方が、もっと豊かだった。反対側の山も全部畑だった。ズボンやベルトなど日用品は自分たちで作っていた。この村で取れない塩、砂糖、灯油のみ、養鶏と牧畜で得た現金で買っていた。」
「途上国」とされるペルーの中でも、先住民族(インディヘナ/カンペシーノ)の住むアンデスの農村は特に「貧しい」と、リマのような都市から蔑視される。しかし、実際に訪れて実感するのはそれとは違っている。ここには確かな安心感がある。それはお金に依存する都市ではついぞ経験したことのない、生活に必要なものは自然の恵みを受けながら、自分たちでまかなえるという安心感である。
グローバル資本主義に急ブレーキをかけたCOVID-19
「次は8月に来ますからね」と約束をして、私は3月12日にリマの空港を出発した。「8月」というのはサルワ村最大の水の祭りがその月にあるからだ。しかしその約束を果たせなくなりそうな事態が、その後急速に進行した。
再度入国したカナダでは、トルドー首相の妻が感染していることが分かってから、対策がぐっと厳しさを増した。そのカナダのユーコン準州で予定していた対面型インタビューはすべてキャンセルされた。そうこうする間にペルーからは、ビスカラ大統領が国家緊急事態宣言を発布して、翌日には国境を封鎖するとの連絡が入った。これにより出国すら許されない外国人旅行者が多くペルーに取り残されることになった。数日の違いで自分もそれに巻き込まれていたかと思うと冷や汗ものだ。追いかけるようにカナダでも自主隔離中のトルドー首相が、外国人の入国禁止をテレビ会見で発表した。うかうかしていると出国も危うくなると感じた私は、予定を早めカナダから脱出した。後ろを振り返ると崩れ落ちていく橋をすれすれで渡りきった、そんな日々だった。
そんな中で感じたことがある。それはCOVID-19がグローバル資本主義に急ブレーキをかけているということ。そして、このパンデミックは人類に対する「スローダウンしなさい、ダウンサイジングしなさい」というメッセージだということだった。飛行機は次々に運休し、工場は稼働を止め、鉱山開発もストップした。その結果、あれほど大気汚染が深刻だった例えばインドのデリーの空気質が「良好」に転じた!フィンランドの研究機関 Centre for Research on Energy and Clean Airは、中国が新型コロナウィルスの感染拡大防止策を取ったことで、同国のCO2排出量が対前年同期比で25%減少したとの分析結果を発表した 3)。
この面だけに注目して、COVID-19を環境問題の救世主のように持ち上げるのはむろん偏っている。この事態によって生命・生活の危機に瀕している人びと――感染し亡くなった方、重篤化し苦しんでいる方、回復したものの社会的スティグマに直面している方、感染対策で切り捨てられているマイノリティ、さらにはロックダウンや休業要請によって経営が立ち行かなくなっている飲食店、小売店、旅行業者、バイトも就活もままならず苦境に陥っている学生たち――こうした一次・二次被害を被っている人びとのことを忘れてはならないし、必要な「経済」対策を講じなければならない。またにわかに国境の壁が立ち上がり、国家による全体主義的な統制とICTを用いた市民の行動管理が浸透して行きつつあることも憂慮される。
それでも、COVID-19を撲滅すべきたんなる「敵」とは私には思えない。コロナ前を思い返してみよう。人類は滅亡のコースを辿っていたのではないか。世界各地が記録的な熱波に襲われ、北極圏はおろか、南極大陸の氷まで溶け出し、シベリア、アラスカ、アマゾン、オーストラリアの森林は大火災に見舞われ、極端なゲリラ豪雨や台風が襲来して土砂災害が頻発していた――異常が常態化していた。このままいくと地球は「臨界点」を超えると気候科学者 4)やグレタ・トゥーンベリさんら活動家が警告を発していた。将来世代に対するジェノサイドと言えるような事態が進行していたのである。それにも関わらず、グローバル気候変動の要因である、温暖化ガス排出と森林破壊を人類は止めようとしなかった。「コロナ危機」以前に、人類はすでに「気候危機」の中にあった。
COVID-19の要因として、コウモリのウィルスがセンザンコウのような他の動物を媒介して人間に移った可能性が指摘されている5) 。だからこれは人獣共通感染症(zoonosis)である。そしてこのような感染症が近年頻繁に発生する背景として森林破壊が挙げられている 6)。森の奥に住んでいたコウモリなど野生動物が、人間の破壊行為によって生息域を失い、家畜や人間と接触するようになった。あるいはウィルスの宿主の野生動物が密輸され、食べられるようになった。そのようにしてウィルスに感染した人間が飛行機によってグローバルに移動し、このパンデミックは発生した。さらに温暖化によって動物の生息域が北上して、熱帯性の感染症の拡大につながっているとの指摘もある 7)。
この病気はグローバリゼーションを背景に発生し、グローバリゼーションを介して拡大し、そしてそのグローバリゼーションを一時的にストップさせている。気候危機とコロナ危機は、グローバル資本主義によってつながっている。グローバル資本主義の中で気候変動と森林破壊が進行し、そのプロセスの果てに発生したのがCOVID-19であった。
だから、マスクも、手洗いも、「ステイホーム」も、都市封鎖(ロックダウン)も、さらにはワクチンでさえも、この病気の「対症療法」に過ぎず、根本的な解決ではない。まず、このパンデミックを発生させた要因である森林破壊とグローバル気候変動をストップすることが求められる。そして、より根本的な解決とは、それらの背景にある経済成長を自己目的化したグローバル資本主義を問い直し、それとは違う世界を構想し、シフトしていくことのはずである。COVID-19によって人類に与えられた、この「隙間」のような時期は、私たちがこれまでのようではない世界を構想し、生み出していく猶予期間とも言えるだろう。
この目に見えないほど小さいウィルスは、人類とその文明に向けられた大きな問いだ。その問いに取り組み、コロナ後の世界を構想することに平和研究者の役割がある。しかしそのためには平和学は自らの枠組みを振り返らなければならないのではないか。私はそう考えている。
生類の平和
COVID-19は「敵」なのだろうか?
それは私たちの外にあって、戦い、撲滅すべき悪なのだろうか。人類は、特に近代になって、「害虫」とみれば殺虫剤(農薬と称する農毒)で殺戮することを企て、雑草を除草剤で駆逐しようとし、体内の「病原菌」を抗生物質で殲滅しようとしてきた。外に「敵」を見出して撃退しようとする、対立的で線形の思考と実践のパターンの結果、環境は汚染され、生物多様性が損なわれ、相手はより強力な耐性をつけ、いたちごっこに陥ってしまっている。生きている自然界はつながり合い、ループを描いている。行為の結果は自身に帰ってくる。そこに「外」はない。COVID-19はその自然の中から現れてきた。
ということは、COVID-19は私たちではないのか? 8)
18世紀の半ばイギリスで始まった産業革命以後、人類は明確に自らを自然から切り離すようになった。行為主体性(エイジェンシー)を人類のみに帰属させて、自然を機械のように表象して所有、収奪、支配の対象としてきた。こうして「自然/文化」の、つまり自然の領域と人間の領域の大分割 9)が近代の「憲法」10) となり、人類中心主義(anthropocentrism)が「文明」の基調となった。ここで現れたのは「人間だけの政治」であり、「人間だけの経済」である。
これは経済人類学者カール・ポランニーが「経済の社会からの離床」11) と呼んだ事態と関りがある。資本主義的な市場経済が自然の循環から遊離し、「経済成長」が自己目的化して追い求められるようになった。客体化された自然から「資源」を収奪し、大量に商品を生産し、自然界へと廃棄し、そうやって自然を破壊すればするほど「経済成長」は進み、GDPは跳ね上がる。これは端的に愚行であり犯罪ですらある。自らとこれからの世代が生きる基盤である自然を汚し、切り崩していっているのだから。
このような近代文明の延長上にグローバル資本主義が現れ、その帰結として人類はCOVID-19に見舞われている。もし人類がこれまでのような自然破壊型の経済活動を続けるならば、仮にCOVID-19が収束したとしても、その後に別種の、ことによるとさらに強力なパンデミックが発生するであろう。だから「コロナとの戦いに打ち勝って、もとの経済活動に戻る」ようなことをしてはいけないのだ。ここで必要なのは近代文明の前提を振り返り、そうではない枠組みの世界を構想することである。
それでは近代文明とは違う枠組みとはどのようなものだろうか?その答えを探るために、何が自然と人間をつなぐのか、という問いを考えてみたい。自然も、人間も、生きている。この生きているということにおいて、自然と人間はつながっている。生きている自然の中で人間も生きている。この「生きている」という根源的な次元が、自然から人間を切り離すことによって見失われ、近代の大前提である「『自然/文化』の大分割」と「人類中心主義」が成立した。近代においては「いのち」の居場所がない。客体化された「自然」から離れれば離れるほど、「近代人(modern people)」はそれを「進んでいる」とみなし、「開発」と「経済成長」を続けてきた。その結果、自然と人間のいのちは破壊され、空疎化されていった。
そのような世界ではない、「もうひとつのこの世」へのシフトは、「生きている」ということ、「いのち」に立ち還ることから始まるだろう。「生きている」というもっともあたりまえでありながら、近代においてもっとも見えなくされている基層につながり直すということである。生きているのは人類だけではない。むしろ人類は生きとし生けるものの、たかだか一員として生きている。そのことを石牟礼道子は「生類」12)という言葉で表現した 。コロナ後の課題は、人類だけではない、「生類の平和」をいかに実現するのかということだ。
ここでいう「生類の平和」とは、だから、人類中心主義的な「自然保護」とか「動物愛護」ということとは根本的に違う。おのずから(自発的に)生成する働き――生命的自発性 13)――の現れとして人間を含めた生類がある。生類たちは互いに関わり合い、循環し合う「いのちの網の目」の中で生きている。むしろ生きている本体は、この「いのちの網の目」だと言える。この網の目を人類(human)が暴力的に切り裂いて、一方的に非人類(non-human)を客体化、所有、支配、収奪することで現在の危機が生じている。「生類の平和」は、人類がみずからを「いのちの網の目」の中に位置づけ直し、生命的自発性を前提とした自然‐社会(nature-society)に立ち戻ることで訪れるだろう。
平和学も、人類の平和だけをみる近代的な人類中心主義のバイアスから、「生類の平和」へと枠組みを広げる必要がある。「将来世代の平和」というときにも、それは人類だけでなく、人類を含めた生類(そこにはコウモリもセンザンコウもシロザケも樹木も微生物も、さらには海も、山も、川も、大気も、土も含まれる)の将来世代へと視野を広げるべきだ。
これを平和学の生命論的転回と呼ぶならば、この視野において平和学は、「自然」の領域と「社会」の領域のハイブリッドに他ならないCOVID-19のような事象と、その後の自然‐社会(nature-society)の構想に、適切に取り組めるようになるだろう。
いのちの網の目を育む暮らしへ
COVID-19の感染対策で持ち上がっているのが、「経済か命か」の二項対立である。感染拡大を防止して、人びとの「命」を守るためには、外出を抑制して休業を要請せざるを得ない。しかしそのために「経済」活動がストップして、窮地に陥る人がいる。そこで現金給付のような経済補償が必要である。もし感染が一定の水準に抑止されたなら、もとの経済活動を再開する――現在のシステムの中で、短期的にはそのように判断せざるを得ないのかもしれない。しかし「もとの経済活動」に戻ることが、グローバル資本主義を再開して、森林破壊とグローバル気候変動に与することなら、私たちはそこからきっぱりと方向転換しなければならない。それは、狭隘な「経済か命か」の二項対立から抜け出して、「いのち育む経済」を取り戻す方向である。コロナ後の世界の基準は、経済成長ではなく、いのちの網の目を育むものかどうかとなるべきである。
「コロナ危機」に伴って「経済危機」が不安視されている。この次には「食糧危機」が起こるだろうと国際機関が警告を発した14) 。そうなれば重工業中心の「経済成長」を追い求めて、食料自給を犠牲にしてきた日本は特に打撃を受けるだろう。食料が入ってこなければ、いくらお金があっても「食っていけない」。これらの危機はすべて、資本主義を前提とした近代的な経済システムの危機である。COVID-19はその特殊なシステムがいかに脆弱なものであるかを明るみに出した。
しかしそのシステムは人類にとって運命でも、必然でもない。その外に経済危機も食糧危機も無関係な世界がある。それを「遅れている」とか「貧しい」と決めつけて、真剣に受け止めようとしなかっただけだ。その例がアンデスのサルワ村だ。いくら物流が止まろうが、他国が食料輸出を制限しようが、水が湧き出、太陽が降り注ぐ限り、この村の人たちは大地からの恵みを受け取って、悠々と生活を続けることができる。それはこの人たちが言葉の真の意味での「生業」、すなわち暮らしに必要な食べもの、衣服、住居を自分たちでまかなう営みを続けているからだ。貨幣経済の尺度から見れば「貧しさ」の極みであるような村の「豊かさ」。ここで、お金が無くても生きていけるという安心感を体感すると、人を大地から切り離し、子どもを学校に通わせることで生業のわざをはく奪し、お金を稼ぎ続けなければ生きていけない不安の状態に置くことが、近代資本主義の原動力であることに気づかされる。そんなシステム社会がいくら「危機」に瀕しても、サルワのような村の暮らしは続いていく。これこそ本当の意味での永続可能(sustainable)な暮らしだ。
近代文明と対峙して、それを根本的に乗り越える世界を構想・実現しようとした人にガンディーがいる 15)。彼はその起点を暮らしに置いた。ローカルで小規模な村を暮らしの単位とし、中央集権的な政府に対して村のスワラジ(自治)を、また機械による大規模な工場生産の代わりに村の中でのスワデシ(自給自足)を重視した。その暮らしの原則はアヒンサ(いのちを損なわないこと)であった。ガンディーはチャルカ(糸紡ぎの車)を、ローカルな土地に根ざした、いのち育む暮らしのシンボルとした。そして、村々はそれぞれ閉鎖的ではなく、ゆるやかにつながるものだった。
今風にいうとそれは小規模分散ネットワーク型の社会である。もしガンディーがアンデスのサルワ村を訪れたなら、ことにそこかしこで羊毛の糸紡ぎをしている村人の姿を見たなら、自らの理想がすでに実現されていることを喜んだに違いない。こうした先住民族が営んできた生業経済、また国家をつくらない社会形成の仕方は、コロナ後の世界を構想する上で、現代的な意義がある。冒頭で引用したアマゾン先住民もまた、せいぜい数百人のコミュニティを暮らしの単位としてきた。後に「北海道」として植民地化されたアイヌモシリに住み習わしてきたアイヌ民族も、小規模のコタンにおいて自治を行い、カムイ(いのち・スピリットある自然)との相互にケアし合う関係性の中で暮らしてきた。ここにはグローバルかナショナルかという対立軸はない。大地と結びついたローカルな暮らしは、一見小規模だが、地球のそして宇宙大の自然の循環へと開かれている。先住民族の視点(indigenous perspective)から学び、自らと世界をいかに脱植民地化し、土地に根ざしたものにする(indigenize)かがこれからの平和学の重要な課題となるだろう。
ガンディーの思想に基づきながら、特に衣の自立をテーマとして、千葉県鴨川で和棉の再生に取り組んだ人に田畑健がいる。田畑がその暮らしから紡ぎ出したことばに耳を傾ければ、ローカルな場でいのちを育む暮らしをすることは、深く平和とつながっていることがわかる。「真に豊かな暮らしとは、誰も搾取されず、誰もが衣食住の心配をせずに安心して暮らせることが前提でなければならないと私は考えます。」16) ここで言われている「安心」はサルワの暮らしと響き合う。誰をも搾取せず、支配せず、また誰からも搾取されず、支配もされない暮らし。田畑は続けて言う。「現在の社会を構成し、支えているのは一人ひとりの日々の生活ではないでしょうか。」17) 何か巨大な代替のシステムを構想し、一挙にそれへと変えようとするのではなく、具体的な暮らしの場をいのち育むものへと徐々に、しかし確実に織り直していくこと。そのようにしてコロナ後の生類の平和、いのちの網の目を育む世界を現わしていくこと。私もそれが望ましいと思う。
生活から離れた平和ではなく、自分の暮らしを現場として、そしてそこから広がっていくつながりが平和なものかどうか。いのちの網の目を育むものかどうか。自分事として、このような平和を実現していくのは、すでに近代社会に組み込まれた、私も含めた多くの平和学会員にとって容易ではないかもしれない。糸紡ぎと言われても、糸紡ぎの車は、私の香川県の祖母の実家の納屋にあると聞いたことがあるだけだ。故郷の田畑は休耕田、耕作放棄地となり、そこにあったローカルなコミュニティの過疎化に一役買いながら、私は札幌という都市で、時おり畑作業をしているとはいえ、賃金に依存して暮らしている。コンクリートとアスファルトで川を圧殺し、大地を窒息させ、アイヌ民族の土地を奪って建てられた、この都市で、大学で。職場では、紛争レアメタルが原料かもしれないタブレット端末を使ってオンライン授業に追い立てられ、温暖化ガスをまき散らす交通手段と電力に依存している。文化人類学者として私は飛行機のヘビーユーザーだった。気をつけてはいても、森林を破壊して生産されたパーム油や大豆を消費しているだろう。またプラスティックごみを否応なく出してしまう。私の暮らしはかくしてグローバル資本主義に組み込まれてしまっている。だからCOVID-19は私(たち)なのだ。
こう振り返ってみると途方に暮れてしまう。この暮らしは250年かけて近代文明に染め上げられてきたのだから、おいそれとは変わらないだろう。しかし地球の年齢(46億年)を尺度にすれば、250年など一瞬よりも短い。だからそれは遅かれ早かれ変わる。それに自分の力だけで「変えよう」とあがくことも、人類中心主義的なのだ。人類が意図して変えられなかったことを、新型コロナウィルスはやすやすと変えたではないか。そしてどれほど強力に映る支配と収奪のシステムも及ばないことがある。それが「生きている」ということだ。それはシステムの以前にあり、根底にあり、これからの世界の起点でもある。いのちは私を含む生類の裡(うち)に、常に脈打っている。自然を深く信頼し、いのちを感じ取って、生きている自然に沿った暮らしへと立ち還ろう。そして自然の働きを人間が尊重し、ケアし、その恵みを分けていただく「仕組み」を手づくりして、結びつけていこう。ほころびかけたいのちの網の目はおのずとつながっていくだろう。
いのちはよみがえる。コンクリートのダムを撤去すれば、水は再び流れ、魚が遡上し始めるように。アスファルトを引きはがせば、大地は息を吹き返し、そこに眠る種子がいっせいに芽吹くように。
初出:日本平和学会 平和フォーラム コロナ危機に立ち向かう 2020年5月25日(3版)
注
1) 南研子『アマゾン、森の精霊からの声』(ほんの木、2006年、63ページ)。
2) 水俣病の患者さんとの関わりの中で石牟礼道子のキーワードとなった言葉。
3) Lauri Myllyvirta, 19 February 2020, “Analysis: Coronavirus temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter”, https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter, 2020年5月5日閲覧。
4)「地球が「臨界点」超える危険性、気候科学者が警鐘」,ナショナルジオグラフィック日本版,2019年11月30日,https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/112900692/, 2020年5月5日閲覧。
5)「新型ウイルス、絶滅危惧の「センザンコウ」も媒介か」,AFPBB News,2020年2月7日,https://www.afpbb.com/articles/-/3267275,2020年5月20日閲覧。
6)「何が森林破壊とCOVID-19をつなぐのか?」,https://onlinefreecourse.com/what-connects-deforestation-and-covid-19/, 2020年5月20日閲覧。
7)「〈新型コロナ〉自然破壊、温暖化もウィルスまん延の一因?地球環境守るための「行動変容」を」、東京新聞、2020年4月9日,https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202004/CK2020040902100020.html,2020年5月20日閲覧。
8) 水俣病患者の緒方正人が『チッソは私であった』(葦書房、2001年)と言ったことを思い起こしつつ。
9) The Great Divide of Nature/Cultureと呼ばれる事態。フィリップ・デスコラ『自然と文化を超えて』(水声社、2020年)を参照。
10) ブルーノ・ラトゥール『虚構の「近代」』(新評論、2008年)。
11) 近代になって「社会」が「自然」から離床したことを鑑みれば、「経済の自然‐社会(nature-society)からの離床」と言うべきだろう。
12) 「生類のみやこはいずくなりや
わが祖は草の親 四季の風を司り 魚の祭を祀りたまえども 生類の邑はすでになし」
(石牟礼道子「幻のえにし」『祖さまの草の邑』思潮社、2014年、5ページ)。
またガンディー『獄中からの手紙』(岩波書店、2010年、83ページ)の訳者・森本達夫は、「生きとし生けるいっさいの生類への献身」という訳語を使っている。
13) 木村敏『あいだ』(筑摩書房、2005年、194ページ)。
14)「国際連合食糧農業機関(FAO)、世界保健機関(WHO)、世界貿易機関(WTO)の事務局長による共同宣言」, https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm, 2020年5月20日閲覧。
15) 1909年に原著が書かれた『真の独立への道』(岩波書店、2001年)は、清冽な脱文明・脱植民地主義論だ。
16) 田畑健『ワタが世界を変える』(地湧社、2015年、83ページ)。
17) 同上。