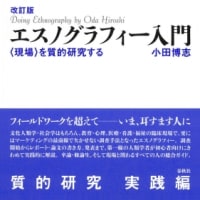生きていると不思議な縁を実感することがある。
例えばハンス・パーシェという人をめぐってそういうことが起こる。
日本で知っている人はまずいないだろう。ヴィルヘルム期ドイツを研究しているとか、ドイツ海軍の歴史が専門だとか、あるいは『ルカンガ・ムカラ』という本をたまたま手に取ったことがあるとか、そんなかなり特殊な関心のある人しかパーシェという名前に出会うことはないはずだ。何しろドイツでもほとんど知られていないのだから。
その人の孫で、カナダのトロントにいるゴットフリート・パーシェという人から、「こんど“パーシェとベルリン”という行事があるよ」と聞いたのは、つい先月のことだった。ではなぜ僕がゴットフリートさんを知っているのかということにも面白い縁があるのだが、それはまた後ほど。
ともかく、パーシェに関心を抱くまれな日本人として僕は、主催者に「できれば参加させてください」とメールを出しておいた。長らく返事がなかったが、4月29日になってメールがあり「明日からやるんだけど、部分的にでも加わってみますか」とあった。
その行事というのは、「ハンス・パーシェの足跡を辿る、ドイツ・ポーランド青少年セミナー」というタイトルで、4月30日から4日かけて開催されるものだった。ドイツからは中部のヴィッツェンハウゼンという町から、そしてポーランドからはKrzyz(いまだに読み方がわからない)という町からおよそ20人の高校生がベルリンで合流して、時間を共にするというのだ。
* * * * *
ハンス・パーシェとは何者か、ここで紹介しておこう。1881年に北ドイツのロストックで生まれた。ドイツ帝国の時代である。父は経済学の教授で、後に帝国議会議員、帝国副大統領を務めることになる国家の中枢に位置する人物だった。ベルリンに家族で転居し、ギムナジウムに入学したハンスだが、「健康上の理由で中退」、海軍幼年学校に編入した。ここからパーシェの軍人としてのキャリアが始まった。
ドイツはその時代、海外に植民地を獲得していった。イギリス、フランスによるアフリカ植民地化競争はすさまじく、ドイツはそこに遅れて参入する形となった。1884年に南西アフリカ(現在のナミビア)、翌年には東アフリカ(現在のタンザニア)を植民地化した。ドイツは現地住民に対して過酷な税や強制労働を課した。そのために反撥の気運が高まっていた。そんな時期に、20代前半の若き海軍軍人パーシェは巡洋艦ブサードに乗って、ドイツ領東アフリカへと送られた。
パーシェが他のドイツ軍人たちと違っていたのは、現地の文化や自然への並外れた好奇心をもっていたことだ。ドイツにいるときから、準備のためとスワヒリ語を勉強していた。当時のドイツ軍人でスワヒリ語を喋ることができたのはパーシェだけだったという。
パーシェが着任した翌年の1905年、現地の人びとはドイツの支配に対して武装蜂起を開始した。これがいわゆる「マジマジ戦争」である。「マジ」とは「水」という意味で、現地のある呪術師が調合した水を体に塗ると、ドイツ軍の弾丸をもはねのけると言ったことから来ている。その効き目は空しく、次に抵抗者たちが取ったのはゲリラ戦だった。これに対してドイツ軍は、ゲリラが潜んでいると思われる地域一帯を焼き払い、住民を殺戮していった。生き残った住民は飢え死にする他なかった。この戦争の被害は壮絶で、ドイツ軍の死者は十数人にすぎなかったが、アフリカ人の死者は少なくとも十数万人にのぼったと言われている。
すでに現地住民を友に持つパーシェは、ドイツ軍人としてこの戦争に巻き込まれていった。そこでパーシェは何を体験したのか。それを後年になって悔恨をもって書き記している。
撃たれたのが友か敵か、はっきりわかるとは限らなかった。実際に、トウモロコシ畑で死んでいく男が私にこう言ったのだ。自分とその近くの死人たちは、敵だと間違われて撃たれたのだ、と。それはひどいことだったし、戦争というものを表わしている。きつい日差しの下、植物の間に横たわる撃ち殺された人間たちのことを、私は決して忘れないだろう。
パーシェはこのときすでに、この戦争の原因がドイツの不当な支配に対する現地の人びとの不満の爆発だということも認識していた。この植民地戦争の体験が、パーシェを平和主義者へと方向転換させることになった。
パーシェは軍隊を離脱し、ドイツに帰国した。そしてエレン・ヴィッティングと出会い結婚した。エレンの父は国立銀行取締役であり、ユダヤ系の出自であった。この出自がパーシェの子どもたちの運命に大きく影響するのは、ナチが政権を握る1930年代のことである。1909年から10年にかけて、パーシェは妻エレンと共に今度は民間人として再びアフリカに渡った。
パーシェはアフリカの視点からドイツを見られる人だった。その思考が結晶したのが、1912年と13年に雑誌『先遣隊』に連載された、『アフリカ人ルカンガ・ムカラのドイツ奥地への調査旅行』である。これはあるアフリカ人がドイツを見て回った感想を、故郷の王様に手紙で伝えるという形式を取った風刺文学である。ワスング(白人の意味)がありがたがる貨幣、衣服、文字、酒、煙草などを、パーシェはアフリカ人の筆を借りて皮肉った。
この『ルカンガ・ムカラ』は1921年に一冊の本として出版された。。
1914年に第一次世界大戦が始まると、パーシェは最初、志願兵として従軍する。ドイツが他国によって脅かされており、そのための防衛戦争だと思ったためらしい。しかし、この戦争がやはり間違いであると悟って1916年に除隊、ドイツ東部(現在ポーランド領)の農園「ヴァルトフリーデ」やベルリンで反戦と政府批判の論文を発表し始める。そのために政治犯として捕らえられる。だがもし大逆罪として告訴されたりすると、帝国副大統領の父の名声に傷がつくという思惑が働き、ベルリンの精神科病棟で拘束されることになった。1918年11月9日、ドイツで反乱を起こした水兵たちの手で、パーシェの身柄が解放された。
それから1月足らずの後、政治活動中のパーシェは、エレンがインフルエンザのためにヴァルトフリーデで急死したという知らせを受け取った。その死を悲しみ、悔いたパーシェは、ヴァルトフリーデにこもって、残された4人の子どもの世話をしながら、以後の活動をそこでの執筆だけに専念することにした。ドイツの戦争と植民地支配を根底的に批判した二つの文書「世界戦争に対する私の共罪」「失われたアフリカ」が書かれたのはこのときのことである。
何者かの密告によって、共産主義者の武器をヴァルトフリーデの農園に隠しもっているという疑いがパーシェにかけられた。これは全くの濡れ衣であった。しかし1920年5月21日、右翼軍人の集団が農園に押し寄せた。パーシェは近くの湖から帰ってきたところを射殺された。39歳であった。