
春の季節になりました。今日は、気温がぐんぐん上がってきました。そして桜の花が満開を迎えています。花見をしたいところですが、そんな時間もありません。年度末って何かと忙しいですよね。滋賀県内を車で移動していると面白いものに出会います。神社にある勧請縄に興味を持つものとしては、わずかな時間があればちょっと寄ってみたくなります。本当は別の神社へ向かっていました。竜王町の曲がりくねった道路を走り、祖父川の橋を渡って降りたカーブで突然目に飛び込んできたのが勧請縄でした。「!」慌ててブレーキを踏んで停車し、目的地を変更してお参りすることにしたのが鵜川天満宮です。こんな風に偶然訪れるのも良いではありませんか。とても立派な勧請縄なので放っとくこともできません。道路から入る参道をふさぐように注連縄が張られ、中央にには木材のトリクグラズがあり、デザインはサークル内にクロス(十字)という最もシンプルなものです。注連縄の左右には6本ずつの小縄が吊り下げられて枯れかかっていますが青葉が取り付けられていました。注連縄の上部には左右6本ずつ白羽の矢のようなものが突き刺さっています。合わせて十二の飾りはどこも同じのようです。大きさもしっかりして勧請縄としては模範的な造りだと思います。しかし、この天満宮、ちょっと寂し過ぎるところです。境内に入ると異様な感じがします。普通の神社とは何かが違います。周囲には寺や神社が密集しているとは言え、殺風景な印象です。鎮守の森がないからでしょうか。土手の横だからでしょうか。社務所と大きめの社があるけれど、拝殿はとても小さなものでした。本殿はなさそうです。天満宮なので菅原道真を祀っているはずです。ちゃんと牛がいました。でも真新しいです。鳥居は最近作ったコンパクトなものですし、拝殿以外は寄せ集めて作ったものであるのは否めません。土手の脇の余った土地であろうというのも透けて見えます。相当古い歴史を持つ、由緒のある天満宮だと思われますが、貧弱なのは残念でした。でも勧請縄を毎年張り替えているのであれば、地元の氏子さん達が大切に扱っているのは間違いないと思われます。それにしても見れば見るほど勧請縄って面白いですね。どうしてこのデザインにしなければならなかったのか誰か教えてください。


























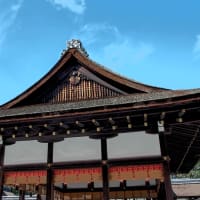






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます