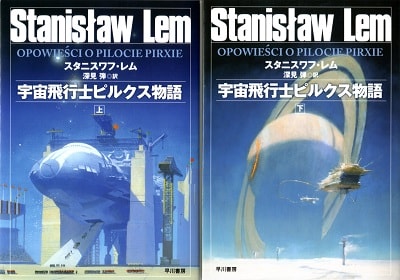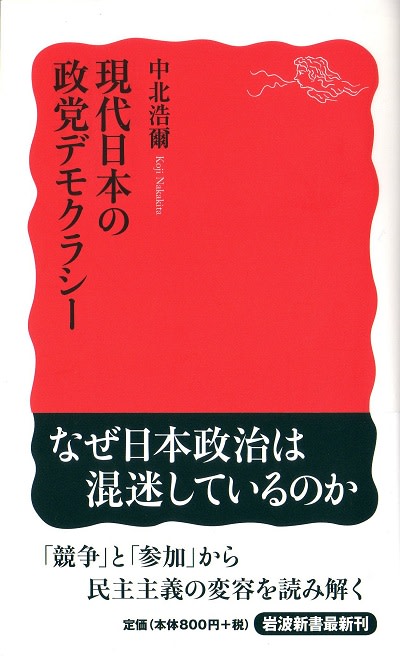新年早々、マルク・ペストラク『ピルクスの審問』(1979年)のDVDを観る。

スタニスワフ・レムの短編連作集『宇宙飛行士ピルクス物語』の1編「審問」の映画化である。
レムの小説を原作とする映画には、アンドレイ・タルコフスキー『惑星ソラリス』、そのリメイク版(観ていない)、インドジヒ・ポラーク『イカリエ号XB1』があるが(他に何かあったっけ)、タルコフスキーの作品はもう別格としても、この映画は決して悪くない。ポーランドとソ連の製作ゆえ、同じ東欧のチェコスロバキア(当時)で製作された『イカリエ号XB1』のショボさを半ば期待して観たのだが、そんなものではない。宇宙船が「ピロ~」などといううら寂しい電子音をたててよろよろ飛ぶことはないし、セットも結構ちゃんと作ってある。
映画は原作にほぼ忠実である。
ピルクスは、ユネスコ(勝手に使っていいのか)に呼び出され、奇妙なミッションを依頼される。いくつもの民間企業が精巧なロボットを作っており、それらが宇宙での仕事に耐えうるのかどうか、試してほしいというものだった。企業はロボット開発で激しく競争しており、そのために、ピルクスは暗殺されそうにさえなる(ここが原作に追加されたエピソード)。但し、クルーの誰がロボットなのか、事前にピルクスには明かされない。ところで、ロボットは「非線形」と呼ばれている(たいへんなユーモアだ)。
さて乗ってみると、何人ものクルーが、私がロボットですが安心です、私は人間ですが誰某はロボットに違いありません、などと三々五々告げにやってくる。そして、カッシーニの輪(土星の環の空隙)に来ると、探査機を打ち出せないトラブルが起きる。実はロボットが予め誤作動を仕組んでおき、ピルクス船長に止めてもらう計画だった。ロボットの有用性が証明されれば、大量生産され、自分たちの価値が貶められてしまうと判断したのだった。しかし、思惑が外れ、ロボットはおかしな行動に出る。
エンタテインメントではあるが、面白いテーマ性も提示しているように思える。
例えば、政府や国連がコントロールできない民間企業の活動(軍事産業など)へのアナロジイ。
あるいは、人間が、感情を共有できるかどうかわからない存在と、如何に共存できるか。未来の人工知能だけでなく、民族、言語、国籍という壁が感情の共有を妨げ、それが為に無数の軋轢が生じている歴史を考えても、これは示唆的であるに違いない。
もし、その共存の相手が、個々人の心の裡にある記憶や感情の残滓(が、可視化された化物)ということになれば、これはもう『惑星ソラリス』である。その点で、この作品はレム的であると納得できた。
ところで、ピルクス船長が、搭乗前にあるクルーに対し、「神を信じるか?」と尋ねる。肯定しなければ宇宙船には乗せないという。これを、カール・セーガンが読んでいて、『コンタクト』の元ネタにしたのではないかという仮説を立ててみるがどうか。
スタニスワフ・レムの原作『宇宙飛行士ピルクス物語』(ハヤカワ文庫、原著1971年)は、大御所の故・深見弾の訳だが、どうもこれが馴染めず・・・。国書刊行会のレムのシリーズに、新訳など入っていないのだろうか。