南城市の(知念村の、と言ったほうが場所がイメージしやすいのだが)、「八風畑」という黒糖工場、兼、カフェで昼食をとった。砂糖きび畑の中にある。砂糖釜は入口付近に見える。黒糖を自由につまむことができるようになっていた。 これで旨くないわけがないのであって、実際にピザもぜんざいも旨かった。
食後、庭から樹々が繁る山の斜面の小道を歩いた。枝葉の間から知念の海が見えた。久高島は隠れていた。庭には山羊がいた。



旅から帰って、本当は旅の前に読もうと思っていた本を読んだ。名嘉正八郎『沖縄・奄美の文献から観た黒砂糖の歴史』(ボーダーインク、2003年)という、黒糖の歴史を追ったものである。
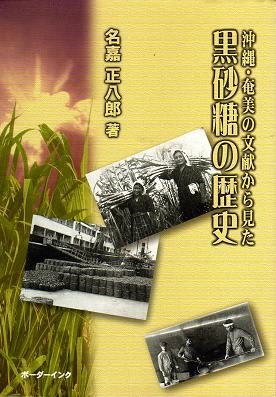
薩摩の琉球侵攻(1609年)後、徳川幕府は鎖国に踏み出した。奄美を割譲され、出米の負担が大きくなった琉球王府は、財政が窮乏し、黒糖の専売制を実施した。つまりこの時期、日本と清国というダブルバインドのことを考えなければならないが、同時に、日本/薩摩藩-琉球王府、琉球王府-琉球農民という2段階のバインドも重要だということだ。農民にとって、「収奪者は琉球王府なのか薩摩藩なのか」という状況であった。
そして、明治維新期における薩摩の財源になったのが、奄美黒糖であり、沖縄産糖であり、密貿易であったのだと指摘されている。
黒糖樽の動きは興味深い。黒糖は中頭、島尻で生産され、樽は国頭から集めていた。国頭村奥間の人の証言によると、自然林に入ってイタジイの木(やんばるの亜熱帯林でもっとも目立つ、ブロッコリー形の木である)を切り倒し、山包丁(山ナタ)、手斧、鉋を順に使って「クリ板」を作る。この頃山原船を持っていた、首里や那覇から都落ちしていた人々が那覇に運んだ。そのような南北の動きがあったという。
明治になってからの黒糖売買に沿ったオカネの流れがいくつか示されている。例えば、鍋島初代県令の時期、黒糖100斤の大阪市場の価格は6.5円。それに対し、農家からの買取価格は当初0.92円、のちに引き上げて3.2円。流通システムが現代よりも単純であったはずだと考えると、それほどマージンは必要ない。運送費を差し引いても県は巨利を得ていたという。ほとんど、現在のコーヒー取引と同様だ。
戦後の黒糖産業の歴史については、断片的な情報があれこれと書かれてはいるものの、整理して体系的にまとめられているとは言い難い。また、単位面積あたりの収量を増加させるための努力が不充分であったとの指摘はいいとしても、自由競争を完全に是とし、自由化もやむを得ないものだったとの論調は、納得できないところだ。ちょっと前、農家の統廃合と大型化に伴う効率化という主張がもてはやされたことがあったが、今では新自由主義に絡めとられたものに見えてならない。










