今日は湯野浜温泉のホテルで、曹洞宗布教師検定があり、検定員の一人を務めてきました。
今年の曹洞宗の教化方針の柱が「利行」になっているので、受験者の法話実演の内容も、ほとんどが利行をテーマとしたものでした。
そして、さらにそのほとんでが大震災のボランティアとの結びつけでした。
ボランティア=利行 と、安易に結びつけてしまうのは問題があると思います。
ボランティアを無理無理日本語に置き換えるとすれば、「利行」と言えるのではないか、とは、私も話してきたことですが、簡単にイコールにしてしまうことには抵抗を感じました。
また、「情けはひとの為ならず」ということわざとは、似ているようで違います。
利行は「利他行」とも言い、他を利する、救う、幸せにする、という意味になりますが、利行の深いところは「利行は一法なり」という教えで、自他ともに幸せになる行い、とでも言うべきでしょうか。
徹底して「利他」の行いは、そのまま「自利」になっている。
「三輪空寂」と言われる、施す側、受ける側、施される物、その三つが執着を離れている、そういう行いのとき、利他は自利になる。
同じように、徹底して「自利」のときは、同時に「利他」になる、という教えなのです。
だから、只管打坐(目的なくただひたすらする坐禅)が「利他行」であるとも言えるでしょう。
だからこそ道元禅師は、
「守るとも 覚えぬながら 小山田の いたづらならん 案山子なりけり」と歌っているのだと受け止めています。
検定員所感を述べるときに、そのことに言葉が及ばず、帰りの車の中で頭に浮かんできたので書いておこうと思った次第です。
















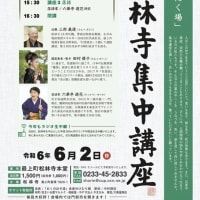



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます