吉本明 ’西行’ 吉本明全著作集7・作家論1 勁草書房
・”西行小論”・「荒地詩集1957」昭和32年(1957)
・”西行論断片”・「帖面・10」昭和36年12月(1961)
ちなみち、’西行’が単行本として出版されるのは、1998年のことである。
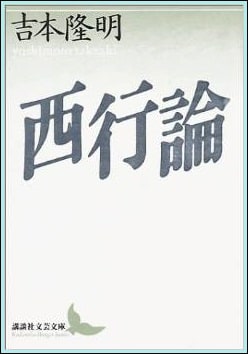
この本の、この頁を開くのは実に48年ぶりになる。
’西行’のことを、吉本がどう捕らえていたか知りたくなった。以前に読んだときの感想は、ほぼ無 いに等しい。というよりも、あの頃は、和歌とか仏教とかにそれほど関心が行かずに、おざなりの読み込みであり、記憶に薄かったのか、あるいは’共同幻想論’に凡庸な頭がついて行かず、ついでに ’西行’も途中で放棄したかのいずれかである。吉本の他書にはある、傍線も書き込みも、この書に はないのである。
改めて、・・・
”西行論断片”
昭和36年頃の吉本と言えば、記憶が正しければ、かなり政治情況に発言をしていたが、私生活にお いては”泥沼”であったように記憶している。つまり、職を失っている時期で、恋愛も三角関係の情況の最中で、精神的にも経済的にも、疲弊しきっていたような状態であった。
この様な状態は、やがて解決していくが、その頃は・「出口の見えない暗闇のトンネル」の真っ直中 であったのだ。
やがて、経済的基盤の方は、完全予約制の”試行”の発行、恩師・遠山啓からの仕事の斡旋で解決し ていき、三角関係は相手方の離婚の了承で解決していく。
詩人で思想家の吉本は、一部に熱狂的支持者がいたとしても、彼の本の出版の環境は芳しいものではなかったことは想像出来る。
”西行小論”
昭和32年の吉本明と、その頃彼の書いた’西行’論は到底無関係には思えない。
昭和36年の吉本明は、泥沼にあった。そして、’西行’を書いた。’西行’を書いて、吉本は泥沼の解決の糸口を見つけようとしたとは思えない。西行の出家とそれに纏わる情況と自分の混沌を重 ね合わせ、おそらく自分の情況を整理したのではないかという伏が見受けられる。げんに吉本は、 現実情況からの脱出を試みてはいないのだ。西行のように、武士社会を”アウトロウ”したとしても 平穏が待ち構えていないことを知性が知っていたかのようである。
西行が生きた時代は、平安末期、保元平治の乱を経て、鎌倉幕府成立と続く時代である。貴族社会の 没落と勃興する武士社会の狭間の中に、北面の武士であった西行は「あさましき」政争を繰り返す貴 族社会と武士社会を嫌って出家したという。
この西行像は、瀬戸内寂聴・”白道”では、史実に忠実に押さえた表現で、西行の人間像を描いてい る。あるいは、西行の出家の原因が”失恋”にある、というのも認識の根底においても、あからさま にしないで、俗世から離れられずに、淡々と描かれている。もう少しあからさまなのが、白洲正子・ ‘西行‘で、吉本明の‘西行’は、白洲や寂聴の二人よりも早い。
○世の中をすててすてえぬここちして都離れぬわが身なりけり
この西行の現実世界への素直な未練は、「未練がありすぎるからかえって厭世的になるという逆説的 な心」に追い詰めていく。
西行は出家僧であり、各地を行脚し、漂泊して山岳に衣を求めるゆえに、歌は自然を扱ったものが多 い。しかし現世への未練が根底に潜むので、叙景の間に潜む叙情は潤いを含むものになる。これが 西行和歌の本随なのだろう。
鳥部野と言う所は京都の葬送の地、それも風葬の地であった。風葬とは、屍を木に吊るし鳥に啄ませる葬送のことで、地名の由来でもある。鳥部野を詠う西行の和歌は意外と多い。
○鳥部野を心の中に分けゆけばいまきの露に袖ぞそぼつる
○亡き後をたれと知らねど鳥部山おのおのすごき塚の夕暮れ
西行の葬送の地・鳥部野は、なにも静かに眠っている祖霊や死霊や昔の亡き人ではないのだ。鳥部野 には、つい先に内乱で命を落とし、山野にゴロゴロと屍をうち捨てられた死人武者や飢餓のため餓死 したりした兵火の犠牲者だったりするのだ。「鳥部野を心の中に分けゆけば」・・・この先の思想の行 く末が、西行の死生観に繋がっていく。このことは、現在の京都の清水寺の後背地の風景から離れて、中世の鳥が・・恐らくカラスであろうが、屍を食む風景に想像を逞しくしなければ、心の中を覗けるわけがないのだろう。
死生観というのは、とりもなおさず、現世の生き方の世界観のこと。
ここで吉本明は、当時を浄土宗の世界観と結びつけていきます。ちょうどその頃、中世思想の体系的な宗 教観がかたまりつつある時期と重なります。「源空が浄土宗を開いたのが安元元年(1175)」でした 。源空から親鸞へ続く浄土宗は、西行の”子供歌”、”恋歌”、”生活歌”の中に「現実上の基盤、思想 上の基盤の骨格を表示し始めす。動乱と厭世と幼児がえりの心を通って、親鸞の逆説的であり、単純 な信仰へと繋がっていきます。
○あそびをせんとやうまれけん
たわぶれせんとやうまれけん
遊ぶ子供の声聞けば
我が身さへこそゆるがるれ
・・・・・梁塵秘抄
○いとほしやさらに心のおさなびてたまきれらるる恋もするかな
○君したふ心のうちは稚児めきて涙もろにもなる我が身かな
上の謡いと和歌を比べると、親鸞より西行の方がはるかに苦くはるかに論理的で、そのくせかなり強靱な思いが醸し出されています。子供歌の範疇を超えています。
○憂かるべきついの思ひを置きながら仮初めの世にまどふ儚さ
○一つ身をあまたの風の吹ききりてほむらになすも悲しかりけり
ここまでくると、出家僧に思えない恋歌です。壮絶な秘匿の恋の雄叫びです。
ここまでくると、平安貴族の流れを踏む藤原定家や同時代の思想家・鴨長明の内面性とかなりかけ離 れた所に、西行は位置してきます。長明の西行に対する評価は知りませんが、定家は西行を高く評価 していたようです。ただ定家の和歌理論の幽玄体や有心体の範囲にはまる西行の歌は乏しく、定家の 歌が時代の流れだとしたら、西行の歌はかなり独立していたのではないでしょうか。
”西行論断片”
定家の歌論の書・「愚祕抄」に”仙洞の歌合わせ”のことが書いてある。
この歌合わせに西行が参加したとき、「西行は、気ままに旅をしているときに優れた歌を作る。それ ならば、座を設けて西行を外へだすな。外へ出すと、いい歌を作られてしまう」。こうして、歌合わ せで作った歌に、西行はいい歌が作れなかった、と言う話である。
これは、当時の西行の周りの人が描く固定観念の西行像である。
これはこれで面白いが、案外西行は遊び事が好きで、ユーモラスな存在であったのだろう。
西行の和歌の本質は、基本が生活の歌であり、それを根っこにした”恋歌”や”情景歌”であった。

寂聴は、西行の出家を”失恋‘と見ています。
○いはれ野の萩がたえまのひまひまに このてがしはの花咲けにけり
野原に一面に萩の花が咲いているが、萩の絶えたところに柏の花がさいている、というなんだか平凡 な歌である。平凡ではあるが、懐かしい気分である。おそらく、旅の見聞を相当積んだ後の、凡庸な 風景がいとほしくなった晩年の作であろう。悟りの境地であったかどうかは、どうでもいいのだ。
さて、吉本明の‘西行’を読んで、西行が解けたのでしょうか。正直よく分かりません。当時泥沼化した経済基盤と三角関係の状況から脱出の糸口は見つけられなかったにしても、文学表現者として 、生活者への視座は、かなり揺るぎないものになっていったという情況だけは、確信して言えると思 います。
白洲正子の視座
白洲正子は、”ねがわくは花の下にて ・・・」の歌の前に、次の二つを配して解説しています。

正子は、西行の漂泊の跡地を自ら辿り、歌と風景から西行の心象に迫ります
○うきよには留めおかじと春風の散らすは花を惜しむなりけり
○諸共にわれをも具して散りね花浮世をいとふ心ある身ぞ
白洲正子には、どうしても、浮き世の未練を引きずった西行であったのでしょう。
こう書いた後、前回に書いた「きさらぎの望月の花は何?」の内容は、あれで良かったのだろうか?
○ ねがはくは花のもとにて春死なむ そのきさらぎの望月の頃 ・・西行
少なくとも、釈迦尊の入滅の時の”涅槃図”に関係する教義的な宗教観とはかけ離れた西行像しか見えてこないのだ。この歌が、確実にある種の宗教観に裏打ちされていることは確かだが、来世への輪廻の思想があるとは到底思えないのだ。あるのは、出家はしたものの、現実世界に未練たっぷりの西行の終焉の姿の、極めて逆説的な美学の世界の、時間軸と空間軸を、あの様に表現しのだと、・・・内面の洞察ですから、これ以上深くは探れません。










