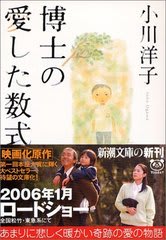本日も、地震のため、午前中から職場で待機しておりましたが、とりたてて緊急の用事が入ることもなく、午後からはわりとゆったり過ごすことができました。
そろそろ、地震の影響もなくなったかな、と油断してみたり。
そんな折、突然、妻から電話が。
すると、ほ乳びんの消毒容器が破損したとのこと。
工エェ工エェ(゜Д゜(゜Д゜)゜Д゜)ェエ工ェエ工
簡単に手に入らない特殊な用品なので、結局、町はずれまで買い出しに行くことになりました。
しかし、素早い連絡が功を奏したのか、特に大きな問題が発生することもなくミッションは終了いたしました。ナイス!妻!
とりあえず、よかったよかった。 ε- (´∇`;)>ホッ
というわけで、昨日読了した2冊をまとめて。
①高橋良斉『「うつ」と上手につきあう心理学』ベスト新書、2002年。
とりたてて特徴はありません。認知療法を中心に、うつ病に関する情報が平易な文章で綴られております。
せっかくなので、認知療法のポイントについて触れられている箇所をちょこっと引用しておきます。
認知療法では、「なぜ、この問題が起こったのか?」ということよりも、「なぜ、この問題が続いているのか?」ということを重視します。(68頁)
なるほど。困難な状況下にあって、アタマを転換することは簡単ではありませんが、こうした表現だとわかりやすいかも知れませんね。
まあ、そういう本でした。
せっかくなんで、個人的に有効だった
「ウツ本」であるクレア・ウイークス(高木信久訳)『不安のメカニズム』(ブルーバックスB237、1974年)を紹介しておきます。
古い本ですが、何年か前の私にとっては、非常に興味深く読むことができました。
比較的手に入りやすい新書なので、なかなかオススメです。
②竹中直人『少々おむづかりのご様子』角川文庫、1996年(単行本は1990年)
俳優や映画監督として有名な竹中さんのエッセイ集です。上記のウツ本同様、古本屋で購入した文庫本。
1992年前後の文章をまとめた本で、彼の映画に関する猛烈な愛情や、独得な感性で書かれた文章を味わえる一冊です。
好きな人は好きでしょうが、そうでない方はそれなりに、というフジカラーの宣伝みたいなことしか記しようがないですね。ていうか、嫌いな人は徹底的に受け付けないでしょう。スミマセン。
まあ、私が紹介しなければ良い話ですが。同じく、別に興味がなければ読まなければいいだけでもありますね。
俳優・竹中直人は、かなり好きなのですが、周防さんが『シコふんじゃった』や『Shall we ダンス?』などで確立した「一途で狂気あふれるオッサン」キャラが、最近、不必要に使われているような気がしてなりません。
他人の才能が無駄に浪費されるのは、見てて気持ちの良いものではないですね。
このままでは、
『欽ちゃんの仮装大賞』における初の不合格者(「松田優作のドラキュラ」)となって以来積み上げてきた、
華麗な芸歴に傷が付いてしまうような気がしてなりません。
なんとかボーイズとか、なんとかガールズとか、なんとかならんか。
ところで、本日は、書籍からの引用部分に「斜体」を使用してみました。
これは普通に「太字」などを使用しているらんくすサンにとっては、苦もない所作でした。
うーむ、徐々に進歩しております。