ここの生活でイラつく習慣のひとつがこれである。冷蔵庫の中の様子。

ハム・ソーセージ、チーズのパッケージを開けると、開いたまま保存するのだ。
しっかり口を止めたり、ラップやビニール袋で包んだりしない。
当然のことながら、空気に触れている部分は乾燥してくる。
が、義父母はもちろん、夫も気にせずその干乾びた固い部分をパンの上などに載せて食べている。
私はその部分は避けて食べているぞ、うふふ。
私は南米での生活経験があるのだが、そこでも同様なことをやっていた。
南米は欧米移住者の生活習慣の影響が大きい土地柄である。当時、欧州を全く知らなかった私も「もしかしたら、これはヨーロッパもやっているかも」予想したものだ。
が、心情的には「冷蔵庫という文明の利器の使い方を知らない『遅れた人々』だ」
と感じてしまったものだ。
日本食文化からか、または気候の違いからか、さらにはラップ製造会社の陰謀からか、
なんでもラップをしないと気がすまないようになっている日本の人々に対して威張ってみよう。
ラップは反エコだぁぁ~!


左は冷蔵庫の外観。上下は戸棚で、冷蔵庫は真ん中だけの小さいものである。
右は最近義母が凝っているヨーグルト。「本物のブルガリアヨーグルト」って書いてあるのだ~
義母が言うには使われている菌が違うそうで、ブルガリアのものは身体にいいとか。
ん?日本にもあるよな~、もっとかっこいいパッケージで!
以下、他のドイツ在住者のブログを真似て、少々クリスマスの状況を報告。
近所の幼稚園のクリスマスの行事。
日没後の午後5時からなんて・・・明るいうちにやってくれないか?って思った私。

なんてったって、こちらの人々は暗がりに目がよく利く。
近所の野原に集合し、真ん中にすえつけられた焚き火の明かりだけが頼り。


ツリーに点灯。生木に本物のろうそくである。野原に火が燃え移る可能性をあまり考えないおおらかな土地柄。


これは野生動物たちへの贈り物らしい。
人間用にしては馬鹿でかいクッキー風のもの。


最後にはニコラウス登場。
このニコラウスの存在は日本には馴染みがないが、要するにクリスマスの前座、と思ってよい(こんなひどい解説のブログは他にないと思う)
甘いお菓子と果物を配っている。昔々の貧しい時代の庶民にはお菓子はなかなか手に入らなかっただろう。
クリスマスくらい、贅沢を、って意味で始まった習慣だろう。
いまとなっては毎週末にこってりしたケーキを食べるここ、果たしてこの程度の贈り物で子供が喜ぶのか不思議である。
いや、なんでもうれしいものだろうな、もらえるものって~
ご安心を、24日には本物のプレゼントが待っている今の子供達!

これは12月になってから義母が備えつけた新しい飾りつけ。
普通はリースのような形状のものにろうそくを立てるのだろうが、
この場所にあわせて買ってきた様子。
ドイツ人、または欧州人のインテリアのセンスはなかなか日本人は追いつくことが難しい。
高価でない安っぽいものも(大体そういうものしかない)、きれいにしてしまうところ、凄い。

一本目のろうそくが点灯された跡がある。
これから日曜になるたびに火が付けられていくらしい。
北ヨーロッパの寒くて暗い時期、特に日が短い冬至に向かっていく陰鬱な日々に、
クリスマスはなくてはならない行事だと思う。

ハム・ソーセージ、チーズのパッケージを開けると、開いたまま保存するのだ。
しっかり口を止めたり、ラップやビニール袋で包んだりしない。
当然のことながら、空気に触れている部分は乾燥してくる。
が、義父母はもちろん、夫も気にせずその干乾びた固い部分をパンの上などに載せて食べている。
私はその部分は避けて食べているぞ、うふふ。
私は南米での生活経験があるのだが、そこでも同様なことをやっていた。
南米は欧米移住者の生活習慣の影響が大きい土地柄である。当時、欧州を全く知らなかった私も「もしかしたら、これはヨーロッパもやっているかも」予想したものだ。
が、心情的には「冷蔵庫という文明の利器の使い方を知らない『遅れた人々』だ」
と感じてしまったものだ。
日本食文化からか、または気候の違いからか、さらにはラップ製造会社の陰謀からか、
なんでもラップをしないと気がすまないようになっている日本の人々に対して威張ってみよう。
ラップは反エコだぁぁ~!


左は冷蔵庫の外観。上下は戸棚で、冷蔵庫は真ん中だけの小さいものである。
右は最近義母が凝っているヨーグルト。「本物のブルガリアヨーグルト」って書いてあるのだ~
義母が言うには使われている菌が違うそうで、ブルガリアのものは身体にいいとか。
ん?日本にもあるよな~、もっとかっこいいパッケージで!
以下、他のドイツ在住者のブログを真似て、少々クリスマスの状況を報告。
近所の幼稚園のクリスマスの行事。
日没後の午後5時からなんて・・・明るいうちにやってくれないか?って思った私。

なんてったって、こちらの人々は暗がりに目がよく利く。
近所の野原に集合し、真ん中にすえつけられた焚き火の明かりだけが頼り。


ツリーに点灯。生木に本物のろうそくである。野原に火が燃え移る可能性をあまり考えないおおらかな土地柄。


これは野生動物たちへの贈り物らしい。
人間用にしては馬鹿でかいクッキー風のもの。


最後にはニコラウス登場。
このニコラウスの存在は日本には馴染みがないが、要するにクリスマスの前座、と思ってよい(こんなひどい解説のブログは他にないと思う)
甘いお菓子と果物を配っている。昔々の貧しい時代の庶民にはお菓子はなかなか手に入らなかっただろう。
クリスマスくらい、贅沢を、って意味で始まった習慣だろう。
いまとなっては毎週末にこってりしたケーキを食べるここ、果たしてこの程度の贈り物で子供が喜ぶのか不思議である。
いや、なんでもうれしいものだろうな、もらえるものって~
ご安心を、24日には本物のプレゼントが待っている今の子供達!

これは12月になってから義母が備えつけた新しい飾りつけ。
普通はリースのような形状のものにろうそくを立てるのだろうが、
この場所にあわせて買ってきた様子。
ドイツ人、または欧州人のインテリアのセンスはなかなか日本人は追いつくことが難しい。
高価でない安っぽいものも(大体そういうものしかない)、きれいにしてしまうところ、凄い。

一本目のろうそくが点灯された跡がある。
これから日曜になるたびに火が付けられていくらしい。
北ヨーロッパの寒くて暗い時期、特に日が短い冬至に向かっていく陰鬱な日々に、
クリスマスはなくてはならない行事だと思う。














 」
」

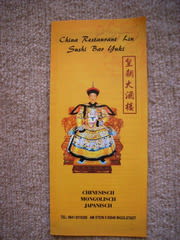











































 をたくさん食べますから」と言って、買ってくれた。
をたくさん食べますから」と言って、買ってくれた。
























































