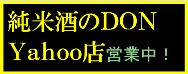熟成古酒こそ燗で呑む「梅津のきもと 純米原酒山田錦8割精米H 28BY」黒糖や栃餅等の含み香(熟成香)をもち、旨味ものってきて奥行きがある。梅津さんの酒らしい太くて旨い酸は、心地良い。28BYの酸もかなり太くてインパクトがある。精米歩合80%だが、荒々しいというよりも、「きもと」の精悍さを感じられてワクワク感がある。余韻には、多分に渋味を感じるので、これからの熟成で、旨味も酸味も、もっとまろや . . . 本文を読む
熟成古酒こそ燗で呑む「睡龍きもと純米H25BY」黒糖・ナッツにも似た熟成の香りが強く、食欲をそそられる。私だけかもしれないが・・(笑) 兎に角、香りはバリバリに熟成感を漂わせている。口に含むと、その香りに違わぬ古酒特有の凝縮感あふれる強い旨味が立体的に現れる。口中で温度が高くなってくると、酸がたち、余韻はスッキリとはねる。透明感のある睡龍の古酒の中で、この古酒は、熟成過程が少し異質に感じる部分 . . . 本文を読む
熟成古酒こそ燗で呑む「奥播磨 白影泉 山廃山田錦純米H30BY」H30BY(平成30酒造年度)の山廃仕込みの熟成古酒「白影泉」。旨味はまだ開ききっておらず、平たいが上品な佇まいだ。太めの鋭角的な酸が存在感を発揮し、爽快にキレる。酸は若いため、まだ角々しさを感じる部分がある。もっと熟成期間が長くなってくると、酸も丸くなり、旨味も開いて、全体のバランスが良くなっていくだろう。まだまだ酒質が変貌しそ . . . 本文を読む
夏の燗酒 第八弾は、にごり酒
「睡龍きもとのどぶR3BY仕込み7号」
奈良の久保本家酒造の加藤杜氏が醸す、この「きもとのどぶ」は、きもと造りを代表する強い酒質の辛口にごり酒だ。
透明な上澄み部分は、まろやかで奥行きある昆布だしのような旨味が前面に出る。のち、酸が立ち、スッキリとしたのどごしだ。なにかリッチな心地になれる酒質だ(笑)
にごり成分(澱)を絡めると、今度は柑橘系の酸が旨味を覆 . . . 本文を読む
夏でも燗酒の贈り物
「奥播磨2酒呑み比べ」
これらの燗酒は究極の食中酒であり、その酒質の対比が大変面白いので、先様にも喜ばれています。
純米スタンダード:地元の酒米の夢錦で醸したスタンダード純米酒。兵庫夢錦への蔵の思い入れが如実に顕れており、夢錦特有のあっさりした旨味とそれを支える酸と渋みのバランスが良い。最初甘さを感じるが、結構太い酸が中心にあるので、徐々に辛口へ導く。色々な温度帯で味の抑揚 . . . 本文を読む
夏の燗酒 「月の井 純米酒」
中心に酸がしっかりと存在し、その周りを旨味がまとう。凄く強さを感じる酒質。まだ旨味の開き方が浅く、酸も角があり、余韻の渋味も強く、熟成感は足りない。でも、これからの熟成でどんどん進化して行く酒質であることを、ひしひしと感じる。熟成過程を愉しみたいなぁ、と思わせる。
燗につけると、旨味と酸の輪郭がクッキリとしてくるが、若い香りも立つ。
原材料: 米・米麹
酒米: . . . 本文を読む
夏の燗酒 第六弾
「さよの煌き蛍星 純米酒」
華やかさはないが、米の旨味に酔いしれる、そんな気取らない滋味深い純米酒なのだ。
当店オリジナル純米酒。
名前の「さよのきらめき」は、「佐用」と「小夜」をかけています。
冷や(常温)では、優しい米の旨味に魅了され、ふんわりと、まろやかな味わいだ。
燗につけると激変!
燗酒特有のツ〜〜ンと来るアルコール臭がほとんど来ず、穏やかでありながら、旨味と甘味がよ . . . 本文を読む
王道の夏の燗酒がこれダァ!
「日置桜 純米酒7号酵母(燗酒専用)」
熟成期間が短い割に米の旨味が優しく、ふくよかだ。淡く洋ナシの様な含み香も上品で、柑橘系の酸もキレる。後半は渋味と若干の苦味が余韻を支配する。これは若さゆえに仕方ない。
燗につけると、旨味の立体感もでて、より膨らみを増し酸と旨味の輪郭がクッキリとして落ち着く。燗冷め燗も良い。
原材料: 米・米麹(鳥取県産
酒米: 玉栄(生産 . . . 本文を読む
朝晩はが寒いくらいになってきて
ようやく「秋らしさ」もかんじられるようになりました
そんな秋の夜長は・・・
「熟成古酒」
の燗酒でほっこり
そこで・・タイプの違う3酒の古酒を紹介します
H28BY(平成28酒造年度)に醸された若い熟成酒!
「奥播磨 白影泉 山廃山田錦純米H28BY」
古酒らしさ満載のH21BYの古酒!
「諏訪泉 純米吟醸 満天星 熟成原酒H . . . 本文を読む
皆さま、今年も大変お世話になりました。
年の瀬も押し詰まってから寒波の襲来・・・
一気に冷え込んで
当店のある兵庫県佐用町の今朝の気温は「―3度」
朝は、うっすらと雪化粧しておりました
お正月も冷え込みが厳しいようです
1月1日のYahooの気象情報の予想最低気温は
「-5度」
冷え込みすぎです(笑)
お正月は、純米燗で心身共に温まり、癒されたい・・・
. . . 本文を読む