
 (年長のAくんの作品)
(年長のAくんの作品)
夕食後、わたしがはまっている韓国ドラマの『ミセン』を見ないか
息子を誘ったら、(娘はすでにいっしょに見たのでわたしは3度目)、
息子は「うん……いいけど……いろいろ済ませてから……。
課題もだけど、ちょっと本も読みたくて」と答えてから、
「ショーペンハイアーの『読書について』がよくってさ、あれを読むうちに、
毎日、ちょっとした時間でも本を読むことにしたんだ」とつけ加えました。
「『読書について』って、そんなによかった?」
「すごくいいよ。読書をしようと思うと、読書する時間が必要だとか、
まとまったページ数を読まなくては……って
構えちゃって、忙しい時期にはつい敬遠しちゃうよね。
でも、『読書のすすめ』じゃ、読書で重要なのはページ数をこなすことじゃなくて、
読書を頭の中で考えるひきがねにすることだって説いててさ。
それで、読書するからにはそれなりに読まないと……っていう縛りをなくしてみると、
本を読むのが前より楽しくなってさ」
このところ息子の趣味は、
読書、プログラミング、数学、ピアノ、電子工作といったものですが、
中高生までは、テレビゲームと漫画が大好きで、
暇さえあればゲームするか古本屋で漫画の立ち読みをするかしていました。
息子いわく、「中学生くらいの時は、(テレビ)ゲームみたいに面白いものはないし、
ゲームさえあれば他に何もいらない……なんて思っていた時期があるのに、
年齢が上がってくると、何に対して面白いって感じるか変わってくるもんだな。
刹那的な楽しさじゃ、満足できなくなってくる。
今、大学の友だちの間で流行っているゲームなんて、全然やりたいとは思わないよ。
ああいうのは、もう十分やったしね。
大学に入ってからは、数学やプログラミングの問題を解いたり、読書したりしている時、
一番、ワクワクするし、心から満足できる」とのこと。
息子 「読書の役割って、知識を増やしていくというより、
むしろ、未確定なまま自分の内外に分散している知識を減らしていくというか、
カオスな現象を収束していくところにあるんだってこの頃よく思うよ。
ニーチェが、人は遠近法で物事を認識しているって言っててさ。
世界は認識されるものだけど、それ自体に意味はないし、別の解釈も可能で、
もともと無数の意味を持っているもんだって。
そう考えると、読書は見る位置と見方をひとつに決めることで、
いったん、見る範囲を狭めることで、
あるテーマについて思考しやすい状態を作ってくれるんだと思う。
そう考えるようになって、本を開いて数行読むか、場合によっては、
タイトルに目を通すだけでも、
そのテーマについて考えていくいいきっかけになるってわかってさ」
わたし 「そうよね。お母さんもこれまで漠然と違和感を覚えながら、
何に対して、どうしてスッキリしない思いを抱いているのか
わからずにいたんだけど、★(息子)のその話を聞きかじっただけで、
自分ともやもやの対象の輪郭がつかめてきたもの。
お母さんは、
子どもに直接、何かの作り方を教えるのは少しの迷いもないのに、
親から、『子どもと工作したいので、○○の作り方を教えてください』と言われると、
相手のニーズにあった答えを伝えられていない気がして、くすぶってたのよ。
ただ何となく違和感があるというだけで、理由ははっきりしなかったし、
深く考えてもみなかった。
というのも、工作については、何をたずねられても、十分把握しているし、
体験もし考えてもきたという思いがあって、情報量って点で心に余裕があったから。
でも、今、気づいたんだけど、違和感の原因は、
わたしの子ども観というか、わたしが知っている幼い子たちの姿にあったのよ。
知識を得るためにカオスな状態から情報を狭めて、収束していこうとする……
子どもって、そういう存在だと思うのよ。
発達に凹凸のある子たちは、その選択の仕方に偏りを感じたり、
そこで無意味に足踏みしているようにも見えるけど、
どの子も、特に幼い子たちは、
知識を確かなものにしようとして、あるひとつの何かにスポットライトを当てるなり
閉じ込められるなりしている。
モンテッソーリは敏感期という言葉を使って、その一部を見えやすいものにしたけど、
その捉えだけでは表現できないものもたくさんあるの。
たいていの人は子どもが今、何にスポットライトを当てているか、
何に閉じ込められているかを気づかないまま、すごく表層的で
自分なりの常識や先入観に染まった考えで対応しようとしているのよね。
子どもが福引でガラガラを回すのを喜んでいたから、親がガラガラの作り方を
調べて、子どもといっしょに作ろうとしても、
大人が思うガラガラの形を再現しても、たいてい子どもの熱心さを引き出せないものよ。
子どもが福引のガラガラに夢中になっていた場合、
ある子はガラガラと内部のものがぶつかりあって
ダイナミックに音を立てる時の手ごたえを楽しんでいて、
ある子はさまざまな色の玉が○等という玉以上の価値を生み出す概念に惹かれているし、
ある子はガラガラの形に、ある子は玉がひとつずつ出てくる仕組みと
その仕組みを作り出す難しさに、ある子は当て物がある空間の活気を味わっているから。
それに、子ども自身が、ある時期は、物を細部にいたるまで観察することが大事で、
ある時期は物をカテゴリーで分けることが、ある時期は理由を推測することが
重要なものよ。
ある時期は物と物のつながりや意味に気づくことが大事だったり、
ある時期は何かを実行する際の手順をイメージすることが大事だったりもする。
子どもの場合、それに収束しているから、大事であることイコール、
他の大事なもろもろを無視したり排除したりすることもよくあるのよ。
子どもといっしょに何かする際は、それを把握しないまま、
ただ子どもに新しい何かをつけ加えようとして関わっても、
大人側の空回りに終わりがちなの。
まぁ、この話は★の言おうとしていたことから、脱線しすぎていて、
単にお母さんの心の中のもやもやが★の言葉をきっかけに少し明るくなったって
ことだけど……
自分が親御さんたちに何を伝えれていなかったのかわかったわ。ありがとう」
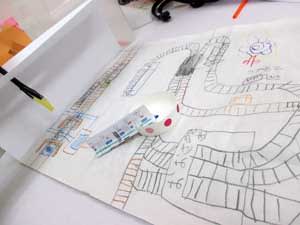






















お久しぶりです。
小学校3年生になった息子はまさにゲームと漫画三昧で、息子さんの記事を読んで男子はこんな感じなのかなと思いました。野球やサッカーのテレビ観戦も忙しく何も教えないのに私よりルールを詳しく知っていて驚きます。
5年生の娘は、幼稚園の頃はとてつもなく育てるのが大変だったのに、少しは感情を爆発させることが少なりました。ただ、自分の信念があり頑固な所は今も変わらずに大変です。基本的に変わらないものですね。
私立の中学受験をしたいと自分から言い出し、どうせ難しいし大量の勉強をしないといけないのですぐやめるだろうと思ってみていますが、今のところ続けています。
そして、最近、娘は旦那によく似ていて、息子は私によく似ていると思うようになりました。それを旦那に話したら同感だそうです。
子供、それぞれにあった育て方が必要だと最近しみじみ思います。