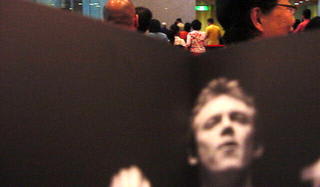東京オペラシティ・3F・C2-15・13,000円・安い
4日間連続演奏の最終日・・私は3度目聴き・・
・ダニエル・ハーディング スウェーデン放送交響楽団のコンビが名演奏を聴かせた
疲れもあったのでしょうが、マーラー1番で本領発揮では、初日とは別人のオケ集団でした
席も3F中央とお値段奮発でしたが、良い演奏で報われた・・笑い・・
マーラー1番で楽器配置が聴き慣れた配列に・・対向配列の左にバス4本、4本2列でバランスが良い・・よこすかでは此処にティンパニで何で・・ハーディングの実験上でした?
帰りに主催者に聞いたところ、都民劇場・初台は同じ配置との事で・・疑問が解けた
音楽の緩急、青春の想い、喜、哀、の音楽表現が明確に創造された演奏では、特に弦群の音色、弾き込みが素晴らしい・・木管の演奏は、最近は特に三角ライン、フルート、オーボエ、クラリネットの歌、演奏技量に耳を澄ます事に興味があります、それに、ファゴット、ホルンの流れが・・・バランスが良かったですね
マーラーの指揮活動・・ドン・ジョヴァンニ、R.シュトラウスと初めて出会う・・当時ワーグーナーの楽劇も指揮したとか・・今日の曲目の流れが、実に上手い・・愛の死で締めくくるとは・・中々考えた曲構成ですね・・ハーディングは35歳にて、良く考え勉強し、あじがある・・
指揮・ダニエル・ハーディング スウェーデン放送交響楽団
曲目・演目:
モーツァルト1756-91:歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲、
R.シュトラウス1864-1949:交響詩「ドン・ファン」op.20・1889
マーラー1860-1911:交響曲 第1番 ニ長調「巨人」・1888年・1896
アンコール 愛の死 (トリスタンとイゾルデ)
終演後、ハーディングのサイン会が長蛇の列でした・・


1885年8月にマーラーは、プラハのドイツ劇場第2指揮者となり、翌1886年8月にはアルトゥール・ニキシュのもとでライプツィヒ市立歌劇場の第2指揮者に就任した。ライプツィヒでは、ウェーバーの未完のオペラ『三人のピント』の補完依頼を受けて1887年にこれを完成。これが縁となって、翌1888年にはウェーバーの孫の夫人マリオン・ウェーバーと恋仲となる。また、
このオペラの上演を機会にリヒャルト・シュトラウスと初めて出会う。詩歌集『子供の不思議な角笛』にも出会い、1888年から作曲を始める。 しかし、ここでもニキシュをはじめとした人間関係が次第に悪化、自身の健康状態も芳しくなく、5月にはライプツィヒを去り、ミュンヘンで手術を受ける。
1888年10月、マーラーはブダペスト王立歌劇場の音楽監督の座につき、ようやく第2指揮者の地位から脱することに成功した。ブダペストでは、『ラインの黄金』、『ワルキューレ』などのワーグナー作品をカットなしでハンガリー初演し、
モーツァルト作品などの上演でも評価を高めた。1890年の『ドン・ジョヴァンニ』では、これを聴いたブラームスを感激させ、「理想的な『ドン・ジョヴァンニ』を聴きたければ、ブダペストに行くべき」とまで言わせている。
こうしたもとで、曲は、ライプツィヒを去る前の1888年3月に書き上げられ、同年ブダペストに移った翌月の11月にオーケストレーションが完成した。マーラーはこの年の6月には後の交響曲第2番となる『葬礼』にもすでに着手していた。
3稿
1896年3月、ベルリンでの演奏に当たって、マーラーは「花の章」を削除して全4楽章の「交響曲」とした。二部構成や各楽章に付けられていた標題もすべて取り払われた。楽器編成は四管に増強され、とくにホルンが4本から7本に増やされたのが特徴的である。
この前年、1895年にはベルリンで交響曲第2番の全楽章が初演された。「交響曲」としての形態では、1番より2番の方が早く初演されたことになる。
このベルリン稿に基づく楽譜は、1899年にヴァインベルガー社より「交響曲第1番」として出版された。その後、1906年にウニフェルザル出版社より出版されたものでは、第1楽章の呈示部と第2楽章にリピートが付加された。その後もマーラーは演奏のたびに細かい修正を加え、最終的にそれらを取り入れたものが、エルヴィン・ラッツ校訂によって1967年に刊行されたマーラー協会の「全集版」(ウニフェルザル出版社)であり、これが現在もっぱら演奏される。しかし、第3稿に限ってもそれまでにも出版された楽譜が複数あるため、実際の演奏では、指揮者のスコアとオーケストラのパート譜が必ずしも同一でないなど一部に混乱があり、第3稿の古い版を用いたと思われる録音も多く存在する。1992年にはカール・ハインツ・フュッスル監修の「新全集版」が出版された。旧全集版との比較では、第3楽章冒頭のコントラバス・ソロがユニゾンに変更されていることが大きな違いとして挙げられる。
楽器編成
フルート 4(3、4番はピッコロに持ち替え)、オーボエ 4(3番はイングリッシュホルン持ち替え)、クラリネット 4(B♭、A、C管/3、4番はE♭管持ち替え、B♭管/3番クラリネットはバスクラリネット持ち替え)、ファゴット 3(3番はコントラファゴット持ち替え)
ホルン 7、トランペット4、トロンボーン 3、バスチューバ 1(ホルンを補強する5番トランペット、4番トロンボーンを加えることがある)
ティンパニ 2人、バスドラム、シンバル、トライアングル、タムタム
ハープ 弦五部(16型)
楽曲構成
第1楽章
Langsam, Schleppend, wie ein Naturlaut - Im Anfang sehr gemächlich ゆるやかに、重々しく ニ長調 4/4拍子 序奏付きのソナタ形式
弦のフラジオレットによるA音の持続のうえに、オーボエとファゴットが4度下降する動機を示す。これは全曲の統一動機であり、カッコウの鳴き声を模したとする解釈もあるが、いずれにせよ、自然を象徴するものと考えられている。遠くからファンファーレや、ホルンの牧歌的な響きが挿入される。低弦に半音階的に順次上行する動機が現れ、4度動機が繰り返されるうちに主部に入り、チェロが第1主題を出す。
第1主題は4度動機で始まり、『さすらう若者の歌』の第2曲「朝の野原を歩けば」に基づく。第2主題はイ長調で木管に出るが第1主題の対位旋律のように扱われるため、あまり明確でない。提示部は反復指定がある。展開部に入ると序奏の雰囲気が戻る。音楽は次第に沈み込むようになるが、やがて、ホルンの斉奏によって明るく解き放たれる。その後、第1主題と第2主題が展開される。やがて半音階的に上昇する動機が不安を高めるように繰り返され、フィナーレを予告する。トランペットのファンファーレが鳴り、再現部となる。型どおりに進み、ティンパニの4度動機の連打で終わる。
演奏時間は15~17分程度。
第2楽章
Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell 力強く運動して イ長調 3/4拍子 複合三部形式
スケルツォ。低弦による4度下降動機のオスティナート・リズム、ヴァイオリンによるオクターヴ上昇する動機の繰り返しにのって、木管が歯切れよくスケルツォ主題を出す。スケルツォ主部はほぼ三部形式をとり、三連符を含む律動的な動機を繰り返して転調していく部分を経てスケルツォ主題が戻る。
中間部はヘ長調。ホルンの4度下降動機に次いで、弦が優美なレントラー風の主題を奏する。演奏時間は7~8分程度。
第3楽章 [
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 緩慢でなく、荘重に威厳をもって ニ短調 4/4拍子 複合三部形式
ティンパニの4度下降の刻みに乗ってコントラバスが物憂く虚ろな印象の主題を奏する。この主題は童謡「フレール・ジャック」として知られるフランスの民謡(オーストリアでは「ブルーダー・マルティン」として、また、一般的に英語名 "Are you sleeping?" でも知られている。日本では「グーチョキパーでなにつくろう」という歌詞が有名である)を短調にしたもので、カノン風に扱われ、オーボエのおどけたような旋律が加わる。主部はほぼ三部形式をとり、哀調を帯びるが俗っぽい進行を経て主題が戻る。
中間部はト長調。ハープに導かれてヴァイオリンが夢見るような表情で奏する。この旋律は『さすらう若人の歌』第4曲「彼女の青い眼が」から採られている。
主部が回帰すると、はじめより自由に進行し、調もテンポも急激に変化する。やがて静まり、ティンパニの4度下降の刻みに収束され、それも消えると、打楽器の暗い響きが残り、フィナーレに休みなくつづく。
演奏時間は10~12分程度。
第4楽章
Stürmisch bewegt 嵐のように運動して ヘ短調 - ニ長調 2/2拍子 ソナタ形式
シンバルの強烈な一撃で開始される。第1主題の断片や半音階的に下降する動機を示して気分を高めたところで導入が終わり、戦闘的な第1主題が管楽器と低弦で提示される。これにはヴァイオリンの激しく上下する音型を伴っている。第1主題は第1楽章の半音階的上昇動機と関連がある。一段落して出る第2主題は変ニ長調、ヴァイオリンによる息の長い美しい旋律。
金管が第1主題の動機を繰り返して再び激しくなるところから展開部。第1主題を扱ううちに高揚して頂点に達し、序奏部が復帰すると再現部となる。
マーラー自身、再現部には相当苦労したようで、ここで終わらせることも考えていたらしいが、当時は交響詩であったにもかかわらずソナタ形式への執着があった模様。ここで第1主題は再現せずに、ハ長調で凱歌をあげようとするが、突如ニ長調に上昇する。ティンパニの連打、トランペットの勝ち誇ったような旋律、ホルンの4度動機と続いていったん静まり、第1楽章の序奏が戻ってくる。第2主題の断片につづいて4度動機や第1楽章の第1主題が示される。その後、第2主題が再現される。これが高まると、ヴィオラが警告的な動機を示し、これが繰り返されるうちにやっと第1主題が再現する。主題の順番を逆にして再現する発想は第6交響曲の終楽章にも現れている。音楽は弱音主体ですすみ、やがて第1楽章のファンファーレが現れ、予告された場面となる。展開部と似たクライマックスが今度はニ長調で頂点に達し、そのままニ長調の長いコーダになだれ込む。ここでマーラーはホルンを起立して吹かせるよう指示している。フィナーレの第1主題と4度動機に基づき、勝利感に満ちた終結となる。
演奏時間は19~22分程度。
「巨人」の標題について
「巨人」という標題は、ジャン・パウルの教養小説からとられている。ジャン・パウルはドイツのロマン派の作家で、ロベルト・シューマンなどドイツ・ロマン派の作曲家にも影響を与えた。1800年から1803年にかけて書かれた『巨人』は、主人公アルバーノが恋愛や多くの人生経験を重ねて、成長していく過程が描かれ、そこには当時ヴァイマール宮廷で活躍したゲーテに代表される文学者や天才主義に対する批判が込められている。
マーラーは、『巨人』のほか、『ジーベンケース』などジャン・パウルの他の著作も愛読しており、自身の生き方とも照らして、パウルの著作と執筆姿勢に共感を抱いていたと考えられる。ただし、マーラーがこの曲に「巨人」の標題を与えたことについては、小説と音楽の関連を意味するというより、もっと私的なものであったと考えられている。なぜなら、マーラーは1896年の友人宛の手紙では、「巨人」の標題は一般の人々に理解しやすくするために付したに過ぎず、これらの標題が適切ではなく、誤解を生む可能性があるので破棄したと認めている。また、同じ手紙で、この曲は恋愛事件が直接の作曲の動機であるとも述べているのである。また、愛弟子のブルーノ・ワルターに、この曲はゲーテ(ジャン・パウルと対立した)の『若きウェルテルの悩み』に共通するものがあるとも語っている。


スウェーデン王女結婚式、3大通信社が報道拒否(読売新聞) - goo ニューススウェーデン政府としては、国家的イベントと国民的人気の高いビクトリア王女の晴れの日に思わぬケチがついた形で、同国外務省筋は「SVTも、もう少し上手に交渉をまとめることができなかったのか。残念なことだ」と話した
4日間連続演奏の最終日・・私は3度目聴き・・
・ダニエル・ハーディング スウェーデン放送交響楽団のコンビが名演奏を聴かせた
疲れもあったのでしょうが、マーラー1番で本領発揮では、初日とは別人のオケ集団でした
席も3F中央とお値段奮発でしたが、良い演奏で報われた・・笑い・・
マーラー1番で楽器配置が聴き慣れた配列に・・対向配列の左にバス4本、4本2列でバランスが良い・・よこすかでは此処にティンパニで何で・・ハーディングの実験上でした?
帰りに主催者に聞いたところ、都民劇場・初台は同じ配置との事で・・疑問が解けた
音楽の緩急、青春の想い、喜、哀、の音楽表現が明確に創造された演奏では、特に弦群の音色、弾き込みが素晴らしい・・木管の演奏は、最近は特に三角ライン、フルート、オーボエ、クラリネットの歌、演奏技量に耳を澄ます事に興味があります、それに、ファゴット、ホルンの流れが・・・バランスが良かったですね
マーラーの指揮活動・・ドン・ジョヴァンニ、R.シュトラウスと初めて出会う・・当時ワーグーナーの楽劇も指揮したとか・・今日の曲目の流れが、実に上手い・・愛の死で締めくくるとは・・中々考えた曲構成ですね・・ハーディングは35歳にて、良く考え勉強し、あじがある・・
指揮・ダニエル・ハーディング スウェーデン放送交響楽団
曲目・演目:
モーツァルト1756-91:歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲、
R.シュトラウス1864-1949:交響詩「ドン・ファン」op.20・1889
マーラー1860-1911:交響曲 第1番 ニ長調「巨人」・1888年・1896
アンコール 愛の死 (トリスタンとイゾルデ)
終演後、ハーディングのサイン会が長蛇の列でした・・


1885年8月にマーラーは、プラハのドイツ劇場第2指揮者となり、翌1886年8月にはアルトゥール・ニキシュのもとでライプツィヒ市立歌劇場の第2指揮者に就任した。ライプツィヒでは、ウェーバーの未完のオペラ『三人のピント』の補完依頼を受けて1887年にこれを完成。これが縁となって、翌1888年にはウェーバーの孫の夫人マリオン・ウェーバーと恋仲となる。また、
このオペラの上演を機会にリヒャルト・シュトラウスと初めて出会う。詩歌集『子供の不思議な角笛』にも出会い、1888年から作曲を始める。 しかし、ここでもニキシュをはじめとした人間関係が次第に悪化、自身の健康状態も芳しくなく、5月にはライプツィヒを去り、ミュンヘンで手術を受ける。
1888年10月、マーラーはブダペスト王立歌劇場の音楽監督の座につき、ようやく第2指揮者の地位から脱することに成功した。ブダペストでは、『ラインの黄金』、『ワルキューレ』などのワーグナー作品をカットなしでハンガリー初演し、
モーツァルト作品などの上演でも評価を高めた。1890年の『ドン・ジョヴァンニ』では、これを聴いたブラームスを感激させ、「理想的な『ドン・ジョヴァンニ』を聴きたければ、ブダペストに行くべき」とまで言わせている。
こうしたもとで、曲は、ライプツィヒを去る前の1888年3月に書き上げられ、同年ブダペストに移った翌月の11月にオーケストレーションが完成した。マーラーはこの年の6月には後の交響曲第2番となる『葬礼』にもすでに着手していた。
3稿
1896年3月、ベルリンでの演奏に当たって、マーラーは「花の章」を削除して全4楽章の「交響曲」とした。二部構成や各楽章に付けられていた標題もすべて取り払われた。楽器編成は四管に増強され、とくにホルンが4本から7本に増やされたのが特徴的である。
この前年、1895年にはベルリンで交響曲第2番の全楽章が初演された。「交響曲」としての形態では、1番より2番の方が早く初演されたことになる。
このベルリン稿に基づく楽譜は、1899年にヴァインベルガー社より「交響曲第1番」として出版された。その後、1906年にウニフェルザル出版社より出版されたものでは、第1楽章の呈示部と第2楽章にリピートが付加された。その後もマーラーは演奏のたびに細かい修正を加え、最終的にそれらを取り入れたものが、エルヴィン・ラッツ校訂によって1967年に刊行されたマーラー協会の「全集版」(ウニフェルザル出版社)であり、これが現在もっぱら演奏される。しかし、第3稿に限ってもそれまでにも出版された楽譜が複数あるため、実際の演奏では、指揮者のスコアとオーケストラのパート譜が必ずしも同一でないなど一部に混乱があり、第3稿の古い版を用いたと思われる録音も多く存在する。1992年にはカール・ハインツ・フュッスル監修の「新全集版」が出版された。旧全集版との比較では、第3楽章冒頭のコントラバス・ソロがユニゾンに変更されていることが大きな違いとして挙げられる。
楽器編成
フルート 4(3、4番はピッコロに持ち替え)、オーボエ 4(3番はイングリッシュホルン持ち替え)、クラリネット 4(B♭、A、C管/3、4番はE♭管持ち替え、B♭管/3番クラリネットはバスクラリネット持ち替え)、ファゴット 3(3番はコントラファゴット持ち替え)
ホルン 7、トランペット4、トロンボーン 3、バスチューバ 1(ホルンを補強する5番トランペット、4番トロンボーンを加えることがある)
ティンパニ 2人、バスドラム、シンバル、トライアングル、タムタム
ハープ 弦五部(16型)
楽曲構成
第1楽章
Langsam, Schleppend, wie ein Naturlaut - Im Anfang sehr gemächlich ゆるやかに、重々しく ニ長調 4/4拍子 序奏付きのソナタ形式
弦のフラジオレットによるA音の持続のうえに、オーボエとファゴットが4度下降する動機を示す。これは全曲の統一動機であり、カッコウの鳴き声を模したとする解釈もあるが、いずれにせよ、自然を象徴するものと考えられている。遠くからファンファーレや、ホルンの牧歌的な響きが挿入される。低弦に半音階的に順次上行する動機が現れ、4度動機が繰り返されるうちに主部に入り、チェロが第1主題を出す。
第1主題は4度動機で始まり、『さすらう若者の歌』の第2曲「朝の野原を歩けば」に基づく。第2主題はイ長調で木管に出るが第1主題の対位旋律のように扱われるため、あまり明確でない。提示部は反復指定がある。展開部に入ると序奏の雰囲気が戻る。音楽は次第に沈み込むようになるが、やがて、ホルンの斉奏によって明るく解き放たれる。その後、第1主題と第2主題が展開される。やがて半音階的に上昇する動機が不安を高めるように繰り返され、フィナーレを予告する。トランペットのファンファーレが鳴り、再現部となる。型どおりに進み、ティンパニの4度動機の連打で終わる。
演奏時間は15~17分程度。
第2楽章
Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell 力強く運動して イ長調 3/4拍子 複合三部形式
スケルツォ。低弦による4度下降動機のオスティナート・リズム、ヴァイオリンによるオクターヴ上昇する動機の繰り返しにのって、木管が歯切れよくスケルツォ主題を出す。スケルツォ主部はほぼ三部形式をとり、三連符を含む律動的な動機を繰り返して転調していく部分を経てスケルツォ主題が戻る。
中間部はヘ長調。ホルンの4度下降動機に次いで、弦が優美なレントラー風の主題を奏する。演奏時間は7~8分程度。
第3楽章 [
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 緩慢でなく、荘重に威厳をもって ニ短調 4/4拍子 複合三部形式
ティンパニの4度下降の刻みに乗ってコントラバスが物憂く虚ろな印象の主題を奏する。この主題は童謡「フレール・ジャック」として知られるフランスの民謡(オーストリアでは「ブルーダー・マルティン」として、また、一般的に英語名 "Are you sleeping?" でも知られている。日本では「グーチョキパーでなにつくろう」という歌詞が有名である)を短調にしたもので、カノン風に扱われ、オーボエのおどけたような旋律が加わる。主部はほぼ三部形式をとり、哀調を帯びるが俗っぽい進行を経て主題が戻る。
中間部はト長調。ハープに導かれてヴァイオリンが夢見るような表情で奏する。この旋律は『さすらう若人の歌』第4曲「彼女の青い眼が」から採られている。
主部が回帰すると、はじめより自由に進行し、調もテンポも急激に変化する。やがて静まり、ティンパニの4度下降の刻みに収束され、それも消えると、打楽器の暗い響きが残り、フィナーレに休みなくつづく。
演奏時間は10~12分程度。
第4楽章
Stürmisch bewegt 嵐のように運動して ヘ短調 - ニ長調 2/2拍子 ソナタ形式
シンバルの強烈な一撃で開始される。第1主題の断片や半音階的に下降する動機を示して気分を高めたところで導入が終わり、戦闘的な第1主題が管楽器と低弦で提示される。これにはヴァイオリンの激しく上下する音型を伴っている。第1主題は第1楽章の半音階的上昇動機と関連がある。一段落して出る第2主題は変ニ長調、ヴァイオリンによる息の長い美しい旋律。
金管が第1主題の動機を繰り返して再び激しくなるところから展開部。第1主題を扱ううちに高揚して頂点に達し、序奏部が復帰すると再現部となる。
マーラー自身、再現部には相当苦労したようで、ここで終わらせることも考えていたらしいが、当時は交響詩であったにもかかわらずソナタ形式への執着があった模様。ここで第1主題は再現せずに、ハ長調で凱歌をあげようとするが、突如ニ長調に上昇する。ティンパニの連打、トランペットの勝ち誇ったような旋律、ホルンの4度動機と続いていったん静まり、第1楽章の序奏が戻ってくる。第2主題の断片につづいて4度動機や第1楽章の第1主題が示される。その後、第2主題が再現される。これが高まると、ヴィオラが警告的な動機を示し、これが繰り返されるうちにやっと第1主題が再現する。主題の順番を逆にして再現する発想は第6交響曲の終楽章にも現れている。音楽は弱音主体ですすみ、やがて第1楽章のファンファーレが現れ、予告された場面となる。展開部と似たクライマックスが今度はニ長調で頂点に達し、そのままニ長調の長いコーダになだれ込む。ここでマーラーはホルンを起立して吹かせるよう指示している。フィナーレの第1主題と4度動機に基づき、勝利感に満ちた終結となる。
演奏時間は19~22分程度。
「巨人」の標題について
「巨人」という標題は、ジャン・パウルの教養小説からとられている。ジャン・パウルはドイツのロマン派の作家で、ロベルト・シューマンなどドイツ・ロマン派の作曲家にも影響を与えた。1800年から1803年にかけて書かれた『巨人』は、主人公アルバーノが恋愛や多くの人生経験を重ねて、成長していく過程が描かれ、そこには当時ヴァイマール宮廷で活躍したゲーテに代表される文学者や天才主義に対する批判が込められている。
マーラーは、『巨人』のほか、『ジーベンケース』などジャン・パウルの他の著作も愛読しており、自身の生き方とも照らして、パウルの著作と執筆姿勢に共感を抱いていたと考えられる。ただし、マーラーがこの曲に「巨人」の標題を与えたことについては、小説と音楽の関連を意味するというより、もっと私的なものであったと考えられている。なぜなら、マーラーは1896年の友人宛の手紙では、「巨人」の標題は一般の人々に理解しやすくするために付したに過ぎず、これらの標題が適切ではなく、誤解を生む可能性があるので破棄したと認めている。また、同じ手紙で、この曲は恋愛事件が直接の作曲の動機であるとも述べているのである。また、愛弟子のブルーノ・ワルターに、この曲はゲーテ(ジャン・パウルと対立した)の『若きウェルテルの悩み』に共通するものがあるとも語っている。


スウェーデン王女結婚式、3大通信社が報道拒否(読売新聞) - goo ニューススウェーデン政府としては、国家的イベントと国民的人気の高いビクトリア王女の晴れの日に思わぬケチがついた形で、同国外務省筋は「SVTも、もう少し上手に交渉をまとめることができなかったのか。残念なことだ」と話した