むかし、ハーグに一週間ほど滞在したことがあった。そのとき、自由時間に同僚たちと、ハーグから8キロほど離れた北海沿いの港町スヘフェニンゲンに繰り出したことがある。公認のカジノの施設もある賑やかな町だが、以前は静かな漁村だったという。この展覧会で、この港町のことが出ていたので懐しく思った。
ハーグ派の画家たちは、海の景色をよく描いたが、このスヘフェニンゲンがもっとも人気があり、多くの作品が誕生した。しかし、当時、静かな漁村をリゾート地化する計画が持ち上がった。もちろん画家たちは猛反対し、デモンストレーションとして、メスダッハを中心に、49日間という短期間に、径14m、総面積1680㎡という世界一の大絵画を完成させた。もちろん、スヘフェニンゲンの海岸の風景画である。それは、現在もハーグにあり、パノラマメスダッハ"Panorama Mesdag"と呼ばれる円形の建物内にあるそうだ。
スヘフェニンゲンは、北杜夫により、”どくとるマンボウ航海記”の中で、スケベニンゲンと改名され(爆)、現在に至っているが、まず、そのスケベニンゲンの風景画から紹介しよう。
メスダッハ ”オランダの海岸沿い” 日没の風景である。

ヤコブ・マリス ”漁船”

オランダといえば、風車と干拓地。ハーグ派の画家もこれらをモチーフにした絵が多い。
ルーロフス ”アブカウデ近く、風車のある干拓地の風景”

ヘラルド・ビルデルス ”干拓地の風景のなかの牡牛

そして、働く人々や日常生活。
トーゼフ・イスラエルス ”縫い物をする若い女”

ブロンメルス ”室内”

アルベルト・ヌウハウス ”母と子供たち”

以上、第二章のハーグ派の作品をまず、紹介したが、展覧会では、ハーグ派の源と言われる、ハルビゾン派の作品が、第1章に並ぶ。お馴染み、コローとミレーの作品も。た、確かにつながっている。
コロー ”浅瀬を渡る山手の番人、イタリアの思い出”
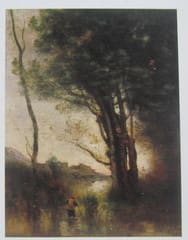
ミレー ”バター造りの女”

そして、第三章では”ハーグ派から出発した画家たち/ゴッホとモンドリアン”。二人ともハーグ派の画家に師事したり、作品を研究したりして、彼らから大きな影響を受けた。その頃の初期の作品が並んでいる。二人とも、その後、大きく変貌する。
ゴッホ ”白い帽子を被った農婦の顔”と”じゃがいもを掘るふたりの農婦”

モンドリアン ”アムステルダムの東、オーストザイゼの風車”と”夕暮れの風車” 雲が印象的。

このように、ハルビゾン派、ハーグ派、そしてゴッホ・モンドリアンへの、繋がりがよくわかる展覧会だった。その上、常設展示室には極上のゴッホ、ルノワール、セザンヌらの作品も観ることができ、まるで天上にいるような、いい気持ちになった。


梅雨の晴れ間になりましたね。今日はこれから太っちょの細君(笑)と観音崎方面へ。











 そのときは、渋谷のデュフィ展も兼ねて!
そのときは、渋谷のデュフィ展も兼ねて!
































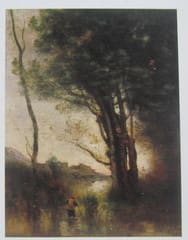

















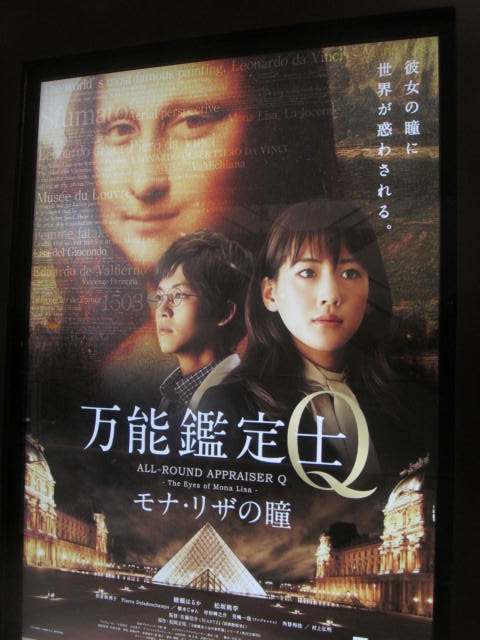



 。
。















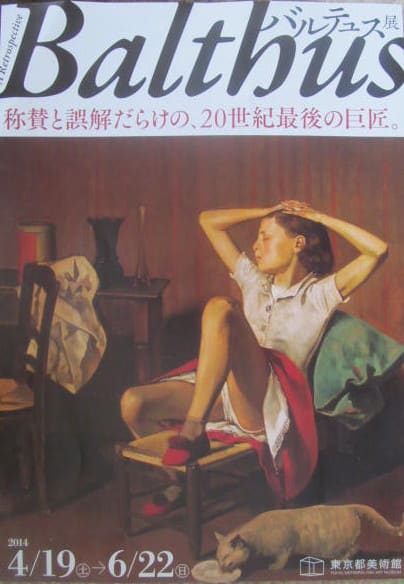
 )
)




















 #花子とアン
#花子とアン

















