
皆さんは、山崎方代さんという歌人をご存知ですか。和歌をたしなむ方の間ではよく知られていると思いますが、私は、2年ほど前に、こちらに越して来るまでは、この歌人について何も知りませんでした。
瑞泉寺の山門の手前の空き地に、松陰・留跡碑や吉野秀雄の歌碑と並んで、方代さんの小さな歌碑が建っています。「手のひらに 豆腐をのせて いそいそと いつもの角を 曲りて帰る」の和歌が刻まれています。この歌碑の存在をはっきり意識するようになったのは、地元出版社の伊藤玄二郎さんの随筆集「風のかたみ」で方代さんのことを知ったときからでした。
伊藤玄二郎さんが方代さんに初めて会ったのは鎌倉八幡宮の段葛の参道でした。どちらもほろ酔い加減で歩いてきて出くわしたようです。ねーこれ食べないか、これもあるんだと、餃子とお酒の四合瓶を出してきました。友達を含め3人で酒盛りが始まったのです。この出会いがきっかけで、伊藤さんは鎌倉山の山裾のようやく一人が寝られるような広さのプレハブの「方代草庵」を尋ねたりして、方代さんのことを次第に知るようになりました。そして、すっかりファンになってしまったようです。
「生まれは 甲斐の国 鶯宿峠(おうしゅくとうげ)に 立っている なんじゃもんじゃの 木の股からですよ」と伊藤さんに和歌で自己紹介したそうです。山梨県右左口村(うばぐちむら)で生まれ、そこで育ちました。故郷を離れてからは、定職にはつかず、生涯独身で、気ままな放浪生活を送りながら、歌をつくり続けます。鎌倉に来てからは、方代草庵に「定住」し、当地にお住まいだった歌人の吉野秀雄さんを師匠として仰ぐようになります。
瑞泉寺とのつながりは、大下豊道和尚との出会いから始まっています。和尚は、ご自分でも和歌をたしなみ、歌人をとても大事にされた方です。方代さんの和歌に「瑞泉寺の 和尚がくれし 小遣いを 確かめおれば 雪が降りける」とありますが、物心両面で支援してもらっていた時期もあったようです。方代さんがこのお寺に親近感があるもうひとつの理由は、開山された夢窓国師が幼少年時代を、自分の故郷、山梨県、右左口村のお寺ですごしたことです。方代さんは歌人でありますが、私が思うに、同時に、ほとんど宗教家ではなかったかと思うのです。毎日の質素な、しかし真善美を追求する生活が、お坊さんの修行となんら変らないと思うからです。それ故、「同郷」の夢窓国師に特別な思いをもっていたに違いないと思うのです。
私はブログを始める前は、結構こまめに日記をつけていました。1年以上も前のことですが、八幡様の第三鳥居(境内前の鳥居のこと)近くの中華料理屋さんで、そこの奥さんから方代さんのことを伺ったことをその日記につづっています。修業時代のご主人は、方代さんより二回りも下の年齢でしたが、とても気があって、自分が独立したときは、方代さんの家も建ててやるよ、と約束したそうです。そして、ご主人は現在の中華料理屋を開店し、鎌倉手広に家も建てます。そして、約束どおり自宅の庭に、前述の方代草庵をつくってあげたのです。
味噌ラーメンを頼んでから、いろいろお話を伺いました。とても人懐っこい人でね、近所の人ともすぐ仲良くなるんですよ。お酒は好きでしたね、朝からコップ酒でしたね、でも人に迷惑をかけるようなことはなかったですよ、度を過ぎるということはなく、ひとりですたすた帰ってしまう、この山梨のお酒、右左口(うばぐち)というのですが、この字は方代さんが書いたものです。私はそのお酒を、コップ酒でいただきました。そしておつまみは餃子にしました。あーあのときの(前述の)餃子と同じものだな、と直感しました。奥の方からご主人がちらりと顔をみせてくれました。とても穏やかな顔つきの方でした。こんないいご夫婦にも支えられ、方代さんは果報者だったなと思いました。
方代さんが昭和60年に、70才で亡くなられたあとも、毎年夏に、瑞泉寺で方代忌が営まれています。
・・・・・
私が好きな方代さんの和歌をいくつかあげておきます。もっと詳しく知りたい方は、青じその花(山崎方代著)かまくら春秋社 をごらんください。
・・・
母の名は 山崎けさのと 申します 日の暮方の 今日のおもいよ
一度だけ 本当の恋がありまして 南天の実が 知っております
こんなにも 湯飲茶碗は あたたかく しどろもどろに 吾はおるなり
こんなところに 釘が一本打たれいて いじればほとりと 落ちてしもうた
死ぬほどの 幸せもなく ひっそりと 障子の穴を つくろっている
寂しくて ひとり笑えば 茶ぶ台の上の 茶碗が 笑いだしたり
茶碗の底に 梅干の種 二つ並びおる ああこれが 愛と云うものだ
広告の ちらしの裏に 書きためし 涙の歌よ わが泪なり
瑞泉寺の山門の手前の空き地に、松陰・留跡碑や吉野秀雄の歌碑と並んで、方代さんの小さな歌碑が建っています。「手のひらに 豆腐をのせて いそいそと いつもの角を 曲りて帰る」の和歌が刻まれています。この歌碑の存在をはっきり意識するようになったのは、地元出版社の伊藤玄二郎さんの随筆集「風のかたみ」で方代さんのことを知ったときからでした。
伊藤玄二郎さんが方代さんに初めて会ったのは鎌倉八幡宮の段葛の参道でした。どちらもほろ酔い加減で歩いてきて出くわしたようです。ねーこれ食べないか、これもあるんだと、餃子とお酒の四合瓶を出してきました。友達を含め3人で酒盛りが始まったのです。この出会いがきっかけで、伊藤さんは鎌倉山の山裾のようやく一人が寝られるような広さのプレハブの「方代草庵」を尋ねたりして、方代さんのことを次第に知るようになりました。そして、すっかりファンになってしまったようです。
「生まれは 甲斐の国 鶯宿峠(おうしゅくとうげ)に 立っている なんじゃもんじゃの 木の股からですよ」と伊藤さんに和歌で自己紹介したそうです。山梨県右左口村(うばぐちむら)で生まれ、そこで育ちました。故郷を離れてからは、定職にはつかず、生涯独身で、気ままな放浪生活を送りながら、歌をつくり続けます。鎌倉に来てからは、方代草庵に「定住」し、当地にお住まいだった歌人の吉野秀雄さんを師匠として仰ぐようになります。
瑞泉寺とのつながりは、大下豊道和尚との出会いから始まっています。和尚は、ご自分でも和歌をたしなみ、歌人をとても大事にされた方です。方代さんの和歌に「瑞泉寺の 和尚がくれし 小遣いを 確かめおれば 雪が降りける」とありますが、物心両面で支援してもらっていた時期もあったようです。方代さんがこのお寺に親近感があるもうひとつの理由は、開山された夢窓国師が幼少年時代を、自分の故郷、山梨県、右左口村のお寺ですごしたことです。方代さんは歌人でありますが、私が思うに、同時に、ほとんど宗教家ではなかったかと思うのです。毎日の質素な、しかし真善美を追求する生活が、お坊さんの修行となんら変らないと思うからです。それ故、「同郷」の夢窓国師に特別な思いをもっていたに違いないと思うのです。
私はブログを始める前は、結構こまめに日記をつけていました。1年以上も前のことですが、八幡様の第三鳥居(境内前の鳥居のこと)近くの中華料理屋さんで、そこの奥さんから方代さんのことを伺ったことをその日記につづっています。修業時代のご主人は、方代さんより二回りも下の年齢でしたが、とても気があって、自分が独立したときは、方代さんの家も建ててやるよ、と約束したそうです。そして、ご主人は現在の中華料理屋を開店し、鎌倉手広に家も建てます。そして、約束どおり自宅の庭に、前述の方代草庵をつくってあげたのです。
味噌ラーメンを頼んでから、いろいろお話を伺いました。とても人懐っこい人でね、近所の人ともすぐ仲良くなるんですよ。お酒は好きでしたね、朝からコップ酒でしたね、でも人に迷惑をかけるようなことはなかったですよ、度を過ぎるということはなく、ひとりですたすた帰ってしまう、この山梨のお酒、右左口(うばぐち)というのですが、この字は方代さんが書いたものです。私はそのお酒を、コップ酒でいただきました。そしておつまみは餃子にしました。あーあのときの(前述の)餃子と同じものだな、と直感しました。奥の方からご主人がちらりと顔をみせてくれました。とても穏やかな顔つきの方でした。こんないいご夫婦にも支えられ、方代さんは果報者だったなと思いました。
方代さんが昭和60年に、70才で亡くなられたあとも、毎年夏に、瑞泉寺で方代忌が営まれています。
・・・・・
私が好きな方代さんの和歌をいくつかあげておきます。もっと詳しく知りたい方は、青じその花(山崎方代著)かまくら春秋社 をごらんください。
・・・
母の名は 山崎けさのと 申します 日の暮方の 今日のおもいよ
一度だけ 本当の恋がありまして 南天の実が 知っております
こんなにも 湯飲茶碗は あたたかく しどろもどろに 吾はおるなり
こんなところに 釘が一本打たれいて いじればほとりと 落ちてしもうた
死ぬほどの 幸せもなく ひっそりと 障子の穴を つくろっている
寂しくて ひとり笑えば 茶ぶ台の上の 茶碗が 笑いだしたり
茶碗の底に 梅干の種 二つ並びおる ああこれが 愛と云うものだ
広告の ちらしの裏に 書きためし 涙の歌よ わが泪なり



















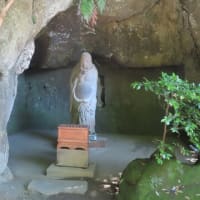




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます