おはようございます。
鏑木清方は画才だけではなく文才もあり、たくさんの随筆を残している。とくに、清方の自伝的随筆集、”こしかたの記”(中央公論美術出版)がよく知られている。その刊行60年記念 として特別展、”清方が愛した江戸、東京。人、暮らし。”が、鏑木清方記念美術館で開催されている。
本展では、江戸の名残をとどめる明治時代の東京の風景とそこで暮らす人々を描いた作品を、『こしかたの記』の文章とともに紹介している。
まず、明治20年頃の東京下町の人々の暮らしを描いた《朝夕安居》。ぼくは、清方の作品の中では、美人画では”築地明石町”、風俗画ではこの”朝夕安居”が一番好き。久しぶりに朝、昼、夕の全公開します。
朝、その1。新聞配達をする少年。道を掃き清める奉公の娘さん。煮豆屋の車を呼び止めるおかみさん。
朝、その2。家の裏では井戸端会議の真っ最中。水桶を運ぶお姉さん。朝顔、物干し。
昼。百日紅の木陰で一服する風鈴屋さん。ちりんちりんと涼やかな音が聞こえてきそう
夕方、その1。娘さんが行水で汗を流している。手前の女性はランプの掃除をしているのだろうか。

夕方、その2。むぎゆ(麦茶のこと)、さくらゆを楽しむ人々。夏の夕方、涼み台を並べ、むぎゆやさくらゆを売るお店がかってあったようだ。

つづいて美人が登場する日々の暮らしの風景。
白梅かをる 昭和7年(1932)個人蔵 まるで築地明石町の美人が現れたよう。春まだ浅い頃、火鉢にあたる女性の指先や頬、耳がほんのり上気している。塗机の表面は黒々と磨きがかかる。白梅の花器がほんのり写っている。この机は清方が愛用していたもの。

美術館の中に清方の画室が保存されていて、そこにこの塗机がある。

五十鈴川 昭和18年頃 (当館蔵)伊勢神宮内苑

ぼくの五十鈴川・御手洗場(みたらしば)2016年11月

春の流れ 昭和34年頃 個人蔵

洛外の春 室町時代の京都の正月風景。扇の太夫と鼓の才三で各戸を巡る。

ちらしの表紙になった。小園夏趣(平塚美術館蔵)手ぬぐいを口に加え、くつろいだ胸元。紫陽花が咲く初夏の風景。


ほかにも、こしかたの記の文章も寄せて、水汲、曲亭馬琴、新大橋之景、大蘇芳年など。こしかたの記の表紙原画、自筆原稿”水汲”なども。
大蘇芳年 月岡芳年のことで、清方のお師匠さんのお師匠さん。寄席で三遊亭園朝の噺を聞いている姿。

清方記念美術館

清方も紫陽花が大好きで、別号として紫陽花舎(あじさいのや)を名乗った。


それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!



















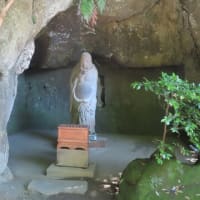




ご紹介ありがとうございます!