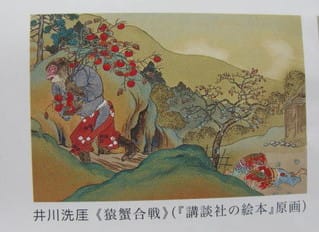ぼくの散歩道に今、真っ赤なデイゴの花が咲いては散っている。
散るデイゴの花も麗しく。
ご近所の娘さんも花を踏まないように、花見しながら歩いていた。

寅さんとひばりちゃんも(遠くのタイル画)、花見をしていた。

咲いてるデイゴの花も麗しく。

家に戻ったら小鳩ちゃんがいた。いつもみるから、
どうも近くに巣があるらしい。
そうだ、デイゴは沖縄の県花だったけ、と思いだした。
身を引いた小鳩は結局、半年間、沖縄県民をまどわしただけだった。
この小鳩ちゃんには罪はない。啼くな小鳩よ、だ。
玄関に君のふんがいっぱいだけど、
ふーん、しょうがないねと、掃除した。

夕方、またデイゴの花を観に行った。
そしたら、誰かが散った花を掃除してしまっていた。
ふーん、これもしょうがないのかな。
ぼくなら、掃かないけどね。
ひとそれぞれだね。

散るデイゴの花も麗しく。
ご近所の娘さんも花を踏まないように、花見しながら歩いていた。

寅さんとひばりちゃんも(遠くのタイル画)、花見をしていた。

咲いてるデイゴの花も麗しく。

家に戻ったら小鳩ちゃんがいた。いつもみるから、
どうも近くに巣があるらしい。
そうだ、デイゴは沖縄の県花だったけ、と思いだした。
身を引いた小鳩は結局、半年間、沖縄県民をまどわしただけだった。
この小鳩ちゃんには罪はない。啼くな小鳩よ、だ。
玄関に君のふんがいっぱいだけど、
ふーん、しょうがないねと、掃除した。

夕方、またデイゴの花を観に行った。
そしたら、誰かが散った花を掃除してしまっていた。
ふーん、これもしょうがないのかな。
ぼくなら、掃かないけどね。
ひとそれぞれだね。