
昨日から本格的に始まった学会は、まず朝の9時半から75分間、社会学部の「農村社会学」の授業において、僕と立松和平氏が5分ほど(実際は15分ほどのなってしまったが)日本の農業に話し、それから学生の質問に応じる形で始まった。なぜ作家と批評家(大学教師)が日本の農業についてアメリカの学生の質問に答えなければならないのか、立松氏については、日本の農業についてさまざまに発言しているのは周知のこととして、僕に関しては、「純」農村にすんでいて、このブログの読者はご存知のように、昨今の食料自給率の低さや農村の実情について「素人」なりの発言をしているから、というのが理由であった(僕にこの学会に来てほしいといってきたダッグ・スレイメーカーは、僕のブログを時々読んでいるとのこと)。
授業に出席していたのは、ほとんどが農家出身の学生(男女)で、トヨタの大工場があるとはいえ基本的には農業州であるケンタッキーにも、主要産業であった「たばこ」や「馬の生産」が廃れ(午後にレキシントン近郊の牧場を見学させてもらったのだが、それこそ大変美しい牧場風景とは別に、市街地に近いところでは、伸張する住宅に次々と牧場が飲み込まれているさまがよくわかった)、後継者が手っ取り早く現金の手に入る工場労働者や他の職種の働き手になる、という現象が最近は顕著で、そのことは日本でも共通な問題なので、僕と立松氏が質問を受けるということになったのである。
食料自給率40パーセントという数字に学生たちはまず驚き、結果手に役割分担をすることになってしまったのだが、立松氏は現状は悲観的なことが多いが、まだまだ農業に未来はあるのではないかと言い、僕は一貫して「絶望的なのではないか」、と言い続けた。学生たちはそのことをどのように受け止めたか、レキシントンの農業の中で生きる自分たちに今日の出来事を重ねてくれればいいが……。
午後は、ダッグが立松氏の「遠雷」(英語版)を読ませてきた教室の学生たち(60数人)を相手に、最初立松氏が「遠雷」を書くようになった由来を話し、質疑応答に、これも登場人物のキャラクターはどのように決めるのかとか、なぜトマトの栽培なのかというような、作品に即した質問が出て、あっという間に75分が過ぎてしまった。授業が終わった後には本にサインを求める学生や(絶版になってしまったので)1冊分のコピーに立松氏のサインを求める学生が並び、立松氏は丁寧に日本語でサインしていた。
夕方は「環境・社会正義」と題する学会の立松氏による基調講演、彼は日本の公害の原点と言われる「足尾銅山鉱毒事件」について書いた「毒ー風聞・田中正造」を中心に話し、現在は赤茶けた足尾の山に「貧者の一灯」(ボランティア精神)で仲間たちと木を植えているという話で締めくくった。(なぜ、鉱山の話をしたかというと、ケンタッキー州は北部アパラチア山脈に炭鉱をたくさん抱えていて、現在公害をはじめいろいろな問題があるので、日本との共通点、と言うことで「足尾」のことを話すことになったのである)
講演は、結果的によくまとまったもので、観客もそのことはよく理解したようである。僕も質問(立松さんの「環境」について書いた本はどの位売れるのか、といった類の)を尾語なう意味で2度ほど発言したが、充実した(疲れた)1日であった。今日(21日)は朝9時からシンポジウム、途中で眠くならなければいいのだが……。
授業に出席していたのは、ほとんどが農家出身の学生(男女)で、トヨタの大工場があるとはいえ基本的には農業州であるケンタッキーにも、主要産業であった「たばこ」や「馬の生産」が廃れ(午後にレキシントン近郊の牧場を見学させてもらったのだが、それこそ大変美しい牧場風景とは別に、市街地に近いところでは、伸張する住宅に次々と牧場が飲み込まれているさまがよくわかった)、後継者が手っ取り早く現金の手に入る工場労働者や他の職種の働き手になる、という現象が最近は顕著で、そのことは日本でも共通な問題なので、僕と立松氏が質問を受けるということになったのである。
食料自給率40パーセントという数字に学生たちはまず驚き、結果手に役割分担をすることになってしまったのだが、立松氏は現状は悲観的なことが多いが、まだまだ農業に未来はあるのではないかと言い、僕は一貫して「絶望的なのではないか」、と言い続けた。学生たちはそのことをどのように受け止めたか、レキシントンの農業の中で生きる自分たちに今日の出来事を重ねてくれればいいが……。
午後は、ダッグが立松氏の「遠雷」(英語版)を読ませてきた教室の学生たち(60数人)を相手に、最初立松氏が「遠雷」を書くようになった由来を話し、質疑応答に、これも登場人物のキャラクターはどのように決めるのかとか、なぜトマトの栽培なのかというような、作品に即した質問が出て、あっという間に75分が過ぎてしまった。授業が終わった後には本にサインを求める学生や(絶版になってしまったので)1冊分のコピーに立松氏のサインを求める学生が並び、立松氏は丁寧に日本語でサインしていた。
夕方は「環境・社会正義」と題する学会の立松氏による基調講演、彼は日本の公害の原点と言われる「足尾銅山鉱毒事件」について書いた「毒ー風聞・田中正造」を中心に話し、現在は赤茶けた足尾の山に「貧者の一灯」(ボランティア精神)で仲間たちと木を植えているという話で締めくくった。(なぜ、鉱山の話をしたかというと、ケンタッキー州は北部アパラチア山脈に炭鉱をたくさん抱えていて、現在公害をはじめいろいろな問題があるので、日本との共通点、と言うことで「足尾」のことを話すことになったのである)
講演は、結果的によくまとまったもので、観客もそのことはよく理解したようである。僕も質問(立松さんの「環境」について書いた本はどの位売れるのか、といった類の)を尾語なう意味で2度ほど発言したが、充実した(疲れた)1日であった。今日(21日)は朝9時からシンポジウム、途中で眠くならなければいいのだが……。












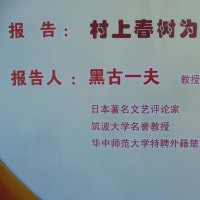

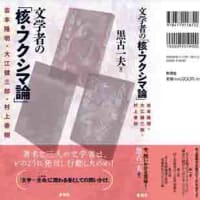




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます